なぜ文学研究をするのか、文学が何の役に立つのか。時折耳にする言葉です。私が文学研究の道に入った理由は単純です。作家が記した言葉に触れることの楽しさを知ってしまったからです。とりわけ、エッセーという文学ジャンルの創始者でありフランス・モラリスト(人間研究家)文学の始祖であるモンテーニュ(1533~一592)の画期的作品『エセー』を読んで、それまで体験したことのないワクワク感、ゾクゾク感を味わいました。これほど面白くて読み応えのある作品に出会ったのは初めてでした。
モンテーニュは30代の終わりに職を辞し、読書三昧の日々を送りつつ物を書き、1580年に『エセー』初版を出版した後も、死が訪れるまで修正増補を続けました。しかし、この間、長期の旅行に出かけたり、政治的仲介役を務めたり、ボルドー市長職を務めたりしていますから、『エセー』はご隠居さんが徒然なるままに手遊びで書いた作品でも、書斎にこもる隠遁者の著作でもありません。また、著者は「自己を描く」、「主題は私だ」と言っていますが、自叙伝の類でもありません。タイトルに込められた意味は、思考の試行の数々とでも言いましょうか。古代ギリシャ・ローマから同時代に至る文学・哲学・歴史など数多くの作品からの直接間接の引用にも、他者の思考と接することで自己の思考を働かせ、他者の言葉を自己の言葉の中に取り込み、新たな意味を持たせる様子が見られます。成熟と青臭さ、鋭い批判精神と度量の大きさ、広い視野と深い内省。時にはシャレやユーモアを交えて語りつつ、人間の色々な問題について考える糸口をふんだんに与えてくれる、心に響く生き生きとした言葉。自己描写を通して人間について様々な観点から判断の試みを続ける「自画像」の魅力は尽きることがありません。
惹かれるものだからこそ難しさも楽しさになります。16世紀のフランス語は、綴り字も語彙も文法も現代フランス語とは違うのですが、原典が原点、テクストを丹念に読み込むことが文学研究の根本。その楽しさが原動力になります。日本では研究室で利用していた一六世紀フランス語辞典をパリ留学中にどうしても手元に置きたくて購入し、七巻本の重さにヨタヨタしながらも気分はスキップでアパルトマンまで帰ったことが、昨日のことのように思い出されます。
作品や作家や時代背景に関する資料や研究書を参照することも、引用された他の著者の作品を読むことも、分からなかった事柄が理解できたり、新たな見方ができたり、発見につながったりと、ワクワク感をもたらしてくれます。なかでも、同時代のアミヨによるプルタルコスの『モラリア』のフランス語訳は、ファクシミリのコピーをようやく入手して読んだとき、まさにこれをモンテーニュさんが愛読しながら思考を刺激されていたのだと実感できて、文字通り鳥肌が立ちました。
作家の手稿を読むことも、文学研究において重要です。『エセー』の場合、1588年版に活字テクストの大幅な修正と夥しい増補文が書き込まれた「ボルドー本」が現存しています。その写真複製本を手にしたときのワクワク感も書き忘れたくありません。4世紀の間に損傷したところも、削除と修正と増補が錯綜しているところもあり、楽に読めるものではないのですが、記された言葉を一つ一つ辿っていると、執筆の現場に立ち会っているようで、ゾクゾクします。
「文学が何の役に立つのか」という言葉に敢えて答えるなら、現時点での私が『エセー』に見出す有用性は、固定観念や既成概念に縛られることなく、人間について個々別々に多様な観点から判断を試み、人間性を深く洞察する言葉とじっくり向き合う充実感、そのような判断の試みへの触発、その意義の認識です。けれども、役に立つか否かという理屈抜きに、文学や芸術をワクワク、ゾクゾクしつつ味わい楽しむ心のゆとりと豊かさも大切にしたいものです。役に立つか否かという論は、役に立たないものは要らないという考えにつながりがちで、人の心を狭くし、社会をぎすぎすしたものにすると思うからです。

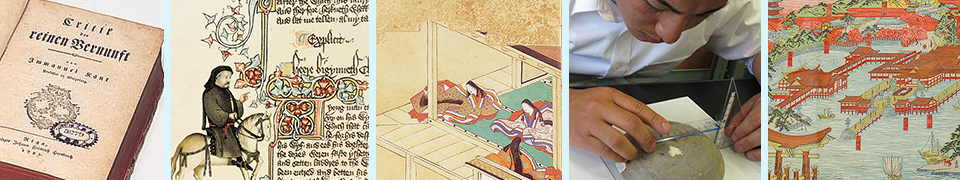
 Home
Home



