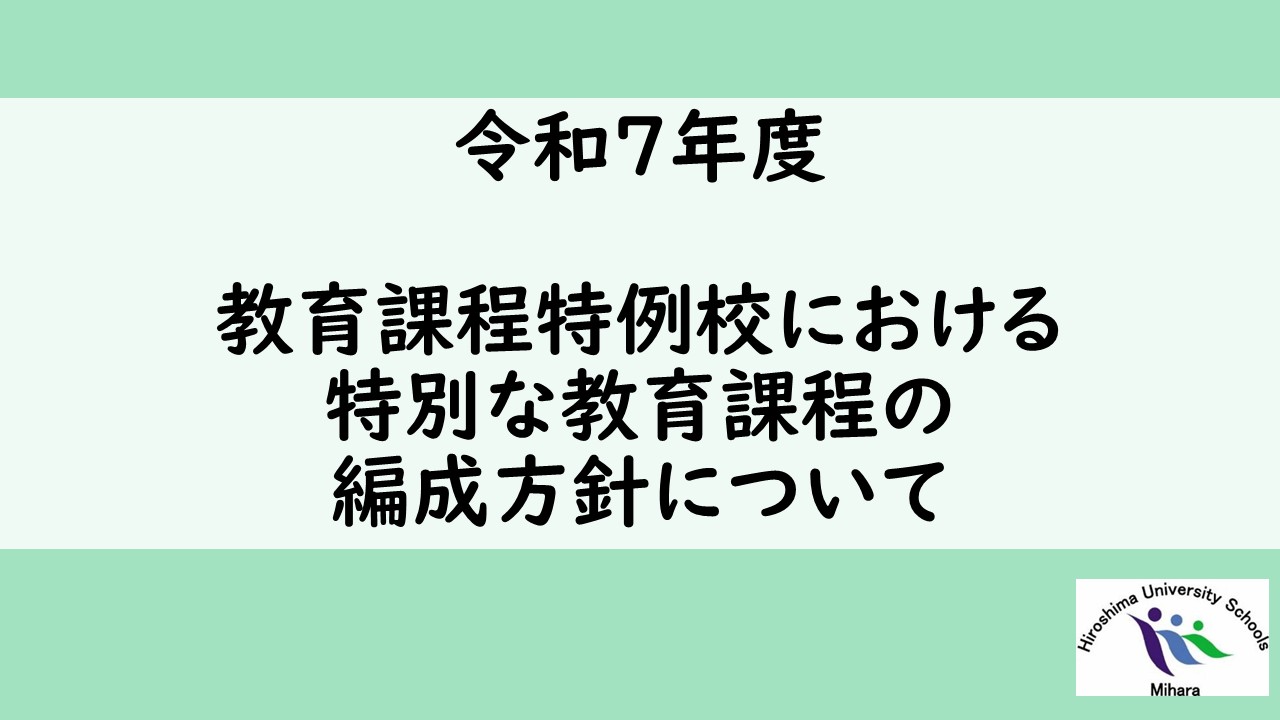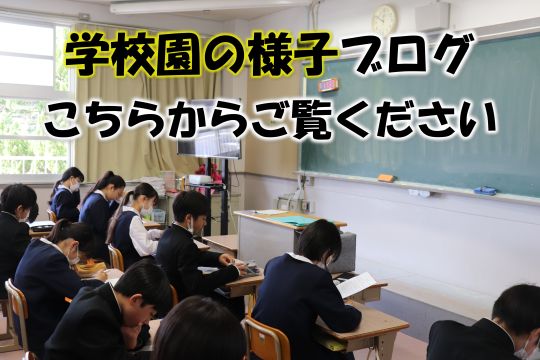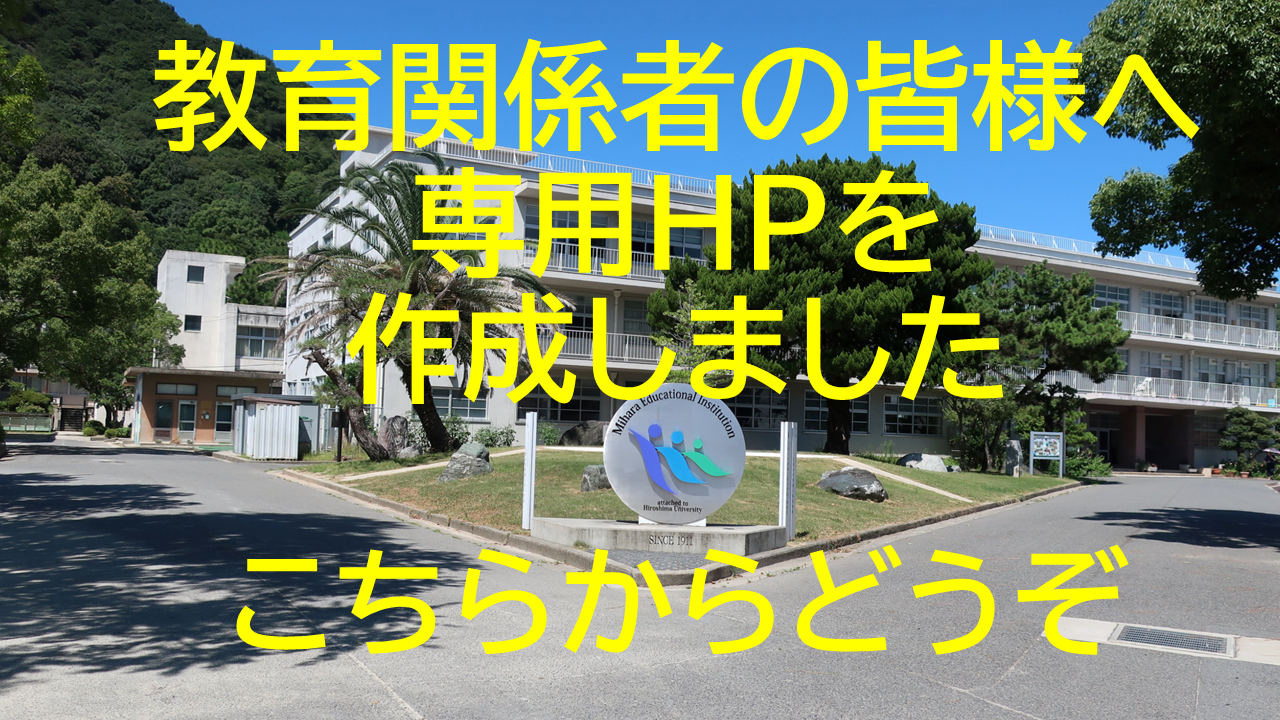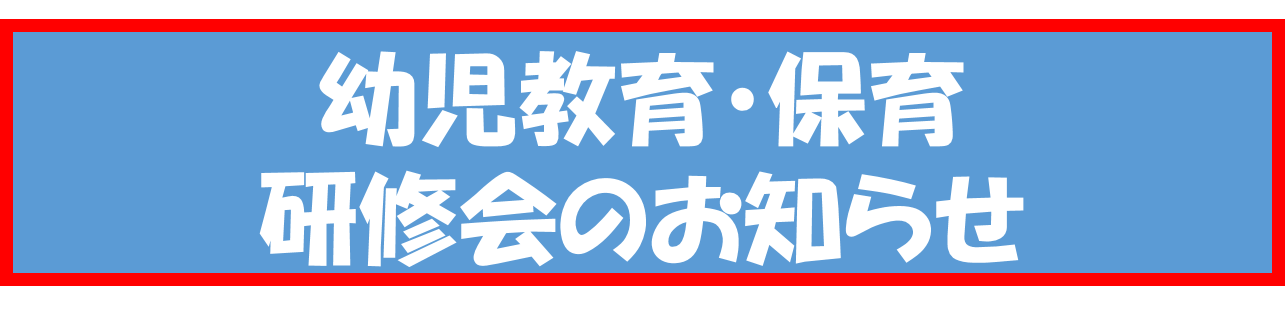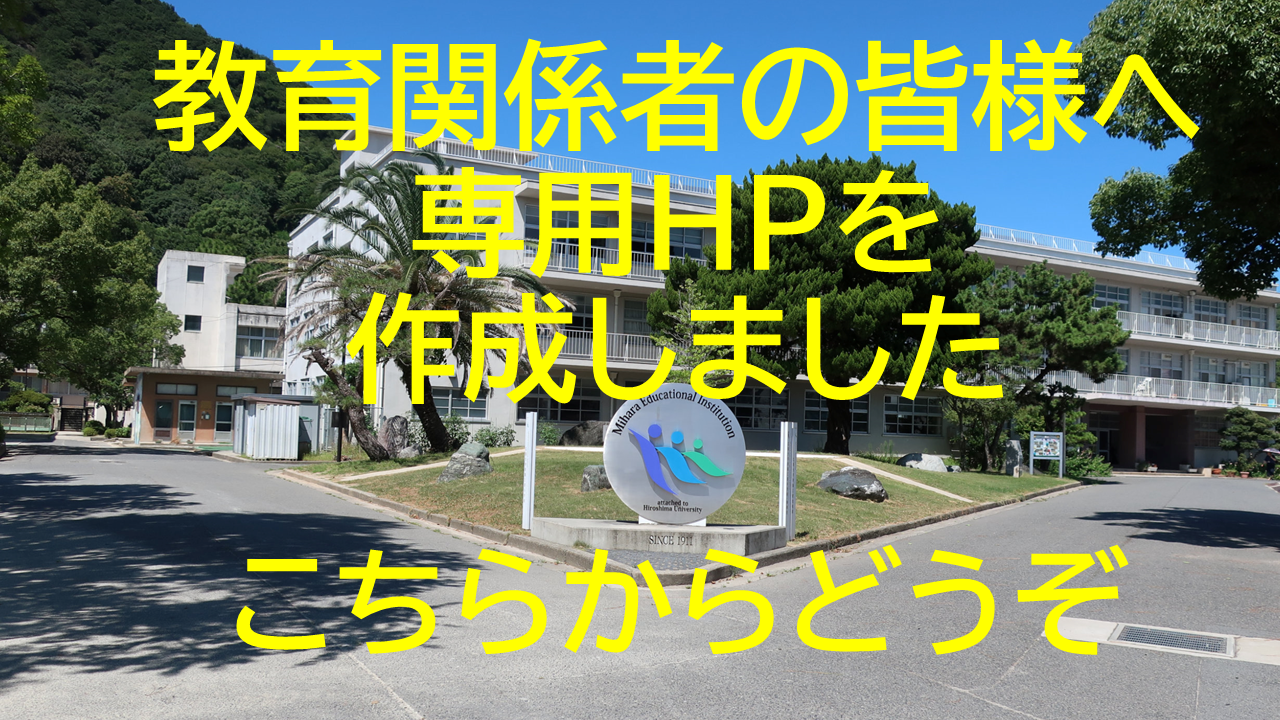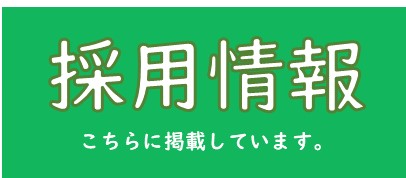2月の子どもたち
2月27日(火)
4月から始まる小学校生活に期待や自覚が持てるようにと,同じ敷地内にある小学1年生の教室に授業参観にいきました。幼小中一貫教育ですので日ごろから交流はありますが,授業参観は初めてとあって,年長児も少し緊張していました。
算数の授業を参観した後,給食の配膳の様子を見学し,昼食(年長児はお弁当を持参しました)を一緒にいただきました。
つい5日前までは固く小さなつぼみだった園庭の紅梅がたくさんの花を咲かせ,豊かに香っています。
2月26日(月)
今日は三村園長先生がハープの演奏をきかせてくださいました。
ハープとバイオリン,フルートの三重奏です。『ドレミの歌』や『エーデルワイス』などサウンドオブミュージックという有名なミュージカルの音楽ナンバーをメドレーで演奏してくださいました。
ハープの実物を目の前で見る子どもたち。ハープの音を初めて耳にする子どもたち。
音に合わせて体をゆすったり,じっと聞き入ったり。
それは優しい音色でした。
最後は園歌の演奏もしてくださり,みんなで演奏に合わせて歌いました。
2月17日(土)
いよいよ「お楽しみ会」の本番です!
年少児も年中児も,保護者の皆さんもハラハラドキドキワクワクです!
たくさんの保護者の方の前で,「はじめのことば」を大きな声で発表する年少児たち
おわりの言葉を言う年中児たち。
子どもたちの頑張りをたたえる大きな拍手で会場がつつまれました。
セキセイインコの『ぴぴこ』はみんなのアイドルです。
みんなに優しくしてもらってうれしいね。
2月
17日の「お楽しみ会」に向けて,会場になる遊戯室での練習が始まりました。
これまで園生活の中で少しずつ劇遊びや歌やリズムを楽しみながら積み上げてきました。
先生や友だちとのやり取りを楽しみながら,セリフや動作などをつくってきました。
【年少】うさぎらしく橋を渡ってみよう!
【年中】7匹の子ヤギたち。声をそろえセリフを言うのも最初はたいへんです
【年中】観客の皆さんによく見えるよう,子どもたちの立ち位置も工夫しました。
【年少】年中児,年長児たちが見守る中,子どもたちはにこにこ楽しんで練習の成果を披露しました。
【年中】練習を重ねて,自信もついてきたようです。本番まであと2日です。
2月7日(水)
暦の上では春ですが,まだまだ厳しい寒さが続く中,水を張ったプールも凍りました。年長児は,コマを持ち出し,氷上でコマ回しを始めました。くるくるくるくるよく回ります。
なんとかプールの大きさそのままの氷を取り出したい子どもたちは,みんなでプールを取り囲みいろいろと挑戦します。しかしさすがにこれは無理と話はまとまり,割って少しでも大きな氷を取り出すことになりました。
「まわった!まわった!」
凍ったプールでコマ回しをする年長児たち
どうやったらうまく氷がすくい上げられるでしょうか?くまで?スコップ?虫取り網?
1月の子どもたち
1月31日(水)
諸事情で土曜日の開催が延期となり,今日の開催となった年長組の「おたのしみ会」。
子どもたちは緊張しながらも,日ごろの練習の成果を見てもらおうと頑張りました。
平日ではありましたが,たくさんの保護者の方に来ていただき,子どもたちの成長ぶりを温かく見守ってくださいました。
子どもたちに拍手を送る保護者の皆さん。鳴り止まないアンコールの拍手に応えて,1曲歌を披露しました。
1月25日(木)
おたのしみ会の本番をまじかにひかえ,練習を重ねる年長児たち。
「どうしたら,蜂らしく見えるかな?どう体を動かしたらいいと思う?」先生の言葉に子どもたちから意見が出ます。「腕を羽のように動かしてみたら?」その通りにやってみます。さきほどより「蜂」らしく見えます。「じゃあ,栗は?」。こうして「さるかにがっせん」の劇は作られていきました。
もう一つの劇「ピーターパン」はワニが出てきます。どうやったらこわいワニを体で表現するのでしょう。フック船長やピーターパン,子どもたちのその時々の気持ちを体とセリフで表現します。
表現方法を子どもたちに考えさせ,試してみては,改善していきます。自分たちで作り上げていく楽しさをあじわい,友だちと協力する大切さを学び,やりとげたという達成感を体験しています。さまざまな体験を通じて,子どもたちは日々成長しています。
「ピーターパン」チームの練習をみる「さるかにがっせん」チーム
1月12日(金)
今日は,園庭にある睡蓮鉢に厚い氷が張りました。
厚さは12ミリもあります。年長児が慎重に睡蓮鉢から氷を引き上げます。見事丸ごと取り出すことに成功しました。「小さいクラスのお友だちにも見せてあげよう!」「うん!こんな大きいのすごいよね!きっとおおよろこびだね!」落とさないよう年少組のもとへそっと運びます。
大きな氷を見せてもらった年少児,「大きいねー!」とみんな手を伸ばします。「つるつる!」「つめたいー!」「もちたいー!」と持ち上げた途端がっちゃーん!こなごなに!「こおりがいっぱいになった!すごいねぇ!」と大喜びしました
1月11日(木)
雪が積りました。この辺りでは珍しいことです。子どもたちは大喜びです。
手袋も靴も雪にまみれて遊びます。
年少児は雪だるまを作っているようです。葉っぱをつけたり,木の小枝をつけたり。「おこったかおー」「ないたかおー」といろいろな表情をつけて楽しんでいます。
12月の子どもたち
12月21日(木)
幼稚園にサンタクロースのおじいさんが,プレゼントをいっぱい持って,遠い北の国から,トナカイのそりに乗ってやってきてくれました。サンタさんと三つの約束をして子どもたちはプレゼントをいただきました。
サンタの後ろのタペストリーは手芸同好会の皆さんの手作りです。
12月15日(金)
年長児が園庭で育てた大根が食べごろとなりました。
じっくり煮込んで,年少児・年中児のお友だちにもわけてあげました。
やわらかいよ!すっごくおいしい!
「おかわりいるひと?」「はあーい!」
12月7日(木)
留学生さんと一緒に今日挑戦したのは『決められた数のカプラを使って,決められた時間の中で高く積み上げよう!』です。1枚の板を縦にしたり,横にしたりとグループで意見を出し合いながら,実際に積み上げてはくずしを繰り返しながら挑戦しました。
「ここにこうのせてみようか?」
「くずれないかなぁ?」
「ここにもう一枚おいてみる?」
「うーん」
12月5日(火)
ざっざっ,ざっざっ,じゃかしゃか,じゃかしゃか。園庭にある藤の木の下から箒を使う音がします。お掃除のお手伝いをしてくれているのかな?
104歳の藤の木からは毎日大量の葉が落ちてきます。
今日は年少児が熊手を手に落ち葉をかき集めてくれています。(後で測ってみると90リットルのビニール袋に入れて3袋ありました)
集めた葉っぱを両手いっぱいにすくってゴミ箱へ…ではなく「シャワー!!!」「おちばのシャワー!!!」とさけびながら空に向かって落ち葉を投げていました。
11月の子どもたち
秋の園庭。銀杏の黄色,桜や楓の紅葉,大王松の松ぼっくりや落ち葉。
さまざまな色や形の葉や実は子どもたちの遊びを豊かにしてくれます。
遊戯室から巧技台をもちだしプールの中に並べた年少児。
その上に上がって始まったショウタイム!歌ったり,踊ったり。いっしょに踊ろうとする先生を目の前に座らせます。
「先生はおきゃくさん!」
なるほど,やはり舞台には観客が必要ですから。
【11月9日(木)】
さあ,今日は『焼いも』をします。
収穫したお芋はきれいに泥をとり,アルミにつつみ,準備完了。
次は焚き木をして炭にし,おいもを焼く準備をします。
今日は,あちらこちらの場面で,年少児,年中児に対する年長児の子どもたちの優しさが感じられました。
「なに,やっているの?」と年少児。
「木をこうやると火がよくつくんだ」
「火をつけてどうするの?」
「おいもを焼くんだよ」
「ほんと!」
木のベンチに新聞紙を貼りつける年長児たち。
なにしているの?
「ちょっとしめっているから,小さいクラスの子どもたちが座ってもお尻がぬれないようにしているの」
どうすれば小さいお友だちが嫌な気持ちにならないか,考えてくれていました。
年少児の中にはこんなに大きな焚き木を間近で見る子どもも多く,「けむい!」「あつい!」「めがいたい!」「くさい!」いろんな言葉が出ました。
それでもお兄ちゃんお姉ちゃんとみんなで火を囲んで,ゆったりとした時間を過ごしました。
ほかほか,あつあつの焼いも。
「どれにする?」「これがいい」
「あついからとってあげる」
おいもをティッシュペーパーに包んで年少児に渡す年長児。
秋晴れのこの日,『やきいも』が終わった後,園庭でお弁当を食べました。
【11月8日(水)】
1年生交流でのひとコマ。
1年生の教室を訪れた年長児ですが,一人ずつ座るには椅子の数が足りません。
一緒に座る子,年長児に座らせてあげる子,落ちないようにそっと手を添える子。
どうすれば年長児たちが心地よく過ごせるか1年生なりに考えた行動です。
優しいですね。
【11月6日(月)】
年少児と留学生。すっかりうちとけて楽しくおままごとをしています。
【11月1日(水)】
今日は『いもほり』です。
長く伸びた蔓を引っ張り,収穫スタートです。
次々と,土の中から丸々としたサツマイモが掘り出されていきます。
園芸サークルのお母さん方が,秋のリースに続いて,クリスマスリースを作って幼稚園に飾ってくださいました。各クラスはもちろん,遊戯室や,園門の前にも。今年はおやじの会のお父さんが園庭のカイズカイブキの木を剪定してくださり,その枝を使って作ってくださいました。
これは手芸サークルのお母さん方の手作りツリーで高さおおよそ160cm。飾り物を新しくしたり,繕ったりしていただきながら大切に飾らせていただいています。
10月の子どもたち
10月31日(火)
広島大学の留学生と一緒にコマ回しを楽しむ年長児たち。ひものかけ方から,回すときの手首の角度など,丁寧に留学生に教えていました。
「こう?」「いい?」「あー,おしい!」「もういっかい!」「ぜったいできるけん!」教えるほうも教わるほうも楽しそう。
年少クラスのお部屋から,「おいしくなぁれ!おいしくなぁれ!」の大合唱が聞こえてきました。朝,園庭で広島大学の留学生と一緒に収穫したピーマンやウィンナーを使ってミニミニピザを作ってみんなでおいしくいただきました。
自分たちで育てたピーマンを留学生と一緒に収穫しました。
「おいしくなぁれ!」のポーズ。みんなのハンドパワーでおいしくなります!
10月26日(木)
中学校の体育館を借りて1年生とコマ回し。いろんな小道具を持参していますが,どんなコマ回しになるのかな?
もっと楽しいコマ回しのやり方はないかな?段ボールを使ったり,ペットボトルのキャップを使ったり。1年生とアイディアを出し合います。
10月26日(木)
今日から後期が始まりました。
式が終わった後,年長児が式場の椅子を片付けました。
年中児の子どもたちは,ススキと一足早く紅葉したモミジの一枝を花瓶に挿してテーブルに飾り,お日様のもとテラスでお弁当をいただきました。
10月20日(金)
今日は前期終業式です。
三村真弓園長先生から,前期の頑張ったところをたくさん褒めていただきました。
式が終わって,みんなで自分たちの使った保育室や廊下を掃除しました。
三村園長先生のお話を静かに聞きます。
年少組の子どもたちも雑巾がけ。なかなか上手です。
年中組の子どもたち。拭く場所や拭き方もみんなで考えながら雑巾がけをしました。
10月18日(水)
手芸同好会のお母さん先生が,子どもたちに折り紙を教えてくださいました。
ハロウィンにちなんだ『かぼちゃお化け』や,子どもたちに人気の手裏剣を折り紙で作ったり,新聞紙で作ったボールキャッチャーとボールで遊んだりと年少組から年長組までみんなで楽しく遊びました。年長児はお母さん先生から教わるだけでなく,年少児や年中児に折り方を教えてあげる子どももいました。
子どもたちにどんなものを作るのか,わかりやすく看板も作ってくださいました。
折ったり,入れ込んだり,貼ったり,書いたり。折り紙一枚でいろんな遊びができます。
10月13日(金)
年長児の保育参加の日です。今日はお父さんもお母さんも,子どもたちと一緒に宇宙の絵を描きました。
10月12日(木)
かろうじて手の届く枝に柘榴の実が一つ。年中児たちは虫取り網を持ってもぎ取ろうと頑張っています。小さな実を見つけた子どもたちは「あかちゃんざくろだ!」「たこさんウインナーだ!」と声を上げます。
「もっと右!」「ちょっと左!」
網の輪に引っかけて・・・取れました!
「たこさんウインナーがなってる!」
10月10日(火)
小学校の音楽の先生がたたいて音を出す『ブームワッカー』(ドレミの音階で音が出るので,曲も演奏することができるプラスティック性の円柱の棒)を持ってきてくださいました。年長児たちはジェットジムや雲梯,鉄棒などいろいろ遊具をたたいて音を楽しみました。自分の身体をたたいて出た音と遊具をたたいて出た音を比べてみる子もいました。棒で棒をたたくとどんな音が出るのかなど,いろいろ試す様子も見られました。
「棒の長さで音が違うのよ」小学校の音楽の先生に使い方を教えてもらいました。
叩くだけでなく,棒を滑らせて連続して音を出すやり方を発見してみんなで試している様子(雲梯)
10月6日(金)
昨日のマテバシイの実を,ホットプレートで炒ってみんなで食べました。
「いいにおいがしてきたよ!」
「どんな味がするのかな?」
「むいてあげる」「ありがとう」
10月5日(木)
年少児と年中児が近くの公園へお出かけしました。その公園にはマテバシイの実がたくさん落ちていました。子どもたちは袋いっぱいの実をお土産にして,園に持って帰ってくれました。
10月3日(火)
今日は待ちに待った遠足の日です。今年はバスに乗って広島大学東広島キャンパスにある大学の農場に行きました。牛や羊の動物の臭いや,鳴き声,自分の身体との大きさの違いなど,映像では見えないことをたくさん体験しました。
ひろい農場の中を広島大学の先生に案内してもらいました。
大きいクラスの子どもたちは小さなクラスの子どもたちの手をしっかりと握って,いよいよ遠足に出発です!
10月2日(月)
年長児と1年生の交流も3回目となり,子どもたちもだんだんと交流を心待ちにするようになったようです。
交流も回を重ねるごとに親密さを増していきます。
10月2日(月)
遠足を翌日に控えたこの日,雨がよく降りました。
年少児たちが「明日は晴れますように」と願いを込めて大きなてるてる坊主を作りました。
これで明日は晴れるよね!
9月の子どもたち
9月20日(水)
園庭の大王松の松葉を使って,年少児が作ったのは,『ベッド』です。筵を下にひいて集めた松葉をお布団に。寝心地はどうかな?
「もっと,まつばがいる?」「うん」埋もれるくらいの松葉が集まりました。
9月20日(水)
年長児のクラスに,おじいちゃんとおばあちゃんが『昔の遊び』を教えに来てくださいました。けん玉,ヨーヨー,あやとり,おはじき,竹馬と達人の技を教えていただきました。
「体重を前にかけてね。」「もっといてよ!」「大丈夫,ちゃんともってるよ。」
9月14日(木)
今日は9月のお誕生日の子どもたちを祝うお誕生会。
お母さんたちも料理の腕を振るいます。子どもたちは歌や踊りでお祝いしました。
9月
保育参加の日です。お家の人が一日先生になって子どもたちと一緒に活動しました。
年中児はお月見だんごを作りました。「耳たぶくらいのかたさになるようにね」ときどき,お友だちの耳たぶを触って「やわらかい?」「まだ,かたいかな?」後ろに見える壁紙は子どもたちの描いた『夜空にうかぶ月』です。
「まだかなあ」「もっとこねないと」「おみずいれて」小さな手でこねる作業もけっこうたいへんなのです。
9月5日(火)
中国,ベトナム,インドネシア,フィリピン,韓国,キューバなど世界各国から広島大学に学びに来ている留学生の皆さんが,幼稚園に遊びに来てくださいました。留学生の皆さんは母国では教員として活躍された方が多く,子どもたちともすぐ仲良くなりました。子どもたちも,国籍も年齢も性別も越えて,話しかけたり,遊びに誘ったりと楽しく過ごしました。
「ここもつなげる?」道路を作っている年中児の子どもたちと身振り手振りで関わる留学生
年長児の子どもたちは言葉(日本語)に身振り手振りをまじえて留学生の皆さんに教えます。なんとか伝わったようです。
「みてみて!すごいでしょ!ころがるんだよ」自作の自動車を転がせてみせる年少児ににっこり微笑む留学生
8月の子どもたち
8月30日(水)
附属三原小学校の1年生と年長組の交流がありました。
今日は初めての顔合わせです。これからの交流でペアになる1年生と年長組の子どもたちが,お互いに自己紹介し,園庭や保育室で一緒に遊びました。1年前に当時の1年生と交流を重ねていた子どもたちは,今度は自分たちがお兄さんお姉さんになって年長組の子どもたちと接しています。どうすれば仲良くなれるか,どんな言葉をかければよいかなど,いろいろと考えてきたようです。年長組の子どもたちもドキドキわくわくしながら,お兄ちゃんお姉ちゃんと交流していました。
「お名前は?」と聞かれて,名札を示しながら自己紹介する年長児
最初はぎこちない様子ですが,いっしょに遊ぶことでだんだんと親しみがわいてきたようです。
7月の子どもたち
7月20日(木)
今日から1泊2日のお泊まり会です。
自分たちの食べる夕食のカレーの材料を切ることから始まりました。
これからの2日間友だちと相談しながら、意見を出し合いながら、助け合いながら何事も自分たちで考えながら活動します。
7月12日(水)
年中組の子どもたち。手押しポンプでくみ上げた水を少しはなれた砂場までどうやって水を運ぶか、試行錯誤を重ねています。どうやら、雨どいを使って水路を作ったようです。うまくいくかな?
7月7日(金)
七夕まつりの行事のひとつ、保護者のコーラスグループ『コーロ・ピオ』によるミニコンサート。
歌声に合わせて子どもたちも一緒に歌ったり、踊ったりして楽しい時間を過ごしました。
7月6日(木)
年長組の子どもたちが園庭で育てた夏野菜が食べごろになりました。
洗って、切って、焼いてそのままぱくり。調味料なしで素材の味そのものを味わいました。
7月6日(木)
3メートル以上ある大きな笹竹に、願い事を書いた短冊と七夕飾りをこよりで結びました。
「なんてかいたん?」
「〇〇になりたい!」
「ええねぇ」
7月3日(月)
地震の避難訓練です。年少組の子どもたちも姿勢を低くして身を守る練習をしました。
このあと、幼小中合同の避難訓練が行われました。
6月29日(木)
園庭に実った梅の実。今日は年少組が収穫しました。年中組、年長組もすでに収穫。なにをつくるのかな?
6月29日(木)
小学校の音楽の先生が、年長組みの子どもたちに歌の授業をしてくださいました。やさしい歌声の出し方を楽しく教えてくださいました。
幼小中運動会特集
6月17日(土) いよいよ幼小中合同運動会の本番です!
今日までの練習の成果をおうちの人たちに見てもらう大切な日です。
かけっこのスタートの練習も何度もしました。友だちに負けないよう一生懸命走る姿。途中でころんでも,自分で立ちあがって最後まで走りきる姿。そんな友だちを応援する姿もおうちの人に見てもらいましたね。
幼稚園,小学校,中学校が合同で運動会をするのには,大きな意味があります。
園児にとってみれば小学生や中学生の姿を見て「おにいちゃん,おねえちゃんになったらこんな演技をするんだ!かっこいいなあ!あんなお仕事もするんだ!すごいなぁ」という憧れの気持ちが生まれます。憧れが「いつかあんなふうになりたい」「あんな演技をしたい」という目標に変わります。その目標に向かって日々の練習を重ねる大切さ,できた時の喜び,できなかった時の悔しさが人間を成長させてくれます。運動会はその日までの練習の成果を披露するだけでなく,小さな後輩たちに目標をもたせてくれる場でもあるのです。
ゴールに向かってGO!GO!きく組
スタート直前の緊張の一瞬 さくら組
ゴールで待っていた三村園長先生がみんなを抱きしめてくださいました もも組
『お兄さんお姉さんといっしょ』練習の時より元気いっぱいです!(小学4年生と)

元気では中学生のお兄さん,お姉さんにもまけないぞ!
おうちの人とのお遊戯も今年で最後のきく組さん。一緒に踊れて良かったね
見つめ合う目と目,とりあう手と手。おうちの人の愛情をしっかり受けとめます
6月の子どもたち
6月2日(金)
2週間後の幼小中合同大運動会にむけて,練習を重ねる子どもたち。今日は小学校のお兄さんお姉さんが踊りの振り付けを教えてくれました。
6月5日(月)
今日はかけっこの練習です。スタートポーズもだんだんさまになってきました。
5月の子どもたち
5月10日(水)
先日摘んだよもぎを使って,よもぎ餅をつくりました。すりこぎとすり鉢を使って,よもぎをごりごり。「ごりごりするのもってあげる!」「わたしも!」「ぼくも!」。すり鉢もささえないと・・・。
楽器の音に合わせて手拍子したり,歌ったり,楽しい時間を過ごしました。
5月26日(金)
中学校の吹奏楽部のお姉さんが幼稚園の遊戯室で演奏会を開いてくれました。
5月
広島大学の学生が,30日まで幼稚園で教育実習を行いました。お姉さん先生,お兄さん先生と遊んだり,田植えをしたり,いろんなことを教えてもらいましたね。
ありがとうございました。
4月の子どもたち
4月12日(水)
年長組の子どもたちが,大きな大きな鯉のぼりを先生と一緒にあげました。
4月13日(木)
10日(月)に入園した子どもたちが,園庭を探検しました。
4月27日(木)
学校園内にある茶室「景露庵」の前で,年少組と年長組の子どもたちがよもぎ摘みをしました。摘んだよもぎはどうするのかな。


 Home
Home