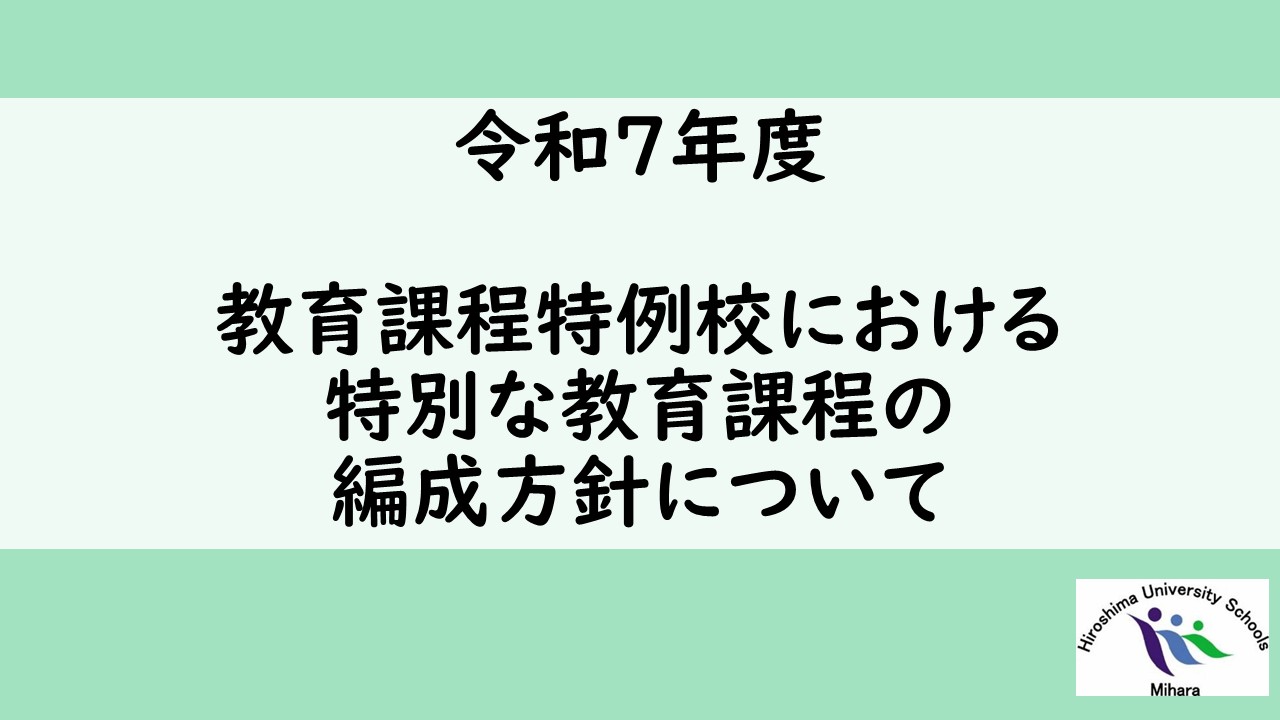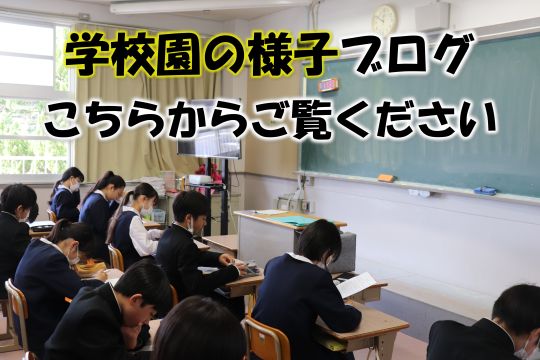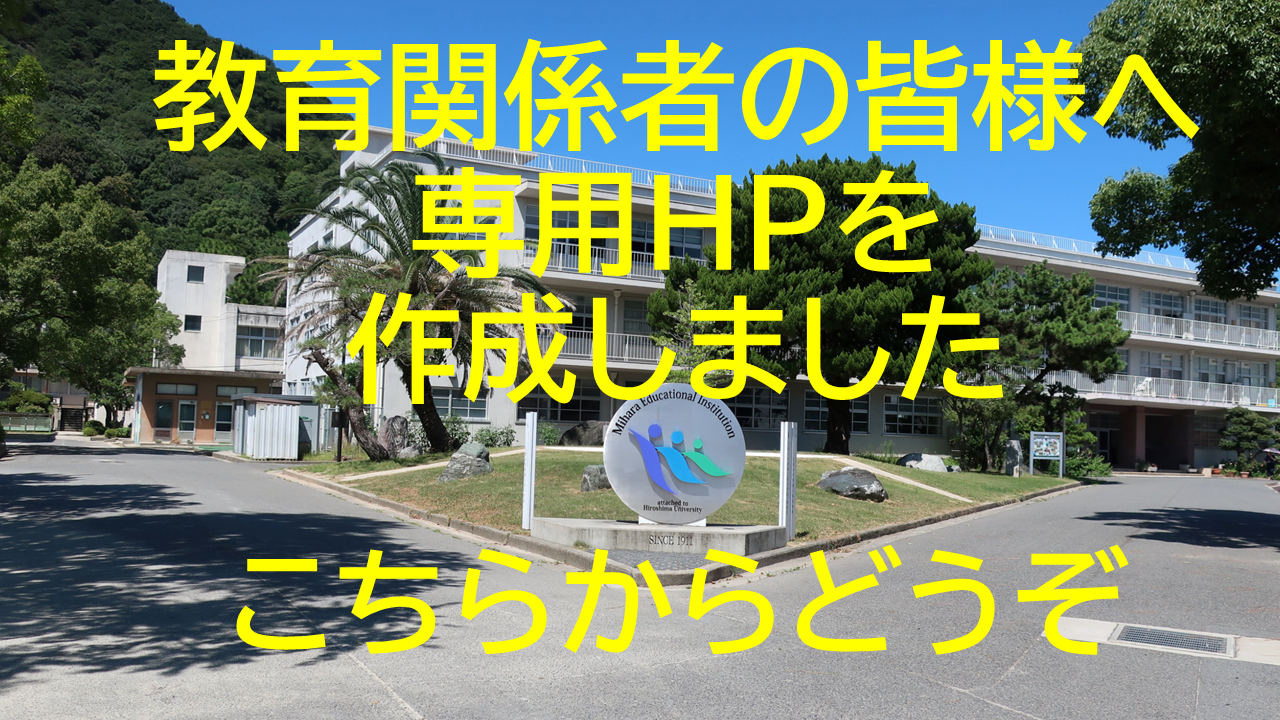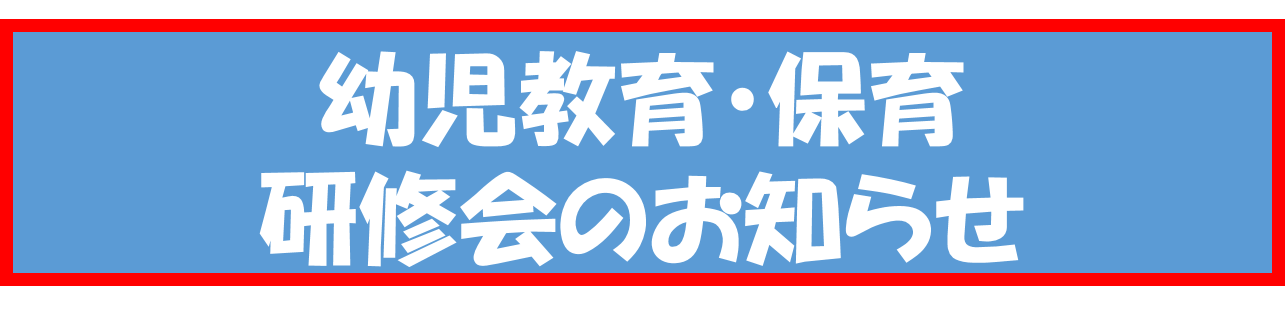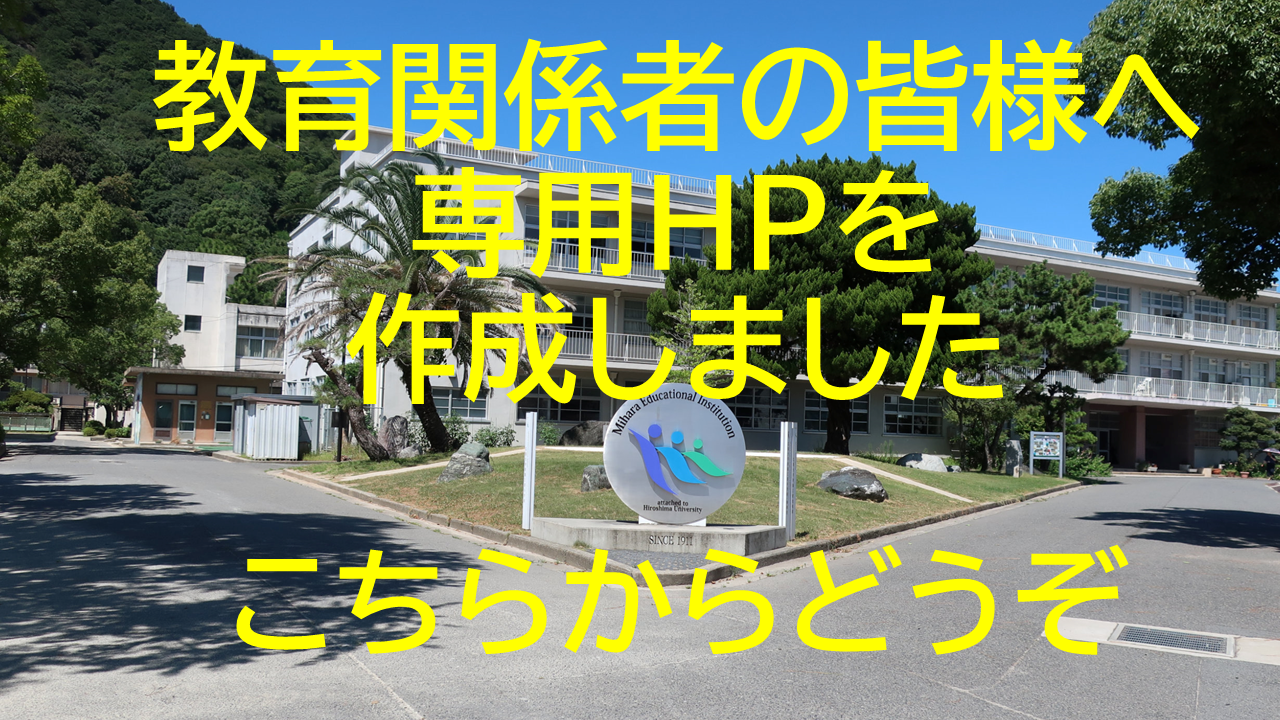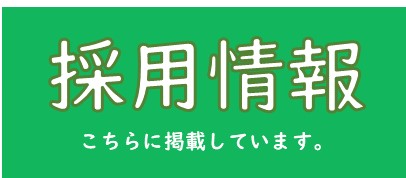前回に引き続き、令和6年度 第27回 幼小中一貫教育研究会について紹介します。
本ページは、協議会について紹介します。研究会についてはこちらのページで最後になります。
授業公開終了後、本学校園で独自に設定している新領域「光輝」の協議会がありました。
本大会のキーワードである「受容と共感」に関して、様々な議論がなされました。
子供の発言に対して、教師がすべて「受容と共感」をするのではなく、
時と場に応じた「切り返し」や「ファシリテーション」が重要であるといった話題が出ました。
そして、本大会で公開した光輝の授業を幼小中における段階で整理すると、
幼稚園では、「プロジェクトを介し伝え合う」、
小学校では、「言語を中心に伝え合う」、
中学校では、「伝え合うこと自体を分析・批評する」といった特徴がありました。
幼小中一貫教育を軸にしている本学校園だからこそ、系統性や各発達段階の接続の重要性を
認識することのできるよい機会になったのではないでしょうか。
また、協議会では、以下の3名の先生方にご指導・ご助言をいただきました。
・広島大学大学院 人間社会科学研究科 中坪 史典先生
・広島大学大学院 人間社会科学研究科 渡邊 巧先生
・広島大学大学院 人間社会科学研究科 草原 和博先生
ご多用の中、貴重なご意見をいただきまして、誠にありがとうございました。


研究会の最後には、各教科に分かれて、教科別協議会が行われました。
お忙しい中、協議会に参加してくださいました皆様、ありがとうございました。
今回いただいた貴重なご意見をもとに、さらに研究を推進していきたいと思います。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
なお、研究会に関する詳細は次のURLからご参照ください。
https://www.hiroshima-u.ac.jp/fu_mihara/R6kenkyu.kokaikenkyukai


 Home
Home