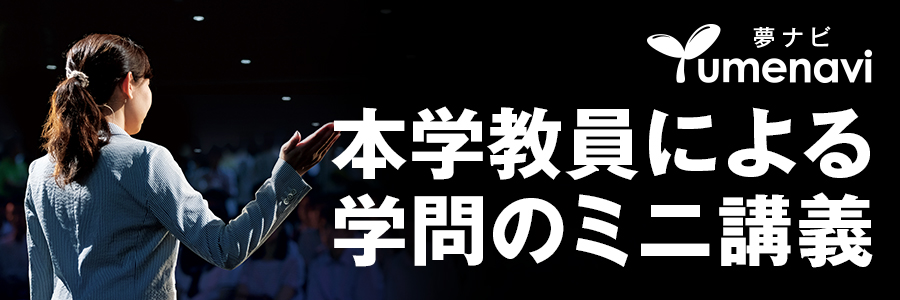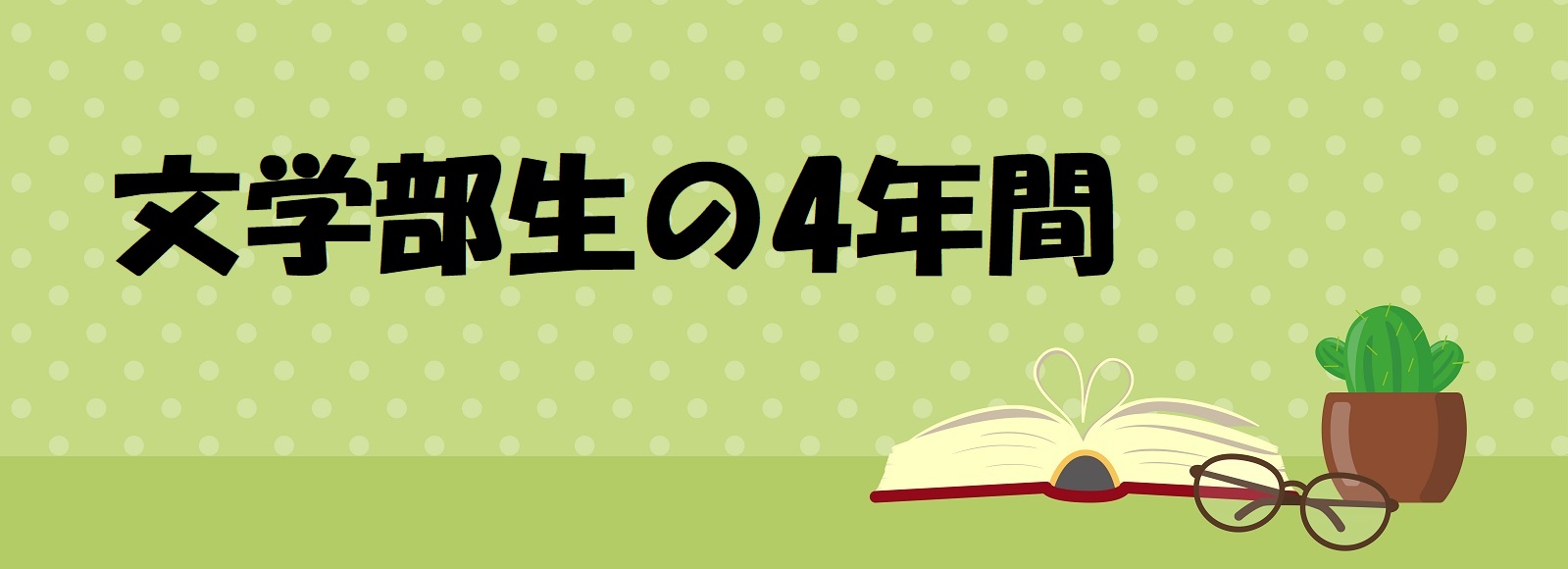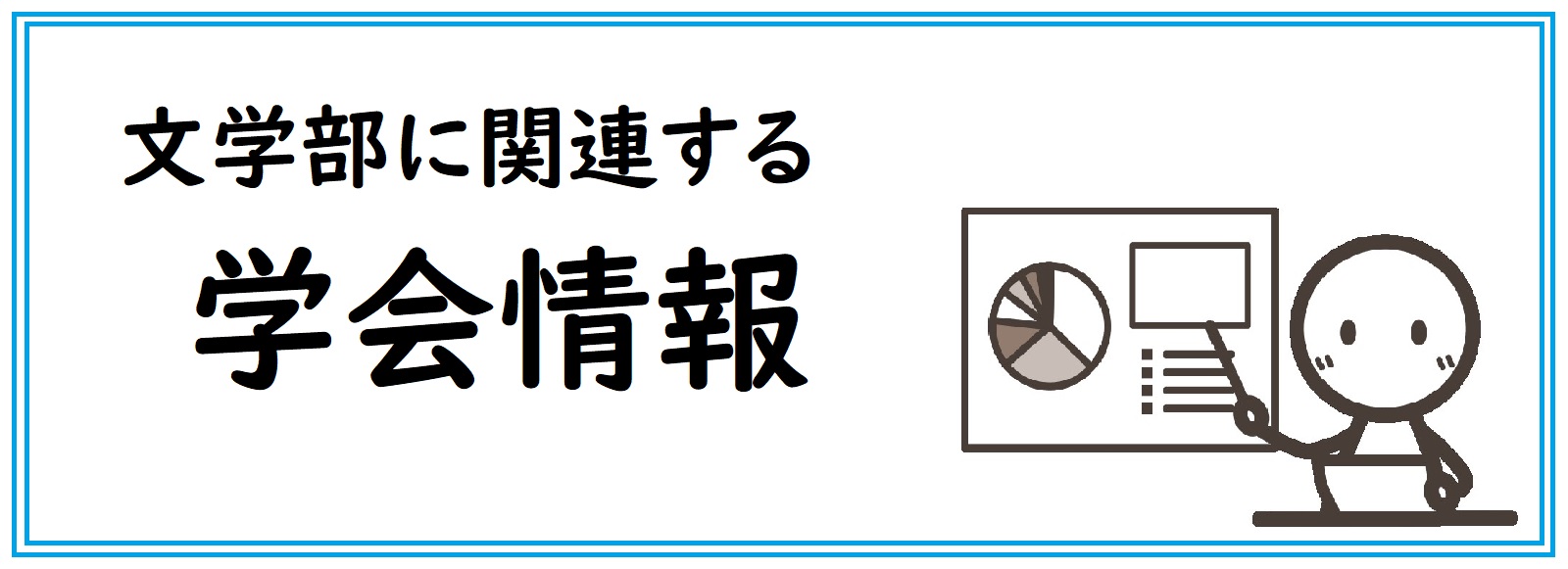いつのころ読んだものか定かではないのですが、夏目漱石の弟子で物理学者の寺田寅彦が、「科学者とあたま」という随筆の中で次のように記しています。
いわゆる頭のいい人は、言わば足の早い旅人のようなものである。人より先に人のまだ行かない所へ行き着
くこともできる代わりに、途中の道ばたあるいはちょっとしたわき道にある肝心なものを見落とす恐れが
ある。頭の悪い人足ののろい人がずっとあとからおくれて来てわけもなくそのだいじな宝物を拾って行く
場合がある。 (『寺田寅彦随筆集 第4巻』岩波文庫、1948)
ここでの「頭が悪い」とは、自明とされていることに対しても素直に疑問を抱くという態度、普通の頭の悪い人よりももっと物わかりの悪い人であることの意義を逆説的に表現しています。私の専門である哲学は、他の分野に増してこうした態度を要求しているように思います。多くの受験生は、こうした素朴な疑問をむしろ封印し、日々をやり過ごしていることでしょう。私自身、広島大学文学部哲学科に入学したとき、人生で初めて勉強が楽しいと感じたのはそのためです。
ただし、もともと哲学の勉強がしたくて文学部に入ったわけではありません。自分は将来高校の英語教師になるんだろうなあと漠然と思い描いていたところ、どういう拍子か倫理学専攻などという抹香臭い研究室に配属になったのは青天の霹靂でした。倫理の倫の字は「人の生きるべき道」という意味なのだという恩師小倉貞秀先生の第一声がそれに追い討ちをかけました(当時の日常生活で「倫理」などという言葉を耳にすること自体が稀でした。それだけ当時の日本人は倫理的だったということでしょう)。

ミュンスター大学哲学研究所
それでも倫理学に関する卒業論文を書くという時限爆弾を逃れる術はありません。そこで私が選んだのが言語哲学、それも、「人殺しはいけない」とか「困っている人を助けましょう」というタイプの文章は言語の誤使用であって、物事の良し悪しを語るなどできないと言い放ったヴィトゲンシュタインの『論理哲学論考』という書物でした。小倉先生からは案の定、「君は西洋2000年におよぶ倫理学の歴史を何と心得ているのかね。われわれの研究はすべて無駄だったと言うのかね」と切って捨てられました。
その後大学院に進み、フッサールという哲学者と取り組みましたが、当時すでに研究職はかなり狭き門で、やるだけやったらあきらめがつくだろうと、現象学研究における恩師小川侃先生(当時総合科学部。後、京都大学)の勧めに従い、本場ドイツのトリア大学への留学を決意したのです。9年にも及ぶ留学ののちに学位を取得して、モーゼルワインに後ろ髪をひかれながら日本に戻った自分は、完全に浦島太郎でした。
異国に長く住んだ人はどちらの国にいても絶えずホームシックを感じるものだと、知り合いのドイツ人から聞かされたことがあります。でも、故郷が二つあるのはやはりすばらしいことです。ドイツ人と知り合えただけでなく、アジアの隣国からの留学生と、戦争のこと、国民性や企業文化についてドイツ語で語り合えたことは、何ものにも代え難い経験です。その経験が、広島大学の協定校であるミュンスター大学との交流にも間違いなく生かされています。
大学での勉強、それは教科書を使って習うのではなく、教科書を作る仕事です。それを人は研究と言います。フッサールが才能あふれる弟子インガルデンに語りかけています。
「人柄がすべてだ。才能などありふれている」
この言葉を胸に、皆さんも研究の道を志してみませんか。

ローマの古都トリア市

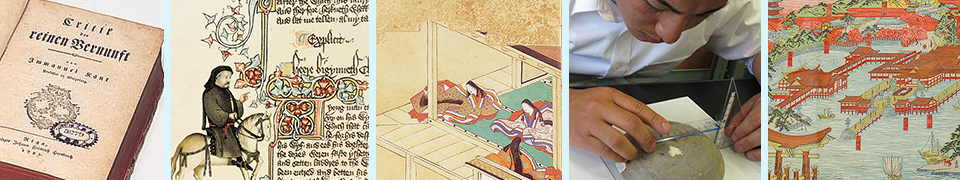
 Home
Home