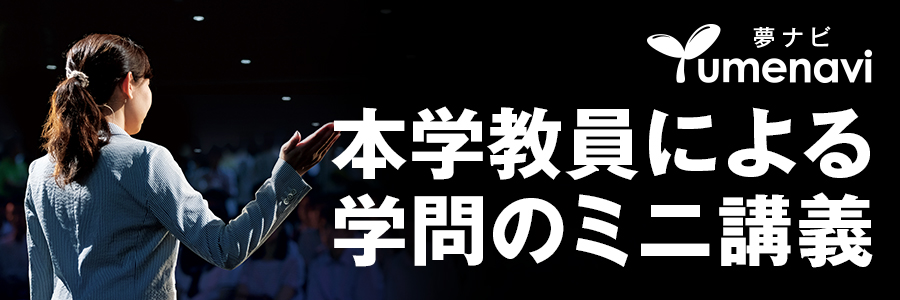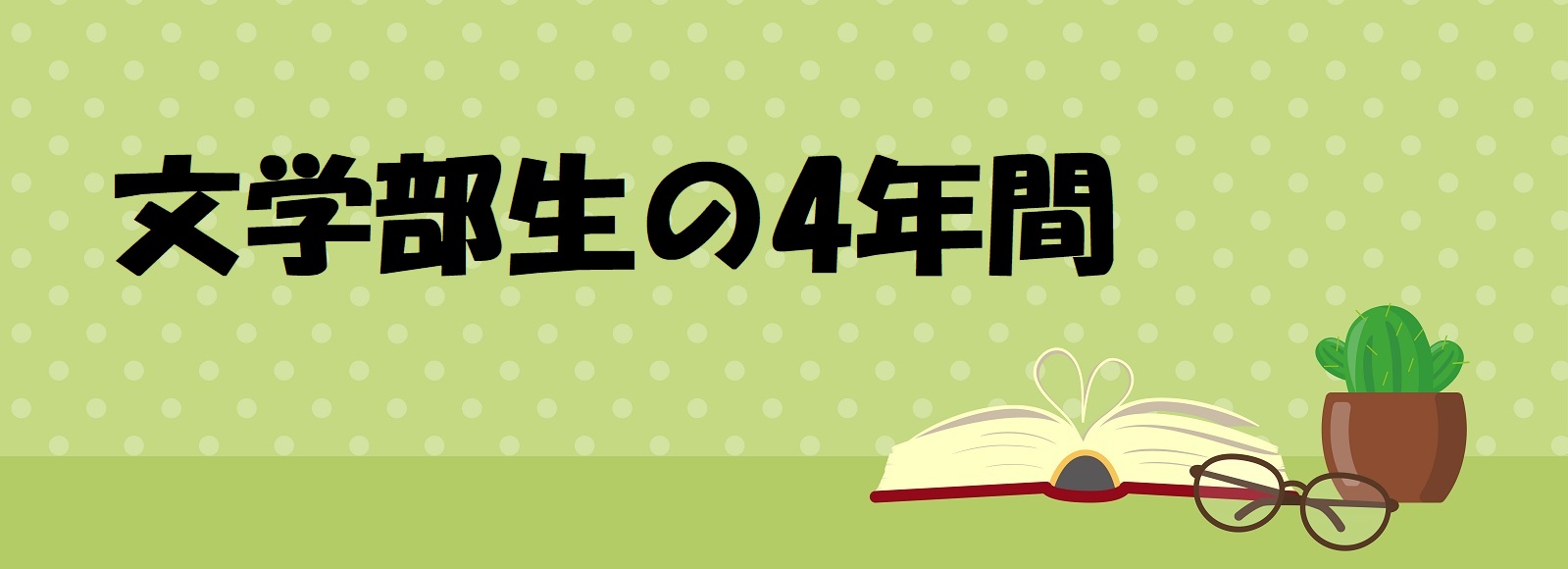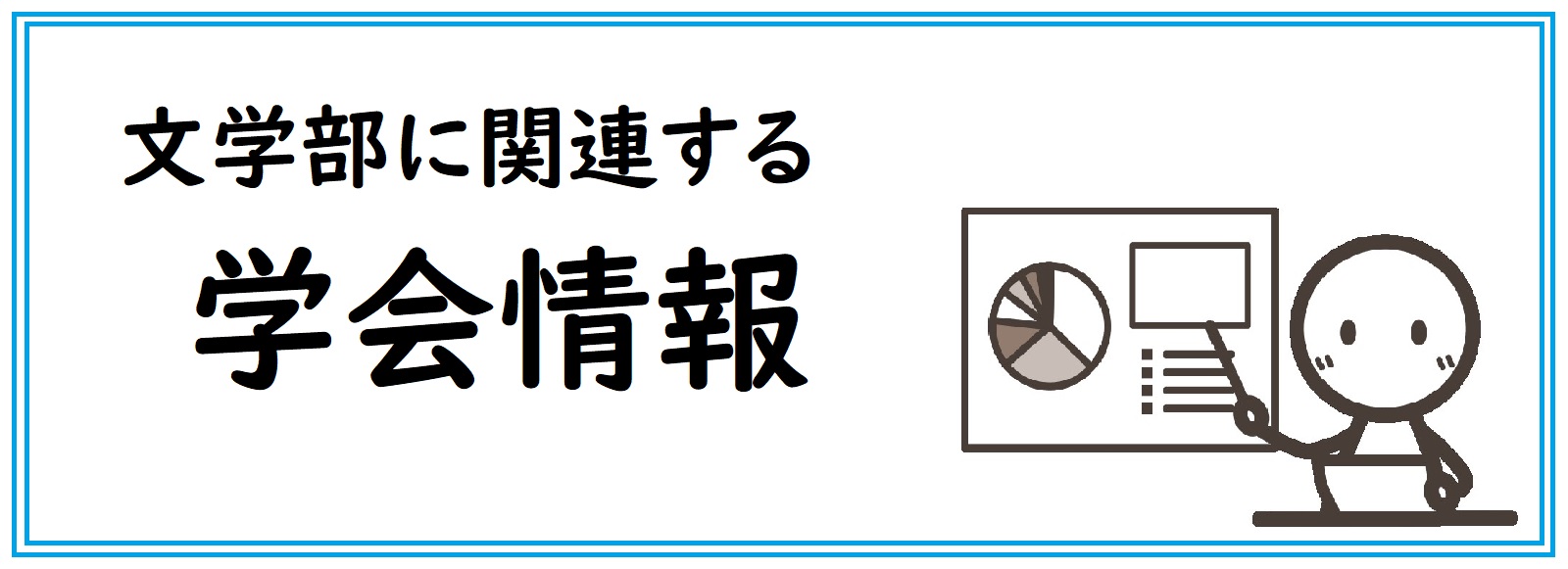陸游(1125~1210)はネコ派の人だったようです。「猫に贈る」という詩に、
裹塩迎得小狸奴 塩を裹みて迎え得たり 小狸奴
尽護山房万巻書 尽く護る 山房 万巻の書
と詠い、大切な蔵書をネズミから守ってくれるネコに感謝の意を表してこの詩を贈っています。陸游の故郷である山陰(浙江省紹興市)の辺りではよそからネコをもらう際、お礼に塩を少し包んで渡す風習がありました。その地方の方言では「塩」は「縁」と発音がよく似ていたからだそうです。「狸奴」はネコの雅称。ネコよりタヌキの方が雅やか、ということなのでしょう。陸游にはネコを詠う詩が二十首あまりあって、飼い猫に「雪児(シロ)」「粉鼻(ハナジロ)」「小於菟(コトラ)」といった名前を付けていたことも分かっています。北宋の梅堯臣(1002~1060)もネコ派の人だったらしく、「猫を祭る」という詩を作って愛猫の死を悼んでいます。
自有五白猫 五白の猫を有ちてより
鼠不侵我書 鼠 我が書を侵さず
表を黒く、裏を白く塗ってある木片を五つ投げて賭けをする樗蒲という遊びがあり、五つとも白が出ることを「五白」と呼んだそうです。その「五白」を名前にしたところからすると、梅堯臣のネコは真っ白だったのでしょう。陸游のネコと同じように書物をネズミから守ってがんばったみたいです。

おがわにゃあ
杜甫(712~770)の「草堂」という少し長い詩に次のような句を見ることができます。
旧犬喜我帰 旧犬 我が帰るを喜び
低徊入衣裾 低徊して衣の裾に入る
生涯の大半を漂泊の内に過ごした杜甫ですが、乾元2(759)年末から5年半ほどは成都を中心とする蜀(四川省)の地に落ち着き、やや安定した時期を過ごすことができました。成都に入った翌年の春には浣花草堂を営みました。杜甫にとって恐らくは生まれて初めて手に入れた我が家だったはずです。残念ながらこの5年半がまったくの平穏無事の日々だったというわけではなく、大風に草堂の屋根を吹き飛ばされたり、宝応元(762)年7月から広徳2(764)年晩春まではいろいろな事情が重なって成都に帰れなくなったりしました。「草堂」詩は久し振りに我が家に帰ることができた時の感慨を詠います。留守の間も飼い主のことをちゃんと覚えていて、喜びのあまり杜甫の足下を駆け回り、裾にまとわりつく様子を「低徊入衣裾」と描写して、イヌ好きにはたまらない表現でしょう。「旧犬」というのはもとから飼っていた犬という意味だと思いますが、中国の古い詩では他の用例がほとんど見当たらない語なのです。当時の俗語だったかもしれませんし、或いは杜甫自身が創作した語なのかもしれません。杜甫には「旧犬」を使った詩がもう一首あります。乾元2年春の作である「舎弟の消息を得たり」という詩に、
旧犬知愁恨 旧犬 愁恨を知り
垂頭傍我床 頭を垂れて我が床に傍う
とあるのがそれです。「旧犬」には私の愁いや恨みが分かるのか、うなだれて私のベッドに寄り添ってくれる。イヌを飼ったことのある人なら容易に目に浮かべることのできそうな光景だと思います。こちらには昔の学者さんが『晋書』という歴史の本に見える陸機(261~303)の故事を用いたのだと注を付けています。陸機は呉(江蘇省)の人で、やはりたいへん優れた詩人ですが、黄耳という名の足の速いイヌを飼っていました。洛陽に寄寓していた時、長く故郷からの便りがなかったので黄耳に「我が家 絶えて書信無ければ、汝 能く書を齎して消息を取るや不や」と声を掛けると、黄耳は尻尾を振って一声「ワン」。手紙を竹筒に入れて首に繋いでやると、そのまま南に走って陸機の故郷にたどり着き、今度は返事を携えて洛陽に帰って来ました。杜甫はイヌ派の人だと思うのですが、愛犬の名前は分かりません。

おがわゆう

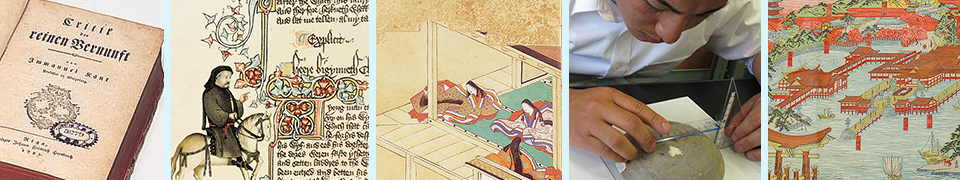
 Home
Home