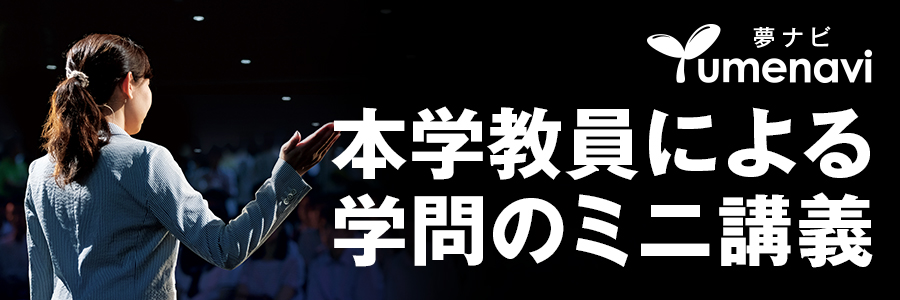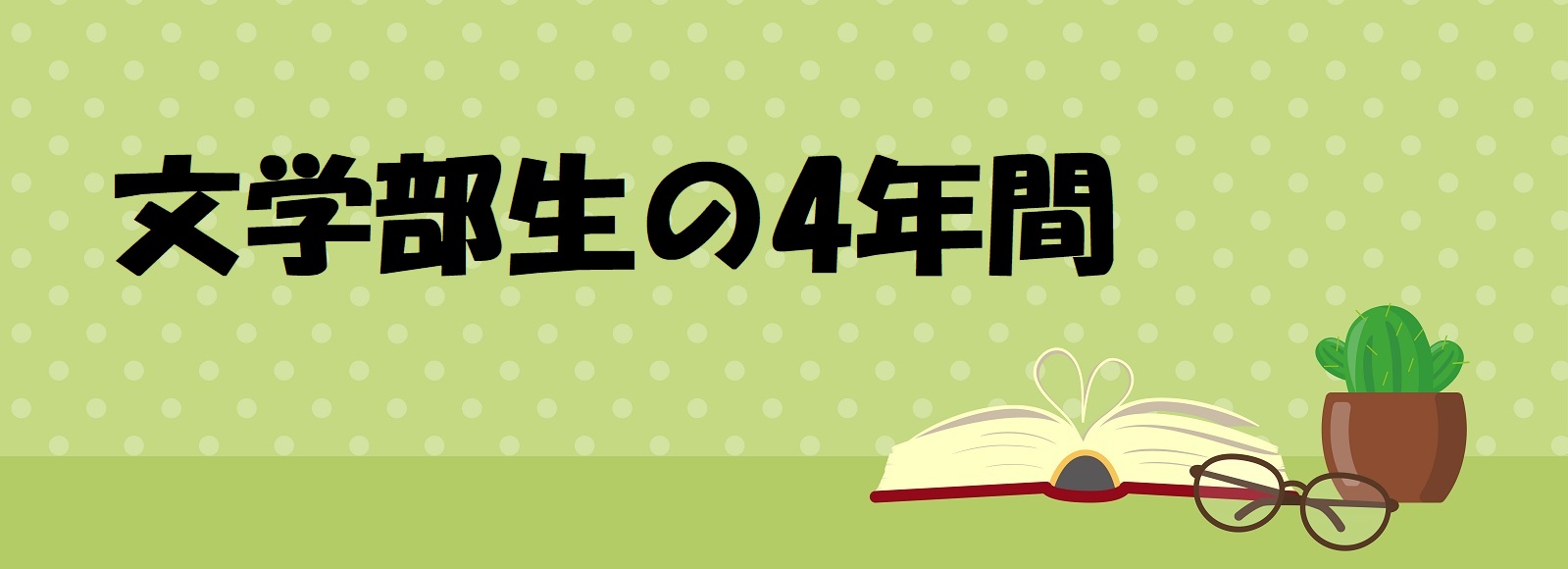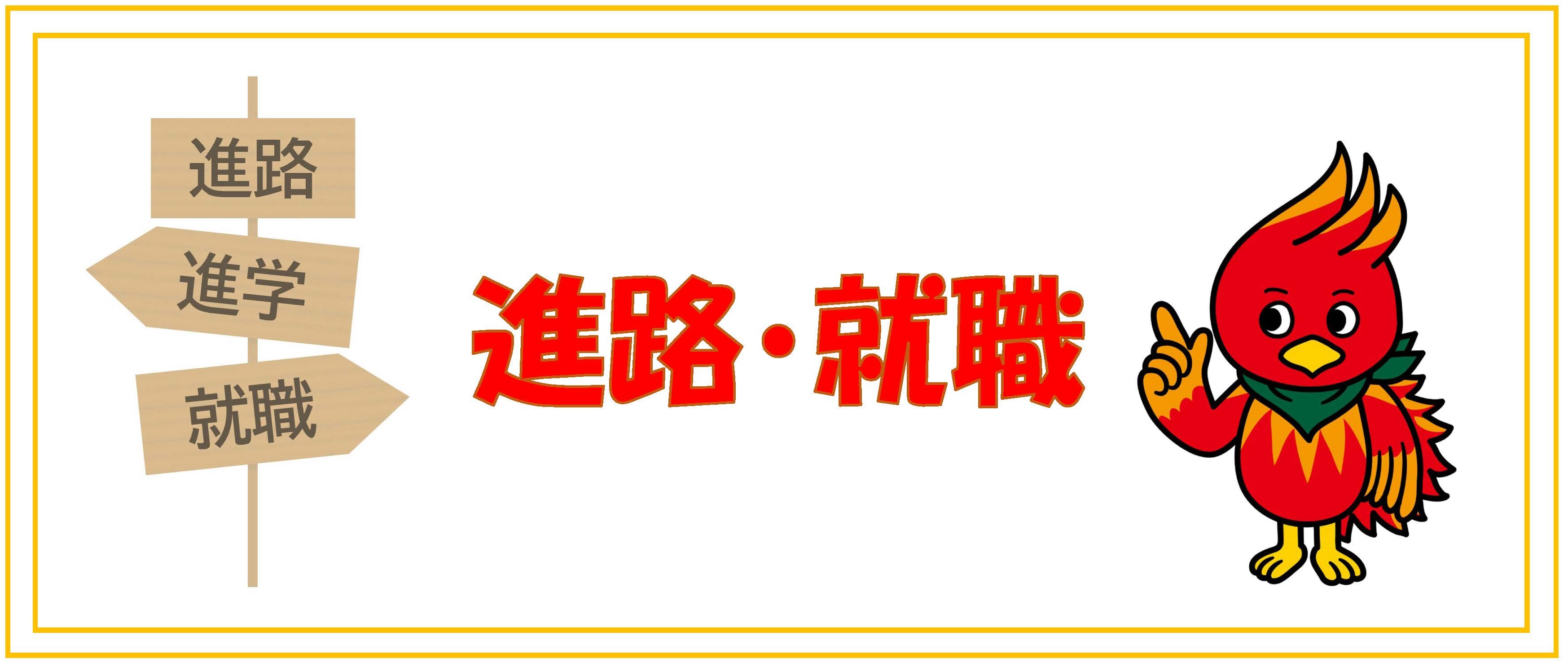私の専門は、明治大正期を中心とする日本近代文学、戦後台湾の日本語文学です。研究活動上、これまで様々な文献を探索、調査、読解し、その評価と位置づけを行ってきました。一般的には、文学と言えば実学からほど遠く、役に立たない学問(虚学)として軽視、敬遠されがちですが、むしろその逆であり、テクスト(文学作品)を精読する力は、まさに自己と世界を読む力に直結すると実感しています。そのことを以下二点から述べたいと思います。

著者寄稿書の一部
第一に、私たちはテクストを読むことを通じて、自らの価値観をより豊かにする多くの他者、ことばに出会うことが可能となります。
もちろん、現代ではインターネット上において、多種多様な人々の言語や映像の洪水の中に身を置くことは容易なのですが、果たしてそこでは本当に「読む」という行為が遂行されていると言えるでしょうか?
時代を超えて残されてきたテクスト=ことばの織物を精確に「読む」ためには、その資料が生まれた時代への理解や、語られている内容と配列(物語構造)の把握、語られていないこと(空白)への気づきなど、読み手の積極的な働きかけが必要です。つまり「読む」とは、非常な労力を要する一つの創造行為であり、ネット上の画面を単に「眺める」こととは異なります。この「読む」という主体的な創造行為を繰り返して身につけることによって初めて、私たちは古今東西のテクストに刻まれた人々の声と価値観と真に出会うことができ、他者のことばをも「我がこと」として考えることができます。そして、自らがそうして体得したことばに支えられ、自身の生の選択肢をより豊かなものに変える力を得るのではないでしょうか。
第二に、私たちはテクストを読むことを通じて、自らを取り巻く世界の構造を客体化する視点を得ることができます。
無論、一人の人間が現在進行中である自身が生きている時間と社会を完全に客観視することは不可能です。しかし、文学テクストという紙の上の黒いインクの染みの羅列に過ぎないものが、なぜ読む者の心を動かすのでしょうか?そのシステムを考察する営みを続けることによって、より巨大で流動的なテクストである現実世界を「読む」能力も自ずから身につきます。その能力により、私たちは今、どのような世界に生きているのか、或いは、今なぜ自分がこんなにも生きることが悲しく、辛く、苦しいのかといったことを精確に認識することができるようになります。それは明日を生きていくため、自らが自らの人生の主人公になるために欠かすことのできない能力です。こうした読解・認識能力は人間という生物に与えられた天恵であり、智慧と言えるのではないでしょうか。
以上のような把握からすれば、文学研究という学問は、まぎれもない実学ということになります。それは大学四年間、否、一生かけて学んでも汲み尽くせぬほどの深い泉なのです。

ゼミ新歓二次会

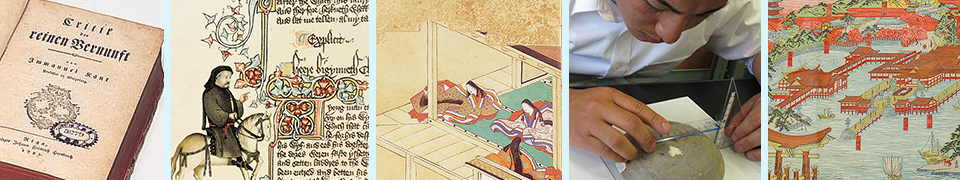
 Home
Home