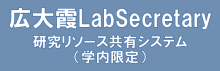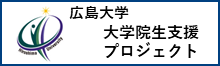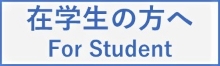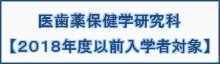AAPM 67th Annual Meeting & Exhibitionに参加して
この度、2025年7月27日~30日にアメリカ合衆国のワシントンDCで開催されたAAPM 67th Annual Meeting & Exhibitionに参加いたしました。私は、「Exploring NSCLC Microenvironments: Multi-Score Survival Models Integrationg Radiomics-Based Regional Imaging Features and Genomics」という題目で口頭発表を行いました。本研究では、早期非小細胞肺がん(NSCLC)患者を対象に、マルチオミクス情報を組み合わせたマルチスコアを用いて予後予測モデルを構築しました。さらに、遺伝子発現量情報をもとに各スコアに対応するエンリッチメント解析を行い、予後を分ける生化学的作用の探索を試みました。本研究で用いたオミクス情報は、CT画像から得た定量的画像特徴と腫瘍組織の遺伝子発現量です。従来は腫瘍全体から抽出された画像特徴を主に用いますが、本研究では腫瘍の周辺部や境界領域など、関心領域を絞った解析も行いました。その結果、様々な視点からの解析が可能となり、予測精度の向上と、より詳細な領域に特化した生化学的機能の解明を図ることができました。
国際学会での口頭発表は今回が初めての経験でした。発表練習や質疑応答への対策など十分に準備を重ねたつもりでしたが、振り返るとまだ改善すべき点も多くありました。それでも本番では、聴衆に伝わる英語で堂々と発表することができ、自身にとって非常に大きな成果となりました。
また、本学会への参加を通して、国内との学会全体の熱量や規模の違いを実感するとともに、最先端の研究に直接触れることで、世界の研究動向を学ぶ大変貴重な機会となりました。
今回の発表にあたり、ご指導と発表の機会を与えてくださった研究室の皆様、ならびにご支援いただきました大学院生海外発表支援関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。
| 氏名 | 研究室名 | 国際学会名 |
|---|---|---|
| 岸 美里 | 放射線腫瘍学 | AAPM 67th Annnual Meeting & Exihibition |
| 李 暁婉 | 国際保健看護学 | The 6th West China Internatonal Nursing Conference |
| 麻田 恭之 | 細菌学 | ASM MICROBE |
| 大段 慶十朗 | 細菌学 | ASM MICROBE |
| 田所 剛志 | 消化器・移植外科学 | ASM MICROBE |
| 三枝 義尚 | 消化器・移植外科学 | World Transplant Congress 2025 |
| 角岡 柚花 | 放射線腫瘍学 | AAPM 67th Annnual Meeting & Exihibition |
| 華岡 晃生 | 漢方医学 | 21st International Congress of Orental Medicine |
| 奥垣 智仁 | スポーツリハビリテーション学 | European Society for Movement Analysis in Adults and Children (ESMAC) 2025 |
| 髙上 凌弥 | スポーツリハビリテーション学 | European Society for Movement Analysis in Adults and Children (ESMAC) 2025 |
| 山﨑 恵里佳 | 口腔腫瘍制御学 | ICOMS 2025 |
| 衞藤 木綿花 | スポーツリハビリテーション学 | European Society for Movement Analysis in Adults and Children (ESMAC) 2025 |
| 小柳 円香 | スポーツリハビリテーション学 | European Society for Movement Analysis in Adults and Children (ESMAC) 2025 |
| 濵口 樹 | スポーツリハビリテーション学 | European Society for Movement Analysis in Adults and Children (ESMAC) 2025 |
| 松尾 勝弘 | 口腔保健疫学 | International Association for Dental Research (IADR) |
岸 美里(博士課程2年 医歯薬学専攻 医学専門プログラム 放射線腫瘍学)

李 暁婉(博士課程後期3年 総合健康科学専攻 保健科学プログラム 国際保健看護学)

Attendance on The 6th West China International Nursing Conference
I attended the 6th West China International Nursing Academic Conference, held in Chengdu, China, from September 25–27, 2025, and presented my research titled “Association between Social Support and Caregiving Preparedness among Caregivers of Children Newly Diagnosed with Acute Lymphoblastic Leukemia.”
This cross-sectional study, conducted at the Department of Pediatric Hematology-Oncology, West China Second Hospital of Sichuan University, aimed to assess caregiving preparedness and examine its association with social support among caregivers of newly diagnosed children with acute lymphoblastic leukemia. A total of 177 caregivers participated between March 2024 and January 2025. The results showed that higher levels of social support were significantly associated with greater caregiving preparedness. All three components, including objective support, subjective support, and support utilization, were positively associated with preparedness. These findings suggest that interventions enhancing caregivers’ social support may help improve caregiving preparedness in the early phase of leukemia treatment.
Participating in this international conference provided an excellent opportunity to share my findings and engage with nursing researchers and clinical professionals from various institutions. Through in-depth discussions, I received valuable feedback regarding the conceptual and methodological aspects of my research, particularly on how to integrate social support strategies into caregiver education and family centered care programs.
I was greatly honored to receive the Second Prize for Oral Presentation at this conference. This recognition has further motivated me to continue exploring ways to strengthen caregiver preparedness and psychological support for families of pediatric oncology patients.
Finally, I would like to express my sincere gratitude to my supervisors and colleagues for their kind guidance and to the organizing committee of the West China International Nursing Academic Conference for providing such an inspiring platform for academic exchange and collaboration.
麻田 恭之(博士課程3年 医歯薬学専攻 歯学専門プログラム 細菌学)

American Society for Microbiology 2025に参加して
2025年6月19日から23日にかけて、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルスにて開催された American Society for Microbiology 2025 に参加いたしました。本学会は微生物学分野において世界最大規模を誇る国際学会であり、感染症学、抗菌薬耐性、マイクロバイオーム解析など多岐にわたる最新研究が発表され、国際的な議論が活発に行われました。私は「鼻腔および口腔における黄色ブドウ球菌とコリネバクテリウムの相互作用」に関する研究成果をポスター発表として報告いたしました。本研究では、脂肪酸に対する耐性の違いや菌種間の相関関係を統計学的に解析し、鼻腔細菌叢の構造に影響を及ぼす仕組みについて検討しました。発表の場では、欧米をはじめとする多くの研究者から質問や意見をいただき、特に黄色ブドウ球菌制御の臨床的意義や細菌間相互作用を応用した感染制御の可能性について議論が深まり、大変有意義な経験となりました。今回の学会参加を通じて、世界における研究動向を直接学ぶことができ、自身の研究テーマが国際的にも重要であることを改めて実感いたしました。今後は、ここで得られた知見を基盤として、基礎研究と臨床応用の両面からさらなる研究の発展に努めてまいります。
大段 慶十朗(博士課程4年 医歯薬学専攻 歯学専門プログラム 細菌学)

ASM Microbe2025に参加して
2025年6月19日から23日にアメリカ合衆国で開催された「American Society for Microbiology Microbe 2025」において、「Analysis of Staphylococcus capitis strain with antibacterial activity against antimicrobial resistant bacteria」という題目で発表を行いました。薬剤耐性菌は世界的に深刻な問題であり、新たな抗菌剤の開発が求められています。本研究では、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)およびバンコマイシン耐性腸球菌(VRE)を含むグラム陽性細菌に対して強い抗菌活性を示すStaphylococcus capitisが産生する2種類の抗菌ペプチドを明らかにしました。鼻腔由来の18株を用い、MRSA MW2株に対する抗菌活性をsoft agar overlay法で評価したところ、強い抗菌活性を示す菌株を見出しました。さらにVRE、Clostridium difficile、Bacillus coagulansに対しても活性を認めました。全ゲノム解析により、プラスミド上にMicrococcin P1およびCapidermicinの遺伝子を確認し、精製と質量分析により両者の産生を証明しました。プラスミド脱落株では抗菌活性が消失したことから、これらのペプチドが活性の要因であると考えられました。本研究成果は、薬剤耐性菌に対する新規抗菌ペプチド開発への応用が期待されます。御支援により得られた貴重な発表機会に、心より感謝申し上げます。
田所 剛志(博士課程3年 医歯薬学専攻 医学専門プログラム 消化器・移植外科学)

American Society for Microbiology 2025に参加して
この度、2025年6月19日から23日にアメリカ合衆国カリフォルニア州のロサンゼルスで開催されました、American Society for Microbiology 2025に参加し、「The effects of negative pressure on bacteria.」という演題でポスター発表を行いました。
近年、臨床現場では難治性創傷に対してNPWT(Negative pressure Wound Therapy)が普及し、創傷治癒促進が期待されていますが、細菌に対する陰圧環境の影響については未だ不明の点が多いです。我々は、圧力刺激装置を用いて細菌に陰圧付加を行い、菌やbiofilmの変化を観察しました。すると、陰圧環境では、菌由来のbiofilm形成能に影響を与えることが判明しました。特に、胆汁酸塩存在下で増強したbiofilmに陰圧を付加すると、有意にbiofilm形成が抑制されました。つまり、陰圧環境は抗biofilm的作用を有しており、NPWTは感染症に対する新たな治療戦略の1つになる可能性が示唆されました。
今回、初めて国際学会に参加し、大変緊張しましたが、英語でのプレゼンや様々な国籍の研究者から質問を頂いたことは、自分の研究の質を高める有意義な機会となりました。特に、細菌学分野の学会参加も初めてであったので、非常にいい経験となりました。私の取り組んでいる研究背景は、特に消化器・移植外科の臨床現場において考えるテーマであったため、微生物学専門家の方々からすると斬新な研究に映ったと思います。そのように、消化器・移植外科医だからこそ発想されるテーマであることを再確認できた学会でした。
最後になりますが、研究に関してご指導いただき、このような貴重な機会を与えてくださいました大段 秀樹教授、小松澤 均教授、消化器・移植外科学教室ならびに細菌学教室の皆様、ご支援いただきました大学院生海外発表支援関係者の皆様に感謝申し上げます。
三枝 義尚(博士課程2年 医歯薬学専攻 医学専門プログラム 消化器・移植外科学)
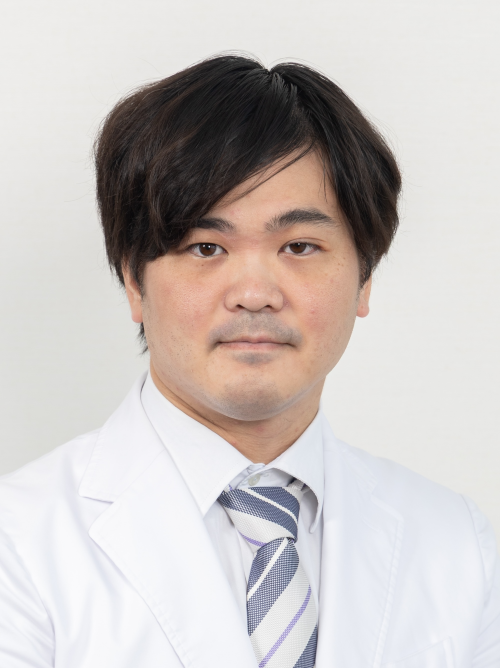
World Transplant Congress (WTC) 2025に参加して
この度、2025年8月2日~6日の5日間、米国、San Fransicoで開催されたWorld Transplant Congress (WTC) 2025に参加しました。
私は「The Utility of the Endoscopic Device "Vasoview Hemopro 2" for Harvesting the Great Saphenous Vein in Vascular Reconstruction During Living-Donor Liver Transplantation」というタイトルでポスター発表を行いました。生体肝移植において、血管再建のために大伏在静脈を採取するのですが、その採取にあたり当科で新規に導入した内視鏡血管グラフト採取デバイスであるVasoview Hemopro 2を用いた手術成績に関して発表を行いました。本デバイスを用いた血管グラフト採取は従来法と比較して総手術時間を延長することなく、創部の整容性を向上させることができ、術後の血管グラフト機能も同等であることが示されました。
今回は私にとって初めての国際学会への参加・発表であり、大変得難い機会となりました。世界各国からの参加者による基礎・臨床に関する最先端の発表は大変ハイレベルで非常に勉強になりました。また、自身の発表では外国語での発表の難しさと自分の未熟さを痛感しつつも、バックグラウンドや母語の違う専門家との質疑応答やディスカッションを通じて、今後の自身の英語運用能力を含めた発信力をさらに磨いていくモチベーションとなりました。
最後に、この度の海外発表にあたり御指導いただいた大段 秀樹教授、大平 真裕先生および研究室の皆様に感謝申し上げます。また、国際学会発表を御支援いただきました大学院生海外発表支援に関わる皆様に心より御礼申し上げます。
角岡 柚花(博士課程1年 医歯薬学専攻 医学専門プログラム 放射線腫瘍学)

American Association of Physicists in Medicine (AAPM) 67th Annual Meeting & Exhibitionに参加して
2025年7月27日~30日に米国ワシントンD.C.で開催されたAmerican Association of Physicists in Medicine(AAPM)第67回年次総会において、口頭発表を行いました。演題は「AI-Driven Drug Discovery through an Interactive Analysis of Radiomics and Biological Insights in Glioblastoma」で、神経膠芽腫(GBM)患者のMRIから得られるラジオミクス特徴(画像特徴)と臨床情報を統合し、生存予後を予測するとともに、画像特徴の生物学的背景を明らかにして薬剤探索へ接続する包括的フレームワークをご報告いたしました。具体的には、複数シーケンスMRIから画像特徴量を抽出しリスク層別化を実現いたしました。さらに、遺伝子データを用いた経路・免疫シグナルの富化解析により、画像表現型に対応する分子機構を推定し、その知見に基づき有望な薬剤候補を提示いたしました。会期中は放射線腫瘍学、医用画像AI、データサイエンスの専門家と活発に議論し、外部検証や前向き試験設計、モデルの説明性、臨床実装に向けた評価指標の整備など、多くの示唆を得ました。今後は国際的なネットワークを活かし、GBMの個別化医療に資する実用的なAI基盤の確立をさらに推進してまいります。
最後に、本学会発表にあたりご指導くださった先生方、ならびにご支援いただいた大学院生海外発表支援関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。
華岡 晃生(博士課程2年 医歯薬学専攻 医学専門プログラム 漢方医学)
第21回国際東洋医学会学術大会(ICOM21)に参加して
2025年8月30日から31日にかけて、台湾の台北で開催された第21回国際東洋医学会学術大会(ICOM21)に参加し、「Efficacy of Maobushisaishinto (麻黄附子細辛湯) for "Knee Collapse Sensation with Dizziness": A Case Report Based on Keiho Theory (経方理論)」という演題で発表を行いました。
本研究は、半年前からの進行性の「膝折れ感」と浮動性めまいに悩む58歳の女性患者に関する症例報告です 。西洋医学的な精密検査では何ら異常が認められませんでした。そこで、伝統医学の中でも気の循環経路を体系的に重視する経方理論(Keiho theory)に基づき診察したところ、後通の衛気が不足という特殊な病態と診断しました。 この診断に基づき、麻黄附子細辛湯(Maobushisaishinto)を処方した結果、6週間で症状は完全に消失しました 。
本症例は、現代の西洋医学的アプローチでは診断・治療が困難であった症状に対し、経方理論という体系的なフレームワークが有効な治療法を導き出したことを示しています 。
私にとって、この国際学会はアジア各国の東洋医学の専門家と直接意見交換ができる貴重な機会となりました。発表を通じて、今回の症例を多角的な視点から見つめ直すことができ、今後の臨床や研究への取り組みを一層深めるための大きな刺激を受けました。この経験を糧に、今後も日々の診療や研究に邁進していきたいと思います。
最後になりますが、本学会発表にあたりご指導くださった先生方、漢方医学教室の皆様、ならびにご支援いただいた大学院生海外発表支援の関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。
奥垣 智仁(博士課程前期2年 総合健康科学専攻 保健科学プログラム スポーツリハビリテーション学)

European Society for Movement Analysis in Adults and Children (ESMAC) 2025に参加して
2025年9月8日から9月13日にスイスのバーゼルで開催された「European Society for Movement Analysis in Adults and Children (ESMAC) 2025」に参加いたしました。私は「Relationship Between Foot Mobility Magnitude and Navicular Displacement During the Stance Phase of Gait」という題目でポスター発表を行いました。本研究では、中足部可動性の静的指標であるFoot mobility magnitudeと、歩行中の内側縦アーチの動態との関係を調査しました。中足部可動性が高い足では、歩行立脚期の64-74%で内側縦アーチ高が低値を示しており、歩行立脚後期に内側縦アーチを挙上させるウィンドラス機構が機能低下を起こしている可能性が示唆されました。
本学会は小児や成人、健常者だけでなく脳性麻痺患者の歩行分析に特化した学会であり、学会に伴ってGait Courseという動作解析や歩行分析の勉強会も行われます。歩行分析の最新の知見を得ることができ、非常に有意義な時間となりました。医療従事者だけでなくエンジニアも参加する学会で、様々な視点から「歩行」をみる、といった点でとても貴重な機会となりました。
最後になりますが、本学会への参加にあたり、今回の貴重な機会を与えてくださったスポーツリハビリテーション学研究室の先生方、ご支援いただいた大学院生海外発表支援の関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。
髙上 凌弥(博士課程前期2年 総合健康科学専攻 保健科学プログラム スポーツリハビリテーション学)
European Society for Movement Analysis in Adults and Children (ESMAC) 2025に参加して
この度、2025年9月11日〜13日にスイスのバーゼルで開催されたEuropean Society for Movement Analysis in Adults and Children (ESMAC) 2025へ参加し、「The effects of a prosthetic walking practice using virtual reality on gait kinematics: a pilot study」という題目でポスターによる発表を行いました。
私の発表した研究は、Virtual Reality (VR)を用いた義足歩行練習が歩行動作に与える影響を明らかにすることを目的としたパイロットスタディでした。健常成人を対象に、模擬義足を装着させ、VR映像を視聴しながら平行棒内で足踏み練習を実施するVR群と、VR映像を視聴しないControl群を比較し、義足歩行練習前後の歩行動作解析を行いました。その結果、VR群では歩幅や模擬義足側股関節の屈曲角度、骨盤回旋角度の増大が見られ、非模擬義足側の推進力向上が示唆されました。これらの結果は、VR映像による視覚的な効果が義足歩行能力向上を促進する可能性を示していると述べました。
発表では、義足リハビリテーションにおいて、動作解析を専門とする研究者と意見交換をすることができました。特にVR映像についての質問が多く、どのような映像を見せているのか、映像の速度は対象の最適な速度に合わせているのか、など研究の細かい部分まで話し合うことができました。私自身2回目の国際学会参加、初めての英語を用いたポスター発表を経験させていただきました。VR映像の設定方法やより正確な動作解析の手法について学ぶことのできた貴重な機会となり、今後はより臨床応用に近い形で研究を発展させたいと考えています。
山﨑 恵里佳(博士課程3年 医歯薬学専攻 歯学専門プログラム 口腔腫瘍制御学)

International Conference on Oral and Maxillofacial Surgeryに参加して
2025年5月22日から25日にかけて開催された26th International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery(ICOMS)にて、治療前の骨格筋量およびIBPS(inflammation-based prognostic scores) が口腔がんの予後に与える影響について発表を行いました。この発表を通じて、自身の研究課題や今後の展望について深く見つめ直す機会となり、研究に対する理解が一層深まりました。
特に印象的だったのは、英語による質疑応答の場面です。海外の参加者からの質問に対して、その場で英語で応答するという貴重な経験を得たことで、自身の研究を国際的に発信する自信がつき、今後の研究活動への意欲にも大きな刺激となりました。また、専門的な内容を的確に伝える語彙力や表現力、そして相手の意図を正確に汲み取ったうえで論理的に自分の考えを展開する英語でのコミュニケーション力の重要性を痛感しました。
今後は、日常的な英語学習の継続に加え、プレゼンテーションスキルの向上にも努め、国際学会の場でより実りある議論が行えるよう努力していきたいと考えています。今回の学会参加は、知識のアップデートだけでなく、人とのつながりや自身の成長を実感する大変貴重な機会となりました。このような経験ができたのも、日頃よりご指導くださっている先生方のおかげであり、心より感謝申し上げます。次回のICOMSは2年後、ドイツ・ベルリンでの開催が予定されています。今回得られた学びとご縁を大切にし、さらに成長した姿で参加できるよう、今後も臨床と研究に励んでまいります。
衞藤 木綿花(博士課程前期2年 総合健康科学専攻 保健科学プログラム スポーツリハビリテーション学)
European Society for Movement Analysis in Adults and Children (ESMAC) 2025に参加して
この度、2025年9月11日~13日にスイスのバーゼルで開催されたEuropean Society for Movement Analysis in Adults and Children (ESMAC) 2025へ参加し、「Dynamic postural stability and compensation strategy for balance deficit during lateral jump landing in individuals with chronic ankle instability」という題目でポスター発表を行いました。また本研究は、ベストポスターにノミネートしていただき、1分間の口頭発表をする機会をいただきました。
足関節捻挫は頻発するスポーツ外傷で、約40%の人が慢性足関節不安定症(Chronic ankle instability; CAI)に移行すると言われています。CAIを有する者は側方方向への不安定性が大きいことが分かっており、前額面上の動作を評価する必要があります。また、動的姿勢安定性を評価する指数(Dynamic Postural Stability Index; DPSI)を用いた研究では、CAIを有する者は動的姿勢安定性が低下することが言われています。しかし、側方方向へのジャンプ着地課題で動的姿勢安定性を研究したものは少なく、代償動作に着目した研究は限られています。そこで本研究では、若年成人をCAI群と健常群に群分けし、側方ジャンプ着地時のDPSIと下肢・体幹の関節角度を測定し、比較しました。結果として、CAI群と健常群のDPSIに有意差は見られませんでした。しかし、関節角度では股関節屈曲角度のみがCAI群で有意に増加していることがわかりました。本研究から、CAIを有する者は股関節屈曲戦略によって、足関節の不安定性を代償し、動的姿勢安定性を高めていることが示唆されました。
初めての学会発表、初めての国際学会への参加で、緊張と不安ばかりでしたが、貴重な経験をさせていただきました。語学力、コミュニケーション力を高め、また国際学会で発表ができるように研究を積み重ねていきたいと思います。最後になりましたが、本研究発表にあたりご指導いただきました先生方、研究室の皆様、ご支援いただきました大学院生海外発表支援関係者の皆様に感謝申し上げます。
小柳 円香(博士課程前期2年 総合健康科学専攻 保健科学プログラム スポーツリハビリテーション学)
European Society for Movement Analysis in Adults and Children (ESMAC) 2025に参加して
この度、2025年9月11日~13日にスイスのバーゼルで開催されたEuropean Society for Movement Analysis in Adults and Children (ESMAC) 2025へ参加し、「Does the anterior tibiofibular gap influence subjective ankle instability?」という題目で口頭発表を行いました。
足関節捻挫を初めて受傷した人の約40%は慢性足関節不安定症(Chronic ankle instability; CAI)を発症することが報告されています。CAI症例では、かねてより距骨の変位により距腿関節の不安定性が生じることが複数の文献で報告されており、さらに近年、腓骨の変位も起こっていることがわかってきています。しかし、腓骨の変位により遠位脛腓関節の不安定性が生じるかどうかや、これらの機械的不安定性が主観的不安定性と関連しているかどうかはわかっていませんでした。そこで本研究では、若年成人を健常群とCAI群に分け、距腿関節不安定性を評価するために前距腓靭帯(Anterior talofibular ligament; ATFL)長、遠位脛腓関節不安定性を評価するために遠位脛腓間距離(Anterior tibiofibular gap; ATFG)を超音波画像装置で測定し,比較しました。さらに、CAIの診断基準として一般的に使用されるCumberland ankle instability tool(CAIT)とATFL長およびATFGとの関連も調査しました。結果として、健常群と比較してCAI群で、ATFL長・ATFGともに大きな値を示し、ATFGがCAITスコアの有意な予測因子であることがわかりました。本調査から、繰り返す捻挫を防ぐために、これまで一般的に調査されてきた距腿関節不安定性だけでなく遠位脛腓関節不安定性も評価することが重要であることが示唆されました。
国際学会での発表は2回目で、英語での発表は1回目と比較し自信をもって行うことができました。質疑応答では準備してきたこと以上のことはできませんでしたが、もっと英語に触れて速く英文が作れるように練習したい、また英語論文を書きたいと今後の課題が明確になるいい機会となりました。最後になりましたが、本学会への参加にあたりご支援いただきました大学院海外発表支援関係者の皆様に感謝申し上げます。
濵口 樹(博士課程前期1年 総合健康科学専攻 保健科学プログラム スポーツリハビリテーション学)

The ESMAC(European Society for Movement Analysis in Adults and Children)2025に参加して
この度、2025年9月11日〜13日(Gait Courseを含むと8日〜13日)にスイスのバーゼルで開催されたThe ESMAC(European Society for Movement Analysis in Adults and Children)2025に参加し、「Acute effects of gait training watching virtual reality video of faster speed on comfortable walking」という題目でポスターによる発表を行いました。
近年、Virtual reality(VR)映像を活用したトレーニングやリハビリテーションが増加傾向にあります。VR映像を用いる利点として、「危険な状況を再現できる」「現実では実施困難ない課題を提示することができる」といった点が挙げられます。本研究は、視覚情報による運動錯覚が歩行動作に及ぼす影響を検討することを目的に、視流速度の異なるVR映像を用いたトレッドミル歩行練習を実施しました。健常な男子大学生28名を対象に、トレッドミル速度を2.5 km/hに固定し、VR映像を2.5、4.5、6.0 km/hの3条件で提示して歩行前後の歩行パラメータを比較しました。その結果、トレッドミル速度と映像速度が一致する条件でのみ歩行速度の低下、ストライド時間および立脚時間の延長、ケイデンスの低下が認められました。これらの結果は、視覚情報と身体感覚が一致した環境下ではより慎重な歩行様式が誘発されることを示唆しており、VRを用いた歩行リハビリテーションにおいて、適切な視覚提示条件の設定が重要であることを言及しました。
発表では、健常な男子大学生を対象にVR映像を用いた歩行練習を実施した際の効果と今後の展望について示すことができましたが、被験者に没入感を与える方法や視覚情報以外の感覚情報の統一などに関して貴重な助言をいただきました。私自身初めてのポスターおよび英語での発表を経験させていただき、どんな相手にも伝わる説明の仕方、伝え方を考える大切さや難しさを痛感しました。また、英語でのコミュニケーションに自信がなく、各国の先生方と話せる機会で少しためらってしまいました。今後は英語力を上げることはもちろんですが、積極的に自ら話しかける姿勢を意識して努めていきます。
松尾 勝弘(博士課程3年 医歯薬学専攻 歯学専門プログラム 口腔保健疫学)

IADR General Session, Barcelona, Spainに参加して
2025年6月25日から28日にかけて、スペイン・バルセロナにて開催された「2025 IADR/PER General Session & Exhibition (第103回国際歯科研究学会総会・欧州地域会議)」に参加いたしました。本学会は世界中から歯科研究者が集う最大規模の学術集会であり、最新の研究成果を共有し、国際的な交流を深める貴重な機会となりました。
私は「Association between the number of missing teeth and total mortality (欠損歯数と総死亡との関連)」という演題でポスター発表を行いました。本研究は、日本歯科医師会会員を対象とした全国規模の前向きコホート研究であるLEMONADE研究に基づいており、欠損歯数を「0-4本」「5-8本」「9-18本」「19-27本」「28本」と分類し、総死亡リスクとの関連をCox比例ハザードモデルにより検討しました。その結果、欠損歯数が増えるほど死亡リスクが高まる傾向が認められ、特に19本以上の欠損では有意なリスク上昇が示されました。
会場では多くの研究者から活発な質問や意見をいただき、今後の研究の方向性を考える上で大変有意義な経験となりました。また、口腔の健康が全身の健康や寿命に大きく関与することを改めて実感し、日常臨床や予防活動の重要性を再認識する機会ともなりました。今回の学会参加を通じて得た知見と交流を今後の研究活動に活かしてまいりたいと考えております。

 Home
Home