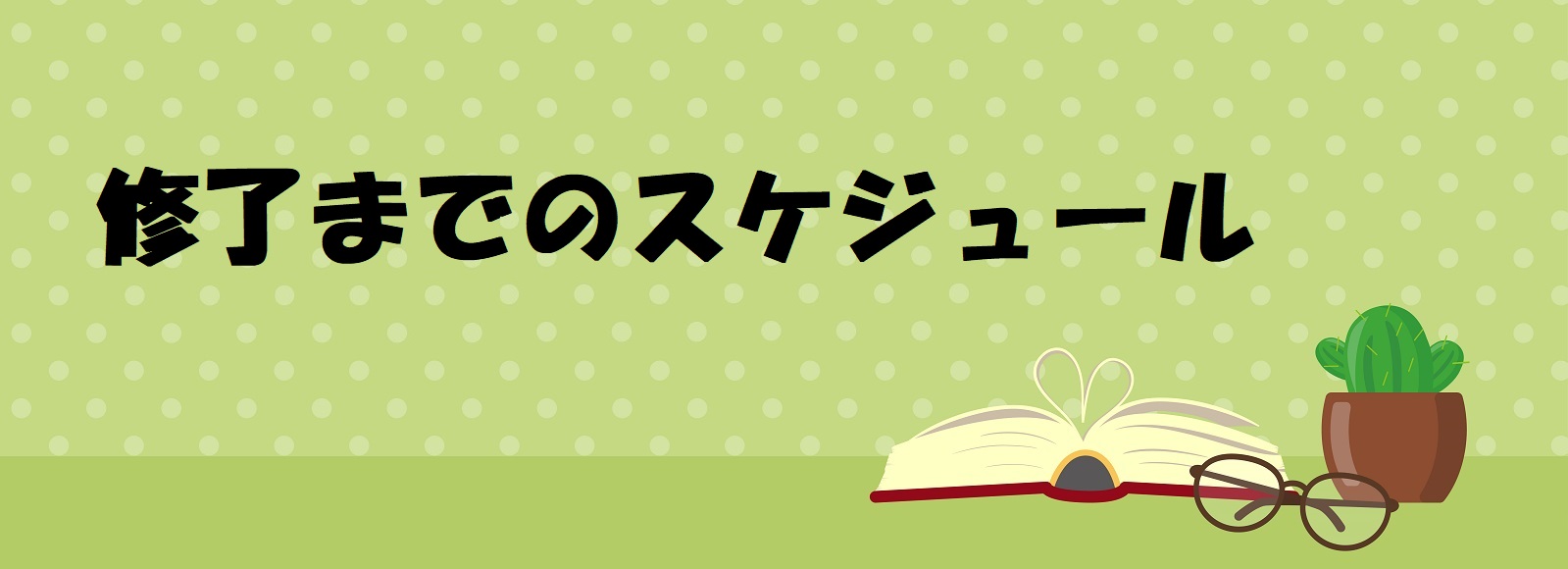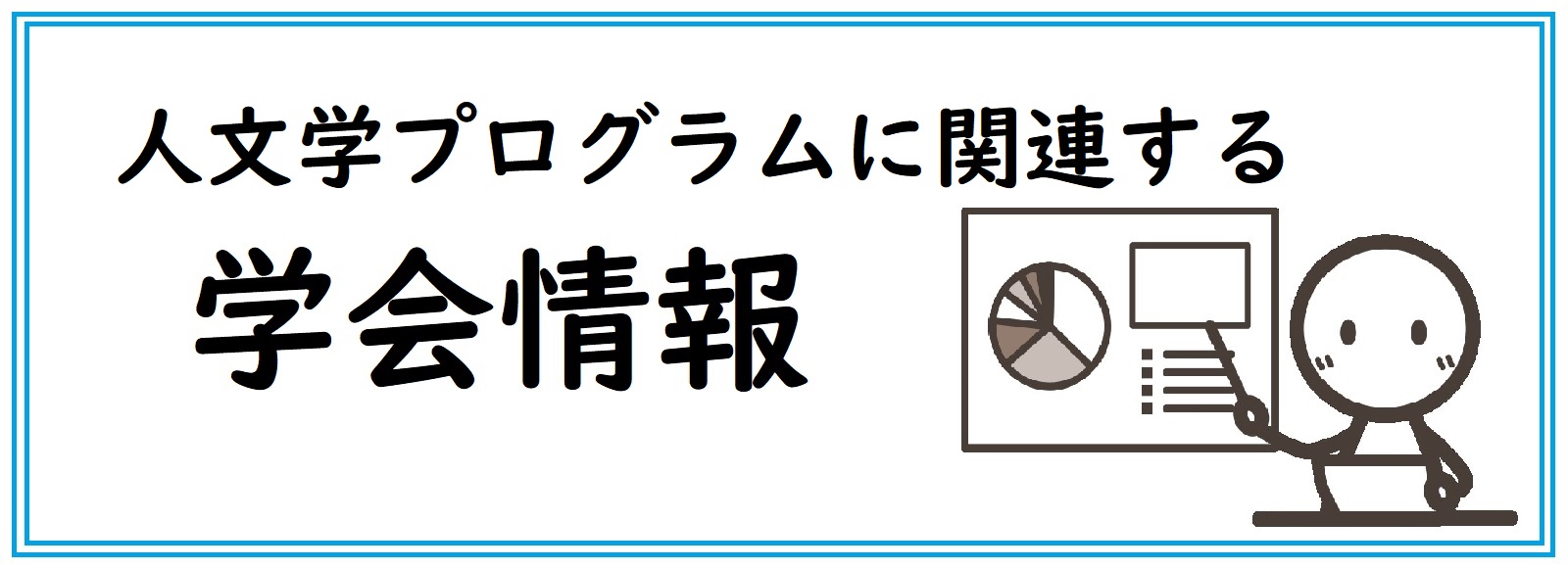東京都出身の原田 一学さん(地理学分野)の声をお届けします。
広島大学大学院人間社会科学研究科人文学プログラムに進学しようと思った理由は何ですか。
私は東京の郊外で育ちましたが、両親が地方出身(母は近畿地方、父は東北地方)だったため、帰省で地方に行く機会が多くありました。文化、産業、景観、気候など、大都市郊外と地方のあらゆる違いを感じながら過ごしていたことから、地方での暮らしに興味を惹かれるようになり、自分にとってなじみのない、東京から離れた島根県の大学に入学しました。学部時代は中国地方の各地をフィールドワークや旅行で訪れたことで、中国地方が好きになり、できれば中国地方で暮らしていきたいとまで思うようになりました。
食を支えるシステムや地方の産業に興味を持っていたことから、農業を対象として研究することになりました。しかし学部時代の短期間ではフィールドワークで得られた情報を整理して成果をまとめることが想像以上に難しく、研究したりないと感じるようになり大学院進学を決めました。進学先を悩んだ結果、これまでに農業地理学の研究者を多く輩出してきた、国内でも有数の地理学の研究教育の拠点である広島大学大学院人間社会科学研究科人文学プログラムの地理学教室に進学しました。これまで研究してきたフィールドである中国地方で一市民として過ごしながら研究ができることも自分にとっては大きな魅力でした。
広島大学や大学院生活の第一印象はどうでしたか。
大学の敷地がとても広く、研究のための施設が非常に充実していることに驚きました。また、人文学プログラムは留学生を多く受け入れていることから、英語や中国語が日常的に飛び交う研究室の環境は新鮮でした。さらに、学部時代にはなかった自然地理学を研究する教員・学生との交流は、自分が触れてこなかった分野の最新研究を知ることができた点で大変刺激的なものでした。
現在どんなことを研究していますか。
少子高齢化や人口流出による社会的変化を受けて、農業を担う人々や食を支えるシステム、そして関連する地域がどのように影響を受けて変化しているのかについて研究をしています。修士論文では、障害者が農業に参画する「農福連携」(農業と福祉の連携)を研究対象として、農家の方々や障害者就労支援施設の職員の方々に聞き取り調査を行い、障害者の農業の担い手としての位置づけや地域的意義について分析しました。

写真1 修論の調査で訪れた茶畑
広島大学での学生生活について教えてください。

写真2 修士論文発表会の様子
授業期間はゼミが週に最大3回あり、特に発表前は論文の精読と発表準備に追われます。M1ではこれに加えて様々な講義を受けて自身の教養を深めることができました。また、地理学研究ではフィールドワークが重視されることから、M1の夏に学部生と一緒に巡検に出かけて調査方法を習得します。この経験を踏まえて、M2の修論執筆にかけて継続的に研究を進めていきます。私の場合、フィールドワークでは休業期間中に農村や山村に通い、一日あたり1~2人ほどにお会いして詳しくお話を伺い、帰ってからデータを整理する、といった調査活動を数週間にわたり積み重ねていきました。
広島大学にある総合博物館では、広島大学の学部生・大学院生で構成される有志のボランティア団体が展示活動を毎年行っており、縁あって私も活動に加わることができました。学生メンバーや多くの教員の方々に支えてもらいながら、自身の専門性を活かした展示活動をすることができたことは、大変でしたが大きな財産となりました。
研究のための費用、趣味の旅行や合唱の費用を賄うため、アルバイトもしながらの研究生活でした。手と足が何本あっても足りないほど忙しく過ごしていましたが、非常に充実していたと思います。
広島大学大学院人間社会科学研究科人文学プログラムは大学院生にとってどのような場所ですか。
広島大学大学院人間社会科学研究科人文学プログラムは、学術界の最先端の研究を行う教員の万全な指導体制のもと自分の研究を深めていくことを軸として、自分の探究心に基づく活動を広島大学を中心に広げていくことができる、研究生活を送る大学院生が過ごす上で魅力的な場所であると思います。
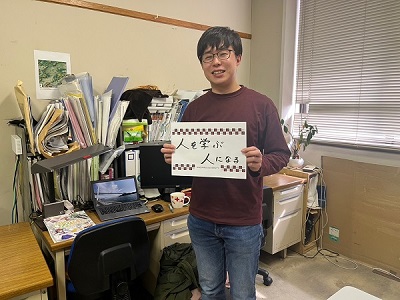
写真3 院生室の自分のデスクにて
将来の夢は何ですか。

写真4 展示活動で作成した展示物
一般的に地理や地図に苦手意識を持つ人も多いと感じますが、地理学の面白さや有用性を、教育を通じて広めていきたいと思っています。また、全国各地にはそれぞれの地域が誇る文化や関連する資料を展示する博物館が数多くありますが、地理学にテーマを定めた博物館は希少であり、それぞれの地域の文化を踏まえつつ地理学の面白さを伝えることをメインとした博物館や展示をつくることがひそかな夢です。
後輩たちに向けてメッセージをお願いします。



 Home
Home