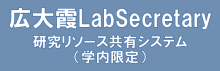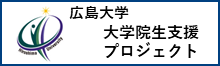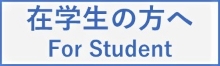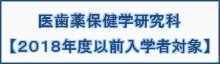AAPM67th Annual Metting & Exhibitionに参加して
2025年7月27日から30日でアメリカ合衆国のワシントンD.C.で開催されたAAPM67th Annual Meeting & Exhibitionに参加しました。私は、「Innovative Biological Adaptive Radiotherapy (BART) Approach for Head-and-Neck Cancer Treatment Interruptions」というタイトルでポスター発表を行いました。
本発表では、頭頸部がん放射線治療における治療の中断に着目し、生物学的モデルに基づいた適応放射線治療(BART)という独自の手法を提案しました.治療の中断が起こると,線量や中断日数により治療効果が低下することが示唆され、線量補償する必要性が明らかとなりました。BARTにより、腫瘍に対しては元の予定されていた線量まで引き上げられる一方で、正常組織への線量を大きく増やさずに補償できることが示されました。発表では、なぜ中断で治療効果が下がるのか、どのように補償するのかといった質問を受けました。それぞれに対して、がん細胞の再増殖や治療期間との関係、線量補償の戦略などを説明し、理解を深める有意義な議論ができました。
現地参加したことで、自身の英語力の課題を痛感しつつも、海外の研究者と直接ディスカッションできたことは大きな刺激となりました。同世代の研究者から質問を受けることもあり、国際的に切磋琢磨できる貴重な経験となりました。さらに、日本の学会とは異なる発表形式や機器展示、就職情報に触れることができ、最新の研究を学ぶ中で今後の研究発展に向けた新しい視点を得ることができました。
今回の発表にあたりご指導いただき、このような貴重な機会を与えてくださいました研究室の皆様、ご支援いただきました大学院生海外発表支援の関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。
| 氏名 | 研究室名 | 国際学会名 |
|---|---|---|
| 和田 拓也 | 放射線腫瘍学 | AAPM 67th Annnual Meeting & Exihibition |
| 長尾 拓海 | スポーツリハビリテーション学 | the 30th Annual Congress of the European College of Sport Science |
| 原田 一冴 | 生体運動・動作解析学 | The 2025 Congress of the International Society of Biomechanics (ISB) |
| 佐藤 颯太郎 | 生体運動・動作解析学 | The Interinational Society of Posture and Gait Research |
| 田島 祥汰 | 生体運動・動作解析学 | The Interinational Society of Posture and Gait Research |
| 池谷 奈那未 | 生体運動・動作解析学 | The Interinational Society of Posture and Gait Research |
| 上田 愛裕 | スポーツリハビリテーション学 | the 30th Annual Congress of the European College of Sport Science |
| 隈元 誠也 | スポーツリハビリテーション学 | the 30th Annual Congress of the European College of Sport Science |
| 塩水 鈴菜 | 口腔保健疫学 | International Association for Dental Research (IADR) |
| 杉本 美晴 | 生体運動・動作解析学 | The 2025 Congress of the International Society of Biomechanics (ISB) |
| Reshad Ashraful Islam | 地域・学校看護開発学 | Preventive Medicine 2025 |
| 麻 思萌 | 薬効解析科学 | 36th World Congress of Neuropsychopharmacology 9th AsCNP Congress |
| 石田 礼乃 | スポーツリハビリテーション学 | the 30th Annual Congress of the European College of Sport Science |
| 郭 文杰 | 国際保健看護学 | The 6th West China Internatonal Nursing Conference |
和田 拓也(博士課程2年 医歯薬学専攻 医学専門プログラム 放射線腫瘍学)

長尾 拓海(博士課程後期2年 総合健康科学専攻 保健科学プログラム スポーツリハビリテーション学)
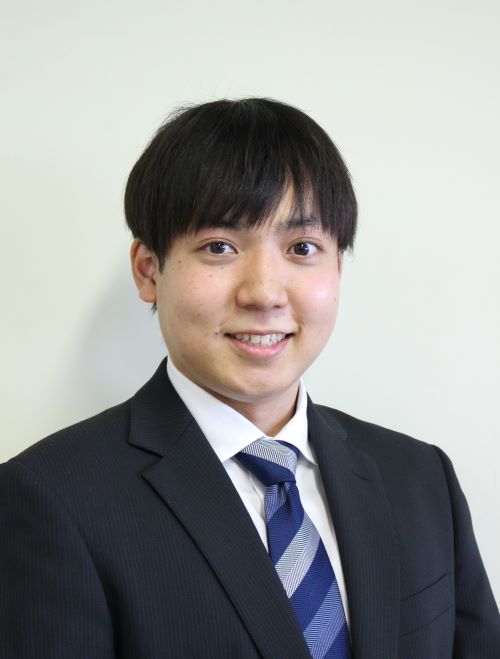
the 30th Annual Congress of the European College of Sport Scienceに参加して
この度、2025年7月1日~4日にイタリアのリミニで開催された、the 30th Annual Congress of the European College of Sport Science (ECSS 2025)に参加しました。本学会は学会名の通り、スポーツ科学・運動科学をテーマとした学会です。学会の規模としては世界各国のスポーツ科学・運動科学にまつわる研究者のべ3,500名ほどが参加されていました。私は「Does prosthetic walking practice combined with virtual reality acutely improve balance ability? A preliminary study using a simulated prosthesis」という題目でポスター形式で発表をしました。ポスター発表の会場は企業ブースや休憩スペースと同室であり、多くの参加者が行き交う環境で、発表時間中も他セッションの発表があり、かなり活気がある印象でした。そのような中、集まってくださった聴衆に向けて、自身の研究内容をよりわかりやすく、聴こえる声量で発表するよう工夫しました。質疑応答では測定方法に関して質問いただきましたが、セッションの時間も押していたため、要点をまとめて簡潔に説明する力が求められました。英語で端的に分かりやすく説明する力は今後も養っていく必要があると感じました。
最後になりましたが、このような貴重な発表の機会を与えていただき、ご指導いただいた諸先生方、ご支援いただいた大学院生海外発表支援関係者の皆様に深く感謝致します。
原田 一冴(博士課程前期1年 総合健康科学専攻 保健科学プログラム 生体運動・動作解析学)

International Society of Biomechanicsに参加して
2025年7月28日~8月1日にかけて、スウェーデン、ストックホルムにてInternational Society of Biomechanics 2025が開催され、「Morphological changes of the infrapatellar fat pad during suquating in patients with patellofemoral cartilage lesions」という題目でポスター発表をさせていただきました。
本学会は、主に生体力学に関する研究をテーマとしており、医療分野だけでなくスポーツ分野など幅広い研究を対象としていました。運動器疾患や中枢神経疾患における姿勢制御の研究だけでなく、加速度センサーを用いた研究発表や企業ブースから最新の技術・測定方法を学ぶことができ、大変刺激的でした。
私は、変形性膝関節症患者において、スクワット動作中に半月板が示す動態的変化を、超音波診断装置を用いて評価した研究発表を行いました。 MRIのような従来の評価方法ではスクワット動作など荷重位かつ膝関節の屈曲伸展を伴う動作における半月板の挙動について連続的に評価することは難しいため、質疑応答では方法論の詳細や、結果が示す意味についての質問を数点いただきました。
私にとって、今回が初めての国際学会への参加となりました。本学会では研究分野の異なる各国の研究者が参加しておりましたが、ポスター発表・口述発表いずれにおいても活発なディスカッションが行われていた印象を受けました。私自身は研究分野の異なる方々に対して、自身の研究内容を英語で説明することに苦戦しました。今後は発表言語に関わらず、他分野の方々に自身の研究内容を分かりやすく伝える力を身に付けたいと感じました。
この度国際学会発表に向けご指導いただいた先生方、海外渡航支援の関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。
佐藤 颯太郎(博士課程前期2年 総合健康科学専攻 保健科学プログラム 生体運動・動作解析学)
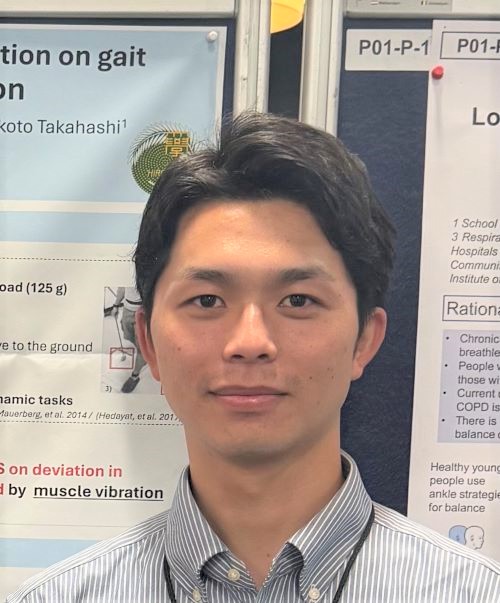
International Society of Posture & Gait Research 2025に参加して
この度、2025年6月29日~7月3日にオランダ マーストリヒトで開催されました「International Society of Posture & Gait Research 2025」に参加し、「Effect of additional somatosensory information on gait trajectory deviated by neck muscle vibration」という演題で、ポスター発表を行いました。
私は、人が安定した歩行のために必要な身体マップ(ボディースキーム)に着目し、頸部の筋肉への振動による頸部感覚の攪乱によって生じる歩行の変化に対して、外部からの感覚入力の有効性を検討し、アンカーシステムによる外部からの感覚フィードバックが胸鎖乳突筋への振動により逸脱した歩行軌跡の修正に有効であることを報告しました。
本学会期間中の様々な分野の研究者との関わりは、たいへん有意義な経験となりました。私自身、二度目の国際学会でのポスター発表で、昨年よりも活発なディスカッションを行うことができたと感じましたが、さらに深く研究を発展させるようなディスカッションを行うためには、さらなる英語力向上が必要であると痛感し、モチベーション向上に繋がりました。
最後になりましたが、この度の学会発表にあたりご指導いただいた先生方、ご支援いただいた大学院生海外発表支援の関係者の皆様に感謝申し上げます。
田島 祥汰(博士課程前期1年 総合健康科学専攻 保健科学プログラム 生体運動・動作解析学)
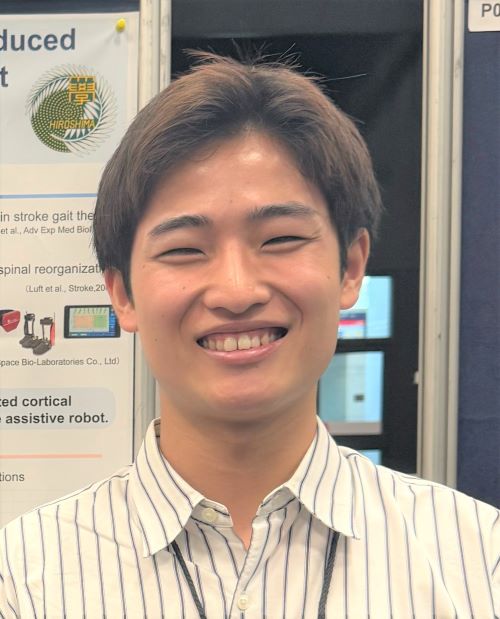
International Society of Posture & Gait Research 2025に参加して
2025年6月29日から7月3日にかけてオランダのマーストリヒトで開催された「International Society of Posture & Gait Research 2025」に現地参加し、「Investigation of cortical activity changes induced by gait training with an ancle assistive robot」という演題で、足関節型歩行補助ロボットを使用した歩行中の脳活動についてポスター発表させていただきました。
今回の国際学会は、私にとって国内外を問わず、初めての学会参加となり、一生忘れることのない経験となったと考えます。ポスター発表を行う中で、質問等を受け、実際にディスカッションをすることができ、世界中で研究を行っている方々の様々な意見に触れることで、自分が行っている研究に関する考え方の幅が広がったと感じました。しかし、深いディスカッションを行おうと思うと自身の英語力ではまだまだ足りないことを痛感し、今後も英語学習を続けていき、英語力を向上させたいと思います。
また、ポスター発表だけでなく、口述発表においても多くの質問が飛び交う様子を目にして、研究を行っていく上で、このように意見を出し合ってお互いに高めあっていけるような雰囲気を作れるような人物になりたいと思うようになりました。
最後に、このような発表の機会を与えてくださいました、生体運動・動作解析学の先生方、大学院海外発表支援関係者の皆様に深く感謝申し上げます。
池谷 奈那未(博士課程前期1年 総合健康科学専攻 保健科学プログラム 生体運動・動作解析学)

International Society of Posture & Gait Research (ISPGR) に参加して
2025年6月29日~7月3日にオランダMaastrichtで開催された「International Society of Posture & Gait Research (ISPGR) 2025」にて、ポスター発表をいたしました。
「The effects of ankle assistive robot on toe clearance during stair climbing in healthy adults (邦訳:健常成人における階段昇降時のつま先クリアランスに対する足首補助ロボットの効果) 」というタイトルで研究発表を行いました。昇段動作は下肢の協調的な運動制御を必要とし、つま先の引っ掛かりによる転倒リスクが高い動作であるため、リハビリテーション分野では重要な課題とされています。本研究では10名の健常成人を対象に右下肢に足関節歩行補助ロボットを装着して10分間の昇段練習を実施し、前後の下肢関節角度や筋活動の変化、クリアランスを測定しました。その結果、練習後には関節角度が変化し、クリアランスの増加が認められました。また、筋活動にも影響を及ぼし、ロボットによる早期背屈補助が効果的であることが示されました。これらの結果から、足関節補助ロボットを用いた練習は、脳卒中患者などの下垂足の改善や転倒予防に有用である可能性が示唆されました。
国際学会に参加し、海外および日本からの様々な分野の研究者と質疑応答を行ったことやご意見をいただいたことは、自身の研究の質を高め、今後さらに発展させるために非常に有意義な経験となりました。
末筆ではございますが、本研究発表にあたりご指導いただいた先生方、教室の皆様、霞国際室関係者の皆様には心より感謝申し上げます。また本支援金により、大変多くの学びを得ることができたことにつきましても、深く感謝申し上げます。
上田 愛裕(博士課程前期1年 総合健康科学専攻 保健科学プログラム スポーツリハビリテーション学)

the 30th Annual Congress of the European College of Sport Scienceに参加して
この度、私は2025年7月1日から4日にかけてイタリアのリミニで開催された「the 30th Annual Congress of the European College of Sport Science」に参加し、「The effect of rebound-jump landings with trunk rotation on knee joint angle in female basketball players」という題目でポスター発表を行いました。
アスリートの選手生命に関わる外傷のひとつに前十字靭帯損傷があり、女子バスケットボール選手は受傷リスクが高いとされています。本研究は、女子バスケットボール選手を対象に、バスケットボール競技のリバウンド動作を模して、体幹回旋を伴うジャンプ着地を3条件行い、回旋方向の違いで前十字靭帯損傷の受傷リスクの高さを比較、検討したものです。踏切脚側と非踏切脚側で回旋方向の条件分けを行った結果、踏切脚側に回旋するとき、踏切側の脚で前十字靭帯損傷の受傷リスクが高い可能性が示唆されました。この結果は、女子バスケットボール選手の前十字靭帯損傷予防の一助になると考えられます。
今回初めて国際学会に参加し、さまざまな分野の先生方と質疑応答をさせていただくことで、新しい視点を見出すことができるとともに、自身の研究のブラッシュアップにつながったと感じました。日本の先生方の参加も多く、たくさんの刺激を受ける良い経験となりました。最後になりますが,このような貴重な機会を与えていただきました先生方,同じ研究室の院生の皆様,ならびにご支援いただきました大学院生海外学会発表支援の関係者の皆様に心より感謝申し上げます。
隈元 誠也(博士前期課程1年 総合健康科学専攻 保健科学プログラム スポーツリハビリテーション学)
The 30th Annual Congress of the European College of Sport Science(ECSS)に参加して
この度、2025年7月にイタリアのリミニで開催されたECSSという学会に参加しました。本学会は4日間の開催期間であり、スポーツのリハビリテーションにかかわる内容から、戦術やコーチング、スポーツ心理学や栄養学のセッションなどスポーツの多岐にわたる分野について発表が行われていました。日本からの参加者も少なくなく、学会場でご挨拶させていただくことも多くありました。国際学会に参加すること自体、私は初めての経験でしたが実際に参加することで世界的にどのような研究がされているのか、それぞれ特徴があったり共通点があったりとさまざまな気づきを得ることができました。学会の3日目にはチャリティーマラソンが行われており、リミニの街を計6km走るというイベントでした。リミニの海岸沿いや凱旋門を通るようなコースで設定されており、自然を肌で感じながらリフレッシュとして運動することができ、非常に思い出に残っているイベントでした。4日間ECSSに参加することで、スポーツに関わる他部門の連携の重要性やそれぞれが担うべき役割というものについて学ぶことが多く、これからの研究としてスポーツ傷害で苦しむ選手の一助になるようなことをしたいと改めて思いました。これから国際学会に積極的に参加し、それぞれの専門性を生かして発表し交流することができるようにこれからも頑張っていきたいと感じました。
塩水 鈴菜(博士課程前期2年 総合健康科学専攻 保健科学プログラム 口腔保健疫学)
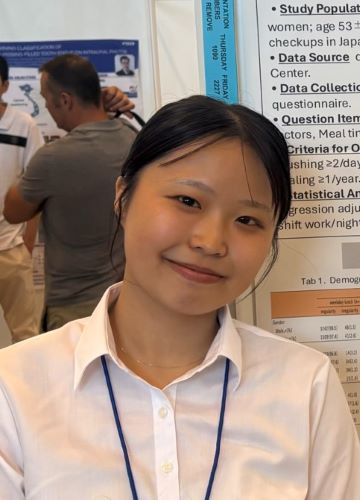
国際歯科研究学会IADRに参加して
2025年6月25日から28日かけてスペインのバルセロナで開催された「103rd International Association for Dental Research (国際歯科研究学会)」に参加し、「The association between meal timing regularity and oral health behavior(食事時間の規則性と口腔保健行動の関連性について)」の演題でポスター発表を行いました。
本研究は、J-MICCのデータを用いて食事時間の規則性が口腔保健行動に与える影響を明らかにすることを目的として実施された横断研究です。研究の結果、不規則な食事時間は口腔保健行動である歯磨き頻度や補助清掃用具の使用頻度の低さと関連しており、規則的な食習慣を促進することが口腔保健行動の改善につながる可能性が示唆されました。
初めて国際学会で発表する機会をいただき、世界中の研究者との交流を通じて大きな刺激と学びを得ることができました。この経験は、自身の研究の可能性を広げる貴重な経験となりました。
最後になりますが、本学会発表にあたり研究に関してご指導していただき、このような貴重な機会を与えてくださいました内藤真理子教授、口腔保健疫学研究室の諸先生方、ご支援いただいた大学院生海外発表支援の関係者の皆様に感謝申し上げます。
杉本 美晴(博士課程前期2年 総合健康科学専攻 保健科学プログラム 生体運動・動作解析学)
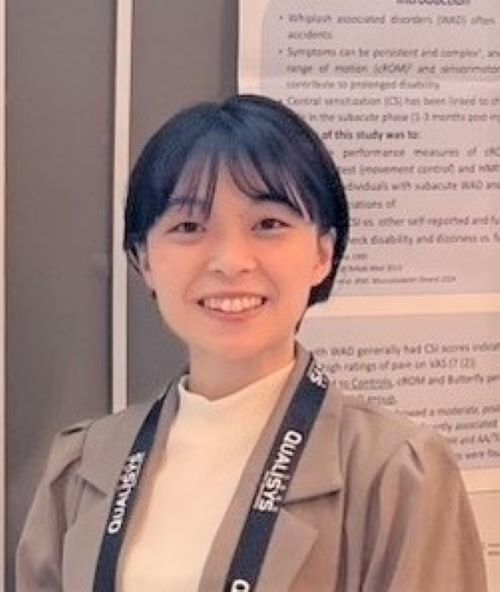
「The Congress of the International Society of Biomechanics (ISB) 2025」に参加して
2025年7月27日から31日の5日間にかけて開催された、The Congress of the International Society of Biomechanics (ISB) 2025 に参加させていただきました。「Kinematic analysis of infrapatellar fat pad dynamics during walking in patients with knee osteoarthritis」というタイトルで、変形性膝関節症(KOA)の病態に関連する膝蓋下脂肪体(IFP)動態と、歩行中の運動学的因子との関連性を検討した研究成果を発表しました。結果として、KOA患者の立脚相におけるIFP動態は、遊脚相における屈曲角度と関連する可能性が示唆されました。
本学会は、自身の研究領域と重なる部分が多く、知見を蓄える上で非常に有意義な機会となりました。また、ポスター発表では、他国の研究者と質疑応答をおこない、自身の研究を新たな視点から捉え直しより一層理解を深める良い機会となりました。さらに、他研究者の発表を聞く機会が豊富にあり、英語で聞き、理解し、質問する力を磨くことができたと感じています。
一方で、短時間で要点を伝えることや英語で議論することについては、まだ課題があると感じました。今後も、臨床や研究現場において、日頃からクリニカルクエスチョン/リサーチクエスチョンをより意識して取り組んでいきたいと感じました。
本学会への参加にあたりまして、ご支援いただきました大学院生海外発表支援関係者の皆様、日頃よりご指導いただいている高橋 真教授はじめ研究室関係者の皆さまに心より感謝申し上げます。
Reshad Ashraful Islam(博士課程前期2年 総合健康科学専攻 保健科学プログラム 地域・学校看護開発学)

American College of Preventive Medicine (conference 2025)
I attended the American College of Preventive Medicine Conference 2025, held in Seattle, United States of America, from May 5 to May 8, 2025. The conference gathered many researchers and professionals from different countries who are working to improve people’s health.
At this conference, I presented a poster titled “Psychological factors affecting smoking behavior among people”. My study was done among industry workers in Hiroshima, Japan. A total of 1519 workers were invited and 820 completed the survey. Among them, 636 were male and 184 were female. We asked about their background and feelings toward smoking. Two scales were used: one measured confidence to quit smoking (self-efficacy) and the other measured how people think about the good and bad sides of smoking (decision balance). The results showed that non-smokers had higher confidence to stay away from smoking, while smokers had only a medium level of confidence. Many smokers also believed more in the good sides of smoking than in the bad sides which shows that their way of thinking may stop them from quitting.
This study shows that people’s thoughts and confidence are important when helping them to stop smoking. Workplace health programs should focus on building stronger confidence and correcting wrong ideas about smoking. Attending the conference was a very good experience for me. I learned a lot from other researchers, received kind feedback and felt encouraged to keep working on health-related studies that can help people live better and healthier lives.
麻 思萌(博士課程後期3年 総合健康科学専攻 薬科学プログラム 薬効解析科学)

CINP-AsCNP 2025 Joint Congressに参加して
私は、2025年6月15日から3日間にわたりオーストラリア・メルボルンで開催された「CINP-AsCNP 2025 Joint Congress」にて、「Effect of cannabinoid CB2 agonist on cold hypersensitivity in post-traumatic trigeminal neuropathy」というタイトルでポスター発表を行いました。本研究では、Cannabinoid receptor 2 (CB2) の活性化が免疫細胞の機能抑制を介して、外傷性三叉神経ニューロパチーの病態改善や治療への応用が可能であることを明らかにしました。
本学会への参加は、私にとって極めて貴重な経験となりました。特に、ポスター発表では、多数の海外研究者との活発な意見交換を通じて、自身の研究に対する新たな視点や解釈を得ることができました。また、関連分野の最先端の研究成果に触れることで、研究の位置づけや今後の展開について深く考察する機会を得ました。これらの学びを活かし、今後はより高みを目指して研究を推進してまいります。
最後に、本研究にご指導を賜りました森岡徳光教授、中島一恵助教、中村庸輝助教をはじめ、発表の機会とご支援をいただきました大学院海外発表支援関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。
石田 礼乃(博士課程後期2年 総合健康科学専攻 保健科学プログラム スポーツリハビリテーション学)

European College of Sports Science 2025に参加して
この度、2025年7月1日から4日の4日間にイタリアのリミニで開催された、European College of Sports Science 2025に参加いたしました。私は、「Dynamic assessment of the talus-lateral malleolus distance during forward single-leg drop landing in individuals with and without chronic ankle instability」という題目でポスター発表をさせていただきました。三次元動作解析装置と床反力計、超音波画像診断装置を同期させることで、ジャンプ着地時の足関節外側の骨の動態評価を試みた研究になります。研究結果として、足関節捻挫の既往歴があり足関節不安定性を有する人は、足関節不安定性のない人と比較して、ジャンプ着地時の骨の動きが大きいことが明らかとなりました。近年ひとつのトピックにもなっている動的超音波を用いた研究として、三次元動作解析装置との同期システム等について質問をいただきました。スポーツサイエンスをテーマにした本学会は、理学療法士や医療者だけでなく工学や精神学など他分野の研究者が集まっており、色々な視点からアスリートの傷害予防やパフォーマンス向上、スポーツ普及について発表を聞くことができました。そのなかで、理学療法士という専門性を活かして自分に何ができるのかを考えることのできる貴重な機会となりました。
最後になりますが、本学会の発表に向けてご指導いただきました研究室の先生、並びにご支援いただきました大学院生海外発表支援の関係者の皆様に心より感謝申し上げます。
郭 文杰(博士課程後期3年 総合健康科学専攻 保健科学プログラム 国際保健看護学)

Attendance on the 6th West China International Nursing Conference
I attended the 6th West China International Nursing Conference on September 25-27, 2025, in Chengdu, where I delivered an oral presentation titled "Factors influencing the provision of breastfeeding support for preterm infants in Neonatal Intensive Care Units: A qualitative study of neonatal nurses’ perspectives". Human milk feeding is crucial for the survival and development of preterm infants, yet their human milk feeding rates at Neonatal Intensive Care Units (NICUs) discharge remain lower than those of healthy newborns. Effective support is essential for improving breast milk feeding outcomes, but remains challenging for NICU nurses. Therefore, this study aimed to examine factors that influence NICU nurses in providing human milk feeding support, including the challenges they face and their needs. This qualitative study identified multiple modifiable factors influencing human milk feeding support for mothers of preterm infants in NICUs, especially offering new insights into the significant role of NICU management policy and postpartum culture. Future interventions should prioritize creating a family-friendly NICU environment and adopting culturally sensitive education and support strategies to address the unique challenges posed by institutional and cultural barriers.
The conference covered nine major themes, offering a valuable opportunity to learn about the latest global research progress and innovations in nursing. It also highlighted the growing importance of interdisciplinary collaboration in advancing nursing science and practice. Engaging with scholars and professionals from various fields allowed me to broaden my academic perspective, gain new insights into emerging trends, and reflect on how cross-disciplinary approaches can enhance evidence-based nursing research and innovation. This experience enriched my understanding of global nursing development and further motivated me to pursue impactful, collaborative research in the future.

 Home
Home