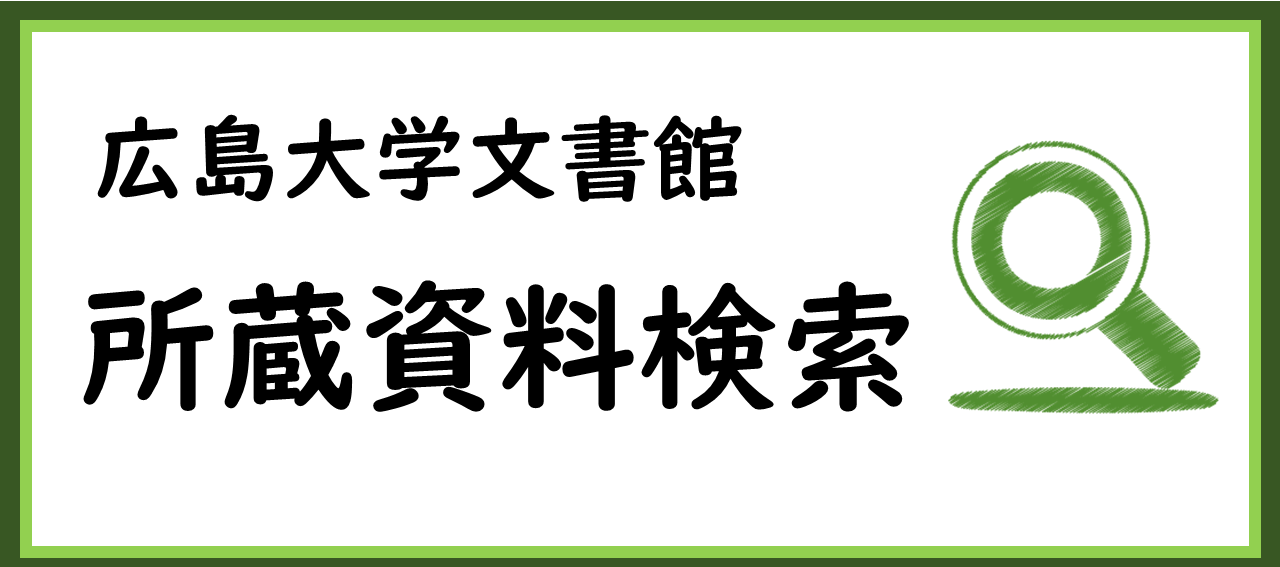執筆者
石田雅春
Ⅰ ビル・シェリフ氏の略歴と史料群の概要
ビル・シェリフ(Bill Sherriff)氏は、本名をウィリアム・ジョージ・シェリフ(William George Sherriff)と言い、1927年にオーストラリアに生まれた。地元の高校を卒業後、1945年4月にオーストラリア陸軍に入隊し、パプアニューギニアの戦争捕虜収容所などでの勤務を経て、1948年2月から1953年3月まで約5年間、英連邦占領軍(BCOF/British Commonwealth Occupation Force)の一員として日本で勤務した。日本勤務中は、主に広島県呉市(旧呉市内および広町)と宮島町で仕事を行った。この間にBCOFへタイピストとして勤務していた片山千鶴氏と知り合い、結婚することとなった。
そして1953年4月にオーストラリアへ帰国した後も、シェリフ氏は引き続き陸軍に勤務した。その後、ベトナム戦争への従軍などを経て1980年に大尉で退役し、2009年5月に82歳で亡くなった。(経歴については、後掲附表1を参照。)
本史料群は、こうしたビル・シェリフ氏の所蔵史料のうち、占領軍の一員として日本に滞在していた期間中に撮影した写真約800点とその関連史料から構成されている。これらの写真の中には、当時貴重だったカラースライドフィルムで撮影されたもの約350点が含まれており、記録資料としての学術的価値が高い。また白黒写真についても、日本人の立ち入りが規制されていた進駐軍の基地内部の写真が多数含まれている。こうした写真は日本人が撮影しているものが少ないため、地域史の記録として貴重である。
以下、本史料群が広島大学文書館に収蔵された経緯と、その概要について紹介する。
Ⅱ 史料の発見と企画展の開催
本史料群を日本へ本格的に紹介するきっかけを作ったのは、小田和美(おだ・たかみ)氏であった。小田氏は、1985年「ヒロシマ・デー国際電話プロジェクト」*1をきっかけとして本史料群の存在を知ることとなった。1991年有限会社コンベンション・クリエイトに勤めるようになった小田氏は、本史料群を戦後50年記念事業向けに活用したいと考え、1991年4月にシェリフ氏に書簡を送り、広島関係の写真のプリントを送付するよう依頼したのであった。
この小田氏の依頼を受けて、シェリフ氏より写真のプリントが送付されてきた。同時に、必要な写真のネガは、翌年予定の訪日時に持参できると記されていた。この時に送られてきた写真は、広島市および呉市周辺の写真が中心であった。そこで小田氏が広島市の文化課と呉市の市史編纂室に連絡したところ、双方とも全写真の収集及び利用に前向きな姿勢を示した。
1992年9月28日~10月4日、シェリフ夫妻が40年ぶりに広島を再訪した。この際にシェリフ氏は、200枚以上の写真スライドとネガを持参し小田氏に預けた。そこで小田氏は、シェリフ氏の了解のもと、これらの写真とネガを広島市公文書館と呉市市史編纂室に提供した。これを受け両機関では、それぞれが経費を負担して複製プリントを作成した。
こうしたなか小田氏に対して写真展開催の提案があり、1993年2月2日~28日に広島市INAXスペースにおいて企画展「アッケラ観HIROSHIMA オーストラリア兵・シェリフ軍曹の呉、広島1948年~1953年」が開かれた*2。この写真展では、松林俊一氏(当時広島市公文書館の担当職員)と石丸紀興氏(当時広島大学工学部助教授)、小田和美氏が中心となって写真の選定とキャプションの作成を行った。
これに続いて1993年5月31日~6月6日に呉市の市役所ロビーにおいて企画展「写真展 出会って くれ―進駐軍ビル・シェリフの見た呉・広島」が開催された。この写真展では、企画に当たって呉市の市史編纂室の千田武志氏や市民有志の協力も得て実行委員会を結成して準備が進められ、広島で使用された写真パネル(22枚)に加えて呉方面の写真のパネル(30枚)を作成して展示が行われた。追加の写真パネルは、呉市の市史編纂室の協力のもとで石丸氏、小田氏が中心となってキャプションを加えて作成を手がけたのであった。この企画展開催中に多くの市民が訪れ、その証言によって新たに撮影場所や人物が特定できたものがあった。
これらの企画展で利用されたスライドやネガは、1993年6月に小田氏がオーストラリア・メルボルンにあったシェリフ氏の自宅まで直接持参して返却した。その後、これらの写真の取り扱いをめぐり小田氏と広島市・呉市との間で協議する機会があった。その結果、上記の写真の利用にあたっては、小田氏を通じてシェリフ氏の許諾を得ることが確認された。
また、2004年にシェリフ氏と子女3人が再来日することとなった。これを受けて小田氏が中心となって、2004年5月24日~6月1日に広島市の旧日本銀行広島支店において企画展「豪兵 ビル・シェリフが写した広島/呉/宮島 写真展 戦後復興とくらし」、2004年7月1日~19日に音戸観光文化会館うずしおにおいて企画展「豪兵 ビル・シェリフが写した音戸/広島/呉/宮島」を開催した。この時は、追加プリント数点と、上述の企画展の写真パネルを一部修正して使用した。
こうした一連のできごとを経て、本史料群の存在は広島県を中心に知られることとなった。(報道や利用の実績については、後掲附表2~4を参照のこと。)ただ、後述のように、この過程で紹介された写真は、シェリフ氏が所蔵していた写真の一部に過ぎず、今回の史料収集によって新たに多数の写真が発見されたのであった。
Ⅲ 広島大学文書館への収蔵経緯
さて、2009年5月にシェリフ氏が死去した。すでにシェリフ氏の妻千鶴氏も他界しており、その自宅が処分されることとなった。これを受け史料の散逸を危惧した小田和美氏から広島大学文書館に史料の保存について最初の相談があり、同年9月に小田氏がオーストラリアに直接赴いて、シェリフ氏の写真関連遺品を整理された。その結果、フィルムの劣化が進んでおり、一部のものは復元不可能な状態になっていることが確認された。また、これまで広島市や呉市が複製を作成したもの以外にも、多くの写真のネガおよびスライドが残されていることが明らかになった。しかし、そのままでは場所の特定ができないものも多く、まず日本で調査研究することが必要と認識された。
そこで広島大学文書館としては、シェリフ氏の娘で、日本関連の遺品の相続人と決まったアン・チジー(Ann Chidgey)博士にフィルムを寄贈してもらう方向で打診したが、同意を得られなかった。しかしながら史料の学術的価値とその保存環境を考えると、そのまま放置することは問題だと思われた*3。そこで代わりに高精度のデジタル・データで複製を作成し、そのデータを広島大学文書館が保存・活用することで当初の目的を達成することとした。
こうした方針に基づいて、小田氏の渡豪とチジー博士の来日の際に複製作成のための史料の貸し出しを受けるとともに、2010年よりデジタル・データの使用条件についてチジー博士との折衝を始めた。ただ、著作権の調整は専門知識を必要とすることがらである上、欧米の慣習を踏まえて英文で契約書を作成する必要があったため、原案の作成にあたっては、広島大学の産学・地域連携センターの山本宏教授の支援を仰いだ。こうして作成した契約書の原案をもとに、数度に渡るやり取りを経て、2012年6月にチジー博士と広島大学の間で著作権の許諾に関するライセンス契約を締結したのであった。
Ⅳ ライセンス契約の概要
本史料群の利用方法と密接に関わってくるため、ここでチジー博士と広島大学の間で結ばれたライセンス契約の概要について紹介しておく。
本契約は、シェリフ氏の相続人であるチジー博士と広島大学(主管は文書館)の間で締結したものである。この契約に基づいて広島大学文書館は、自らの費用で原著作物を複製したデジタル著作物(原著作物のデジタル・データをデジタル記憶媒体に収録してデジタルアーカイブにしたデータベース)を作成し、非営利、教育・学術研究目的で利用する広島大学の構成員(教職員及び学生)にデータを提供できるのである。
一方、本契約では第三者(広島大学の構成員以外)に対して著作権のライセンスが許諾されていないため、広島大学文書館およびデータの提供を受けた広島大学の構成員は、第三者へデータを提供することはできないこととなっている。すなわち広島大学の構成員は提供されたデータを、複製、配信(インターネットなど)、展示、公開、授業や研究報告などで使用できるものの、第三者の手にデータが渡らないようにしなければならない。
たとえばインターネットで写真を公開した場合、データのダウンロードを防止するための措置を講じる必要がある。また展示会等で写真を展示する場合も、カメラでの撮影を禁止する必要がある。
ただ、写真の閲覧をさせることは認められているので、第三者(広島大学の構成員以外)は広島大学文書館において写真を閲覧することができる。もし、データの複写や利用が必要な場合は、改めてチジー博士の了承を得ることとある。(この場合、小田氏を通じて申請する形となる。)
なお、利用にあたっては、次記のような形式で著作権の表示を行うことが義務づけられている。
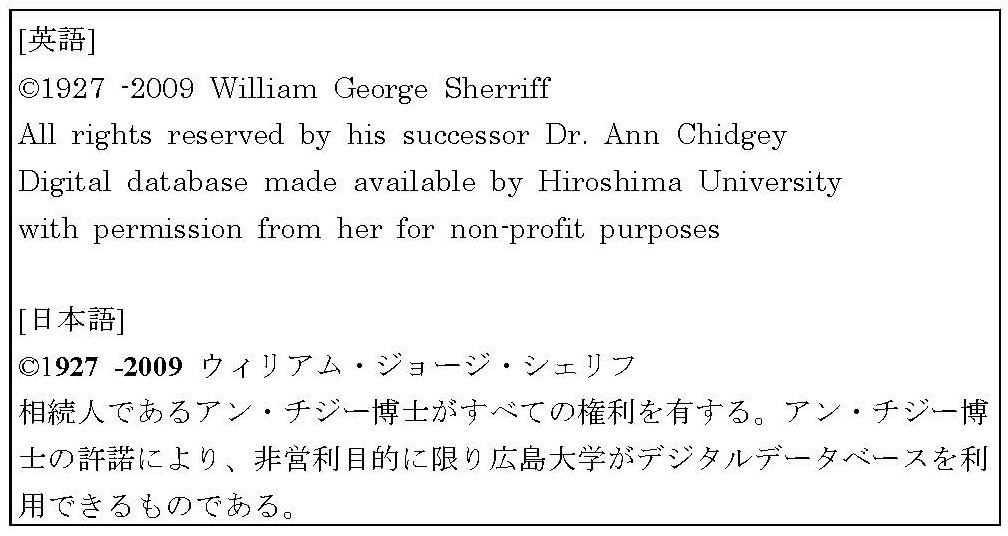
Ⅴ 史料の概要と整理の特徴
さて、上述のような経緯で広島大学文書館は、シェリフ氏の関係文書を収蔵するに至った。その主な内訳は次記のようなものである。
| 分 類 | 内 容 | 点 数 |
|---|---|---|
| 1. 写真 |
(1)Aグループ(白黒) |
287点 233点 3587点 |
| 2. 文書 (シェリフ氏関係分) |
(1)執筆原稿関係 (2)BCOF退役軍人協会機関誌 |
23点 105点 |
| 3. 文書 (小田氏関係分) |
(1)シェリフ氏執筆物コピー (2)シェリフ氏関係資料 (3)書簡類 (4)写真展・報道関係 (5)収集・整理経緯関係資料 (6)物品・写真プリント |
42点 |
| 4. 写真パネル | 写真パネル | 52枚 |
注)令和2年に白黒写真1点の追加寄贈があったため、1.写真(1)Aグループ
(白黒)の点数を286点から287点へ修正した。
収蔵の経緯の概略は、すでに述べた通りである。しかしながらそれぞれの史料について、いろいろな経緯があるため、以下、分類ごとに史料の成り立ちについて説明する。
1. 写真
シェリフが撮影し、チジー博士が著作権を相続した写真のことである。日本に深い関心を寄せていたシェリフ氏は、さまざまな機会に日本に関する写真を撮影している。すなわちl953年にオーストラリアに帰国した後も、雑誌記事の写真など日本の風俗や文物に関するものを写真撮影していることが確認できる。こうして撮影された写真は、フィルムを切断しスライドの形に加工されて整理・保管されており、コマの前後関係が不明確な状態となっていた。また、上述の写真展で使用された写真は、こうした所蔵写真のなかからシェリフ氏が選別して提供したものである。
このため、どのスライドがどこから出され、どこに戻されたかは、シェリフ氏本人しか分からない状態であったと推定される。シェリフ氏の死後、2009年9月と2011年12月の2回にわたり、小田和美氏が遺品の整理と史料の収集を行った。この過程においてスライドのリストが複数種類発見された。しかしながら、これらのリストは必ずしも現物と一致しておらず、数次にわたってスライドの入れ替えが行われたと推定される。(スライドの上部に番号の書き込みが複数種残されているのは、こうしたスライドの順番入れ替えの際にシェリフ氏が書き込みを行ったためと思われる。)
こうした状況のもとで史料の整理と収集を行うこととなった小田氏は、まずシェリフ氏が以前日本に持参した既知の写真のネガおよびスライドを抽出し、その上で、残されたネガおよびスライドの中から日本を撮影したと思われるものを選定していった。こうして抽出したネガおよびスライドを小田氏は、白黒についてはAとB、カラーについてはC1~C5というグループにわけて、機械的にナンバリングして一覧表を作成した。そしてこの一覧表に基づいて、複製データ作成のためチジー博士からネガおよびスライドを借用し日本へ持ち帰った。
現在、写真の目録番号に付与されているA・B・Cはこうした事情のもと、便宜的に付けられた番号である。しかしながら、この番号の配列のままでチジー博士のもとへネガおよびスライドを返却しており、現在もこの状態で保管されている。このため今後、複製データとネガの照合を行う際の利便性を考え、目録の史料番号として採用した。
また、これに関連して写真の目録番号に欠番が生じている。すなわち限られた滞在時間の中で上述のような選定作業を行ったため、日本に持ち帰ったネガおよびスライドの内容を小田氏が再点検したところ、占領期の日本関係以外のものが混じっていた。そこで複製データの作成にあたり、こうした日本以外のものを対象から除外した。このため当該部分が欠番となったのである。
なお、上述のようにフィルムがスライド加工してあったため、コマの前後関係が不明で撮影地の特定ができない写真が少なからずある。現在のところ、広島、呉、江田島、岩国、および宮島のほかに東京、伊豆、鎌倉、富士山、大阪、神戸、玉造、松山、別府、長崎、雲仙、熊本の写真が確認できる。このうち広島、呉、江田島、岩国、宮島、鎌倉については、上述の写真展開催の際に撮影地が特定されたものが多い。また松山については伊予史談会の会員の方々、広については広郷土史研究会の会員の方々、江田島については宇根川進氏のご協力を得て特定することができた。しかしながら撮影地不明の写真が少なからず残されており、これらの特定が今後の課題である。
2. 文書(シェリフ氏関係分)
(1)執筆原稿関係
これはシェリフ氏がオーストラリア軍の兵士として呉に勤務していた時に、広島の原爆被害についてまとめた“HIROSHIMA”の原稿の一部*4と、事実関係の紹介や資料引用の許諾申請などの関連資料である。2009年9月の遺品整理時に見つかり、1. の写真のネガと同時にチジー博士より複製の作成と公開の許諾を受けたものである。すべての文書は、デジタルカメラによる写真撮影と複写機による電子複写で複製を作成した。
(2)BCOF退役軍人協会機関誌 “SHIMBUN” または “SHINBUN” BCOFVeteransAssociationofAustralia
本文書は、小田和美氏がシェリフ氏を通じて入手したものと、シェリフ氏の遺品から成り立っている。すなわち1992年10月頃、小田氏の求めに応じてシェリフ氏が48号までのバックナンバーを入手・送付してきたそうである。BCOF退役軍人協会機関誌は、1979年9月に創刊され、第36号1989年12月号から第97号2000年5−6月号までは、日本人妻の豪入国に初めて成功したゴードン・パーカー氏が編集していた機関誌である。(遠藤雅子『チェリー・パーカーの熱い冬』〈新潮社、1989年〉参照)。シェリフ氏も、同じメルボルン在のパーカー編集長時代を中心に、日本占領時代の思い出などを同誌に何度か寄稿していることが確認できる。
2009年9月の遺品整理時に、小田氏が不足分およびその後のバックナンバーを見つけ、欠号分についてアン・チジー博士から永久に借用することとなった。こうして揃ったバックナンバーについて、今回小田氏が広島大学文書館に寄贈することとなった。(ただし、チジー博士からの永久借用分は寄託扱いとする。)
3. 文書(小田氏関係分)
本史料は、シェリフ氏と親交があり、日本での写真展を企画した小田和美氏の関連文書である。交流の過程でシェリフ氏が小田氏に送った文書、物品や書翰と、小田氏が携わったシェリフ氏所蔵写真の展示会や利用許諾に関する文書が、その主な内容である。写真の収集や展示会等での利・活用の経緯が分かるため、小田氏より一括して寄贈をいただくとともに、関係文書として採録した。
4. 写真パネル
上述の写真展のために作成された写真パネルである。キャプションの執筆は、石丸紀興氏、小田和美氏、松林俊一氏が分担して行った。写真展終了後は、小田氏が写真パネルを譲り受け保管していた。この写真パネルについても、関連史料ということで小田氏より寄贈を受けた。
ただ、写真のネガをもとにデジタル・データを作成する際には、その時のネガの状態(特にカラーの場合は変色のおそれがある)や使用機器、担当者の技倆によって、データの仕上がりに差が出ると推定される。このため今回、広島大学文書館が作成したネガのデジタル・データが必ずしも最良のものであるという保証が得られないため、この写真パネルを単なる複製物と見なすのではなく、オリジナルに準じた史料として保管・管理を行うこととした。
また、これらの写真パネルは、シェリフ氏が小田氏に預けたネガや写真をもとに作成されたものである。しかしながらシェリフ氏の死後、小田氏が旧宅の史料を整理したところ、行方不明になっているものや劣化によりフィルムが破損しているものが6点あった。そこで、これらのものについては、この写真パネルの写真からデジタル・データを作成して「1.写真」のAの末尾に追加した。
なお、当初は、木製のパネル52枚に写真168点が貼り付けてあった。しかしながら、その状態のままでは専用の保存箱への収納が難しく、なおかつ木製のパネルがかさばって多くのスペースを必要とするため、長期保存には不向きであった。そこで写真を木製パネルから剥離して中性紙の台紙へ張り替えるとともにた上で、保存箱に収納する方法を採った。
Ⅵ 本史料群の評価
日本が連合国軍によって占領されていた当時、カラーフィルムは高価であった上、日本国内には現像所がなく、ハワイやアメリカ本土のラボへ依頼していた*5。このためカラーフィルムは、事実上、占領軍の関係者しか利用することができなかった。こうした希少性に加え、カラー写真は色彩情報を有しており、モノクロ写真よりも史料的価値に優れているという特性がある。こうした点から、ビル・シェリフ関係文書のカラー写真は、記録資料としての学術的価値が高いと評価できる。
ただ、占領期の日本を撮影したカラー写真については、ビル・シェリフ関係文書に限らず、これまでも数多くのものが発見・紹介されてきた。たとえば、進駐したアメリカ軍が組織的に撮影した写真が、米国国立公文書館で保存・公開されている。このうち沖縄に関するものは、沖縄県公文書館が収集し「米国政府撮影写真」として公開している*6。これらの写真の中にカラーのものが含まれている。また原爆に関しては、米国陸軍病理学研究所(AFIP)から日本に返還された資料の中にカラー写真が含まれており、広島および長崎の関係機関が所蔵している*7。
その他にも占領軍の将兵が個人的に撮影したものとしては、アメリカ陸軍の将校だったロバート・スティール氏が撮影・収集した「スティール・コレクション」(約1万点)やGHQ専属カメラマンだったディミトリー・ボリア氏が撮影したカラー写真(約3万点、マッカーサー記念館所蔵)が知られている。
「スティール・コレクション」については、毎日新聞社が中心となって整理を行い、毎日新聞社編『決定版昭和史』別巻2(毎日新聞社、1985年)や同前『ニッポン40年前』毎日グラフ別冊(毎日新聞社、1985年)、同前『にっぽん60年前』(毎日新聞社、2005年)などで一部が紹介された。一方、ディミトリー・ボリア氏の撮影写真については、杉田米行氏によって同氏編著『GHQカメラマンが撮った戦後ニッポン』(アーカイブス出版、2007年)および同前『続・GHQカメラマンが撮った戦後ニッポン』(アーカイブス出版、2007年)で紹介されている。
ほかにも、仙台市歴史民俗資料館*8、東京都江戸東京博物館*9、呉市史編纂室*10がそれぞれカラー写真のネガやスライドを収蔵している。
以上が、管見の範囲で判明している占領期のカラー写真であるが、いずれもそれぞれの史料群の写真を断片的に紹介するにとどまっている。このため現時点では、残された写真の全体像が把握されていない。今後、各史料群の写真を相互に検証し、より詳細な評価を行う必要があると思われる。ただ、それには多くの時間と費用を必要とすることが予想されるため、本解題では今後の課題として指摘するにとどめておきたい。
付表1 ビル・シェリフ氏略歴
| 年月日 | できごと |
|---|---|
| 1927年4月19日 | オーストラリア、ビクトリア州ミルドラ(Mildura)で生まれる |
| 1944年 | ミルドラ高校卒業 |
| 1945年4月 | オーストラリア陸軍に入隊(18歳) |
| 1946-47年 | AustralianWarGravesUnit所属、パプアニューギニア・ラエ戦没者墓地で カメラマンとして勤務 |
| 1947年 | パプアニューギニア・ラバウル戦争捕虜収容所でカメラマンとして勤務 |
| 1948年2月 | 英連邦占領軍の一員としてMerkur号で呉に上陸 |
| 1948年2月-6月 | 呉BCOF本部管理局で勤務(Staff Sergeant Statistics) |
| 1948年7月-12月 | 宮島保養所(旧宮島ホテル)で兵士職業訓練校開設準備に従事 |
| 1949年1月-12月 | 呉BCOF本部管理局で勤務(Chief Clerk) |
| 1949年 | BCOF内で片山千鶴(タイピスト)と出会う |
| 1950年1月21日付 | 中国新聞で英語本「ヒロシマ」を執筆中のシェリフ軍曹が紹介される |
| 1950年4月 | カメラ・ライカとイコンタを基地内で盗まれる。4月29日付で盗難届を提出。 ('A' Branch HQ BCOF,3/1284 Sgt SHERRIFF WG) |
| 1950年1月-53年3月 | BCOF広陸軍本部にて勤務(二等准尉:Warrant Officer Class II) |
| 1952年12月20日 | 呉英国教会で結婚式を挙げる(Warrant Officer:准尉) |
| 1953年4月 | 3月呉港を出港、4月妻とともにオーストラリアに帰国(Sergeant:軍曹) |
| 1953年6月1日-1955年 | Puckapunyal第一歩兵旅団の書記長として勤務、准尉(Warrant Officer)になる |
| 1955年12月-1966年 | メルボルンの陸軍本部で勤務 |
| 1965年 | 中尉に昇進 |
| 1967年-68年 | ベトナム・Niu Datで特別編成部隊の中尉として勤務 |
| 1969-70年 | ノーザンテリトリー州ダーウィン(Darwin)でオーストラリア陸軍中尉 (Lieutenant)として勤務 |
| 1971年 | ベトナム・Vung Tauで後方支援部隊の大尉(Captain)として勤務 |
| 1972-1980年 | メルボルンの陸軍本部兵站部で参謀将校(Staff Officer)として勤務 |
| 1980年 | オーストラリア陸軍を退役(Captain:大尉) |
| 1992年9月 | 1953年4月の帰国後、初の日本再訪 |
| 2002年10月25日 | 妻・千鶴が死去 |
| 2009年5月8日 | メルボルンで死去、享年82歳 |
付表2 これまでの報道実績一覧(新聞) 平成24年12月現在
| 記 事 名 | 新聞名 | 掲載年月日 | 備 考 下線はシェリフ氏写真使用 |
|---|---|---|---|
| 「被爆から復興へ力強い市民の姿/ 元豪兵から写真届く/24、5年ごろの街並み」 |
『中国新聞』 | 1985年10月9日 | 写真「中央百貨店大売り出し」、 「広島西向寺再建と原爆ドーム」 |
| 「被爆4年後のドーム周辺/ 撮影の元豪州兵40年ぶり広島訪問/ 今はない「平和塔」対岸にくっきりと」 |
『中国新聞』 | 1992年9月28日 | 写真「ドームと平和塔」 |
| 「こんにちは・ビル・シェリフさん(65)」 | 『中国新聞』 | 1992年10月10日 | |
| 「元豪兵、戦後のヒロシマ写す」 | 『読売新聞』23面 | 1993年2月3日 | INAXスペース展示記事 |
| 「五流荘全景写真あった」 | 『中国新聞』14面 | 1993年2月5日 | INAXスペース展示記事、 写真「ドームと五流荘」 |
| 「豪州兵が撮った終戦直後の日本」 | 『プロパン新聞』3面 | 1993年2月15日 | INAXスペース展示記事 |
| 「天風録」 | 『中国新聞』1面 | 1993年2月6日 | INAXスペース展示記事 |
| 小田和美「でるた・千鶴さんのこと」 | 『中国新聞夕刊』1面 | 1993年2月9日 | INAXスペース展示記事 |
| 「戦後の呉町並み/豪軍人がパチリ/ 31日から呉で写真展/ 市民生活を語る170点/撮影場所の特定呼びかけ」 |
『中国新聞』呉版 | 1993年5月22日 | 呉市役所展示記事、 写真「呉市政50周年花電車」 |
| 「出会って くれ/呉・広島写真展/ 進駐軍人の撮った170点」 |
『読売新聞』 | 1993年5月23日 | 呉市役所展示記事、 写真「呉市政50周年花電車」 |
| 「戦後の生活ぶり生き生き/豪軍人が撮った呉。広島/ 31日から呉で展示/青空市場、紙芝居…」 |
『毎日新聞』 | 1993年5月27日 | 呉市役所展示記事、 写真「呉中通胡講」 |
| 「進駐軍兵士が撮った写真展/呉で始まる」 | 『朝日新聞』呉・広島版 | 1993年6月1日 | 呉市役所展示記事 |
| 「ニューススクエア/戦後間もない街の風景170枚/ 呉市で写真展/英連邦軍兵士撮影/復興への世相とらえる」 |
『朝日新聞』広島版 | 1993年5月25日 | 呉市役所展示記事、 写真「呉中通胡講」、 「呉中通はきもの屋」、 「広島駅前闇市火事後」、 「1949年呉メーデートラック眼鏡橋付近」、 「呉二河プール建設現場よいとまけ」、 「1949年11月呉映画館前晴れ着の少女」 |
| 「昭和20年代の広島・呉/戦後のアルバム鮮明/ 呉市役所駐留兵士撮影の写真展始まる」 「敗戦から復興よみがえる広島・呉/豪軍人写真展/庶民イキイキ」 |
『中国新聞夕刊』1面・2面 | 1993年5月31日 | 呉市役所展示記事、 写真「広島本通布を売る露店」「己斐電停」、 「呉本通チンドン屋」、 「1949年呉メーデー行進入船山付近」、 「広島流川教会」、 「広島西向寺再建と原爆ドーム」 |
| 「写真展「出会って くれ―進駐軍ビル・シェリフのみた呉・広島」」 | 『日豪プレス』18面 | 1993年7月 | 呉市役所展示記事、 オーストラリア内発行日本語新聞 |
| 「戦後の苦難まざまざと」 | 『毎日新聞』23面 | 2004年5月25日 | 旧日本銀行広島支店展示 |
| 「ビルさん会場で再会」 | 『中国新聞』 | 2004年5月28日 | 旧日本銀行広島支店展示 |
| 「展示今日まで」 | 『朝日新聞』 | 2004年6月1日 | 旧日本銀行広島支店展示 |
| 「戦後の呉・音戸 日常を切り取る/元駐留豪兵の写真展」 | 『中国新聞』呉・東広島版23面 | 2004年7月2日 | 音戸観光文化会館うずしお展示 |
付表3 これまでの報道実績一覧(テレビ) 平成24年12月現在
| 番 組 名 | テレビ局 | 放送年月日 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 「知ってるつもり!?オーストラリア初の戦争花嫁 ―桜元信子」 |
日本テレビ | 1995年4月23日 | |
| 夕方のニュース特集「1枚の写真から―宮島ホテル」 | テレビ新広島 | 1995年6月1日 | 宮島ホテル写真 |
| ニュース「己斐地区再開発」 | 中国放送 | 2003年9月 | 写真「己斐電停」 |
| フランス映像作家作品 (Envie de Tempete Production扱) |
不明 | 2007年 | 3点(ドーム) |
付表4 これまでの利用実績一覧(書籍) 平成24年12月現在
| 書 籍 名 | 編著者・出版元 | 発行年月 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 『呉の歩み』2 | 呉市史編纂室、呉市役所 | 1996年、増補版2006年 | 写真2点 |
| 『呉市史』第7巻 | 呉市史編纂委員会、呉市役所 | 1993年 | 写真18点 |
| 『呉市史』第8巻 | 呉市史編纂委員会、呉市役所 | 1995年 | 写真25点 |
| 『英連邦軍の日本進駐と展開』 | 千田武志著、お茶の水書房 | 1997年 | 写真11点 |
| 『呉・戦災と復興-旧軍港市転換法から平和産業港湾都市へ-』 | 呉市史編纂室、呉市役所 | 1997年 | 写真1点 |
| 『街のいろはレンガ色―呉レンガ考』 | 呉レンガ建造物研究会、中国新聞社 | 1993年 | 写真1点 |
| 『広島大学医学部50年史』通史編 | 広島大学医学部五〇年史編纂委員会、広島大学医学部同窓会 | 2000年 | 写真1点 |
| 『図説戦後広島市史 街と暮らしの50年』 | 広島市 | 1996年、2001年再版 | 写真3点「五流荘」「万年筆売り」「己斐電停」 |
------------------------------------------------------------
*1 「ヒロシマ・デー国際電話プロジェクト」(英語名:World Hiroshima Day Telephone Project)」とは、広島市の平和祈念式典の模様約15分間(献花、黙祷、平和宣言)を、国際電話回線を利用して各国語で生放送し、電話、及び郵便での感想を受け付ける事業のことである。同名のボランティアグループが主催した。
1985年8月6日が第一回で、7カ国語で発信した。オーストラリアには、全豪国営ラジオ放送ABC東京支局を通じて、英語放送がライブで全土にラジオ放送された。シェリフ氏は、この放送を聞き、広島のカラー写真プリント6枚を同封した書簡を送ってきた。同プロジェクトの発案者Raurence Wiig氏(米ハワイ出身)とともにco-directorを務めていた小田が書簡を受け取り、同封以外にも広島の写真が複数あることを知った。(附表2『中国新聞』1985年10月09日付記事)
*2 当時、INAX広島支店では、企業メセナとして営業部長加藤進氏によりINAXスペース(広島市中区八丁堀)で、企画展示を行っていた。松林俊一氏、菊楽肇氏、写真家の井手三千男氏らは、広島市の戦後50年史担当であると同時に、INAXスペース展示の企画委員でもあったことからINAXの展示が決まったのであった。
*3 一般的に、当時広く使用されていた硝酸セルロース・酢酸セルロースのフィルムベース、および発色現像方式カラー写真は、劣化を抑えるために低湿(30~50%)、低温(18度以下)の環境下で保存することが望ましいとされている。(マーク・ルーサ、アンドリュー・ロブ改訂、国立国会図書館訳『写真の手入れ、取り扱い、保存』日本図書館協会、2006年参照。)
*4 この原稿を執筆するため、シェリフ氏は、ジョン・ハーシーの著書『ヒロシマ』に登場する藤井医師や愛宮(ラサール)神父に取材している(「1.写真」にその時撮影したと思われるものあり)。ただ、現在はその部分の原稿は無い。かつてシェリフ氏は、書信にて引っ越しの際に失われたと小田氏に伝えている。
*5 杉田米行編著『続・GHQカメラマンが撮った戦後ニッポン』(アーカイブス出版、2007年)173頁、および沓沢博行「東京都江戸東京博物館所蔵の占領期カラースライドについて」東京都江戸東京博物館事業企画課資料係編『東京都江戸東京博物館資料目録占領期カラースライド』(東京都、2011年)参照。
*6 沖縄県公文書館ホームページ、および仲本和彦「在米国沖縄関係資料調査収集活動報告Ⅱ:米国国立公文書館新館所蔵の映像・音声資料編」『沖縄県公文書館研究紀要』第9号(2007年3月)参照。
*7 広島大学原爆放射線医科学研究所被ばく資料調査解析部Webページに掲載されている「AFIP(米国陸軍病理学研究所)返還資料(第一次)」(http://home.hiroshima-u.ac.jp/kohosha/AFIP.html)等参照。
*8 仙台市歴史民俗資料館編『なつかし仙台:いつか見た街・人・暮らし』特別展図録2(仙台市教育委員会、2006年)および仙台市歴史民俗資料館Webページ
(http://www.city.sendai.jp/kyouiku/rekimin/note/natsukashi.html)
に掲載されている企画展「なつかし仙台2」の紹介記事参照。
*9 前掲『東京都江戸東京博物館資料目録 占領期カラースライド』。
*10 「50年代の呉のカラー写真贈る」『中国新聞』2012年7月14日。

 Home
Home