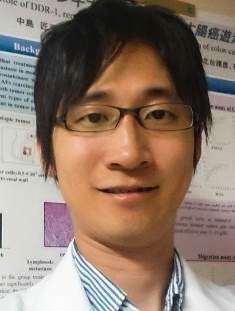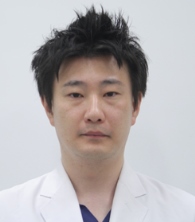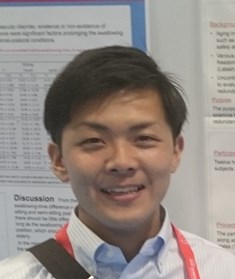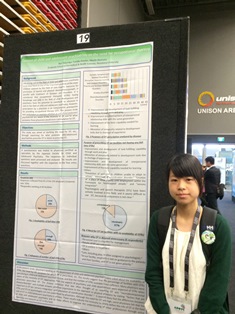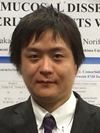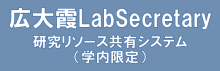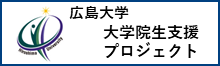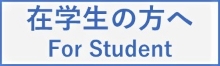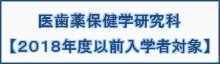ESSR 2015(リバプール)に参加して
ESSR 2015が2015年6月10日から13日にかけてイギリスのリバプールにて開催されました。ESSRとは、European Society for Surgical Researchのことであり、年に一度盛大に開催され、特に今年は第50回目という節目の年でもありました。メイン会場はリバプール大学でしたが、ヨーロッパの伝統的な建物と近代的な洗練された建物が調和する大変趣深い大学風景でした。すぐ近くにはリバプール大学病院があり、そちらは2017年の開院をめざし現在建設中でした。私はポスタープレゼンテーションで『Title-Face, Content, and Construct Validity of Lap-X, a Novel Virtual Reality Simulator for training basic laparoscopic skills』という演題で、新しい内視鏡外科手術用バーチャルリアリティートレーニングツールであるLap-Xについて、その有用性、妥当性について検証した研究結果をまとめ報告しました。英語の苦手な私にとって、英語でのポスタープレゼンテーションはかなり緊張を強いられましたが、なんとか制限時間内に発表を終えその後の質疑応答にも的確とはいえないまでも応じることができました。腹腔鏡手術のセッションでは他国の最新の手術手技・知見について学ぶこともできました。今回の学会に参加して、海外へも目を向ける良い機会になりました。これからも研究に励むとともに、その成果を積極的に発信していきたいと思います。

 Home
Home