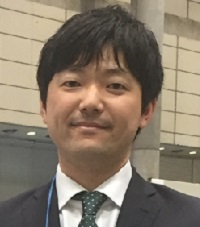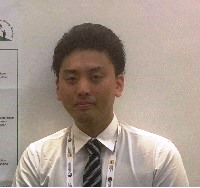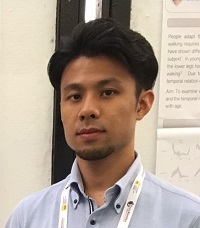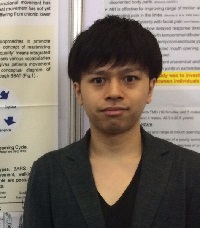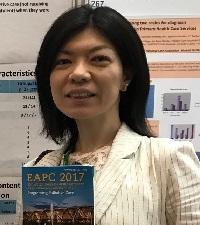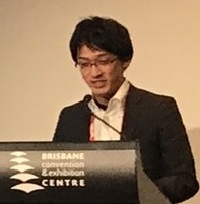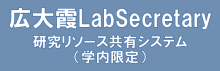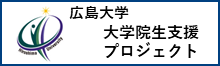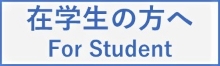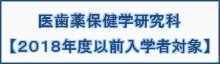第108回American Association for cancer research (AACR) (Washington, D.C.)に参加して
2017年4月1~5日までの5日間、アメリカのワシントンD.C.で開催されました第108回American Association for cancer research (AACR)に参加・発表する機会をいただきました。AACRでは、日本では考えられない大きさのコンベンションセンターでplenary sessionの会場はスクリーンが6枚ほど並んでおり、ポスター会場を見て回るだけで疲れてしまうほどでした。また論文で目にするような著名な先生達の講演が多く催され、とにかく規模の大きさに圧倒されました。
私はExpression of the transcribed region Uc.63+ in prostate cancerという演題を発表させていただきました。内容としてはnon-coding RNAの一つであるTranscribed ultraconserved regionは生物種を超えて保存されている領域なのですが、この中でUc.63+が前立腺癌で高発現しており、また増殖や抗癌剤耐性に関与しているというものです。発表形式はfree discussionで4時間ほどポスターの前で質問する人を待つものでした。英語での発表、質疑応答に最初は緊張しながらも、徐々に慣れていき、いろいろな人種、職種の人たちと交流することができ、刺激的な発表になりました。日本との大きな違いの一つとしては、欧米の人たちは、褒めてくれることが多く、研究の問題点を指摘する際も、非常に前向きであり、今後の研究への大きな励みとなりました。
今回、AACRに参加させていただき、自分の研究成果をこのような大きな学会で発表できることに喜びを感じるとともに、今後の研究にむけて課題も感じました。このような国際学会にまた参加できるように研究を、頑張って行きたいと思います。

 Home
Home