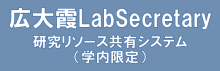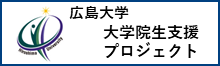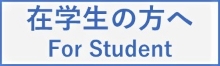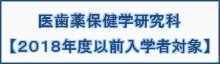International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine Congress 2023に参加して
2023年6月18日から21日にかけて、アメリカのボストンで開催されましたInternational Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine (ISAKOS) Congress 2023に参加させていただきましたので、ご報告いたします。
ISAKOSは全国約92か国の会員が所属している関節鏡・膝関節およびスポーツを中心とした国際学会です。今回の学会は、越智学長が名誉会員にも選ばれた記念すべき学会でもありました。
今回、私は“The preoperative prognostic factors influencing of postoperative results of manipulation under anesthesia for frozen shoulder”という題名で発表させていただきました。肩関節疾患としてよく遭遇する疾患に凍結肩があります。俗にいう五十肩のことですが、腱板断裂や変形性関節症などの器質的疾患がないにも関わらず、頑固な肩関節痛や可動域制限を来たし、十分に寝られない、衣服の着脱が難しいなど、患者のADL(日常生活動作)を大きく低下させることもあります。鎮痛薬、関節注射、リハビリテーションなどの保存療法で治療されることが一般的ですが、それらに抵抗性を示す場合に、非観血的授動術(manipulation)を行うことがあります。本術式は外来で行えることが大きな長所ですが、その術前不良因子に関する報告は少ない状況でした。今回、我々はそれを見出すことができたため、その成績をe-posterで報告しました。
他にも、肩関節を中心に最近の治療法やその長期成績などの発表を聞いて知見を深めることができ、今後の治療や研究への刺激となりました。最後に学会発表にあたりご指導、ご支援いただきました整形外科学教室の皆様、ならびに大学院生海外発表支援関係者の皆様に、この場を借りて厚く御礼申し上げます。
| 氏名 | 研究室名 | 国際学会名 |
|---|---|---|
| 住元 康彦 | 整形外科学 | International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine Congress 2023 |
| 磯部 伶緒 | 放射線腫瘍学 | AAPM's 65th Annual Meeting & Exhibition |
| 渡部 智也 | スポーツリハビリテーション学 | World Physiotherapy Congress 2023 |
| 西岡 陸 | 放射線腫瘍学 | AAPM's 65th Annual Meeting & Exhibition |
| 河井 美樹 | スポーツリハビリテーション学 | World Physiotherapy Congress 2023 |
| 水田 良実 | スポーツリハビリテーション学 | World Physiotherapy Congress 2023 |
| 石原 萌香 | スポーツリハビリテーション学 | World Physiotherapy Congress 2023 |
| 村田 菜奈子 | スポーツリハビリテーション学 | World Physiotherapy Congress 2023 |
| 上村 慶高 | 神経薬理学 | EMBL Symposium:The ageing genome:from mechanisms to disease |
| 田村 佑樹 | スポーツリハビリテーション学 | World Physiotherapy Congress 2023 |
| 小田 さくら | スポーツリハビリテーション学 | World Physiotherapy Congress 2023 |
| 水谷 将之介 | 生体運動・動作解析学 | International Society of Posture & Gait Research 2023 |
| 岡本 冴子 | 生体運動・動作解析学 | International Society of Posture & Gait Research 2023 |
| 橋爪 孝和 | 生体運動・動作解析学 | International Society of Posture & Gait Research 2023 |
住元 康彦(博士課程4年 医歯薬学専攻 医学専門プログラム 整形外科学)

磯部 伶緒(博士課程前期2年 総合健康科学専攻 医学物理士プログラム 放射線腫瘍学)

AAPM's 65th Annual Meeting & Exhibitionに参加して
この度、2023年7月23日-26日にヒューストン(テキサス州)で開催された「AAPM's 65th Annual Meeting & Exhibition」に参加いたしました。
私は「Radiomics-based decision support tool with GGO status of 5-year survival prediction for early-stage non-small cell lung cancer」というタイトルでinteractive e-poster発表を行いました。早期非小細胞肺癌患者のRadiomics解析にGGO Statusを組み合わせることで、予後予測精度の改善を図った、という内容になります。30分の持ち時間で3名の方と意見を交わし、自身の研究内容が世界に通用するレベルのものであることを認識できる良い機会となりました。今回の学会参加経験を通して、医用画像におけるRadiomics解析は活発に行われているものの、それを臨床にどう結び付けるか、といった点がこれからの課題であると感じています。単純にRadiomics解析を行うだけではなく、それに付加価値としてどのような因子と組み合わせるか、という視点を今後の研究に活かしていきたいと思いました。
また、初めての国際学会での発表であり、研究内容を英語で説明する難しさを痛感するとともに今後の英語学習のモチベーションを高められる機会にもなりました。
最後に、この度の発表にあたりご指導いただいた先生方、放射線腫瘍学教室の皆様、並びにご支援いただいた大学院生海外発表支援の関係者の皆様に心より感謝申し上げます。
渡部 智也(博士課程前期2年 総合健康科学専攻 保健科学プログラム スポーツリハビリテーション学)

World Physiotherapy Congress 2023に参加して
アラブ首長国連邦のドバイで開催されたWorld Physiotherapy Congress 2023に初めて参加しました。会期は、2023年6月2日~4日でした。
国際学会に参加させていただいて一番痛感したことは、事前準備の大切さです。特に初めての国に行く際は、交通手段やその国における禁止事項、および注意事項を事前に確認・共有しておくことは、リスク管理のうえで大切なことであると痛感しました。また、事前準備は、研究にも通じるものがあると感じました。日常生活と研究活動は繋がっている、このような実体験をできたことが今回の一番の収穫です。
私は、「傾くVR映像の視聴により端座位姿勢の重心動揺は変化するか」について、printed posterで発表し、7名の研究者から質問をいただきました。初めにいただいた言葉は、「あなたの研究の抄録を読んできました。とても興味深い内容です。」というものでした。この言葉をいただいたときに、他者から見ても興味深い内容であるということを体感し、「他者のためになる研究」を体現できていることに感動を覚えました。
国際学会でのディスカッションを通じて、海外の研究者の方は、研究の過程よりも結果を重視しており、その結果について、発表者がどのように考えているのかを、意見として求めていると感じました。また、会場でポスターを見ていると、国内の対面で行われる学会以上に、発表者側から研究の説明をしてくださるので、自然とコミュニケーションが生まれていました。このような姿勢は私も真似していきたいと思います。
西岡 陸(博士課程2年 医歯薬学専攻 医学専門プログラム 放射線腫瘍学)

AAPM's 65th Annual Meeting & Exhibitionに参加して
2023年7月23日~27日の期間にアメリカのヒューストンで開催されたAAPM’s 65th Annual Meeting & Exhibition 2023に参加し、「A comprehensive Radiogenomics approach for risk assessment of overall survival in clear cell renal cell carcinoma」という題目でポスター発表を行いました。本研究は、淡明細胞型腎細胞癌患者に対して、手術後の予後に関連する医用画像特徴を同定し、さらにその画像特徴がどのような生物学的な背景を捉えている可能性があるのかを探索することを目的としています。現在、癌の進行度合いを評価する指標としてTNM分類があり、治療方針の決定に広く活用されていますが、同じ進行度合いであっても、患者間で治療予後に大きな差を生じることが現在までに報告されています。近年、医療分野では、患者一人ひとりの体質や病態に合わせた治療を行うという「個別化治療」への関心が高まっており、実現のためには患者個々の違いをより把握する必要があります。そこで、我々は比較的取得が容易である医用画像を用いて患者個々の生物学的な背景の違いを捉え、「個別化治療」の実現を目指すために本研究を行なっております。
最後になりますが、このような貴重な発表の機会を設けていただいた粟井 和夫 教授、放射線腫瘍学教室並びに腎泌尿器科学教室の皆様には、心より感謝を申し上げます。
河井 美樹(博士課程前期2年 総合健康科学専攻 保健科学プログラム スポーツリハビリテーション学)

World Physiotherapy Congress 2023に参加して
2023年6月2日から6月4日にかけてUAEのドバイで開催されたWorld Physiotherapy Congress 2023に参加いたしました。会期中は、ポスター発表の機会をいただき、「Influence of ball positions in volleyball spike jump on knee valgus angle at landing」というタイトルで発表しました。バレーボールのスパイクジャンプ動作を分析した内容で、ボール位置の違いでジャンプ着地時の膝関節運動がどのように変化するのか確認した研究になります。発表の際は、多くの研究者の方々から質問をいただき、研究の意義から測定方法に関してディスカッションいたしました。気づきとしては、自分から話しかければ、発表者(研究者)の皆さんは、気さくにコミュニケーションを取ってくださるということです。英語が拙くて上手に話せなくても、話を聞いてくれようとしてくださる研究者が大勢いらっしゃいました。逆に、自分の伝えたいこと、例えば研究に関する質問や、自分が現在取り組んでいる内容などを英語で相手に伝わるように話すことができれば、会話の時間は自ずと長くなると感じました。今回の学会に参加し、様々なテーマの口演を聴くことができ、例えば「women’s health」など一つのキーワードについて話されている研究者や、実体験から疑問に思ったことをテーマに話されている研究者などがいて、何か一つのことを詳しく語れることは、研究者としての強みであるなと感じました。今後も積極的に、色んな方々とコミュニケーションを取り、より専門性を身に付けていきたいです。
水田 良実(博士課程後期2年 総合健康科学専攻 保健科学プログラム スポーツリハビリテーション学)

World Physiotherapy Congress 2023に参加して
この度、2023年6月2日~4日にアラブ首長国連邦のドバイで開催されたWorld Physiotherapy Congress 2023に参加いたしました。発表タイトルは「Acute effects of local vibration and visual feedback on the pelvic floor muscle training in Japanese healthy adults: cross-over study」で、振動刺激や視覚的なフィードバックを併用した骨盤底筋トレーニングの有効性について報告してきました。世界中の理学療法士が集まる大規模な学会で、会場には多くの聴衆が集まっていました。現地開催の国際学会で口頭発表をしたのは初めてで、このような機会をいただけたことは、今後の研究の励みとなりました。また、Pelvic, sexual and reproductive healthというセッションで発表をしたのですが、ウィメンズヘルス分野の国際的な関心の高まりを感じました。次回の東京開催のWorld Physiotherapy Congressでも研究成果の報告ができるように、骨盤底筋トレーニングをはじめ、当該分野での研究を続けていきたいと思います。
石原 萌香(博士課程後期1年 総合健康科学専攻 保健科学プログラム スポーツリハビリテーション学)

World Physiotherapy Congress 2023に参加して
この度、2023年6月2日~4日の3日間、ドバイで開催された「World Physiotherapy Congress 2023」に参加してまいりました。本学会は各専門分野の理学療法士が世界中から集まる学会で、2年ごとに開催されています。私は、「Abnormal lateral malleolus morphology and physical function in adolescent athletes classified with peak height velocity age」という題目で口述発表を行いましたので、報告します。
本研究は、ジュニア世代の強化指定アスリートを対象に、成長期の捻挫による外果の裂離骨折の有無が、足部アライメントおよびジャンプ着地パフォーマンスに影響しているかを調べたものです。学会2日目の「Sports and Sports Injury (platform presentation session)」に演題が組み込まれ、スクリーンが5つ設置された本大会で最も大きいメイン会場で口述発表をさせていただく機会を得ました。この度の学会参加では、非ネイティブ(英語圏以外の国籍)の参加者の活躍が印象的でした。実際、私が発表したセッションでも、座長がポルトガル、発表者は日本、フランス、トルコ、ドイツと多国籍でした。その他、私が学会期間中に交流を深めた研究者も非ネイティブの方が多数でした。非ネイティブであっても非常に熱く勢いのある発表と討論が多かったことを記憶しています。発信力・情報収集力の点で、日本人として越えなければならない壁の高さを痛感しました。次回、2025年の開催地は東京です。日本人研究者の一員として、学会での情報発信と交流を加速させられるように、この2年間を過ごしたいと思います。最後になりましたが、この度の海外発表にあたりご指導いただいた先生方、ご支援いただいた大学院生海外発表支援の関係者の皆様に感謝申し上げます。
村田 菜奈子(博士課程前期2年 総合健康科学専攻 保健科学プログラム スポーツリハビリテーション学)

World Physiotherapy Congress 2023の参加を通して
2023年6月2日~4日に、アラブ首長国連邦の中心都市であるドバイで開催されたWorld Physiotherapy Congress 2023に参加させていただきました。
私は車いすテニス選手の肩関節傷害予防を目的とし、立位と車いす座位でのサーブ動作中の肩関節周囲筋の筋活動を比較することで、車いすテニス選手の傷害発生原因を検討した内容を、ポスターにて発表しました。
ポスター発表は質疑応答など決められた時間は設けられていませんでしたが、学会は英語のネイティブスピーカーが多く、少し緊張してしまい、自分から話しかけることに躊躇ってしまうこともありました。今後は、英単語などを覚えるだけではなく、ボディランゲージなど含めた表現力を身につけたいと感じました。
学会には、様々な地域から女性の参加者・発表者も多く来られていて、様々な内容の研究に取り組まれており、強い刺激を受けました。
今回得た貴重な経験を活かし、今後の研究活動をより実りあるものにしていきたいと思います。
上村 慶高(博士課程2年 医歯薬学専攻 医学専門プログラム 神経薬理学)
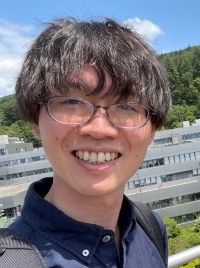
EMBL Symposium The ageing genome: from mechanisms to diseaseに参加して
2023年6月4日~7日の4日間、ドイツ(ハイデルベルク)で開催された「EMBL Symposium The ageing genome: from mechanisms to disease」に参加しました。私は老化とDNAの関係、中でもエピジェネティックな制御を介した関係に興味があり、海外での最新の老化研究の流れを知るために参加を決意しました。
発表タイトルは「Klotho protects chromosomal DNA from radiation-induced damage」で、抗老化作用があるとされるKlothoタンパク質の発現を抑制することによって、放射線照射した際にDNAの損傷が増加することを報告しました。先行研究では、Klothoはリン代謝を介して抗老化作用を示すと考えられていましたが、今回の研究でKlothoタンパク質が、染色体DNAを保護することで抗老化作用を示すという新しい機序の可能性を提示しました。日本から本学会の参加者は私だけで心細さはありましたが、博士課程の学生や博士研究員、有名な論文の責任著者や基調講演者等、様々な国籍、肩書の方々と議論することができ、非常に有意義な時間を過ごすことができました。自身の研究に対するモチベーションの向上とともに、卒業後海外留学することを強く意識するきっかけになりました。今回の学会参加を通して得られた経験を踏まえ、今後も精進していきます。この度の海外発表にあたりご指導いただいた先生方、ご支援いただいた大学院生海外発表支援の関係者の皆様に感謝申し上げます。
田村 佑樹(博士課程前期2年 総合健康科学専攻 保健科学プログラム スポーツリハビリテーション学)

World Physiotherapy Congress 2023に参加して
2023年6月2日~4日にアラブ首長国連邦(UAE)のドバイで開催されたWorld Physiotherapy Congress 2023に参加しました。
世界131か国から約5,000人の研究者たちが参加した本学会は、理学療法士の学会としては世界最大規模の学会になります。アジアや欧米諸国だけでなく、アフリカや中東などの発展途上国からも多くの研究者が参加していたことが印象的でした。発表テーマも多種多様で、各分野での最近のトレンドについて多くの報告があり、口頭発表やポスター発表、さらには研究者同士で意見を交換し合うセッションなど、様々な形の発表がありました。
私は、立位と車いす座位でバドミントンのスイング動作を行った際の肩関節、体幹運動とスイング速度の比較に関する研究をポスター形式で発表しました。測定方法や発展性などについての質問をいただき、今後の参考となるようなディスカッションをすることができました。ポスター発表は初めての経験でしたが、人の目に留まるようなポスターにするためには、図を大きくすることや、配置、色使いなどにもこだわり、今後は、見る人にインパクトを与えるようなポスターを作成していきたいと感じました。また、自分の英語力に自信がもてず、自ら話しかけられなかったことも反省点でした。流暢な英語でなくても、ジェスチャーなどを用いて、伝えたいことの最低6割くらいは相手に伝えられるような練習をしていきたいと感じました。
小田 さくら(博士課程前期2年 総合健康科学専攻 保健科学プログラム スポーツリハビリテーション学)
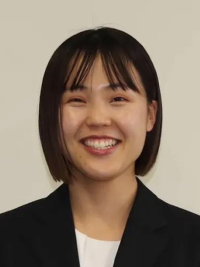
World Physiotherapy Congress 2023に参加して
2023年6月2日~6月4日にドバイで開催されたWorld Physiotherapy Congress 2023に初めて参加しました。普段、非常勤で理学療法士として働く中で、海外の理学療法士の方と接する機会は多くありませんが、今回の学会を通して、幅広い視野を持ち、海外に目を向けることの重要性に気づくことができました。
今回私はポスター発表を行い、45分間の発表時間の中で7名から質問を受けました。発表内容は「睡眠の質が月経随伴症状に与える影響」でしたが、ウィメンズヘルスに興味のある男性の研究者から質問を受ける機会も多くあり、ウィメンズヘルス分野が男性にも浸透していることを実感しました。
本学会では、ウィメンズヘルス関連のセッションに多く参加したため、研究に関する現在のトレンドを知ることができ、また、学会で口頭発表に選ばれるレベルになるためには、自らの研究成果にどのような工夫をすればよかったのか、という点で新たな気づきも得ることができました。
また、国内外の多くの研究者の方々とお話する機会がありました。研究以外のところで、国際学会に参加するうえで武器となる「英語」に関して、海外留学の経験がある国内研究者の方に、「英語力を高める方法」について尋ねてみました。単語を聞き取りながら相手が言いたいことは何かを予想しながら聞くことや、まずは海外のドラマなどを見てシャドーイングを繰り返しすることが英語力を高める第一歩だと教えていただきました。今後は、本学会で感じた悔しさを忘れず、毎日コツコツと英語の学習にも取り組んでいきたいと思います。
水谷 将之介(博士課程前期2年 総合健康科学専攻 保健科学プログラム 生体運動・動作解析学)

International Society of Posture & Gait Research 2023に参加して
2023年7月9日から13日にかけてオーストラリアのブリスベンで開催された「International Society of Posture & Gait Research 2023」に現地参加し、転倒と転倒リスクに関するセッションにて「Muscle synergies for the transition from double to single -leg stance under the opened/closed eyes conditions in young adults」という演題でポスター発表させていただきました。
現在、日本社会は超高齢社会に突入し、高齢者の転倒問題への対策が求められています。その中で、転倒が多く発生しているといわれている動作中姿勢制御戦略を明らかにすることで転倒予防に対する重要な知見を得ることができると考えています。そこで、視覚情報がある条件/ない条件の2条件において両脚立位から片脚立位への移行中における姿勢制御戦略を筋シナジー解析によって明らかにし、比較する研究を行いました。発表では、両脚立位から片脚立位への移行においては、股関節外転筋群と前脛骨筋および長腓骨筋の協調的な制御が求められ、視覚情報制限下では、前脛骨筋と長腓骨筋に求められる貢献が増加する可能性を報告しました。
初めて国際学会に参加し、世界中の同じ分野における研究者が様々な考えのもとで研究を行っていることに触れることができ、とても有意義な時間となりました。同時に、英語での質疑応答やコミュニーケーションの難しさを感じ、今後の英語学習をより一層進めていく決心につながりました。
最後に、このような発表の機会を与えてくださいました、生体運動・動作解析学の先生方、大学院海外発表支援関係者の皆様に深く感謝申し上げます。
岡本 冴子(博士課程前期2年 総合健康科学専攻 保健科学プログラム 生体運動・動作解析学)

International Society of Posture & Gait Research 2023に参加して
2023年7月9日~13日にかけて、オーストラリア クイーンズランド州 ブリスベンにてInternational Society of Posture & Gait Research 2023が開催され、「Effect of Asymmetry of Cumulative Knee Adductor Load on Medial Meniscus Extrusion in healthy Volunteers」という題目でポスター発表をさせていただきました。
本学会は、主に姿勢・歩行制御に関する研究をテーマとしておりました。運動器疾患や中枢神経疾患における姿勢制御の研究だけでなく、加速度センサーを用いた研究発表や企業ブースから最新の技術・測定方法を学ぶことができ、大変刺激的でした。
私は、健常者に5kmの歩行負荷を課し、その前後で半月板がどのような動態的変化を示すかを、超音波診断装置を用いて評価した研究発表を行いました。従来、歩行中の負荷量については三次元動作解析装置などを用いて外的に評価することが一般的であるため、質疑応答では方法論の詳細や、結果が示す意味についての質問を数点いただきました。
私にとって、今回が初めての国際学会への参加となりました。本学会では研究分野の異なる各国の研究者が参加しておりましたが、ポスター発表・口述発表いずれにおいても活発なディスカッションが行われていた印象を受けました。私自身は研究分野の異なる方々に対して、自身の研究内容を英語で説明することに苦戦しました。今後は発表言語に関わらず、他分野の方々に自身の研究内容を分かりやすく伝える力を身に付けたいと感じました。
この度国際学会発表に向けご指導いただいた先生方、海外渡航支援の関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。
橋爪 孝和(博士課程前期2年 総合健康科学専攻 保健科学プログラム 生体運動・動作解析学)

International Society of Posture & Gait Research 2023に参加して
この度、2023年7月9日~13日にオーストラリアで開催されました「International Society of Posture & Gait Research 2023」に参加し、「The effect of mechanical stress during descending stairs on the behavior of medial meniscus extrusion」という演題で、ポスター発表を行いました。本邦では、高齢化に伴い、変形性膝関節症の罹患率は急激に増加しています。変形性膝関節症は、膝のクッションである半月板の機能が低下することで進行することが報告されており、近年、半月板が関節の外に逸脱してしまう半月板逸脱が問題視されています。しかし、この半月板逸脱の評価は動いていない状態で行われ、過小評価されることもあります。そこで本研究では、変形性膝関節症の患者さんにとって問題となりやすい、降段動作で半月板逸脱が評価できるかどうかを検討しました。発表では、降段動作中の半月板逸脱は評価可能であり、歩行動作よりも逸脱が大きいという結果を報告しました。
今回の国際学会は異分野の研究者と関わる機会が多く、様々な視点を養うことができ、大変有意義な経験となりました。一方で、言語の壁の高さを痛感し、より一層精進しなければならない、というモチベーション向上にもなりました。
最後になりましたが、この度の学会発表にあたりご指導いただいた先生方、ご支援いただいた大学院生海外発表支援の関係者の皆様に感謝申し上げます。

 Home
Home