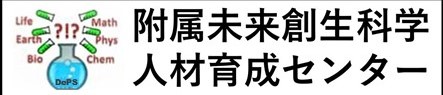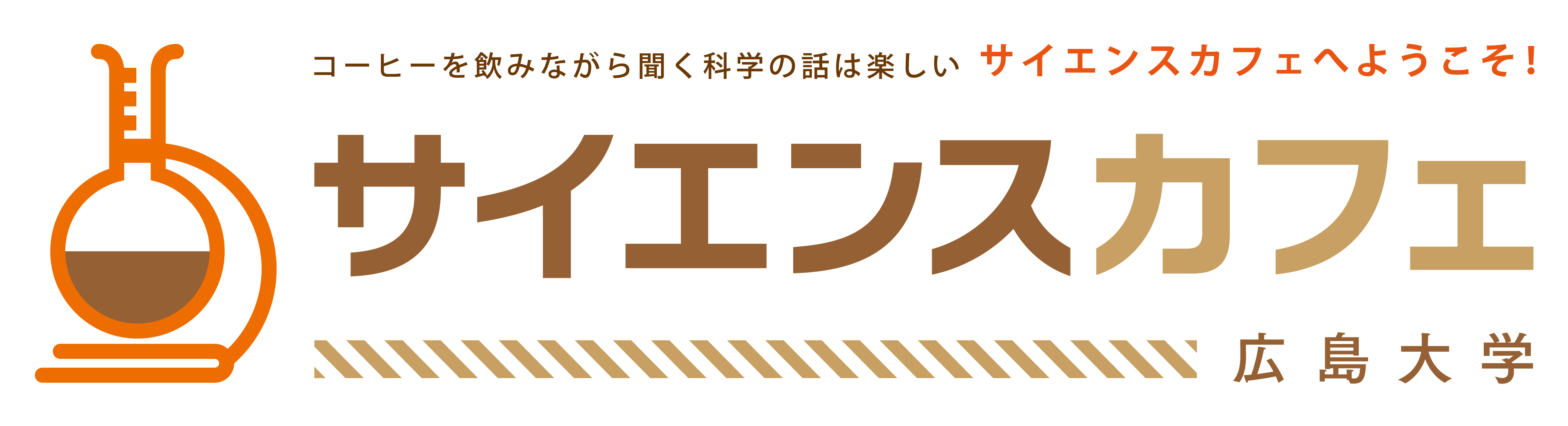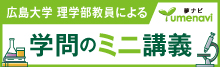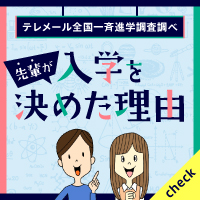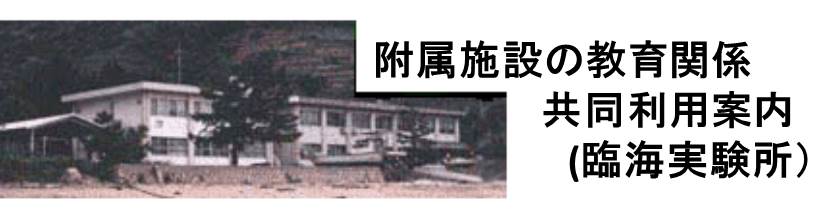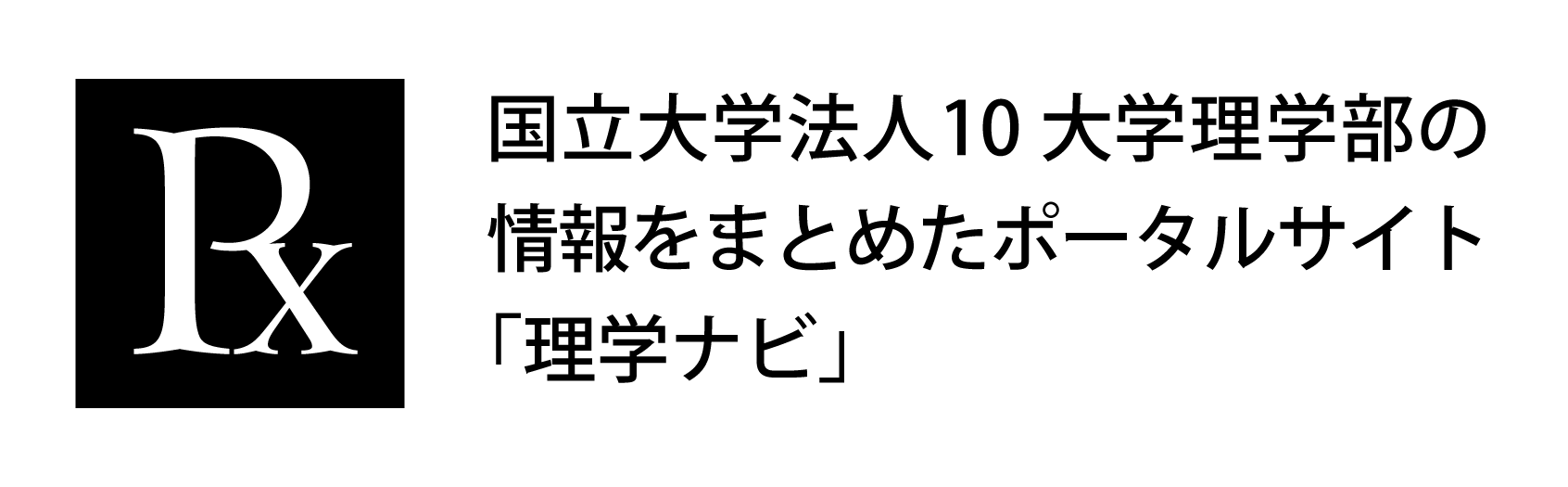大学院先進理工系科学研究科 教授 吉田拡人
Tel:082-424-7724
E-mail:yhiroto*hiroshima-u.ac.jp
(*は半角@に置き換えてください)
本研究成果のポイント
- 新しい反応法の開発:有機ホウ素反応剤を使った鈴木カップリング反応の新しい手法を開発し、反応剤の安定性と反応性を両立させることに成功しました。
- 反応性と安定性のジレンマ:通常、有機ホウ素反応剤は高い反応性を持っていますが、特定の条件では不安定になりがちです。一方で、安定性を高めると反応性が低下します。この研究では、そのジレンマを解決する方法を見つけました。
- 機能性分子の創製で幅広い応用が期待:安定性と反応性を高める新しい手法は、産業上役立つ化学プロセスの開発や、ポリマー系太陽電池などの有機材料や医薬品の合成などに利用できる可能性があり、今後の応用が期待されます。
概要
広島大学大学院先進理工系科学研究科の吉田拡人教授を中心とした研究チームは、有機ホウ素反応剤のホウ素部位の「ルイス酸性」1を綿密に制御することで、極めて高い安定性と、適切な反応性を併せ持つ、鈴木–宮浦クロスカップリング反応(鈴木カップリング)2の開発に成功しました。一般に鈴木カップリングに用いられる有機ホウ素反応剤は、ホウ素が元来持つルイス酸性の高さゆえに高い反応性を示す一方、有機基によっては不安定で反応利用できないものも存在します。一方、ルイス酸性を置換基によって抑制することで化合物の安定性は向上できますが、同時に反応性が低下し、一般的な鈴木カップリング条件下では反応しなくなります。このように有機ホウ素反応剤の「反応性」と「安定性」はトレードオフの関係にあるため、このジレンマ解決が鈴木カップリングにおける唯一の課題でした。本手法は、強力にルイス酸性が抑制されているがゆえに、極めて安定で反応性に乏しかった有機ホウ素反応剤を、通常の鈴木カップリング条件下反応利用可能とした世界初の成果です。本手法は、有機ホウ素反応剤を用いる他の反応開発への応用、生活を豊かにする有機材料や機能性分子3創製への展開、医薬品の新しい合成ルートの発見、などに貢献することが期待されます。
本研究成果は、米国化学会「JACS Au」オンライン版に10月7日に掲載されました。
論文情報
- 掲載雑誌:JACS Au
- 論文題目:Weak Base-Promoted Direct Cross-Coupling of Naphthalene-1,8-diaminato-Substituted Arylboron Compounds
- 著者:Kazuki Tomota, Jialun Li, Hideya Tanaka, Masaaki Nakamoto, Takumi Tsushima, and Hiroto Yoshida*
*Corresponding author(責任著者) - DOI:10.1021/jacsau.4c00665
背景
クロスカップリング反応は、有機化合物の炭素–炭素結合を構築し、ビアリール4をはじめとする様々な分子を簡便に合成する極めて重要な反応です。この反応に用いられる金属元素は主に5つですが、有機ホウ素反応剤を用いる鈴木カップリング(2010 年 ノーベル化学賞受賞対象)は、ホウ素の毒性の低さ、取り扱いやすさから最も実用的であり、実際に血圧降下剤ロサルタンをはじめとする、多くの医薬品や機能性材料の工業生産にも用いられています(図 1A)。この鈴木カップリングでは塩基5を活性化剤として使用することで反応が進行しますが、その塩基に対する耐性が低く、反応利用が困難な有機ホウ素化合物も存在します(図 1B)。特に、2-ピリジルやペンタフルオロフェニル、チアゾリルは医薬品や機能性材料に頻出の骨格であるにも関わらず、それらの対応するボロン酸は中性条件や塩基性条件で非常に不安定であることが知られています。一方、本研究グループでは、この不安定ホウ素化合物のホウ素周りを、1,8-ジアミノナフタレン(dan)で置換することで、塩基に対して極めて安定になることを明らかにしています(図 2A)。しかし、塩基に対する安定性の向上は、鈴木カップリングにおける反応性の低下をもたらすため、この保護型ホウ素反応剤[Ar−B(dan)]を鈴木カップリングに用いる際は、強い活性化剤である強塩基の使用が必須でした(図 2B)。この条件では2-ピリジルB(dan)の反応は効率よく進行しましたが、ペンタフルオロフェニルやチアゾリルB(dan)は、反応系への僅かな水の混入で即座に分解してしまい、反応効率が大幅に低下します。また、強塩基を反応に用いる際には、塩基に鋭敏な官能基を用いることができない、すなわち官能基許容性6が低くなる課題もあります。
図1. 鈴木カップリングの概要
図2. 保護型ホウ素反応剤の概要と鈴木カップリングへの利用
研究成果の内容
今回本研究グループは、これらの課題解決に向け、通常の鈴木カップリングで用いられるパラジウム(Pd)触媒に加え銅(Cu)を協働触媒7として用いることで、Ar−B(dan)の弱塩基条件鈴木カップリングを達成しました(図 3A)。実際に、ボロン酸構造では極めて不安定で、従来の鈴木カップリングが唯一苦手としていた、2-ピリジルやペンタフルオロフェニル、チアゾリルを有機基とするB(dan)のカップリング反応は効率よく進行し、対応するカップリング体を効率よく得ることに成功しました。また、弱塩基を用いる本手法は、以前の強塩基を必要としていた条件とは対照的に、様々な官能基を利用でき、それらを損なうことなく高収率でカップリング体を得られます。さらに本反応の応用展開として、元来低反応性なB(dan)部位を残したまま、スズ(Sn)のような他の金属部位や、異なる置換基を有するホウ素部位、B(pin)8を選択的、連続的にカップリングさせることにも成功しています。これによりテトラアリール9を短工程かつ高収率で得ることができます。
図 3. 本研究の概要
今後の展開
これまで不安定性ゆえに鈴木カップリングに利用することができなかった一群の有機ホウ素化合物を、ルイス酸性を抑制することで格段の安定化を図りながら反応利用可能にした本研究は、合成化学だけでなく、薬学や材料化学など周辺分野の発展にもつながる成果といえます。今後はdan置換有機ホウ素反応剤の安定性を利用した、新たな炭素骨格構築反応などへの利用が期待されます。
用語解説
1. ルイス酸性:ルイスによる酸の定義であり、電子対を受け取る性質を指す。
2. 短工程合成:従来法よりも少ない手順で有機分子の合成を可能にすること。
3. 鈴木–宮浦クロスカップリング反応:パラジウム触媒存在下「炭素-ホウ素結合」と「炭素-ハロゲン結合」を選択的に反応させ「炭素-炭素結合」を形成する反応。略して鈴木カップリングとも呼ばれる。
4. ビアリール:化学構造の一部に2つのアリール基(ベンゼン環のような芳香族環に基づく構造)が結合した分子。
5. 塩基:酸と対になる化合物で、ルイス酸と反応する。鈴木カップリングにおいては特にホウ素と相互作用する。
6. 官能基許容性:分子に置換した官能基が反応条件下で安定であるかどうかを指す。
7. 協働触媒:2つ以上の触媒が一緒に働くことで、通常の1つの触媒だけでは達成できないような化学反応を引き起こすもの。
8. B(pin):ボロン酸のホウ素部位をピナコールで置換した化合物。ボロン酸同様ルイス酸性を示し、鈴木カップリングに多用される。
9. テトラアリール:化学構造の一部に4つのアリール基(ベンゼン環のような芳香族環に基づく構造)が結合した分子。

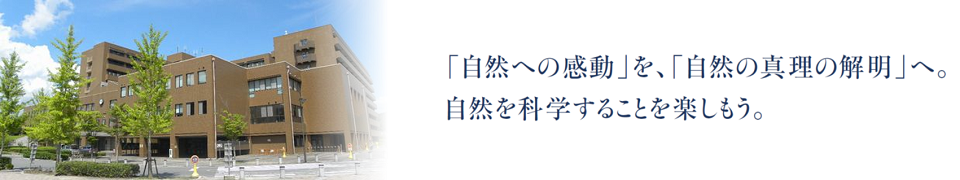
 Home
Home