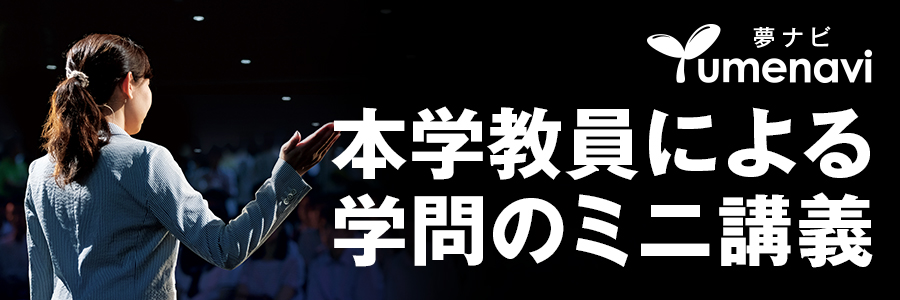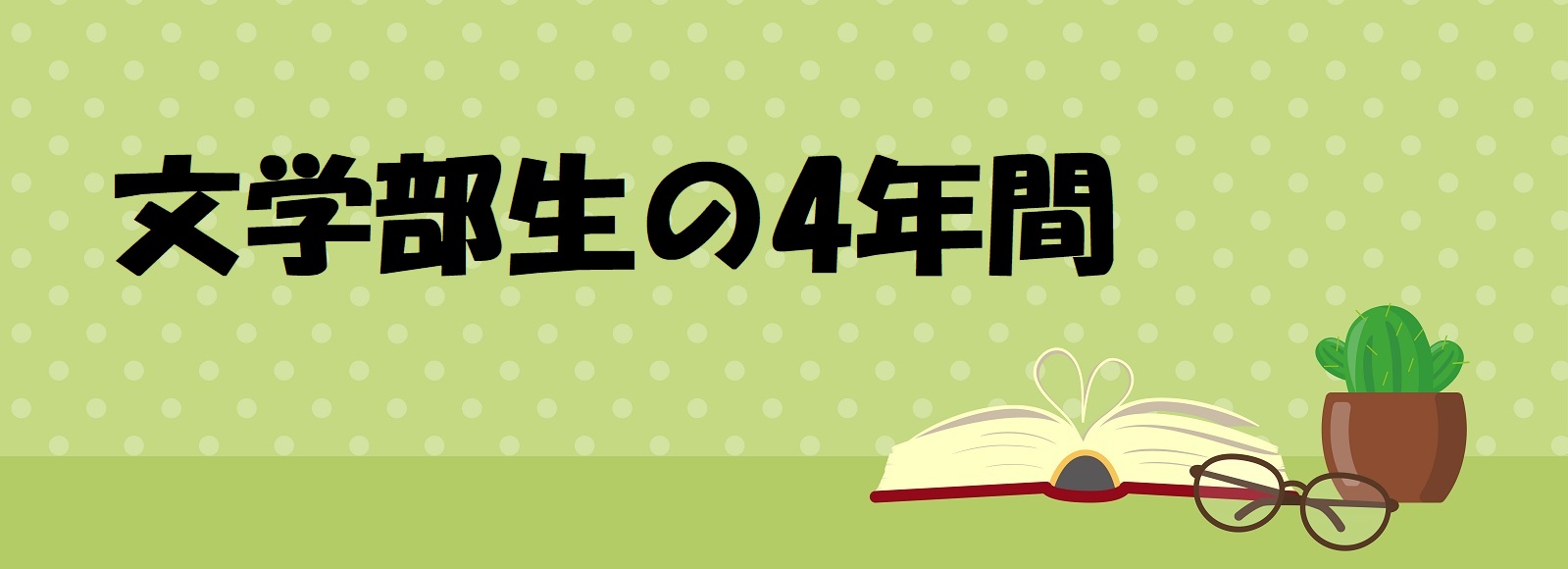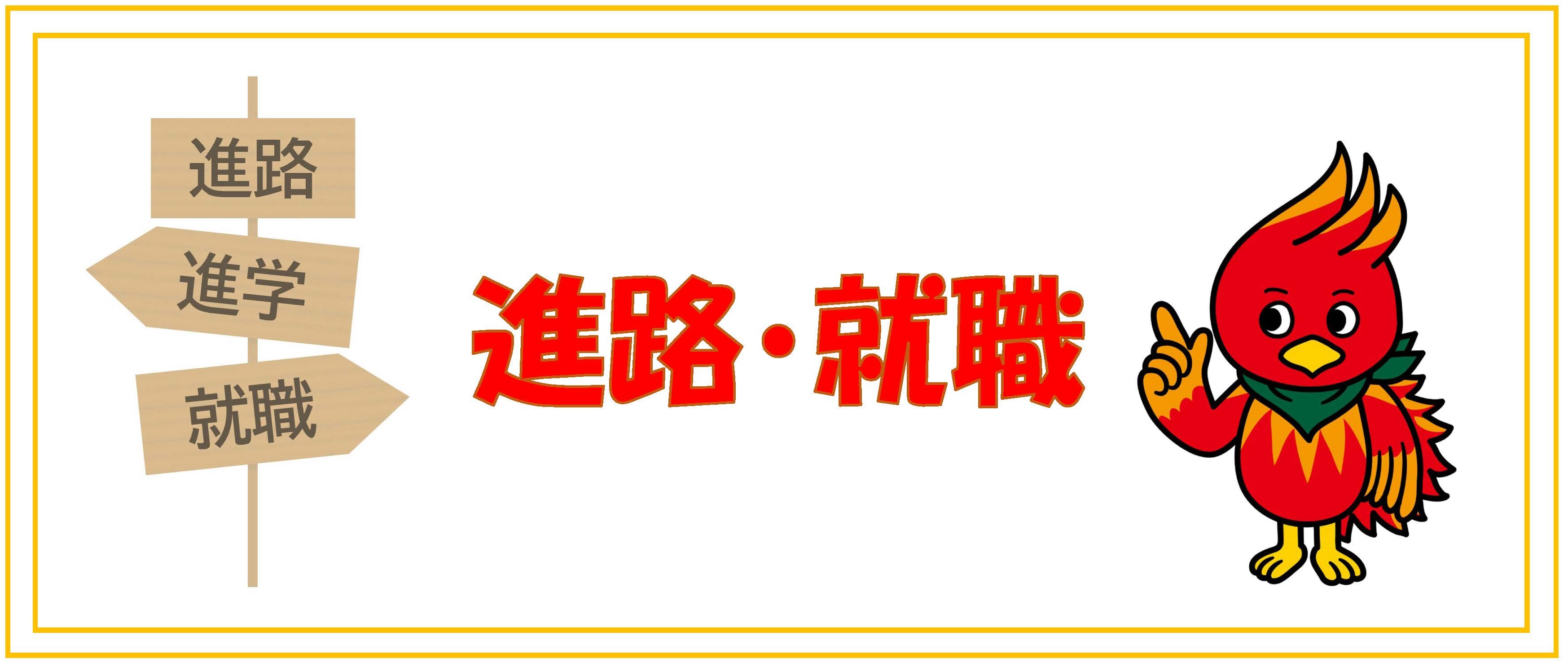| 修了年度 | 氏名 | 専門分野 | 博士論文題目 |
|---|---|---|---|
| 人間文化学分野 | |||
| 23 | 尹 祥漢 | 比較日本文化学 | コンピュータ媒介コミュニケーション言語の総合的研究 |
| 思想文化学分野 | |||
| 15 | 渡辺 俊和 | インド哲学 | ダルマキールティ推理論の研究 |
| 15 | 小林 裕明 | 哲学 | ヘーゲルの哲学体系と精神の意義についての研究 |
| 16 | 村下 邦昭 | 哲学 | フィヒテ初期知識学の実践的部門の研究 |
| 16 | 田頭 世光 | 倫理学 | 法然による善導受容とその意義 ―「偏依善導一師」をめぐって― |
| 17 | 宮田 健一 | 倫理学 | G.E.ムーア研究 |
| 17 | 小林 久泰 | インド哲学 | プラジュニャーカラグプタ自己認識理論の研究 |
| 17 | 江崎 公児 | インド哲学 | ウダヤナ刹那滅論批判の研究 |
| 17 | 川尻 洋平 | インド哲学 | シヴァ教再認識派アートマン論の研究 |
| 19 | 硲 智樹 | 倫理学 | 自己意識と反省 ―ヘーゲルにおける承認の理論とその論理的構造について― |
| 20 | 根本 裕史 | インド哲学 | ゲルク派における時間論の研究 |
| 20 | 田坂 素恵子 | 倫理学 | 生命の研究 ―生命倫理の視点から― |
| 21 | 村澤 琢磨 | 倫理学 | アダム・スミス徳倫理学の研究 |
| 21 | 濱井 潤也 | 哲学 | ヘーゲル『法の哲学』における国家論について |
| 22 | 野村 卓史 | 哲学 | ヘーゲル『精神現象学』研究 ―「絶対知」の解明― |
| 23 | 山崎 一穂 | インド哲学 | クシェーメーンドラの仏教説話の研究 |
| 23 | 片山 由美 | インド哲学 | 法華経一乗思想の研究 |
| 歴史文化学分野 | |||
| 15 | CHONLAWORN PIYADA | 東洋史学 | シャムと東アジア諸国との交流史 ―15世紀から17世紀前半まで― |
| 16 | 石田 雅春 | 日本史学 | 戦後日本における文教政策の展開と構造 ―教科書問題を中心に― |
| 16 | 渡邊 誠 | 日本史学 | 平安時代貿易制度の展開と東アジア海商 |
| 19 | 鴨頭 俊宏 | 日本史学 | 近世瀬戸内海路を巡る情報とその特質 ―幕府公用通行を中心に― |
| 20 | 細川 月子 | 東洋史学 | 植民地期アチェにおける住民農業と原住民首長 |
| 21 | 上田 新也 | 東洋史学 | 黎鄭政権機構の研究 |
| 22 | 齋藤 拓海 | 日本史学 | 平安時代の王朝儀礼と武士・武芸 |
| 24 | 奥山 広規 | 西洋史学 | 古代東地中海地域の碑文研究 ―都市ティールを中心に― |
| 25 | 加納 亜由子 | 日本史学 | 近世後期地域社会の存立構造と「家」と成員 |
| 中国文化学分野 | |||
| 16 | 武 宇林 | 中国文学語学 | 中国西北部口承民歌「花児」研究 |
| 17 | 趙 建紅 | 中国文学語学 | 六朝説話と日本文学 ―動物説話を中心に― |
| 17 | 工藤 卓司 | 中国思想文化学 | 『賈誼新書』の研究 |
| 18 | 本多 道 | 中国思想文化学 | 明末仏教の研究 ―紫柏真可を中心として― |
| 19 | 中木 愛 | 中国文学語学 | 白居易詩研究 |
| 21 | 郭 穎 | 中国文学語学 | 『東瀛詩選』研究 ―兪樾の修改を中心として― |
| 22 | 章 剣 | 中国文学語学 | 『蒙求和歌』の研究 |
| 24 | 許 飛 | 中国文学語学 | 小説と墓券から見る漢魏南北朝の冥界 |
| 言語表象文化学分野 | |||
| 15 | 鄭 寶賢 | 日本文学語学 | 井伏鱒二研究 |
| 16 | 山下 悠水子 | 日本文学語学 | 三島由紀夫研究 |
| 16 | 小川 陽子 | 日本文学語学 | 『源氏物語』享受史についての研究 ―続編としての『山路の露』『雲隠六帖』を中心に― |
| 16 | 福田 泰久 | アメリカ・イギリス文学 | ヴィクトリア朝後期の冒険小説におけるジェンダー表象と性の政治学 ―H.R. ハガード、ブラム・ストーカー、R.L.スティーブンソンを中心に― |
| 16 | 楠木 佳子 | アメリカ・イギリス文学 | Poetry under Pressure: Irresistible Power at the Count of Henry VIII and Sir Thomas Wyatt |
| 16 | 福元 広二 | 英語学 | The Grammaticalization of Pragmatic Markers in Early Modern English: With Special Reference to Verbs of Saying |
| 17 | 樋口 友乃 | アメリカ・イギリス文学 | ヴラジーミル・ナボコフ文学の転機 ―亡命の軌跡と作家像の変遷― |
| 17 | 栗原 武士 | アメリカ・イギリス文学 | "Where I'm Escaping from: Raymond Carver's Conservatism and Its Deconstruction" |
| 17 | 重迫 和美 | アメリカ・イギリス文学 | Faulkner文学の「語り」の技法 ―巨きな実験の軌跡― |
| 17 | 前村 晃子 | ドイツ文学語学 | クライスト小説研究 |
| 17 | 石 小軍 | 英語学 | Gerund and Progressive Form in ME and EModE:With Special Reference to THE ENGLISH HEXAPLA |
| 17 | 今林 修 | 英語学 | Charles Dickens and Literary Dialect |
| 18 | 藤澤 博康 | アメリカ・イギリス文学 | シェイクスピア後期劇と初期近代イギリスにおける社会階層 |
| 18 | 二宮 智之 | 日本文学語学 | 夏目漱石研究 ―小品の独自性と可能性― |
| 18 | 西村 政人 | 英語学 | Further Investigation into the Scansion of Chaucer's Troilus and Criseyde :Revising the Scansion Dictionary of Chaucer's Troilus and Criseyde ( チョーサー『トロイルスとクリセイデ』の韻律研究と韻律辞典の改訂) |
| 18 | 橋本 朝子 | 英語学 | A Stylistic Approach to Katherine Mansfield's Short Novels キャサリン・マンスフィールドの短篇小説における文体的考察 |
| 18 | 竹山 友子 | アメリカ・イギリス文学 | ‘Our beeing your equals,free from tyranny’: Female Appropriation of Stoicism,Christian Humanism and Neostoicism in Writings by Aemilia Lanyer and Elizabeth Cary (「専制支配から解き放たれ、あなた方と同等な私達」−エミリア・ラニヤーおよびエリザベス・ケアリーの作品におけるストア主義・キリスト教人文主義・新ストア主義の女性側からの領有) |
| 19 | 木原 貴子 | アメリカ・イギリス文学 | ヴィクトリアン・フェミニニティ |
| 19 | 住田 光子 | アメリカ・イギリス文学 | 現代のShakespeare演劇・映画翻案にみられる抑圧と被抑圧の意匠 ―1970年代から2000年代初頭までの演出家・映画監督の<adaptation>に着目して― |
| 19 | 辰本 英子 | 英語学 | Negative Expressions in Jane Austen's Novels (ジェイン・オースティンの小説における否定表現) |
| 19 | 吉田 敬 | 日本文学語学 | 荒川洋治の現代詩研究 ―虚構と隠喩― |
| 19 | 田多良 俊樹 | アメリカ・イギリス文学 | ジェイムズ・ジョイスと引喩の政治学 ―植民地性,民族主義,間テクスト性 |
| 19 | 新居 和美 | 日本文学語学 | 『とりかへばや』享受史についての研究 |
| 19 | 黄 峻 | アメリカ・イギリス文学 | Tension between Fact and Fiction in Hemingway's Writings:His Journalism and Creation of Fiction (ヘミングウェイの作品における事実とフィクションの間のテンション:彼のジャーナリズムとフィクションの創作) |
| 20 | LEONG YUT MOY | 日本文学語学 | 夏目漱石研究 ―初期作品における語りに関する比較文学的考察― |
| 20 | 城戸 光世 | アメリカ・イギリス文学 | ナサニエル・ホーソーンの場所表象 ―ウィルダネスからユートピアへ― |
| 20 | 藤吉 清次郎 | アメリカ・イギリス文学 | ホーソーンと人種問題 |
| 20 | 本岡 亜沙子 | アメリカ・イギリス文学 | 19世紀後期アメリカ児童文学における孤児 |
| 20 | 平野 温美 | アメリカ・イギリス文学 | Typee and Beyond:The Dynamics of History,Fiction and Myth 『タイピー』他 ―歴史、虚構、神話の力学 |
| 20 | 石倉 和佳 | アメリカ・イギリス文学 | Coleridge and the Age of Science:The Romantic Pursuit of Ideal Visions through Scientific Practice コールリッジと科学の時代:ロマン主義における科学的実践からの理想的ヴィジョンの追求 |
| 20 | 川口 千富美 | アメリカ・イギリス文学 | William Faulkner の作品におけるJohn Keats の足跡 ―フォークナーが創り上げた「ギリシアの甕」― |
| 21 | 東海 麻衣子 | フランス文学語学 | シャルル=ルイ・フィリップにおける「時」・「時間」・「時間意識」の考察 |
| 22 | 佐藤 由美 | アメリカ・イギリス文学 | The Poetess and the Prostitute: Female Identity and Fallenness in Christina Rossetti and Elizabeth Barrett Browning (詩人と娼婦-クリスティーナ・ロセッティとエリザベス・バレット・ブラウニングの作品における女性性と堕落の研究) |
| 22 | 島田 隆輔 | 日本文学語学 | 宮沢賢治研究/文語詩集の成立 ―鉛筆・赤インク〈写稿〉による過程― |
| 22 | 佐伯 友紀子 | 日本文学語学 | 「西鶴独吟百韻自註絵巻」の基礎的研究 ―俳諧観の研究から内容論へ― |
| 23 | 長福 香菜 | 日本文学語学 | 明治御歌所派歌壇の研究 ―高崎正風・税所敦子を中心に― |
| 23 | 舩田 佐央子 | 英語学 | Rhetorical Expressions in Charles Dickens’s Novels |
| 23 | 中元 さおり | 日本文学語学 | 三島由紀夫研究 ―時代との交錯― |
| 23 | 澤田 真由美 | 英語学 | Infinitival Complementation in Late Middle English:With Special Reference to Chaucer's Works (後期MEにおける不定詞補文―チョーサーの作品を中心に) |
| 23 | 末柗 昌子 | 日本文学語学 | 浅井了意『可笑記評判』の研究 |
| 23 | 五十嵐 博久 | アメリカ・イギリス文学 | Comic Madness, or Tragic Mystery, That is the Question: The Loss of Comic Features and the Invention of the Tragic Mystery in Shakespeare's Hamlet |
| 地表圏システム学分野 | |||
| 15 | 近藤 久雄 | 地理学 | 横ずれ断層の幾何学的形態と単位変位量からみた大地震の繰り返しに関する研究 |
| 16 | 高田 圭太 | 地理学 | 沖積層の堆積構造にもとづく古地震イベントの解明に関する研究 |
| 16 | 山田 岳晴 | 文化財学 | 安芸国における神社玉殿の起源と発展に関する研究 |
| 17 | 中條 曉仁 | 地理学 | 中山間地域における高齢者の生活維持とそのメカニズムに関する研究 |
| 17 | 宮内 久光 | 地理学 | 本土復帰以降における沖縄県離島地域の変容に関する地理学的研究 |
| 17 | 八幡 浩二 | 考古学 | 古代日本の鉄・鉄器生産体制の考古学的研究 |
| 17 | 山口 直子 | 文化財学 | 日本古代中世不動明王画像の研究 |
| 18 | 斎藤 丈士 | 地理学 | 米政策転換期におけるわが国大規模稲作地域の構造変動に関する地理学的研究 |
| 18 | 佐藤 裕哉 | 地理学 | 知識集約型産業の立地展開とイノベーション創出に関する地理学的研究 |
| 18 | 河本 大地 | 地理学 | 有機農業の展開と有機農産物産地の形成に関する地理学的研究 ―日本およびスリランカを事例として― |
| 20 | 原田 倫子 | 文化財学 | 考古学からみた中世地域社会の構造 ―中国地方の中世遺跡を中心として― |
| 20 | 佐藤 大規 | 文化財学 | 安土城天主の研究 |
| 20 | 柳川 真由美 | 文化財学 | 室町時代における武家服飾の特質と変遷 |
| 20 | 山口 佳巳 | 文化財学 | 中世厳島神社社殿の研究 |
| 21 | 宇根 義己 | 地理学 | タイにおける自動車産業の空間的展開に関する地理学的研究 |
| 21 | 川后 のぞみ | 文化財学 | 居住空間に対する民俗的心性 |
| 21 | 髙間 由香里 | 文化財学 | 日本中世浄土教絵画論 |
| 21 | 和田 崇 | 地理学 | ジオサイバースペースの空間構造に関する地理学的研究 ―地域のコミュニケーションの視点を中心に― |
| 22 | 谷岡 能史 | 考古学 | 考古遺跡で検出された洪水痕跡と古気候の関係 |
| 23 | 田中 健作 | 地理学 | 農村地域における公共交通の再編成に関する地理学的研究 |
| 24 | 村松 洋子 | 文化財学 | 近代における入浜塩田の浜子に関する研究 |
| 24 | 絹川 一徳 | 考古学 | 西日本後期旧石器時代における横剥ぎ石器製作技術の成立と展開 |
| 26 | 脇山 佳奈 | 考古学 | 小型仿製鏡をめぐる考古学的研究 |

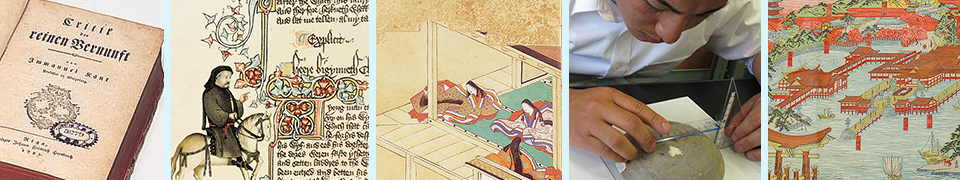
 Home
Home