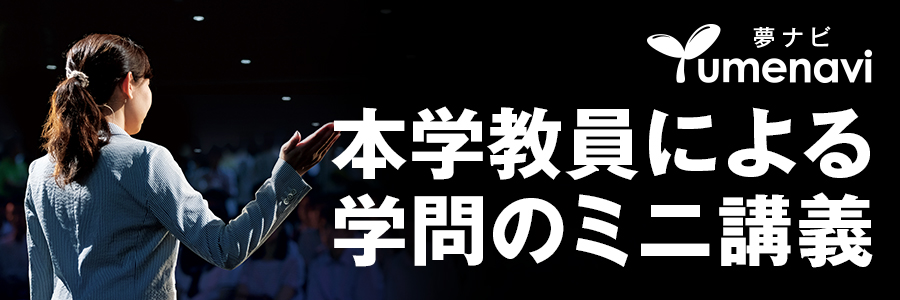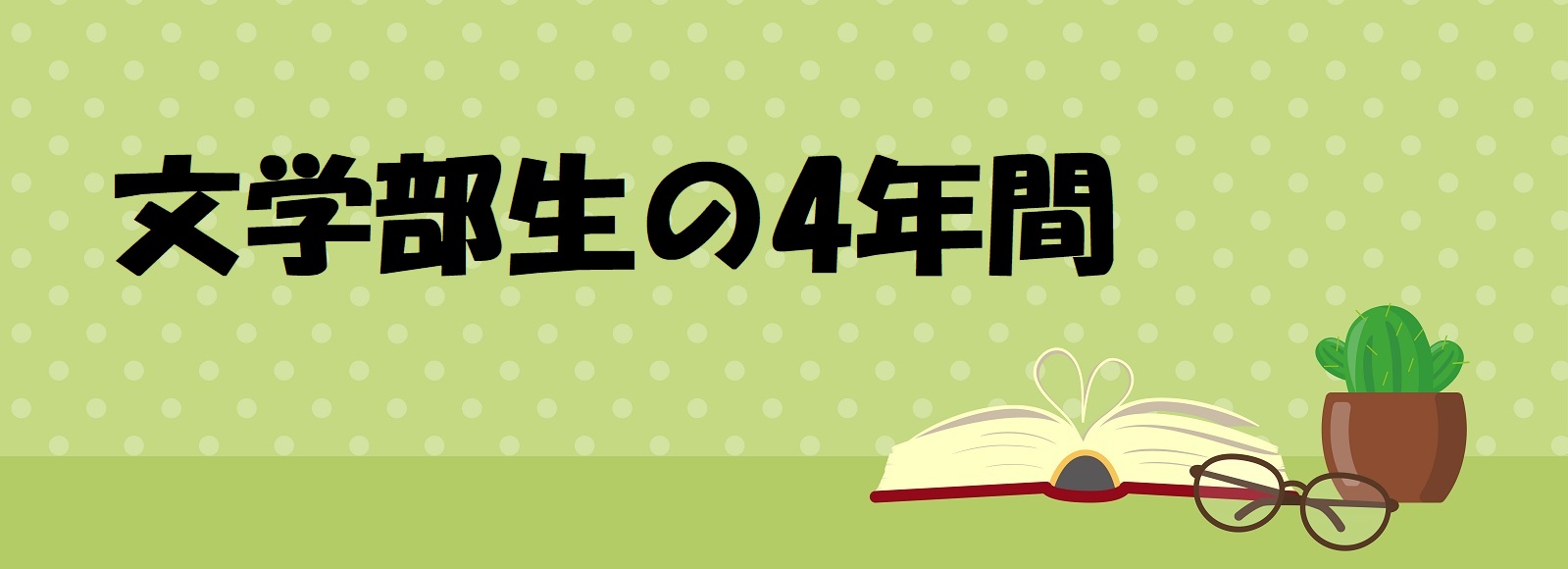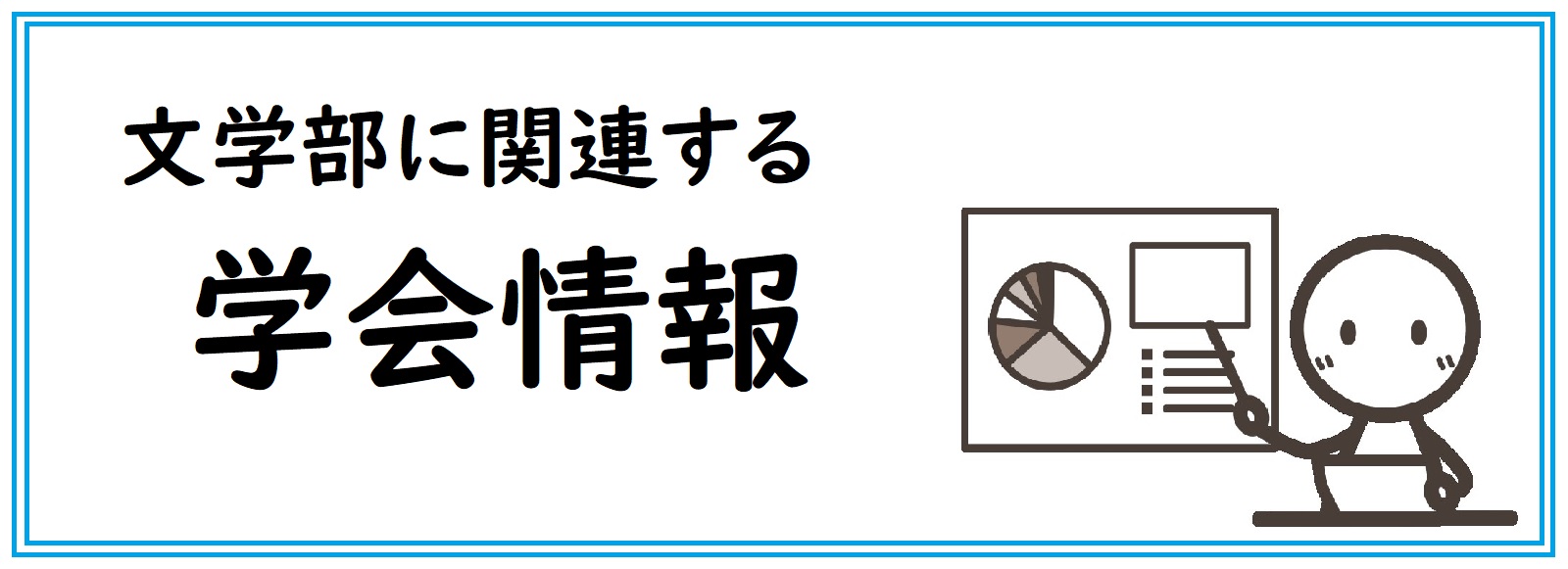「職業」「天職」のことを英語で「calling」といいますが(神に呼ばれる、召命という意味)、はじめてそれを知ったときは、なるほど、と思いました。職業とは自分の意思で選ぶものではなく、「呼ばれる」ものなのだと。原義からは離れますが、文学研究に関していえば、「作品に呼ばれる」というようなことがあるように思います。
私が研究をしているのは、今から四百年ほど前、明の時代に作られた『金瓶梅』という長編小説です。『三国志演義』『水滸伝』『西遊記』とともに中国四大奇書のひとつにかぞえられますが、他の三作品と違って、ひとりだけ日の当たらない存在です。そんな「名前は聞いたことがあるけれど、よく知らない」といわれる作品をなぜ研究しているのか、結論からいうと、「呼ばれた」からなのではないかと思います。
ジャッキー・チェンが好き、という不純な動機で中国に興味を抱くようになり、中国文学を専攻した私でしたが、授業を通して様々な作品を読むうちに、次第に「女性の描かれ方」に興味を持つようになりました。特に衝撃的だったのは、漢王朝を打ち立てた劉邦の后「呂后」の有名な話です。歴史書の記述によると、劉邦の死後、呂后は劉邦の寵愛を受けていた戚夫人の両手両足を切り落とし、目をえぐり耳をいぶして、声の出なくなる毒薬を飲ませ、便所に閉じ込めると、息子の恵帝を呼んで「彘(人豚)だよ」と言って見せたといいます。ぞっとしました。しかし中国の古典を見渡してみると、呂后は決して特別ではありませんでした。似たような女性の例は他にもたくさん出てきます。日本ではあまり描かれることのない暴力的で残酷な姿に、寒気がすると同時に、なぜこんな女性たちが繰り返し描かれるのだろうかと疑問を抱きました。そこには中国の社会制度や思想的な問題など、様々な要素が絡み合っているのですが、そういう女性たちが実際にいたかどうかは別として、描かれ方があまりにも極端で、パターン化していることが気になったのです。

愛しい人を待ちわびて(『『金瓶梅』の挿絵より)
そんな時に手に取ったのが、『金瓶梅』の訳本でした。『金瓶梅』というタイトルは、登場する三人の女性(潘金蓮、李瓶児、春梅)の名前から一文字ずつをとって付けられたものです。主人公の潘金蓮は、不倫の揚げ句、夫を毒殺したり、恋敵を死に追いやったりと、従来の典型的な悪女の系譜を継ぐ人物として描かれていましたが、私はなぜか潘金蓮に惹かれました。原文できちんと読んでみたい、と強く思いました。
先ほどの呂后のように、中国の文学作品に登場する女性たちは、やや現実離れをしたステレオタイプなものが目立ちます。血も涙もない徹底的な悪女、完璧すぎる良妻賢母、そうした一面的ともいえる女性たちの中にあって、『金瓶梅』には、もがき苦しみつつ人を陥れてしまう第五夫人、良妻賢母とされながらも腹黒さを持つ正妻、そうした複雑で重層的な女性の姿が描かれていました。私は中国文学の中ではじめて「生身の女性」を見た気がしました。性的な描写のせいもあって、日陰に追いやられるという運命を背負ってしまった『金瓶梅』ですが、そうした描写も含め、日々の細かい営みを通して人間の欲望や苦しみが浮かび上がってくるように作品が構成されています。この作品は当時の文人たちにとっても衝撃的だったようで、その中のひとり、馮夢龍という名プロデューサーに、『金瓶梅』を含む四作品が「四大奇書」と名付けられたほどです。
しかし『金瓶梅』のような作品がなぜ明代の終わりに突如として現れたのか、詳しいことは何もわかっていません。作者すら不明です。誰が何のために書いたのかもわからない作品ですが、時間と空間を超えて、現代の日本に生きる私の心をとらえました。私が『金瓶梅』を選んだのではなく、『金瓶梅』が私を呼んでくれたのではないか、そういう気がしています。
強い意志や情熱によって、能動的に何かにアプローチをするという方法ももちろんあるでしょうが、自分の中の小さな興味や疑問に対する呼びかけにじっと耳を傾けるという受動的なアプローチの仕方もあるように思います。職業や学問に限らず、人や場所、物に関しても、そうした呼びかけに耳をすまし、流れに身を任せてみることで、世界がぱっと開けることもあるかもしれません。

日本人学生も留学生も、みんなでひたすら読む!(演習風景)

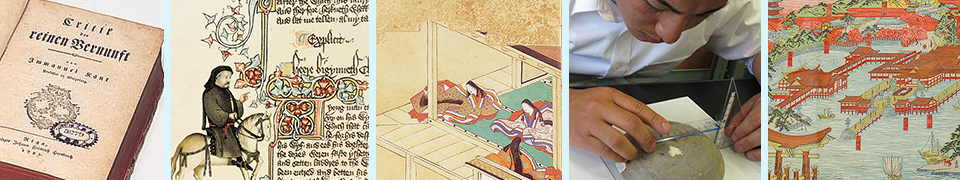
 Home
Home