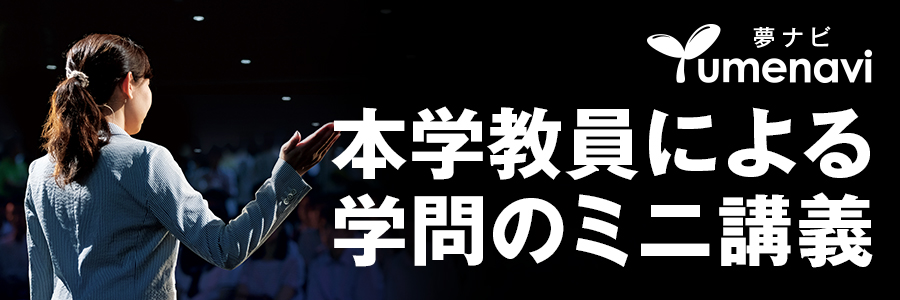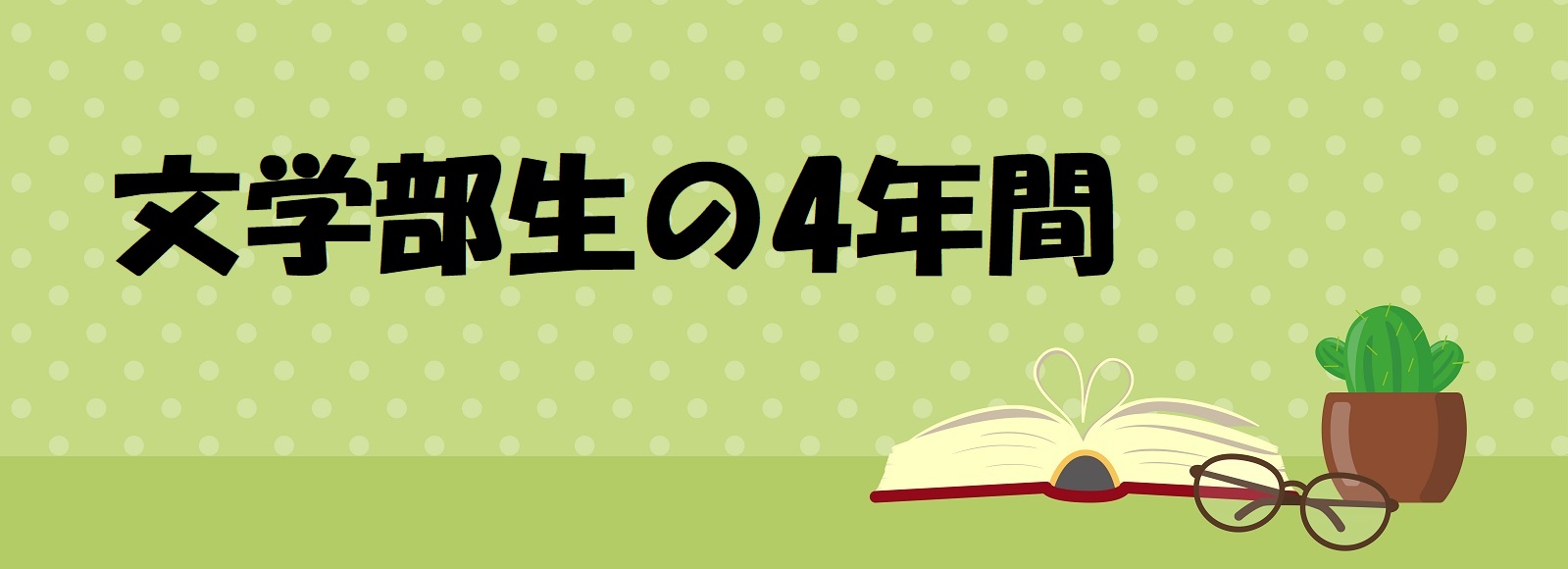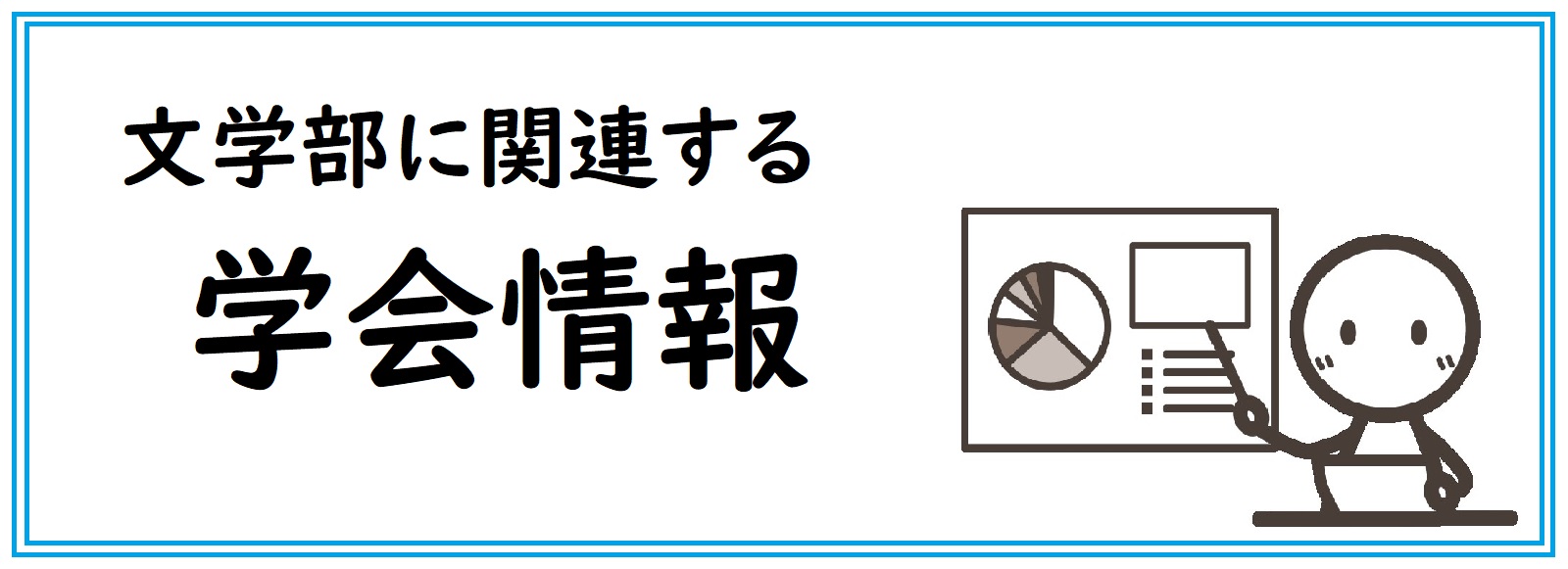自分がこの世に存在することが疑問で、時空間のゆがみに落ちてしまったような感覚にとらわれることがしばしばある、そんな幼少期を過ごしました。
ある夜、深夜零時を回っていたと思います。乗っていた車の後部座席に、赤い小人と緑の小人― しかも、古いグリム童話にでてくるような風貌で、メルヘンの要素はなく、ただ、やたらと不気味な風貌― がはりついて、ずっと家まで追ってくるのです。小児科からの帰り道、高熱を出した後の解熱剤の副作用だと後から聞かされたのですが、その幻影は、その小人たちは時々夢の中に表れては、にたにた笑うのでした。
人は死んだらどこに行くのか、鏡の向こうや水の向こう側に違う世界があるのではないか、と怖くなって一人で震えていることもありました。そういった疑問を口に出すことはいけないことだ、と思い、心の中にそっとしまっていました。時計の針が出す音が怖くて眠れないこともありました。成長するにつれ、小人たちの姿は少しずつ朧げになり、歯を磨くときに鏡をみても、流れる水をみても、時計の針の音が響いていても、あまり怖くはなくなりましたが、それでも自分だけが世界に取り残されているような感覚に襲われることが度々ありました。
中学に入学した頃に見ていた映画には、よく幽霊が登場しました。死後の世界。死者たちの世界。今のような3Dもない時代ですから、幽霊といっても特殊加工はされていません。見る人の想像力に拠るところが大きく、舞台での演出によく似ていました。映画『ゴースト ニューヨークの幻』の中で描かれていた、死者たちの世界は、その後、いつまでも追ってくる世界でした。この映画で、主人公は『マクベス』の観劇に行った帰りに友人の策略で殺される設定なのですが、イギリス留学中に、ウィリアム・シェイクスピアを読み漁るようになってから、『マクベス』の復讐劇が予表として登場していたのだと、英文学を研究するようになってから、それまでに観た映画などを改めて解釈できるようになりました。
当たり前の光景、建物の影が動物のように動いてそれが集まって悪魔になったり、という映画の中の描写は、トマス・ハーディの詩の中に見出すことが出来ました。映画『ゴースト ニューヨークの幻』のラストシーンの、主人公が天に昇る際に、光の円の中へと入っていくような描写がずっと心に残っていたのですが、同じような表現をヘンリー・ヴォーンの「みんな光の国へ行ってしまった」という詩の中で見つけ、とても衝撃を受けたのを今でも覚えています。
教育学部を卒業し、文学研究科に進学して、ヴォーンを研究対象にすることを決めてからは、エイブラハム・カウリーの言葉を借りれば、「まるで私があなたを殺してしまったかのように」、まるで亡霊のように、ずっと私を追いかけてきました。肖像画がないヴォーンの存在は、より濃さを増していきました。寝ても覚めても、電車に乗っていても、星を見ても、珈琲を飲んでいても、どこにいても。
17世紀の詩人たちが憧れ、悩み、苦悩し、葛藤し、喜びを見出した世界、科学技術が発達する以前の人々が作り出した、魂の行方、死者の復活、鏡の向こうに広がる世界、時間を飛び越えた空間の表現は、小さい頃の私が思っていた疑問に答えを与えてくれるものでした。
利益が数値化され、世界と戦おうとする大学構想のなかで、「役にたたない」文学部が解体されようとされている昨今の日本の社会において、文学研究者は、死者の声に耳を傾け、それを現代の人々の声に重ねていく、「声の伝道者」であるとも、思っています。
語りえないものや目に見えないものをどう描くか、その中に学問の本質があること、学問の特質のひとつに慰めがあること、を学生時代の授業で教わり、今はそれを伝えていく立場になりました。死者でもある詩人たちの声を聞くことを大学で教えられるようになりました。英詩のなかで描かれた言葉が、自身の自然との出会いのなかで思い出される、という学生たちの言葉は私の教員生活の支えとなっています。文学に携わることで、学生が一つの物事を多角的に見ることができ、また他人の苦しみや痛みを自己のものとして捉えるような感性を培うことが出来るような授業を目指しながら、文学作品を精読することで作家という死者たちの声に寄り添い、学生たちの声に重ねることで、死者の声を復活させていきたいと思っています。

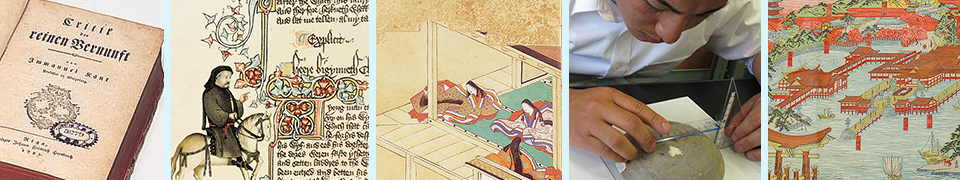
 Home
Home