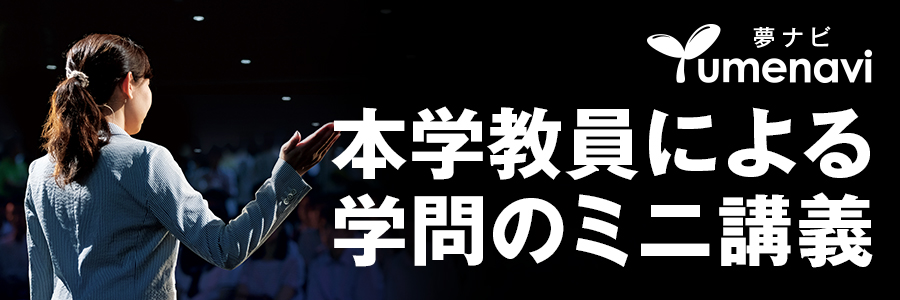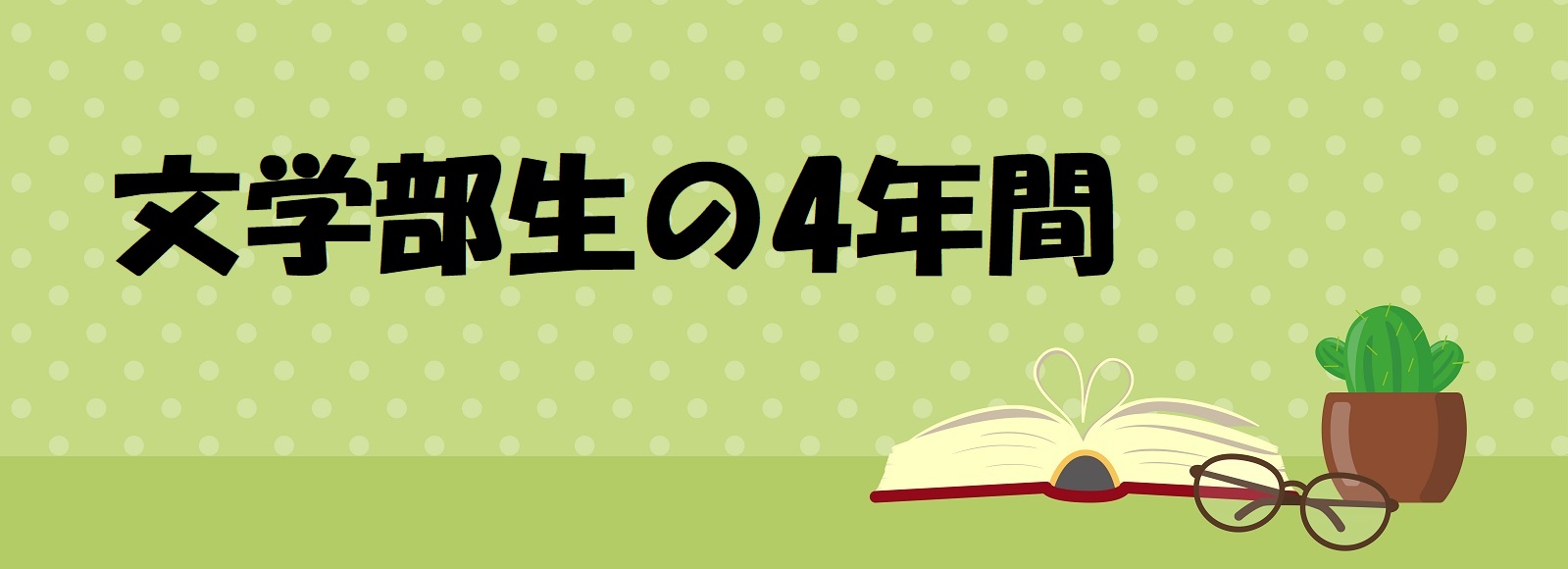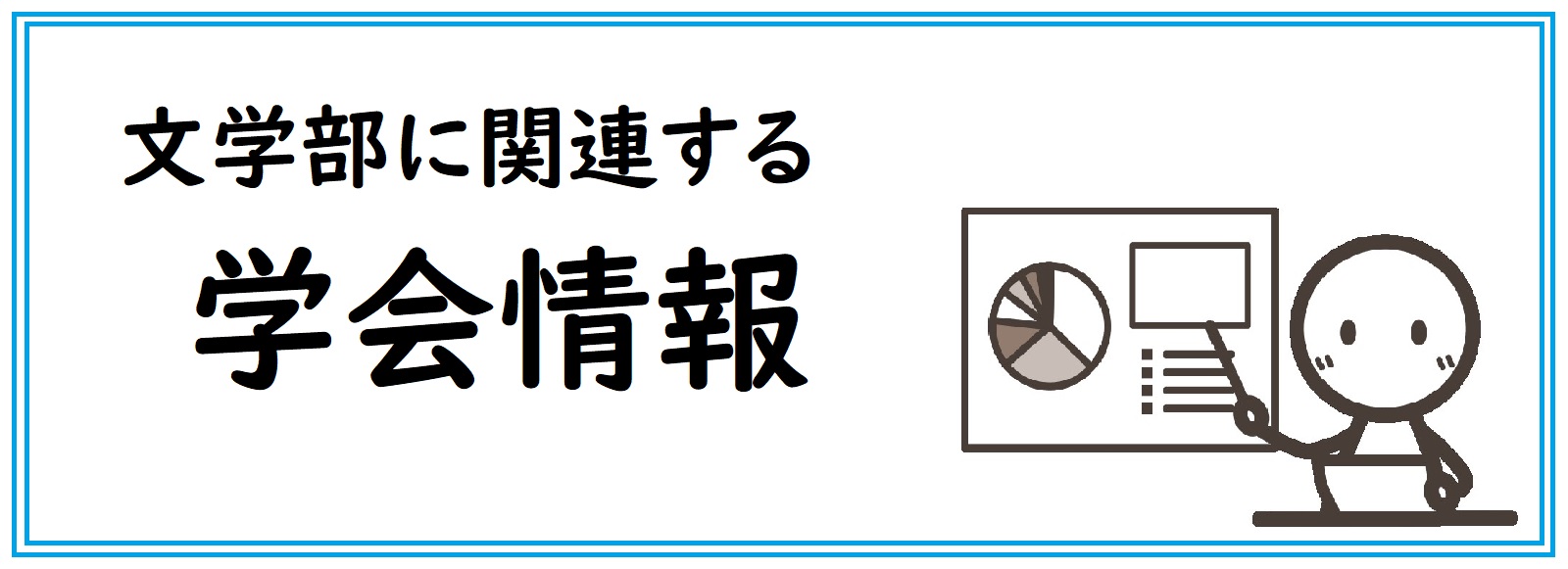幸運なことに、私は、自分の好きなこと、つまり、好きな本を読むことができる仕事に就いています。そもそも、そのために文学を志したのですが、当初は、自分の選択に後ろめたい気持ちもありました。というのも、私の周りには、社会正義に燃え、困っている人たちのために活動をしている人たちや、一流企業に就職し、華々しく社会へ飛び立ってゆく人たちで一杯だったからです。そんなすごい人たちを前に、自分にできることなど考えても無駄で、結局、「これだけ世のため人のためになりそうな人がいるのだから、一人くらい、役に立たないことをやってもいいよね。」という屁理屈をこねて、大学院で学ぶことにしたのでした。
案の定、お世間様からは、「文学などやって何になる。」「もっと地道な仕事に就いた方がいいんじゃない?」というありがたいご意見をいただいたこともありました。そんなときは考え込んだものですが、その時の私の暗い気分など、今考えればごく些細なものでした。というのも、本好きには、もっとつらい時代があったからです。
身近なところでは今から五〇年ほど前の日本。宮崎駿監督は、DVD『ジブリの本棚』の中で、監督の学生時代(一九六〇年代)、本ばかり読んでいる奴は本に夢中になって働こうとしなくなる、と言う大人たち、さらに、読んでいい本と悪い本という区別があって、小説などは娯楽だからろくでもない、と言う大人たちが結構いたと話しています。

『モンテ・クリスト伯』の舞台・イフ島
また、小説好きにはもっと厳しい時代もありました。国はかわりますが、十九世紀のフランス。逆説的ですが、十九世紀はフランス文学にとって華々しい時代です。ではなぜ小説を読むことはいけなかったのでしょうか。その理由として、格調高い文学が生み出される一方で、大衆の気をそそる小説が量産されていたことが挙げられます。そういった大衆小説の中には、今日まで読み継がれ、映画化もされて変わらぬ人気を獲得し続けているデュマの『三銃士』や『モンテ・クリスト伯』、ルルーの『オペラ座の怪人』といった名作もありますが、こういった小説は、同時代の知識人から、「産業文学」「民衆のアヘン」と手酷く非難されました。こんな物語に、美的価値や深い思想などない、あれはオンナコドモ向けだというわけです。ではオンナコドモは許されたのか。そうでもありません。この時代の小説には、身分の高い婦人が「うちの娘は、小説などまったく読みませんのよ。」と語る場面がしばしば登場しますが、これは、うちの娘は小説なんか読む不良ではありません、と娘の道徳観の確かさを自慢する言葉なのです。
まじめな読み物ですら、この時代には、女性が読むことに対しては偏見があったようです。バルザックの『ゴプセック』には、夫の死後の遺産の行方が気になり、法律書を読み漁る女性がおぞましい姿で描かれていますし、ゾラの『金』では、聡明なカロリン夫人が、投機師サッカールが目論む銀行の設立計画の合法性についてこの男を問いただすと、逆に「ナポレオン法典を読んだのか。」と聞かれて顔を赤らめてしまいます。夫人は法典を読んでいたのですが、赤くなったのは、この質問が、オンナダテラニ法律など読んでという非難で、そのために恥じ入ってしまったからなのです。
読書は、それゆえ、必ずしも世間からよく思われてきたわけではなかったのですが、そう考えると、私が今いる文学部は、読書に価値を置く稀な環境と言えるでしょう。私にとって、読書は何よりの娯楽であり、支えであり、逃げ場でもある、不可欠なものであるだけに、読書が主な仕事でもあるのはこの上ない幸せなのですが、そう思うのは、私だけではないでしょう。読書が好きなあなたには、好きな本と共に過ごせる文学部は、きっと居心地がよい場所になると思います。世間の目など気にせず、長い人生のせめて四年間、本を読んで過ごしてみてはいかがですか。

ゾラとその親友で画家のセザンヌが学んだブルボン中学校(現ミニェ中学校)。
小説家で映画監督としても知られるマルセル・パニョルも一時期ここで復唱教師をした。

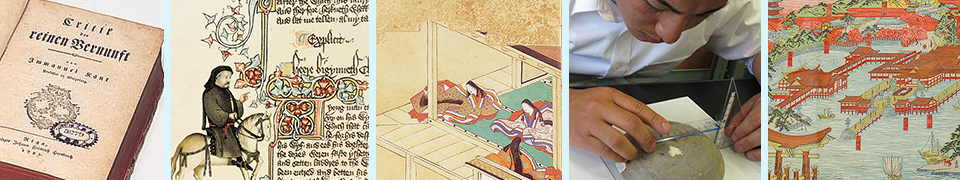
 Home
Home