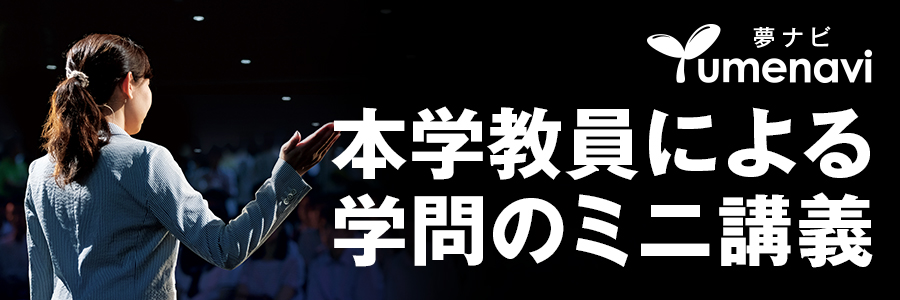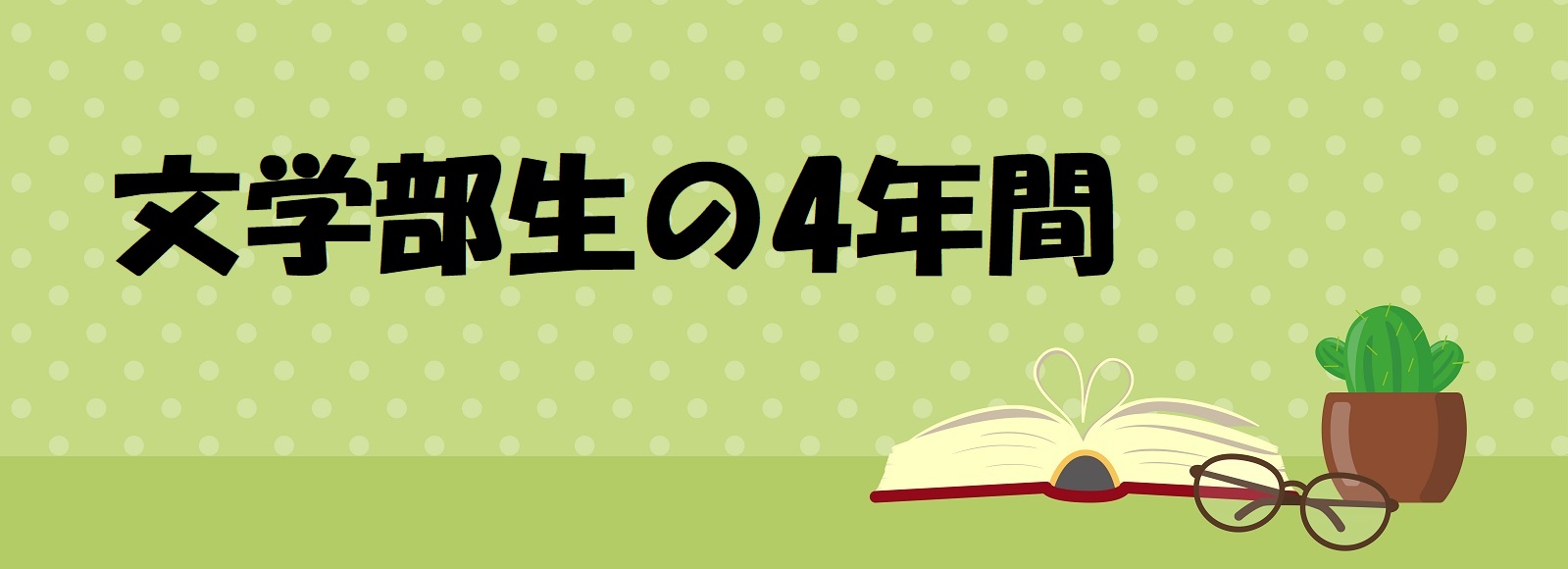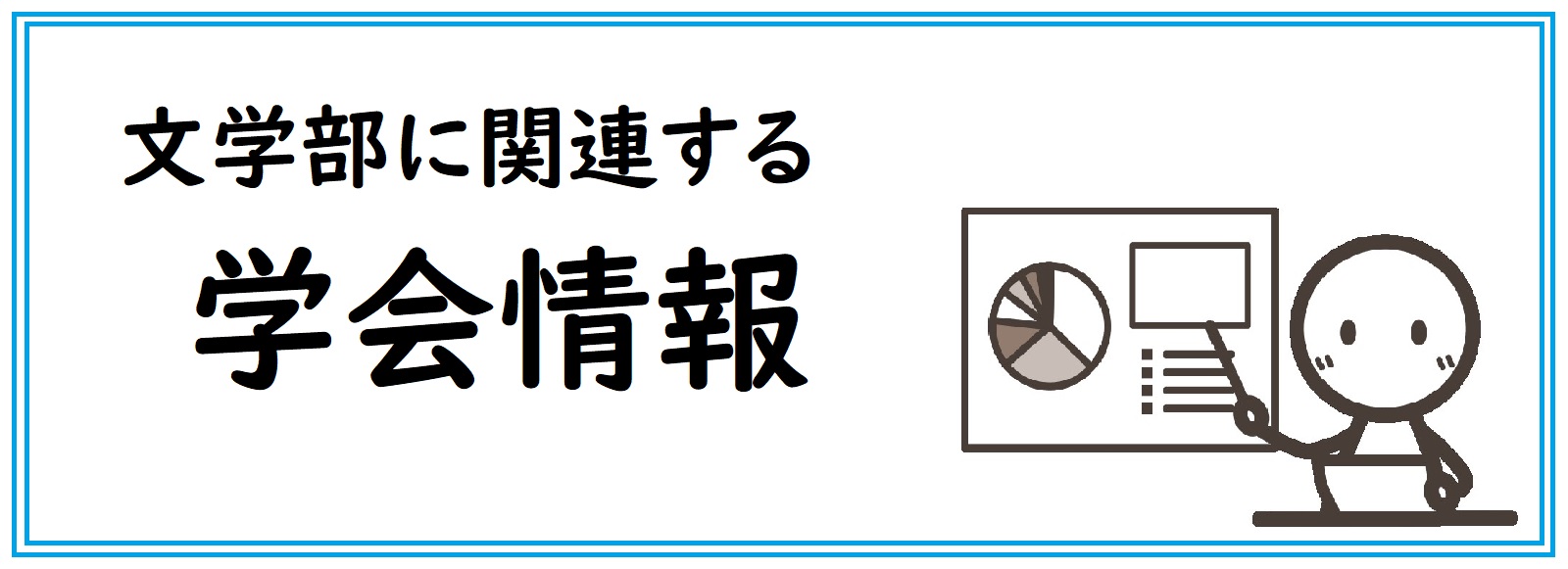人間はだれしも傷のようなものを負っているのではないでしょうか。傷つけられない人生は存在するでしょうか。
自分にとって重要な問題が、こうした傷をめぐるものであったのだと気づかされたのは、博士論文を執筆するプロセスにおいてのことだったと思います。博士論文のテーマは、台湾高地先住民の間でのフィールドワークや史料の分析から、特に暴力の記憶や歴史経験という側面に焦点をあてて、日本の植民地統治の影響に迫ろうとするものでした。
農業経済学や市場史を研究していた父に引き取られたのは私が6歳の時で、離婚した母とはその後8年間ほど、父の有形無形の意思表明によって会うことがかないませんでした。1980年代にあって父子家庭という環境は、何というか「普通」のこととして当たり前に語られる対象ではありませんでした。そのことで憐憫のまなざしを受けたこともあります。その後アカデミズムにおいて出会う、マイノリティという問題に子どものころに出会っていたことになります。
父の影響を陰に陽に受けて、学部で教育社会学、台湾に留学した修士課程で人類学を専攻し、博士課程は植民主義について継続して思考する教員がいる「日本学」というところを渡り歩きました。すべて別の大学になります。博士課程における「日本学」は、たこつぼ化した人文諸学を「現場」との関係のうちに批判的にとらえ返し、自分にとっての方法論をもがきながら探究する、そうした場でした。こうした学びと探究の経験が、広島大学(総合人間学講座)での現在の仕事の中身に大きく影響しています。
私にとっての問題は、父子家庭ということだけにあったのではありませんでした。問題は、それを普通のこととして自由に語れなかった、語ってこなかったということにありました。それはまず、そのことを語らせない父の力(権力)に原因がありました。私の生育家庭では、母という存在はないものとしてあったのです。(家庭と子育ての文脈では、1994年の子どもの権利条約の日本政府批准や、親権や共同養育というパラダイムの問題などがあります。)
語るということは、経験を意味を持ったものにすること(意味付与実践)と関係があります。「腑に落とす」ということでもあります。私は自分の物語を持てないまま「大人」になったのであり、そのことに気づかされたのは、博士論文とその後の論文執筆の中にあってでした。マイノリティの経験と物語る力、暴力やトラウマと言語、書く行為自体の問題など、そうしたことが、人文学の様々な位相で問題になっていたのです。しかし、そうした知見を必要としていた青少年期の私が、それら人文学の一つの前線の議論に触れ、自らの生きる力とすることはかないませんでした。私にとってそれは、アカデミズムという装置(制度)を通して触れ、時間をかけながらゆっくりと理解していったことになります。

「歴史を正視し、正義を返せ」。
台湾の総統府前のケタガラン大通での先住民によるデモ(2016年7月31日、中村撮影)。
「父の問題」は「祖父の問題」に遡ることに、同時に気づかされました。祖父の問題とは、日中戦争で徴兵され、前線で中国人を殺めたことです。祖父はそれを公言しており、若き父が祖父の戦争責任を追及し、祖父が逆上したという話が伝わっています。「中村家」の特殊性は、おそらく多くの日本家庭で秘められてきた、あるいは物語られなかった戦争についての話が、いや傷そのものが、顕在化してしまったことにあるのだろうと思います。また、東京の下町に生育家庭を持った父は、大学院などへの進学とともに、自らの階級性を自覚せざるを得なかったようです。父は東京大空襲に一歳で遭ったのですが、子どものころ、小学校の先生に「最悪の(教育・生育)環境ですね」と言われたこともあったそうです。重なりながらも祖父の傷と父の傷はずれており、またそうした生育プロセスを経た父にとって、私の傷は見えにくいものだったのでしょう。
祖父と父の、傷のようなものの一端を記しましたが、それは、私の形成(成型)ということにずれながらも重なっています。こうしたことに向き合う(向き合える)ようになったのは、先に書いた通り、博士論文の執筆を通してでした。そして、こうした傷が、こうした私のポジション(立っている場所)こそが、私を日本植民主義の暴力の問題に駆り立てたのだと分かってきました。博士論文のテーマは、日本の植民地統治の影響と言えるものですが、それをいかに語ることができるのか悩んだ末、到来する暴力の記憶と歴史経験ということが最終的な軸となっていきました。この「到来する」という部分は、台湾高地のフィールドワークの現場で、私という存在の介入が記憶の到来という事態を引き起しているということを含意します。つまり、私という「日本人」が日本の植民地統治の影響を「聞き‐書く」という事態そのものを、読者に提出しています。
博士論文を基に、『植民暴力の記憶と日本人:台湾高地先住民と脱植民の運動』という本を2018年に出版しました。日本植民主義の傷の探究の旅は、当事者性の問題や責任という問題をいかに考えるかということとも関わり、未だ途上にあります。マイノリティの脱植民(decolonial)的思想=運動と、それはすでに重なっています。この小文を読んでくださった方々の個人史や、家族史と、いつかどこかで(書き物を通しても)触れ合うことができますなら幸いです。

台湾先住民タイヤルが日本兵と戦った時に奪った刀剣。
スマクス集落(台湾新竹県)の歴史資料館にて(2005年、中村撮影)。

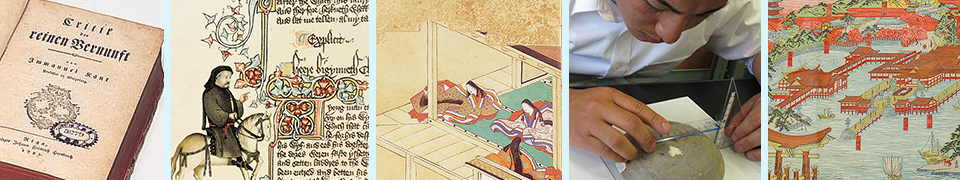
 Home
Home