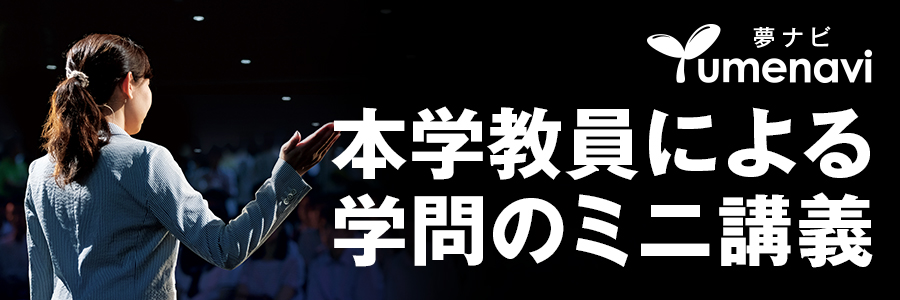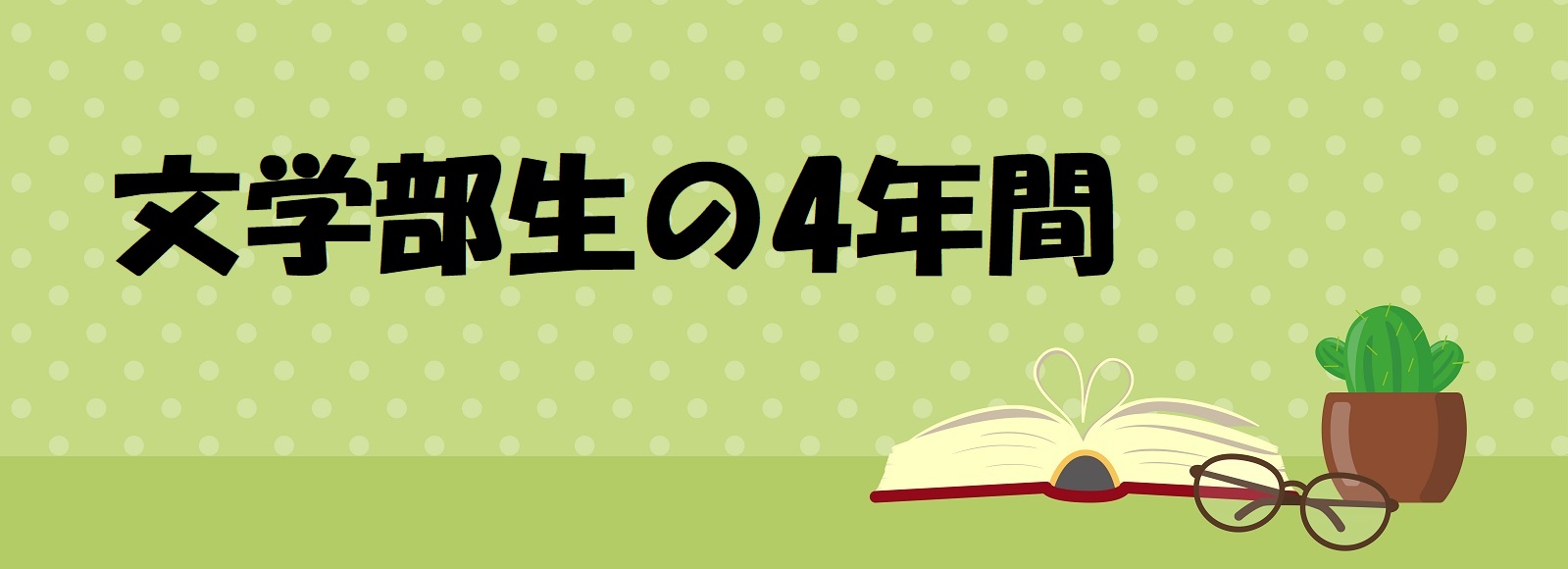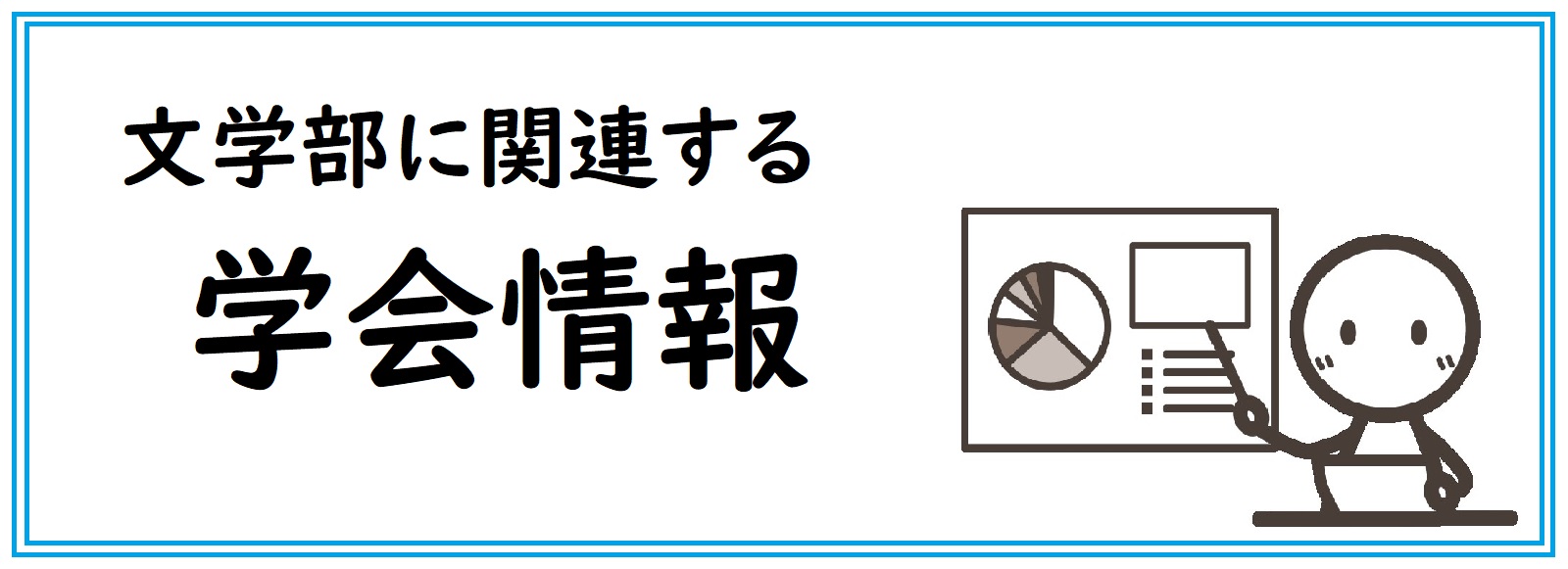私が学生時代を過ごした言語学研究室は、天井まで本が並べられていました。
はじめて研究室へ入ったとき見上げるような書架に圧倒されたことを覚えています。この研究室に大学一年の秋ごろからしばしば出入りするようになりました。広島大学の中で「学問の空気」を呼吸しながら研究の道に進んでいきました。
卒論では『万葉集』の形容詞を扱いましたが、文献を調べれば調べるほどすでに誰かが手がけていることばかりでした。こうなると急にやる気が失せてしまいます。「なあんだ、やり尽くされているのか。この領域はあまり発展が見込めないかも」という閉塞感を感じ始めました。『万葉集』の研究は卒論で打ち止め。大学院に進学するとすぐに次の目標を探し始めました。
このとき出会ったのが社会言語学です。何がきっかけだったのかは忘れましたが、周りに誰もやっている人がいなかったというのが一つの動機になったと思います。しかし今考えてみると無謀でした。誰かに指導してもらえるもないのに、その領域の研究を始めようとしたわけです。ただ幸いなことに、言語学研究室自体、様々な言語を研究する人たちでいっぱいでしたから、何をしようとかまわないよという雰囲気がありました。指導教員の吉川守先生(専門はシュメール語)も決して止めようとはなさいませんでした。かえって、「おもしろそうだね」と励ましてくださったのを覚えています。

学生と資料整理を行う筆者(奥)
文字通り独学で社会言語学の知識を身につけ、修士論文を仕上げました。ほとんどゼロから出発して修士論文までたどり着く過程は楽ではありませんでした。しかし研究自体が嫌になったことはなかったと思います。とにかく目にすること全てが新鮮な概念や術語でした。毎日ノートにメモしながら整理していきました。知識を蓄え、調査を設計し、実施し、データを分析する。そのプロセスを全部、自分一人の手でやりきったことは今でも私の財産として残っています。
大学院を修了してから本格的に研究者の道を歩み始めることになりました。しかし、生来一つのところに落ち着くのが苦手な性分なのかもしれません。社会言語学という表看板を出しながらも、そこに安住しようという気はありませんでした。とくに博士(文学)の学位を取得してからは、一層その傾向が強くなりました。社会言語学を志す人が社会を見る目をほんとうに持っているのだろうか、という疑問が湧いてきました。言語を観察するセンスはあっても、もうひとつ、社会現象を読み解く眼力が必要だろうというのが私の考えでした。この眼力は自ずと身に付くものではなく、やはり専門的な勉強を必要とします。博士論文を書いているときから、社会学や思想史を専門にしている先生方にお世話になりました。
そして今は、医療系の先生方とともにコミュニケーションについて研究を進めています。現在では「医療コミュニケーション」という呼び方がだいぶ定着してきましたが、十年前に私が研究を始めたころは他の人に説明するのにもひと苦労するというような状況でした。医療者と大学の研究者だけでなく、SP(模擬患者)のみなさんとも交流を続けています。社会の中でもその必要性が認識されてきたので、研究のすそ野が広がっていると感じます。ただしこの領域の研究が言語学の研究と違っているのは、いつも何のために研究するのか、誰のための研究なのか、そして研究した成果をどのように現場に還元していくのかを常に問われている点です。学界に貢献すればそれでよし、というわけにはいきません。
振り返ってみると、人との出会いによって自分の世界がだんだんと広がってきたように思います。皆さんも文学部の狭い建物に閉じこもらずに、どんどん世間に飛び出してください。

インドネシアで講演を行う筆者

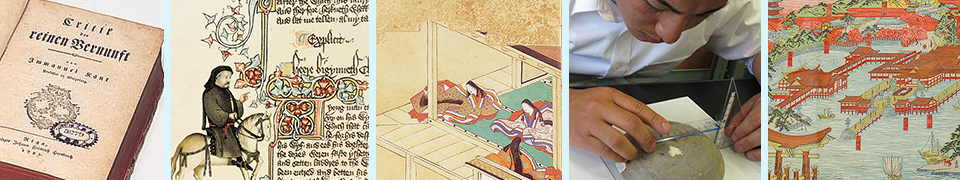
 Home
Home