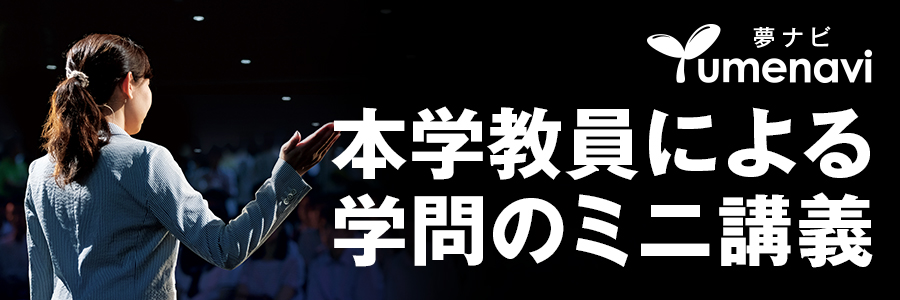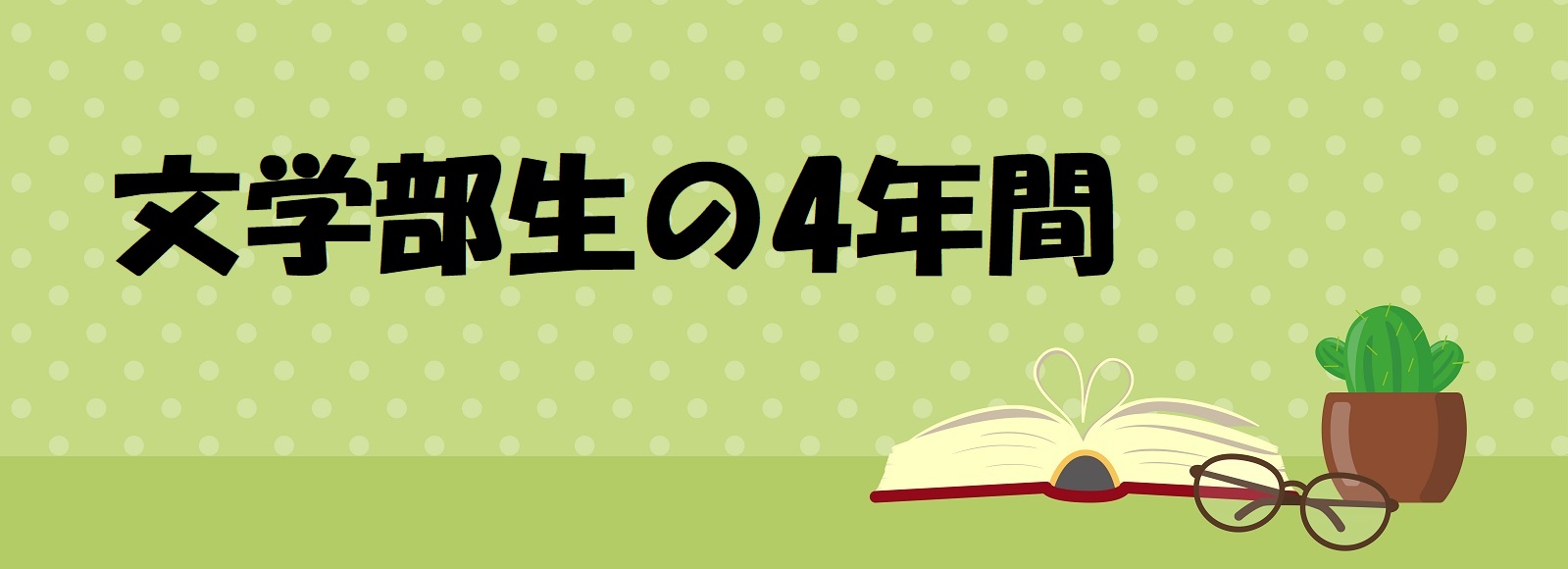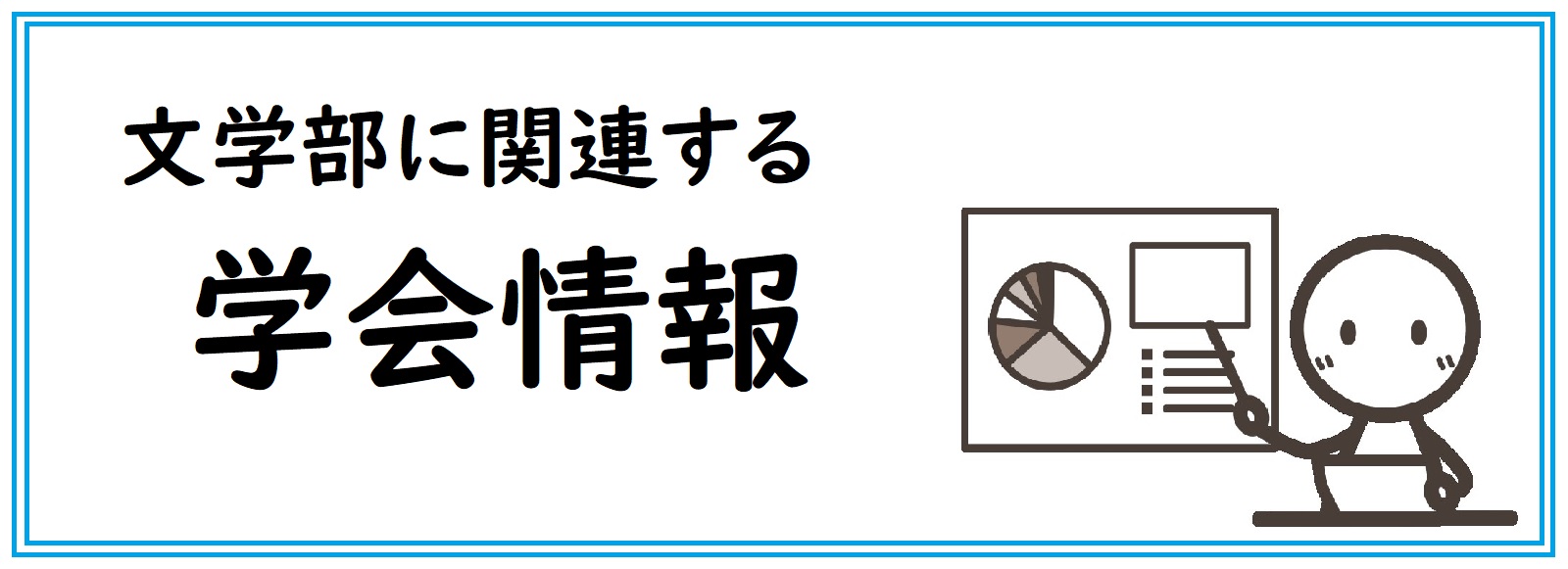私は今、自分の好きなことを職業にさせて頂いているとても幸せな人間だと思っています。いい論文が書けた時、いい英詩を読むとき、充実感を味わうことができます。
私は、とにかく英語が好きな少年でした。厳密には英語の音が好きだったのだと思います。ラジオの英会話番組から流れてくるネイティヴ・スピーカーの発音にうっとりとし、それを真似た自分の発音を人から褒められると余計に英語が好きになりました。そのすぐ近くに住んでいましたから、平和記念公園へ行って観光客の外国人を捉まえて、覚えたての英語を使ってスリルを楽しんでいました。
もう一つ小さな頃から好きだったものがあって、それは、歌謡曲でした。当時、カラオケは未だありませんでしたが、テレビでも歌謡曲番組が花盛りの時代で、フォーク歌手が一世を風靡し、ヒット曲の歌詞を集めた所謂、歌本がたくさん出回っていました。少々、大袈裟ですが、私の言葉への感性や思想は、歌謡曲の歌詞が作ってくれたのかもしれないとさえ思っています。たとえば、泉谷しげるの「黒いカバン」のユーモラスな歌詞の底に流れている、権力に対する反抗精神は、中学生の私に妙な快感を与えてくれていましたし、武田鉄也の「贈る言葉」の冒頭「暮れなずむ街の光と影の中・・・」という歌詞は今では陳腐に響くかもしれませんが、当時の私には涙が出るほど綺麗な言葉に聞こえました。
高校生の頃、進路を考える中で、朝から晩まで好きな英語を読んだり、聞いたりしていられたらどんなに幸せだろう、と思うようになりました。そうだ、英語の先生になろう。それで英文科へ進んだのです。私の文学との出会いは、大学生になってからで、遅ればせながら、かたっぱしから世界の文学を読み漁りました。当時、至る所で学生主導の読書会が開かれていました。大学院生の先輩たちが、文学作品の英語を見事な日本語に翻訳していく様子を見て、私のやりたいのは、単なる薄っぺらな紙のような「ぺらぺら」の英語をしゃべることではなく、もっと深い思想や、もっと精緻に、芸術作品として作られた美しさを英語の文学の中に見出すことだ、と考えるようになったのです。
英文学の面白さに目覚めた私には、同時に「偉くなりたい」という若さ故の野心が取り付くようになりました。ともかく当時の大学の教授たちは、「乞食と大学教授は三日やったらやめられない」と言うほど楽しそうでしたから。私自身はその頃、教授にまでなろうとは思いませんでしたが、まるで呪文のように「勉強せにゃ、勉強せにゃ」と自分に言い聞かせていました。英語の先生ではなく、英文学の研究者になること、これも厳密には英文学を研究していられる状態をできるだけ長く続けること、が目標になりました。今のように、お金にならない文学を勉強することが大勢の人たちから疎まれ、「高尚な学問」として見てもらえない環境であれば、おそらく私の生き方は違ったものとなったかもしれないのですが、ともかくその頃は、文学をやることは立派なことと見なしてもらえました。ですから今でも、たとえば、夏目漱石が「僕は一面に於て俳諧的文学に出入りすると同時に一面に於て死ぬか生きるか、命のやりとりをする様な維新の志士の如き烈しい精神で文学をやつて見たい。」と書いているのを読んだりすると、大げさだな、と感じざるをえないのと同時に強く共感もしてしまうのです。
イギリスの叙情詩人シェリーが書いた恋愛詩の中で使われている The desire of the moth for the star (星を求める蛾の願い)という美しい言葉があります。夜の暗さは詩人の悲しい心の暗さに呼応し、遠く、とどかない処にいる恋人を求める詩人の魂が、闇夜に輝く星の光を求めてあこがれる蛾の気持ちに喩えられています。普通、恋愛詩の中では、蛾が惹きつけられ、飛び込み、挙句の果てに焼け死んでしまうのは、恋の炎であることが多いのですが、ここでは、遥か彼方の光を、少々、いや、かなり、愚かにも願い求めている虫のけなげさが胸を打ちます。遥か彼方の光を求める、というロマン派的な思いが、私の人生を動かしていました。偉くなりたい、という願いが、学部時代、留学というものが今ほど簡単にできる時代ではなかった頃、しかも私は学力の点でまだ準備が出来ていないという先生方の反対を押し切って、バイトで貯めた資金を使い、一年間ロンドンで暮らすことをさせた唯一の動機でした。そしてその劣等感と挫折感に苛まれた、わからないことだらけの孤独な一年間が、それからの私の姿勢を形作りました。
大学院へ進学した私の次の願いは、英文学をやる以上、イギリス人やアメリカ人と対等にやりとりができるようになりたい、というものでした。外国人としての英語に甘んじるのではなく、英語を母語とする英文学研究者に教えてやれるようなことを言い、書けること。しかも日本の影響を受けた作家や作品を扱うことで外国の研究者の関心を買うのでは、まだ対等ではない、という意識が私には拭い切れず、完全にイギリス人やアメリカ人の土俵で学問という相撲をとりたい、と願うようになりました。科学やスポーツの分野ではそれが出来るのだから、英文学でもできるはずだ、と少々、いや、たぶんかなり、愚かにも信じ続けているのです。

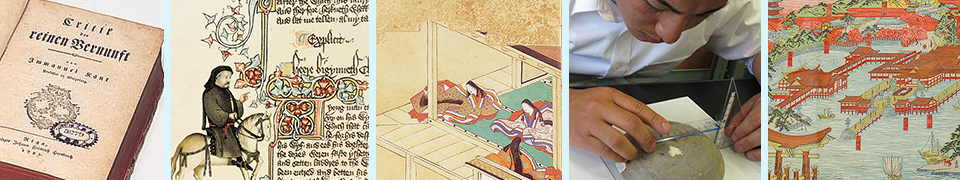
 Home
Home