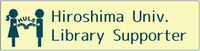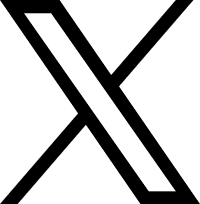広島大学では、広島大学図書館が所蔵する貴重資料(古典籍、洋書等)や漢籍などのコレクションを所蔵しています。これらは貴重資料室や和装資料室に保管されているほか、いくつかの資料は広島大学デジタル資料アーカイブや国文学研究資料館から画像ファイルを公開しています。
デジタルコレクションについては、下記「特別コレクション」ページにて記載しております。
貴重資料目録
貴重資料の目録は以下からご覧いただけます。国書総目録や日本古典籍総合目録データベース(国文学研究資料館)で広島大学所蔵となっている資料の一部は戦災にて焼失しています。
代表的な貴重資料
知新集
広島藩は『芸藩通史』編集にあたり、文化・文政年間各町村に地誌の書き出しを求めた。各町村では国郡志御用掛が任命されてその編集にあたったが、広島府では西町奉行所内に編集局を設置して進め、1822 (文政5) 年4月に完成して国郡志編集局に提出された。これを同年10月、町方付奉行飯田篤老が書写し体裁を整えて25巻にまとめ『知新集』として藩庫に納めたもの。1966 (昭和41) 年に広島県重要文化財の指定を受けた。
狐物語
14世紀前半にイギリスで作成されたと推測される本の断片で、犢皮紙(とくひし:動物の皮でできた紙)に書かれている。『狐物語』は20数編の「枝篇」と呼ばれる小品から成り、各枝篇は異なった作者により12世紀から13世紀にわたって書き継がれた。また、動物叙事詩と呼ばれ、動物寓話や動物説話とは異なる独特のジャンルを構成していた。
『伊勢物語』(奈良絵本)
在原業平に擬した主人公の初冠から亡くなるまでを流麗な和文と和歌を盛り込んで描いた平安時代の歌物語。連れ出した女を鬼に一口で食われる芥川の章段や、筒井筒で遊んだ幼馴染との恋の章段などが有名。奈良絵本は室町時代後期から江戸時代中期にかけて書かれた絵入り写本。奈良絵本という用語の由来は、奈良興福寺周辺の絵仏師が副業に作ったという説など、諸説がある。初期は古奈良絵本と呼ばれる素朴なものだったが、次第に大型化し、豪華な装丁となった。嫁入り本とも呼ばれる。
『すゝめの夕かほ』(奈良絵本)
『宇治拾遺物語』巻三の十六「雀報恩事」を奈良絵本に作ったもの。文章も『宇治拾遺物語』の話に近い。前後二段の構成で、前段が善因善果の話、後段が悪因悪果の話という対照をなしている。このような腰折れ雀の話は、日本各地に伝承されている有名な昔話で、また類話は中国やモンゴル、韓国などアジア各地にも広く分布している。諸本として広島大学蔵本と高安六郎旧蔵本が知られていたが、後者が戦災により焼失したため、これが現存する唯一の伝本になる。
漢籍目録
広島大学図書館が所蔵する漢籍の目録は、以下の資料に収録されています。
- 廣島大學文學部舊藏漢籍目録. 赤迫照子編. 東京大学東洋文化研究所附属東洋学研究情報センター, 2016. 東洋学研究情報センター叢刊 20輯
- 廣島大學文學部舊藏漢籍目録書名索引. 赤迫照子編. 東京大学東洋文化研究所附属東洋学研究情報センター, 2017. 東洋学研究情報センター叢刊 23輯
- 廣島大學斯波文庫漢籍目録. 廣島大學附屬圖書館編集. 広島大學附屬圖書館, 1999.
代表的な漢籍
『六臣註文選』(明呉勉学重校本、六十巻)
南朝の梁(502~557)の昭明太子が編纂した『文選』は、周から六朝時代までの詩文を選んで文体別に編纂した詞華集。孔子の弟子の子夏の「毛詩序」から、梁の陸倕(470~526)まで約130人の作品800編近くを三十七(一説に三十八)の文体別に収めています。その選択基準は、昭明太子の「文選序」に、「事は沈思より出で、義は翰藻に帰す」、つまり深い施策に基づく内容を、修辞を凝らした美しい表現でまとめた作品を選んだといわれています。各時期を代表する文人たちの主な作品がほぼ網羅され、六朝までの中国文学の粋を集めたものとなっていて、唐代以降の知識人の必読書として中国文学の典型となりました。日本にも早くから伝来し、必読の中国古典の一つとなったとされています。
利用方法
以下のページをご確認ください。
問い合わせ先
レファレンス主担当
E-Mail:tosho-fukyu-wrc[at]office.hiroshima-u.ac.jp
TEL:082-424-5631


 Home
Home