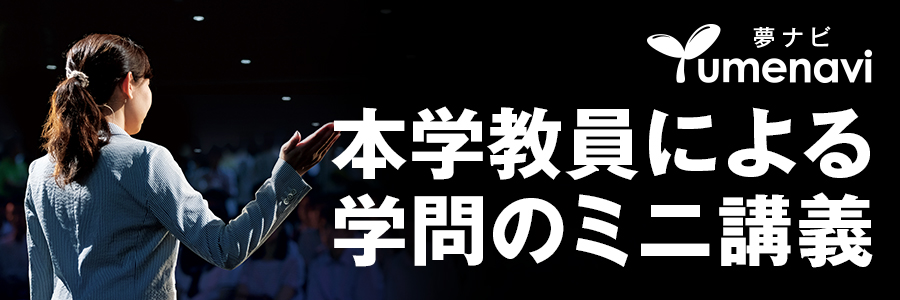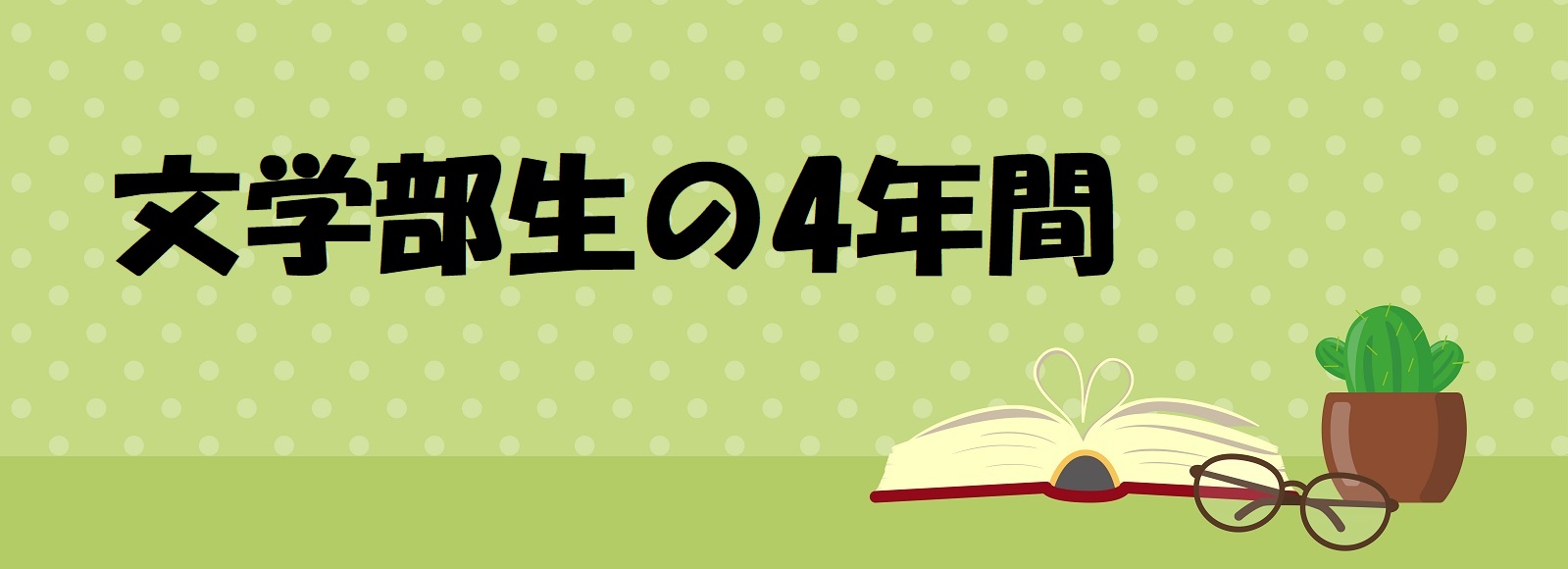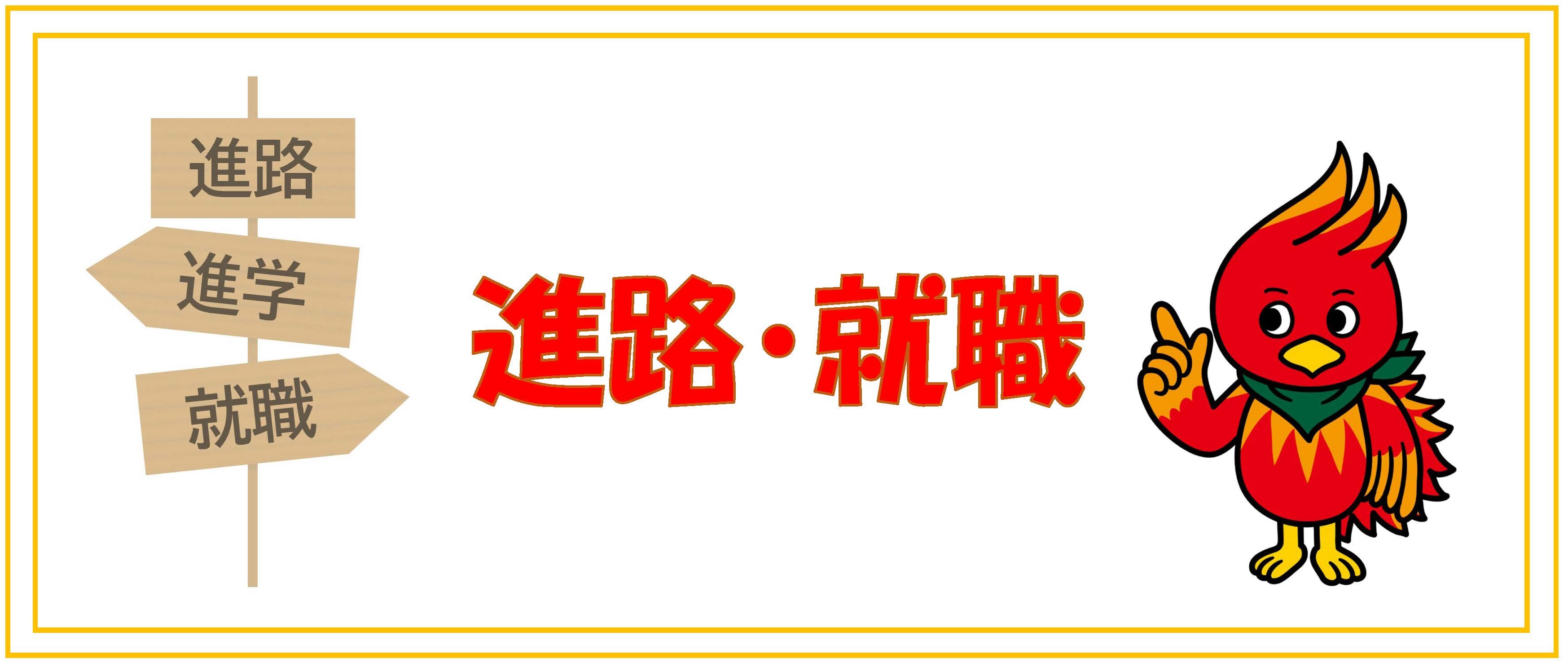映画学という学問分野を最初に知ったのは、学部生時代の交換留学でイギリスの北アイルランドにあるアルスター大学で一年間学んだときのことだ。アルスター大学では、アイルランド文学を扱う英文学科の授業に加え、映画学科の授業をいくつか受講した。ジガ・ヴェルトフの『カメラを持った男』(一九二九年)にはじまり、ヒッチコックの『恐喝』(一九二九年)、ダグラス・サークの『天はすべて許し給う』(一九五五年)、日本で撮影がおこなわれたクリス・マルケルの『サン・ソレイユ』(一九八三年)など、そのときに出会った映画の数々はいまでも強く印象に残っている。映画学校のように映画を作りたい人のためのプログラムではなく、映画をつぶさに見てそこから意味を見出す学問分野があることに胸が躍ったことをおぼえている。それがどんな就職につながるのかといった現実的な問題は、まったく考えていなかった。そもそも学部の卒業が一年延びるのをわかったうえで四年次の夏に留学したのだから、卒業後のことなんて大して考えていなかったのだ。
北アイルランドから地元の沖縄に戻ったあと、残りの半年で宮崎駿の『ハウルの動く城』(二〇〇四年)に関する卒業論文を書いて学部を卒業した。その後、モラトリアム的に同じ大学に残って英米言語文化専攻でひとつめの修士号をとったあと、県費派遣留学生としてカンタベリーとパリに一学期ずつ滞在して学べるイギリスのケント大学に留学して映画学の修士号をとった。このときは沖縄の映画作家、高嶺剛について研究したのだけれど、映画学は英語で学ぶべきものというイメージが、すでに私のなかに刷り込まれていたように感じる。当時の日本では今日に比べて映画学科のある大学ははるかに少なかったが、それでも京都大学や日本大学など一部の大学で映画を学べる課程は存在した。そういった内地の大学を受験する選択肢が頭によぎりすらしなかったのは、やはり最初の留学体験が大きかったからだと思う。

英国映画協会(British Film Institute)の外観
現実的な問題を考えれば、国内の大学に入って影響力のある教授の研究室に入って学んだほうが、大学院を出たあとの就職にも有利に働くのだろう。実際、そうしなかった私はロンドンの大学で博士課程を終えて帰国したあと、非常勤の口も得られずに二年間在野に放りだされるかたちになった。しかし当時の私は、イギリスで学問として映画を学ぶ面白さしか念頭になかった。映画のシーンを分析したり、一日じゅう図書館にこもって文献を読みふけったり、学友と一緒に映画を見て延々と議論を交わしたりするのが楽しくてしょうがなかったのだ。アカデミックな職を得られなかった博士修了後の二年間のあいだも、実家に寄生しつつ字幕翻訳の仕事をこなしたり研究会を立ちあげたりして、大した危機感ももたずにのんきに過ごしていた。

迷子必至のバークベック・カレッジ内の映画館
留学のよいところは、語学に磨きをかけられるとか、他国の文化を学べるなど数多く挙げることができる。だけど私は、日常が押しつけてくるさまざまな問題をいったん棚上げできる点を強調したい。少なくとも留学しているあいだは進路について思い悩む必要もないし、人間関係のしがらみからも物理的に離れられる。周りを気にして焦るのをやめれば、自分が本当に何をしたいのかが見えてくる。「~しなきゃいけない」と当然のごとく思いこまされていたのが、違う環境に身をおいてみるとそうでもないことがわかってくる。自国とは異なる言語や生活様式に接し、それまで当たり前のこととして受け入れていた価値観を相対化できることは、留学生活の大きな強みである。
だからといって、この文章を読んでいる日本の高校生に「広島大学なんて受験しなくていいから、とりあえず海外に飛びだせ!」などと勧めたら、私はたちまち失業してしまうだろう。本学は交換留学や研修プログラムが充実しているので、学生諸君にはぜひそれらを活用してもらいたい。あらゆる現実的な問題をさしおいて本当に心が躍ることをとことん追求する時間をもつことは、きっとその後の人生の大きな糧になるはずだ。少なくとも私の場合は、好きなことばかり追求してたどり着いた今の自分に、まあまあ満足している。

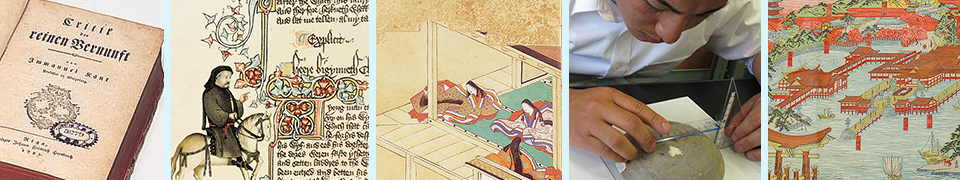
 Home
Home