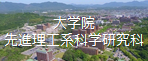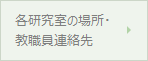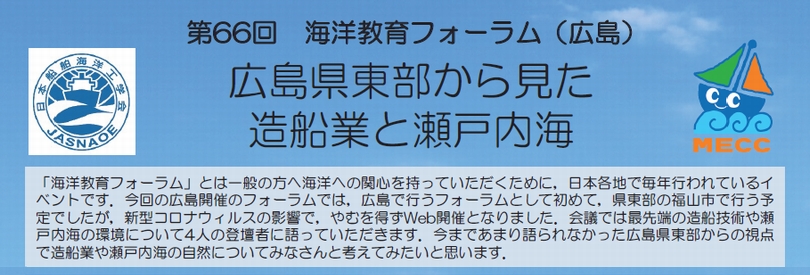
日本船舶海洋工学会 海洋教育推進委員会は 福山大学ならびに本学 (大学院先進理工系科学研究科 輸送・環境システムプログラム) と共催で,2020(令和2)年12月6日(日)に第66回海洋教育フォーラム「広島県東部から見た造船業と瀬戸内海」を,オンラインで開催しました。
広島地区でのこのフォーラムは,2013(平成25)年度以来毎年開催しており,8回目となりました。今回は福山市において広島県東部では初めて開催する予定でしたが,新型コロナウイルスの影響からその開催自体が危ぶまれたものの,オンライン (Microsoft Teams使用) により無事開催することができました。オンラインの配信は,新型コロナウィルス対策として,福山大学社会連携推進センター,三和ドック,自宅,ならびに本学の,各会場に分かれて少人数で実施しました。今回の参加者は,行政職員,民間企業,学生,一般など,総計約32名でした。当日のプログラム (講演内容) は以下の通りです。
開会挨拶「うみのことをもっとみんなで知ろう」
小林 正典 (日本船舶海洋工学会 海洋教育推進委員会委員長)
講演1: 国際環境条約と瀬戸内海船舶修繕業
寺西 秀太 (株式会社三和ドック 代表取締役社長)
講演2: 瀬戸内海発環境にやさしい船作り
施 建剛 (常石造船株式会社 設計本部 設計管理部長 / 広島大学 大学院先進理工系科学研究科 客員教授)
講演3: 瀬戸内海の成り立ちと魚類の遺伝的集団構造
阪本 憲司 (福山大学 生命工学部 海洋生物科学科 准教授)
講演4: 瀬戸内海の藻場観測技術の開発
仲嶋 一 (福山大学 工学部 スマートシステム学科 教授・安全安心防災教育研究センター長)
閉会挨拶
作野 裕司 (広島大学 大学院先進理工系科学研究科 准教授 / 第66回海洋教育フォーラム実行委員長)
講演は,まず広島県東部に位置する造船所として株式会社三和ドックの寺西社長より,最新の国際環境条約の話や最先端の環境対策技術について紹介がありました。次に,常石造船株式会社の施部長より,環境にやさしい船づくりの実際について紹介されました。休憩を挟んで,福山大学の阪本准教授より,瀬戸内海の環境評価の視点で長い時間スケールでの魚類の遺伝的多様性について紹介がありました。その後,福山大学の仲嶋教授より,ROV,衛星,海中ロボットなどを駆使した藻場観測技術を工学的な立場から紹介されました。各発表後には,世界的な視野に立つ高い造船技術および環境分析技術の詳細や地域の特性を生かした取り組みについての質問など,参加者同士で活発な議論が交わされました。
当日は広島地方は快晴に恵まれ,対面開催ができなかったことが残念でしたが,その一方で,オンライン開催であったために通常広島での開催では参加が難しいと思われる遠方から参加された方がおられたことは良かったと言えます。今回,広島市や呉市を離れて広島県東部で初めての開催を目指したものの昨今のコロナ禍でその現地開催は叶いませんでしたが,県東部の企業や大学の高い技術や考え方に触れることができ,広島県全体で海洋教育を盛り上げていける機運が一層高まったことは,非常に大きな収穫となりました。
当日の様子 (写真)


この記事に関する問い合わせ先
大学院先進理工系科学研究科 (工学) 輸送・環境システムプログラム(/専攻)
航空輸送・海洋システム研究室
准教授 作野 裕司
TEL: 082-424-7773


 Home
Home