取材日:2025年2月18日

統合生命科学研究科の飯田愛実さんにお話を伺いました。
飯田さんは、令和3年12月に広島大学女性科学技術フェローシップ制度の理工系女性M2奨学生に採用され、令和4年度からは理工系女性リサーチフェローとして支援を受けています。
今回は、飯田さんに、博士課程後期で実施している研究や生活の様子など、様々なお話を伺ってきました。(記載の情報は取材時点のものです。)
博士課程に進学するまでの経歴について
飯田さんが博士課程に進学されるまでの経歴についてご紹介いただけますか。
私は早稲田大学商学部を卒業後、東京で企業4社に勤務しました。3社目に在籍中に筑波大学で経営学の修士号を取得しました。そして、4社目に勤務している時に、日本でやりたい仕事はやり尽くしたという実感を得たので、青年海外協力隊に応募し、フィールドで活動する「環境教育」隊員として、ケニアの漁村に赴任しました。漁村に着いた時、海岸に広く自生する海藻が目に留まり、強い印象を受けました。それが、後年私が海藻について研究することになるきっかけでした。
ケニアでの青年海外協力隊の任期が終わり、日本に帰ってきた後、在ケニア日本国大使館の草の根・人間の安全保障無償資金協力の仕事で、再びケニアに戻りました。その時は海から離れ、主にインフラ整備支援案件のコーディネーターとしてケニアの農村部を中心に各地を回っていたのですが、「ケニア沿岸で取れる海藻を肥料に使うのはどうだろう」と想像したりして、海藻のことはずっと気になっていました。その後、インドネシアでJICA技術協力プロジェクト(気候変動対策)の仕事に従事したのですが、こちらは政策の支援だったこともあり、やはりフィールドに出て海藻に関わる仕事がしたいと思い、任期満了後日本に帰ってきました。
帰国してからは、離島で現地の海藻を使った商品開発の仕事をしていましたが、新たな活用法を見出すためには化学の知識が必要だと痛感しました。そこで、島を離れ、平日は環境分析の会社で働きながら、週末に分析化学の専門学校に通うことにしました。
そこで1年経たない頃に、海藻の系統分類を専門とされている広島大学の教員を通して博士課程前期の指導教員を紹介していただき、社会人特別入試を受験し、研究室に入ることになりました。
博士課程後期の研究内容について
飯田さんの研究内容について教えてください!
私の研究テーマは「農薬シーズとなりうるアミジグサ科褐藻類由来成分の探索」というもので、人間社会でまだ利用されていない褐藻類アミジグサ科の海藻に着目し、農業害虫に対する殺虫効果や忌避効果をもつ成分を化合物まで分けて探索しています。アミジグサ科に属する海藻が産出するテルペノイドなどの二次代謝産物(化合物)には、海洋植食動物に対する摂食阻害効果が知られており、さらに、抗菌、殺真菌、抗腫瘍、抗炎症などの生理活性も研究報告されています。一方で、従来の化学合成農薬に対する使用規制が厳しくなる昨今、代替農薬となりうる天然化合物のニーズも高まっていて、陸上植物由来成分を中心に探索研究が既に行われています。しかし、海藻を材料とした農業害虫防除効果の研究は抽出物レベルで留まっており、化合物まで探索が及んでいません。ここに研究の余地があると思って始めたテーマです。
研究内容としては、「アミジグサ科海藻の採取→成分の抽出→抽出物から化合物の単離→化合物の同定と構造解析」、および「農業害虫に対する生物活性試験方法の確立→単離した化合物の生物活性試験の実施→結果のデータ解析」というのが一連の流れとなります。
これまでに、アミジグサから単離した11化合物(3種の新規化合物を含む)の中に、イネシンガレセンチュウ(イネを宿主とする植物寄生性線虫)に対する殺虫活性を有するものを確認して国内・国際学会で発表しました。また、チョウ目コナガの幼虫(アブラナ科植物を食害)に対する摂食阻害活性を持つ化合物の報告を、小さな実験系での生物活性試験法の紹介とともに、国内学会で発表する予定です(2025年3月)。
このテーマを選ばれた背景を教えてください。
先にお話しした内容とも重複するのですが、私が最初に海藻に興味を持ったのは2009年のことで、当時、青年海外協力隊員としてケニアの漁村で生活していたとき、海藻の食文化のない現地で海藻の利用法を自ら試行錯誤したのが始まりです。その後、ケニア以外も含めて海外にトータル6年強滞在し、帰国後に本格的に海藻の活用について模索し始めました。当初は理系的なアプローチではなく、海藻のある地域と海藻活用の専門家を繋ぐコーディネーター的な仕事ができればと思っていたので、まずは現場を知るために離島で働きました。アミジグサとの出会いはその時です。海岸でふと目に留まってかじってみた海藻が刺激的に辛くて衝撃を受け、図鑑で調べたら、それがアミジグサ科のアミジグサだったのです。その二次代謝産物がウニやアワビなどの海洋植食動物からの摂食を阻害しているということも、そのときに知りました。それでも当時は、「辛い海藻があるんだ」という程度の認識でしたが、後に化学分析の技術を習得する過程で、ごく微量の物質でも解析できるということを知り、「あの海藻を農業害虫防除に使えるかもしれない」と、本研究テーマを思いつきました。
研究の面白さ、苦労について教えてください。
材料の採取から、その後の成分抽出、化合物の単離、機器分析、生物活性試験などを経てデータを取り終えるまで、過程の全てを自分自身で行っていることです。材料である海藻は、東広島キャンパスから30 km先にある竹原市の海岸で採取するのですが、生育状況によっては求めるものが見つからないこともありますし、再現性の高いデータを得ようとすれば活性試験の方法も自分で工夫して確立していかなければなりません。当然、苦労も多いですが、それだけに達成感は高く、また、そのような試行錯誤の中で新しい方法論を生み出していくことにも喜びがあります。
それから、これまでの経験を通じて「点」として感じてきた「なんだろう」という色々な疑問が、何かのタイミングで「線」として繋がり、理解が広がる瞬間、それを感じたときは楽しいです。


飯田さんが研究を行う様子
博士課程後期の生活について
毎日のスケジュールについて教えてください。
D3になってからは海藻の採取はしておらず、化合物の単離も夏までに終えたので、今は、化合物のコナガ幼虫に対する生物活性試験が中心になっています。朝10時頃に研究室に来て、午前中に必要な頭数の幼虫を飼育容器から取り出し、午後、活性試験のセットをします。この合間に、前日までにセットした活性試験の経時観察と記録、そしてデータ解析などのデスクワークをして、19〜20時に帰るという感じです。平日と土曜日がこの流れで、日曜日も経時観察と記録を取りに来ています。それから月に1回の研究報告会があり、研究進捗を伝えたり、ディスカッションしたりします。それ以外は一人で黙々と研究を進めるスタイルですが、私の行っている活性試験に関心を持ってくれた学部生の後輩がいるので、やり方を伝えたりもしています。
モチベーションが下がるときはありますか?
気分が落ち込むことはあっても、基本的にモチベーションが下がることはありません。行き詰まったときは「どうして今回はダメだったんだろう」と常に考え、気になる要因を潰していくという作業を続けて、決して手を止めないようにしています。あとは自分一人で抱え込まず相談することです。話すだけでかなり気が楽になりますし、会話が意外なヒントになったりする場合もあります。
博士課程後期への進学について
博士課程後期への進学を決めたきっかけを教えてください。
2020年から2年間の博士課程前期では、COVID-19の流行によって制限された状況で、海藻材料の採取から化合物単離までに多くの時間と労力をつぎ込みました。このため、生物活性試験は、蚊の幼虫(ボウフラ)を使った予備的な試験に留まりましたが、高い殺幼虫活性を示す化合物があり、手応えを得ました。そこで、本命の農業害虫に対して効果を示す化合物を引き続き探索したいと思い、博士課程後期への進学を決めました。
進学について、不安はありましたか?
私の場合は社会人としての期間があるので、経済的な面は貯金を取り崩しながらやっていくしかないと考えていましたが、同時にサポートを受けられるチャンスがあれば積極的にチャレンジしていこうとも思っていました。研究テーマは明確でしたので、研究活動そのものに対する不安はありませんでした。
どんな人に博士課程後期への進学を勧めますか?
「研究のアイデアを自ら探究する意欲と行動力のある人」です。研究のアイデアが湧いたとしても、そのアイデア自体は世界のどこかで誰かがすでに抱いている可能性は否めません。ですので、真価が問われるのは、そのアイデアを自ら行動して形にしていくことであり、行動の結果得られた知見を伝えていくことが研究者にとって重要なことだと思います。
将来のキャリアパスについて
今後のキャリアについてはどのようにお考えですか?
海藻の活用法を研究し、社会実装に繋げる仕事をしたいと思います。それができるのであれば国内外問わず、どこへでも行くつもりです。例えば、今研究をしているアミジグサは熱帯から温帯の海域に広く分布する種です。それ以外にも海藻の種類はとてもたくさんあり、その活用のアイデアはいろいろな分野にあると思うので、そうしたことに関わっていきたいと思っています。
女性科学技術フェローシップ制度について
女性科学技術フェローシップ制度に採択されるまでの準備について教えてください。
募集を知ったのが博士課程前期2年でまだ投稿できるような論文もなく、研究に芳しい成果が出ていない状態で応募しても無理だろうなと考えていました。しかしちょうどその時、参加した学会で自分の研究に対して大きなヒントになるようなアイデアが得られ、帰路ではもう応募する気持ちになっていました。「チャレンジしてみれば何か分かってもらえるかもしれない、面白いと関心を持ってもらえるかもしれない」と思い、一気に書類を作成しました。振り返ると転機となるタイミングでした。
(注:飯田さんが女性科学技術フェローシップに応募された時は、博士課程前期2年時に募集が開始されました。)
女性科学技術フェローシップ制度についてコメントがあれば、お聞かせください。
採択されたとき、私の研究はまだトンネルの先の光が見えた程度の状態でした。フェローシップ制度の支援がなければ、博士課程後期で研究に専念し、成果を世に出していくことができなかったと思います。学生であればこそできる独自の研究に、根気強く注力できていることについては感謝しかありません。それに、初めて外部の方に自分の研究を認めてもらえたことが、すごくうれしかったです。また、博士課程前期2年からサポートを受けられるのも、良い点だと思います。
理工系に進学する女性を増やすために思うことはありますか?
大人たちの主観や周囲の環境が、若い人の方向性を定めてしまうという問題はあるかも知れないです。その意味では、理工系に関心を持った人の受け皿や、気持ちを後押しするような環境は大事です。特に実験系では施設が不可欠ですし、指導を仰げる専門の先生方の存在も必須要件でしょう。例えば私の場合、新鮮な海藻が採取できる場所、その近くにある研究施設、そして研究室と指導教員という環境が揃っているからこそ研究ができている訳です。本来、理工系に興味を持つことに性別や年齢、国籍は関係ないはずなので、その興味を持ち続けることのできる環境が、意欲を育てることに繋がるのではないかと思います。
博士課程後期を目指す学生へのメッセージ
もし学部生の自分にアドバイスができるとしたら、どんなことを伝えますか?
「そのまま行けば面白い未来が待っています」という感じです。早稲田大学の商学部に在学していた頃は、海藻の研究をするとも、広島にいるとも、青年海外協力隊に入ってケニアに行くとも思っていませんでした。それまで興味もなかった海藻に出会った途端にピンときて、そのときは研究者になるとは思っていなかったのに、今では博士課程後期で研究しているわけですから、人生何があるか分からないです。
最後に、博士課程後期を目指す学生たちにメッセージをお願いします!
人生において、いつ、どこで、どんなきっかけで研究のアイデアが湧くかは分かりません。
なので、アイデアが湧いた時に、それを実行できる場所やチャンスを掴みに行ってください。面白いと思ったらその気持ちを大切に、実際に動いて挑戦です。
私は文系出身で、社会人を経て(国内外での実務経験27年)、今は理系大学院生です。私のケースが多様な生き方の一例として、幅広い世代の探究心を持つ方々の参考になれば嬉しいです。
取材者感想
「博士課程後期の学生としては稀有なご経験を持たれており、何事にも恐れずチャレンジする飯田さんのバイタリティに敬服致します。特に、ケニアでの滞在中に海藻の活用可能性に気づかれたというお話は、いわゆる学士→修士→博士という一般的なキャリアを歩もうとしている私では到達できない、ユニークなご経験であると感じました。飯田さんの海藻研究の今後のご発展をお祈り申し上げます。」(先進理工系科学研究科 量子物質科学プログラム 博士課程前期2年・横山貴之さん)
「飯田さんにご自身の研究について伺うなかで、熱く語られる姿がとても印象的でした。その言葉の端々から、研究に対する熱意や探究心の強さが伝わってきました。一度社会人としての経験を積みながらも、それまで扱ってこなかった化学の分野に飛び込み、博士課程後期へ進まれた行動力と意思の強さには、心から尊敬の念を抱きました。今後ますますのご活躍を期待しております。」(先進理工系科学研究科 応用化学プログラム 博士課程前期1年・山口龍一さん)
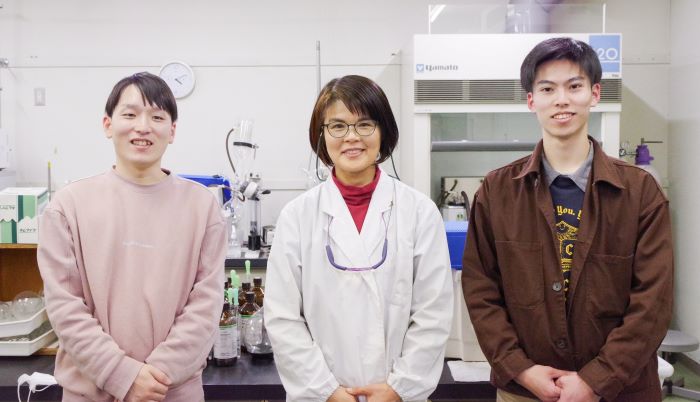
左から横山さん、飯田さん、山口さん

 Home
Home