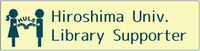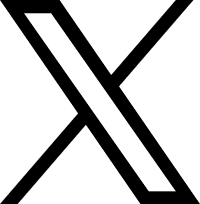大学院生だった頃、研究に煮詰まると、よく図書館地下の書庫に足を運んでいました。書庫には学術雑誌や古い本がぎっしりと配架されており、お目当ての論文や書籍を探しに入るのですが、ふと目にとまった本や雑誌を手に取って頁をめくっているうちに、あっという間に時間が過ぎてしまいます。出会うはずのなかった知に触れ、書庫特有の何ともいえない空気に包まれながら考えを巡らせていると、不思議と頭が整理され、少しだけ前向きな気持ちになることができました。生産的ではなかったかもしれませんが、そこで過ごした時間は、私にとってかけがえのないものでした。
広島大学図書館は、1902年(明治35年)に開設された広島高等師範学校図書館を前身とし、百二十年を超える歴史を有しています。1929年(昭和4年)には広島文理科大学の設置に伴い、広島文理科大学附属図書館と改称しましたが、1945年(昭和20年)には原子爆弾の投下により建物と蔵書(27万冊のうち19万冊)が焼失するという大きな被害を受けました。そうした苦難を乗り越え、1949年(昭和24年)の新制広島大学設置後も、図書館は本学の教育・研究を支える基盤的組織として、その役割を果たし続けてきました。
現在は、中央図書館、西図書館、東図書館、霞図書館、東千田図書館の五つの館を中心に、蔵書は約340万冊にのぼります。とりわけ注目していただきたいのは、広島大学ならではの貴重なコレクションです。江戸時代の往来物から現代に至るまでの教科書コレクション(うち約4,400点を画像公開)、国内外の平和に関する資料を収めた平和文庫や平和学コレクション、小林芳規名誉教授により収集された角筆資料など、ここでしか出会えない特色ある資料群も数多く所蔵しています。
近年は、オープンアクセス、電子ジャーナル、データベースといったデジタルライブラリ化が急速に進み、図書館を取り巻く環境やその役割も大きく変わりつつあります。もはや図書館に足を運ばずとも最新の知に触れられる時代となりました。広島大学図書館はこうした変化にもいち早く対応し、電子的学術情報の整備やオープンアクセスによる論文公開などを通じて、本学の教育・研究を力強く支援してきました。
しかし一方で、図書館には「場」としての空間的機能があることも事実です。特にコロナ禍を経て、改めてリアルな「場」の大切さが見直されている今、広島大学図書館では、デジタル環境のさらなる充実と同時に、「場」の整備にも力を入れています。日本語・英語での論文作成をサポートするライティングセンターや、多様な国際交流の機会を提供するグローバルラーニングセンターなど、静的な知との出会いだけでなく、動的な知と出会える空間やサービスの提供も、今後より一層充実させたいと考えています。
広島大学での時間が、そして図書館で過ごす時間が、みなさん一人一人にとってもかけがえのないものとなりますよう、広島大学図書館はこれからも、みなさんの学びと研究を全方面からサポートしてまいります。
2025年9月
広島大学図書館長
川島優子


 Home
Home