大学院先進理工系科学研究科 物理学プログラム
准教授 中島伸夫 nobuo(at)hiroshima-u.ac.jp
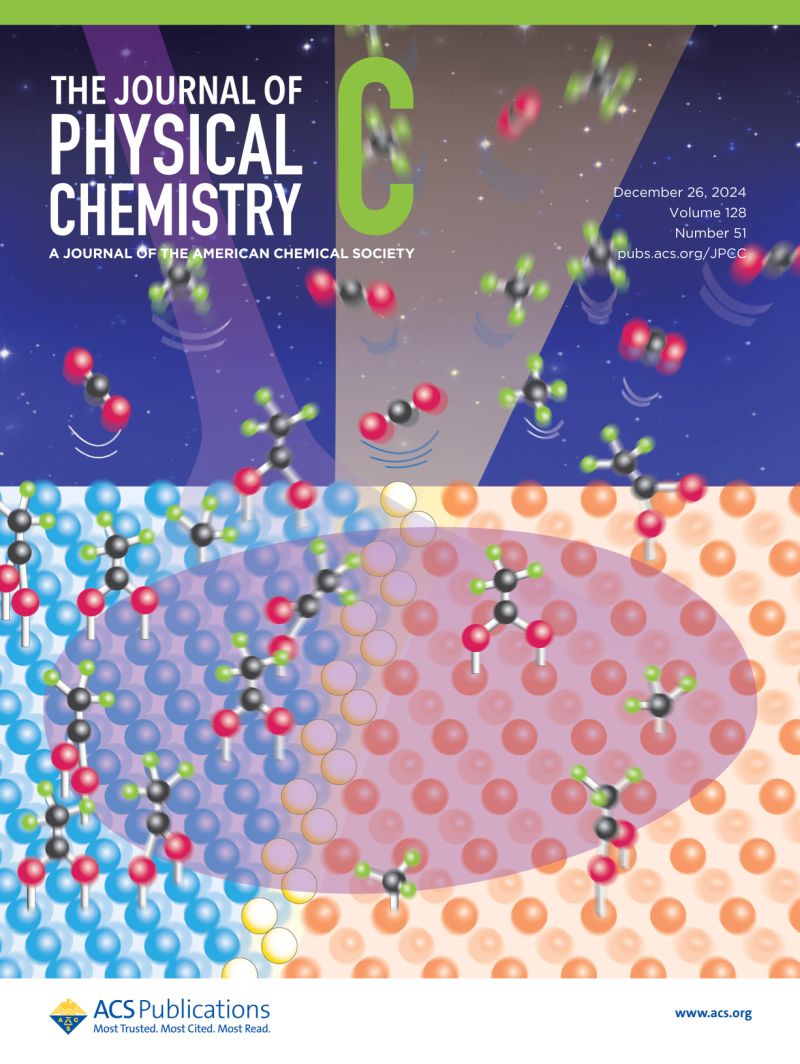
道路標識や建築物外壁の汚れを太陽光で除去する効果が知られている二酸化チタン(TiO2)の光触媒活性について、放射光X線を用いたさまざまな手法(X線光電子分光法、X線吸収分光法、X線光電子顕微鏡法)で解明しました。特に、これまで経験的に知られてきた「アナターゼ型」と「ルチル型」と呼ばれる異なる結晶構造の境界での活性向上の起源を、新たに導入した顕微X線集光技術とともに調べ、境界での急峻な電子エネルギー準位の折れ曲がりが活性向上に繋がることを初めて突き止めました。
これまでは、適当な割合で異なる結晶構造の粉末を混ぜたものが使われており、活性向上が頭打ちになっていましたが、細密な境界線をもつ塗布膜などの作製により、少ない材料でかつより高効率な光触媒物質という持続可能社会に必要とされる材料開発に繋がると期されます。
Keita Hiromori, Nobuo Nakajima, Takumi Hasegawa, Shin-ichi Wada, Osamu Takahashi, Takuo Ohkochi, Kazuhiko Mase, and Kenichi Ozawa,
“Electronic Origin of Enhanced Photocatalytic Activity at the Anatase/Rutile Boundary: A Case of Acetic Acid on the TiO2 Surface”,
The Journal of Physical Chemistry C, 128, 21767-21775 (2024).
2024年12月2日オンライン掲載:DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.4c05630
大学院先進理工系科学研究科 物理学プログラム
准教授 中島伸夫 nobuo(at)hiroshima-u.ac.jp
掲載日 : 2024年12月27日
Copyright © 2003- 広島大学