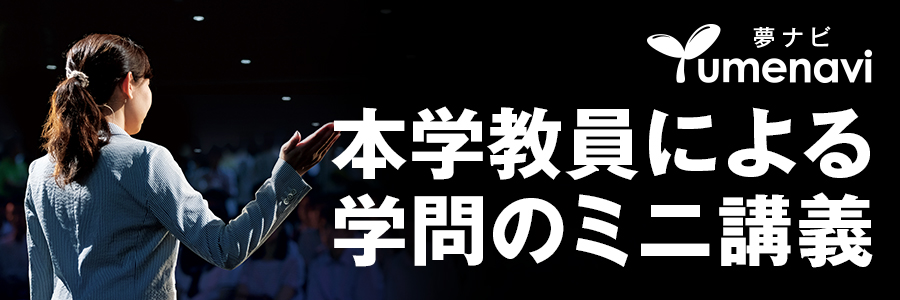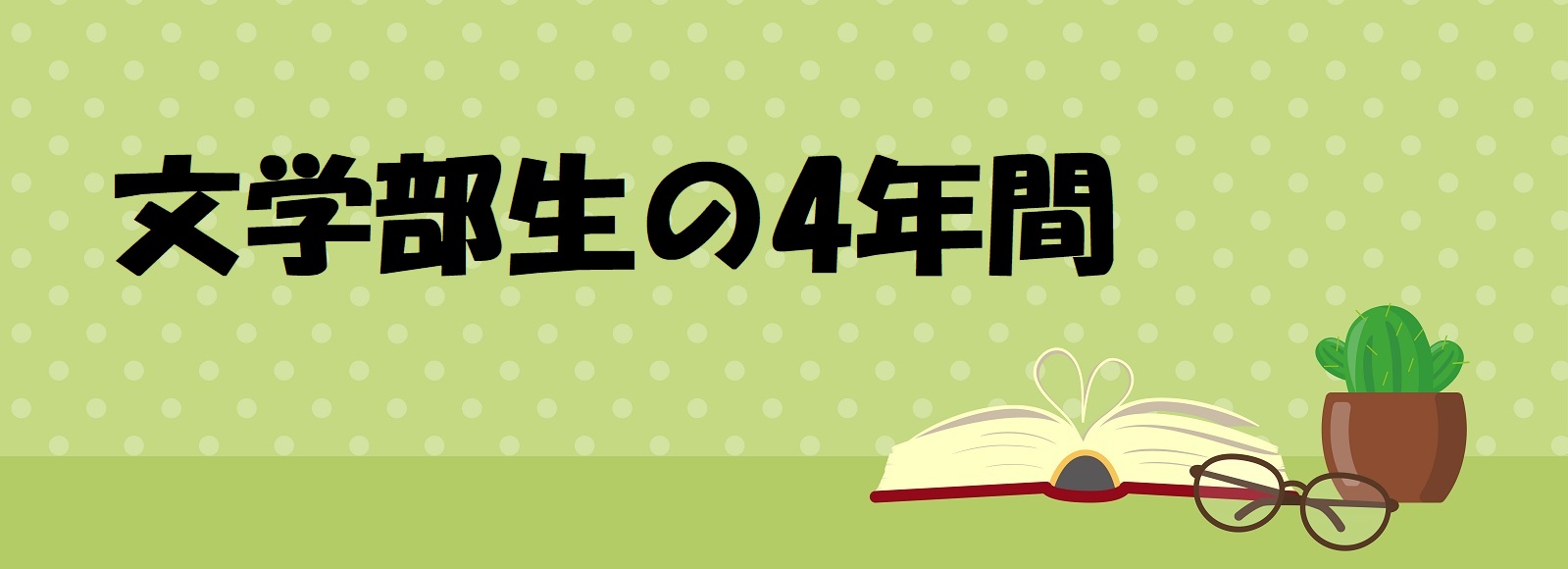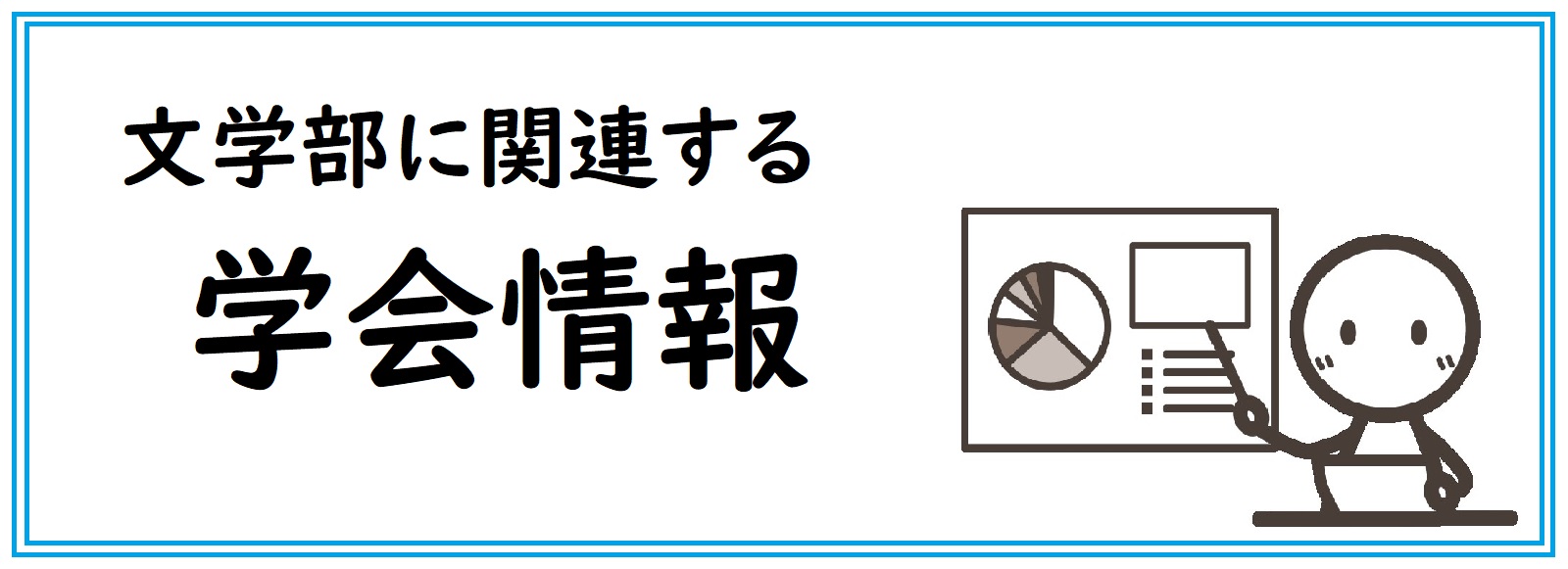English >

Figure 1: Peter Cheyne in a library
2200年前、ローマの劇作家テレンティウスは「我は人なり、人間に属するものは何も我にとって他人事ではない」(‘Homo sum, humani nihil a me alienum puto [I am human, and nothing that is human is alien to me].’)と書きました(紀元前165年頃)。この初期人文主義的な心情の発露には、私がこの短いエッセイで、人文学へのいざないとして考察したいことの核心が表れています。人文学とは何でしょうか。人文学とは、歴史学、哲学、宗教学、法学、政治学、美術史・美学、文学などの学問分野を含む総合的な学問領域のことを指します。これらの学問をつなぐ共通点は、人間の生産的活動の技法や業績を研究・考察し、社会生活の問題に対する解決策を考え、論証的かつ創造的な表現と、想像力の技法を磨くことにあります。
文学の研究では、人間の創造的才能と知性が生み出した、最も偉大な芸術的・言語的創作を調べ、考察します。人が言わんとすること、感じること、探求したいと望んでいることをできるだけ完全に表現することは、洗練された技術です。実際、それは最も偉大で、常に最大限に称賛されてきた芸術の一つです。しかし能力の如何にかかわらず、自分の考えや好奇心、驚きやその他の感情を表現する試みは、価値があると同時に充実感をもたらすものです。ここで鍵となる言葉は「試み」(‘attempt’)です。なぜなら、思考や感情を整理し配列する努力は、共有したい内容を他者に伝えるのに役立つだけでなく、あなたが時間をかけて思いをめぐらし、それを整理し、感受性豊かに構成することのできる思慮深い人間であることを示すからです。
こうした能力は、単に文や段落をいかに書くかという問題ではありません。注意、思いやり、熟考、目に見えない考えや感情の整理と構成、洞察、表現――これらはすべて精神的な資質です。このような理由から、偉大な詩人、物語作家、小説家、随筆家は、自国のみならず世界中で、何世紀にもわたって、時には何千年もの間、尊敬されてきたのです。偉大な作家は言語を育て、人間の共同体を心や精神のさらなる高み、自然界の奥深くや宇宙の果て、おそらくはさらにその先の、神秘にまで向かわせます。
したがって、たとえ成功しなくとも、ほとんど知られていないことや曖昧にしか理解されていないことを他者に伝えようとする「試み」は、それ自体に大きな価値があり、人間の精神が他者とつながろうとする欲求、さらには他者に、また後の世代にも、自分の生の限界を超えて語りかけようとする願望を表すのです。英語の「エッセイ」( ‘essay’)という単語 が「試み、試すこと」を意味するのは、まさに示唆的です。人間の想像力は、創造的に表現しようと願う強い能力です。この願いは、一人の人間として他者と意思疎通をし、自分の経験や、未来を探る想像力を、他者のために役立てたいという思いから生まれます。そうすることで、孤立や単なる利己主義から脱し、人類の生きた歴史に積極的に関わる一員になり得るのです。きわめて偉大な文学作家は、これらの能力の達人です。そして、私の考えでは、その中で最も偉大な作家たちは、言葉で伝えられる可能性の限界を押し広げる人々です。これらの先駆者たちは、以前は表現不可能と考えられていたものを明確に表現します。それまで混乱していたり、曖昧だったものをはっきりさせ、その結果、読者はしばしば、読書という行為を通じて、自己自身をさえ、よりよく理解できたと感じるのです。
イギリスのモダニズム作家のヴァージニア・ウルフは広範な読書が言語の熟達に役立つと言っています。彼女はまた、想像力によって自らを他者の精神や人生の中に置き、自分自身の視点からだけでなく他者の視点からも書くことが大切であると信じていました。
文章を書くという技術・・・それは、言葉を自在に操る芸術です。言葉の重み、色合い、響き、そしてそれが呼び起こすさまざまな連想を深く理解し、英語において特に求められる「言葉以上のものを語らせる力」を宿らせること。この技術は、読書によってある程度は身につけることができます――読書には、これでよいという限度はありません。しかし、それ以上に強力で、効果的な方法は、自分自身を離れて、まったく別の誰かになったつもりで想像することです。たった一人の自分だけを題材にしていて、どうして豊かな文章が書けるようになるでしょうか。(ヴァージニア・ウルフ『若き詩人への手紙』1932年より、菰田真由美訳)
彼女はまた自分の書いていることに合ったリズムで考え、そのリズムに合わせて書くことを勧めています。そうすることで文章が生き生きとし、読者の頭に事物を浮かび上がらせることを、より容易くするのです。
あなたの内なるリズムの感覚を、街を行き交う人々やバス、雀たち――通りに現れるあらゆるもののあいだを、自由に漂わせてみてください。そしてそれらを縒り合わせ、ひとつの調和ある詩へと編み上げていくのです。それこそがもしかすると、ものを書く人間の使命なのかもしれません――一見すると相容れないものたちのあいだに、どこか神秘的なつながりを見出だし、出会うすべての経験を恐れずに受け入れ、それを心の奥深くまで染み渡らせることが。(同上)

Figure 2: Virginia Woolf and T. S. Eliot, photograph by Lady Ottoline Morrell, 1924
初期の――例えばシュメール、ギリシャ、ローマ、中国の――詩人たちは、まるで魔法のような力で、語る言葉に深い感情と響きを吹き込みました。彼らは韻律やリズム、押韻、イメージといった技法を用いて、これを成し遂げたのです。文学技法はその後も進化を続けていますが、最初期の技法の力は色褪せていません。イギリスのロマン派詩人パーシー・シェリーは、「詩の擁護」(1840年)の中で、偉大な詩を次のようにたとえています。
偉大な詩とは、英知と喜びにあふれる永遠の泉である。そして、ひとりの人、ひとつの時代が、それぞれ特殊な関係を共にするその泉の聖なる流れをことごとく汲みつくしたあとも、人と時代はつぎつぎにおこり、つねに新しい関係が生じて、予見も予想もされぬ歓びの源泉となるのである。(「詩の擁護」より、上田和夫訳)
この見方によれば、偉大な文学とは「神聖な」水の溢れる「泉」であり、時代を超えて人々を啓発し、楽しませ、新たな作家の登場によって、その煌めく水は永遠に新たに湧き続けるのです。
シェリーから百年後、アメリカ生まれのイギリスのモダニスト詩人T. S. エリオットは、この考えを反響させるかのように次のような詩行を書いています。
さように私は人生の半ばにいる、・・・
言葉を用いることを学ぼうとした、どの企ても
全く新しい出発となり、皆違った失敗となった
言葉を征服することだけ学んだからだ
も早や言う必要もないことのために学んだり
も早や言いたくないものの表現法を学んだからだ。
またそれがためにどの冒険も新しい初めとなり、
不明瞭なものを攻撃したが、こちらは
不正確な感情の一般的混乱によって
いつも低下するみすぼらしい装備の
未熟な情緒の小隊だった。
また力と服従によって征服すべきものは
皆すでに対抗などと及びもつかぬ人々に
よって一度も二度も幾度も発見されていた。
だが競争などということは不可能だ――
失われ、発見され、また失われたものを回復しようとする闘いにすぎない
またそれも不祥の条件のもとである。
それはおそらく得や損の問題ではない。
われわれにとってはただ努力することだけだ。
あとは皆われわれの仕事ではない。
(T. S. エリオット「イースト・コウカー」『四つの四重奏曲』1941年より、西脇順三郎訳)
伝統的に、言語化できないことは、超越性の重要な指標だと理解されてきました。それは、通常の経験を超えたところにあるとふつう信じられているものの条件なのです。恋に落ちること、深い悲しみ、自然や宇宙の美しさと力、神聖なものや神秘的なものへの感覚は、人々がしばしば超越的なものと考える典型例です。買い物リストや休暇中にしたことの日記などは、簡単に書き残して伝えることができますが、川面の上を旋回しながらハエを捕まえるツバメを見て感じる喜びや畏怖の念、あるいは、より劇的かつ複雑な例では、シェイクスピアの有名な戯曲におけるハムレットのように、自分の最も身近にいる人々が、見かけとは異なって、裏切り者や嘘つき、あるいはそれ以上に恐ろしい存在だったことに気づいたときの苦悩、怒り、自己疑念、混乱を、明確な言葉にして伝えるのは、はるかに困難であり、より多くの思考を必要とします。しかし、偉大な作家たちのなかでも最も偉大な作家は、これらの困難な課題を完璧な技術で達成し、しかも、出来事や思考、感情を現実のように感じさせ、私たち自身の人生と深く共鳴させるような新しい手法を用いてそれを成し遂げるのです。したがって、人文学へのいざないとは、人間性へのいざないであり、自分自身の、どこかより深い部分へのいざないでもあるのです。

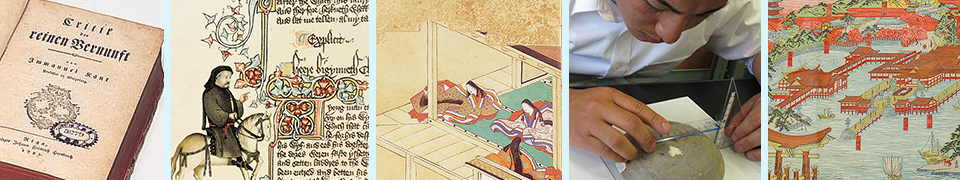
 Home
Home