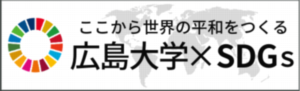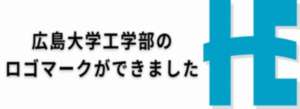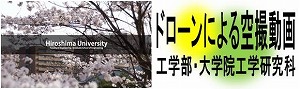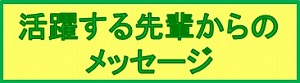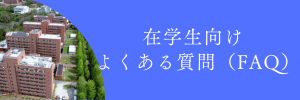以下の授業が2023年度後期の学部の「名講義」の上位10科目に挙げられました。(ただし、実習等及び受講者10人未満の講義は除いています。説明文は、講義概要や到達目標等から抜粋しています。)
材料科学 松木 一弘
近年、技術の進歩に伴って、機械や機械システムの高度化のために新しい材料の開発が迫られる場面も多くなり、「材料のわかる機械技術者」や「機械のわかる材料技術者」の要請が強くなった。この場合の「材料」には微視的な性質や挙動にまで立ち入らなければならない内容が多く含まれるようになってきている。本講義では、後続の材料関連の講義の基礎として、機械材料の構造と変化をもたらす諸現象を理解する。
(1)結晶構造の種類、結晶内の方向と面の表示、結晶欠陥および材料の構造を理解・説明できる能力。(B-1)
(2)平衡の概念、平衡状態図および原子の拡散、相変態を理解説明できる能力。(B-1)
(3)弾性変形、擬弾性および熱膨張等の原子の結合に起因する性質を理解・説明できる能力。(B-1)
(4)結晶のすべり変形と塑性変形、転位の運動および材料の強化機構を理解・説明できる能力。(B-1)
なお,「知識・理解」,「能力・技能」の評価項目は,下記のとおりである。
「教科書の各章末問題を十分な知識・理解のもとに回答できる能力。」
伝熱論 荻 崇
基礎化学工学及び応用数学をベースとして、物質間の温度差に基づいて移動する熱エネルギーの移動の評価について基礎的事項を学び、物質の種類、熱源の有無、非定常性、流体の流動状態などによる熱の移動量の変化および熱の移動が関係する操作の設計の基礎を学ぶことを目的とする。
なお、「知識・理解」、「能力・技能」の評価項目は、下記のとおりである。
(1) 伝導伝熱、対流伝熱、放射伝熱の特徴および相違点を確認する。
(2) 熱伝導方程式を直交座標系、円筒座標系、球座標系で導出し、意義を確認する。
(3) 平板、円筒、球体での定常熱伝導を理解する。
(4) 発熱を伴う定常熱伝導を理解する。
(5) フィンからの放熱現象を理解し、放熱の重要性を把握する。
(6) 非定常熱伝導を理解し、変数分離法を取得する。
(7) 非等温流れにおけるエネルギー保存式の解法を理解する。
(8) 自然対流伝熱および沸騰伝熱における熱の移動を理解する。
(9) 伝熱係数の意義と求め方、関連する無次元数を理解する。
(10) 黒体および非黒体間の熱放射による熱の移動を理解する。
有機構造解析 池田 篤志
有機化学の研究において、スペクトル測定を利用した化合物の構造解析・同定は欠くことのできない基本的な手法である。
本科目では、水素および炭素の核磁気共鳴スペクトル(NMR),赤外線吸収スペクトル(IR),および質量分析法(MS),紫外可視吸収スペクトル(UV-vis)を利用した構造解析に関する基本的知識の講義とそれらを用いた演習を行い,以下の知識と能力を習得することを授業の目標とする.
(1)各スペクトルの定量性,定性性を理解し,得られる情報の種類・質の差異と特徴を理解する.
(2)水素核磁気共鳴スペクトル(1H-NMR)における化学シフトと簡単なスピン結合を理解し,これらを利用した構造同定ができる.
(3)1H-NMRにおける比較的複雑なスピン結合系を解析することが出来る.
(4)磁気的非等価性について基本的な考え方が理解できる.
(5)炭素核磁気共鳴スペクトル(13C-NMR)における化学シフトを利用し,構造解析に利用することができる.
(6)赤外線吸収スペクトル(IR)における種々の官能基の特性吸収を理解し,構造解析に利用することができる.
(7)質量分析法(MS)における,分子イオンピーク,フラブメンテーション,同位体パターン,不飽和度などの各概念を理解し,これらを構造解析に役立てることができる.
(8)紫外可視吸収スペクトル(UV-vis)の予測と評価ができる.
(9)上記各手法を組み合わせ,スペクトル的手法のみで未知化合物の構造解析ができる.
専門有機化学I 大下 浄治
第三類応用化学プログラムの中で有機化学を取り扱うものの一つとして、以下の有機化学の知識を修得させる。
1)原子と分子;結合と軌道
2)アルカン
3)アルケンとアルキン
4)立体化学
5)環状化合物
6)ハロゲン化アルキル、アルコール、アミン、エーテル、およびその硫黄類縁体
システム制御II 脇谷 伸,木下 拓矢
「システム制御I」に続き,制御工学の基礎となる現代制御の理論,ならびに制御系設計法について講義する。また,近年産業界で注目されているモデルベース開発(MBD)において,制御系がどのような役割を果たすかについても概説する。
この講義で学習する主な内容は次の通りである。
(1) システムモデリング(微分方程式・状態方程式)
(2) システムの特性(可制御性・可観測性)
(3) システムの構造(正準構造・可制御/可観測正準形・実現問題)
(4) 制御系の安定性(内部安定・入出力安定)
(5) 状態フィードバック制御系設計(極配置・オブザーバ)
(6) 最適制御系設計(レギュレータ問題・サーボ問題)
(7) モデルベース開発(MBD)と制御系設計
専門有機化学II 大下 浄治
第三類応用化学プログラムの中で有機化学を取り扱うものの一つとして、以下の有機化学の知識を修得させる。
1)求核置換反応
2)置換アルカンの脱離反応
3)アルケンへの求電子付加反応
4)アルケンへのその他の付加反応とアルキンへの付加反応
5)アルカン、アルケンのラジカル反応
6)ジエン類の構造・性質と反応
生産管理論 森川 克己
生産活動を効率的に行うためには,生産の固有技術としての生産技術に加えて,生産システムの構成や構成された生産システムの計画管理に関する生産管理技術も欠かせない.本講義では,生産システムの設計と運営に関する生産管理の考え方や技法について講義する.
本講義の受講により,生産システムの設計と運営に関する生産管理の問題が解決できるようになり,生産活動の効率化のための基礎力を養うことができる.具体的には,
1) 生産システムの設計や計画管理と生産活動の効率との関係についてとらえる能力が身に付く.
2) 生産システムの設計や運営に関する生産管理の基本的考え方や技法がわかる.
3) 生産管理の考え方や技法を応用して,生産システムの設計と運営に関する生産管理の問題を解決する能力が付く.
河川工学 内田 龍彦
流域における水循環系の素過程とともに,治水計画の策定や河川生態系の保全に必要な基礎的事項を講義する。
なお,「知識・理解」,「能力・技能」の評価項目は,下記のとおりである。
1.水循環系を構成する素過程や都市化が水循環系に与える影響を説明することができる.(C:問題構成力)
2.河川構造物の整備において生態系に配慮すべき事項やその理由を説明することができる.(C:問題構成力)
3.降雨-流出解析,洪水流解析,河床変動を説明することができる.(D:問題解析力)
腐食防食 矢吹 彰広
金属の腐食,防食を理解するために金属の表面状態,溶液との界面状態,電気化学の基礎的知識を学ぶ。本講義を受講することにより,電位,電極反応,分極,腐食の形態,防食技術を習得できる。腐食防食技術は化学プラントの安全運転のための重要な基盤技術の一つである。
なお,「知識・理解」,「能力・技能」の評価項目は,下記のとおりである。
1) 金属の表面,金属と溶液の界面を理解できる。
2) 腐食の形態,電極,電位を理解できる。
3) ネルンストの式,電位-pH図を理解できる。
4) 分極,Butler-Volmer式を理解できる。
5) ターフェル式,分極曲線,腐食電流,腐食電位を理解きる。
6) 不働態,腐食抑制剤を理解できる。
7) コーティング,防食技術を理解できる。
ナノテクノロジー 鈴木 仁
電子デバイスの作製・評価、電子材料、電気材料の評価等で必要とされる真空技術、表面分析・観察技術の基礎理論および技術について講義する。電子デバイスの最先端で必要とされるナノメートルサイズの物質で発現する物性および特徴的振る舞い、ナノメートルサイズの各種材料について講義する。
これらを通して、表面科学やナノテクノロジーの基礎的な知識および考え方を理解する。
この授業で学習する主な内容は次の通り。
1.真空技術
2.表面科学の基礎、表面物性
3.表面分析・計測技術
4.ナノ構造,ナノ材料の物性


 Home
Home