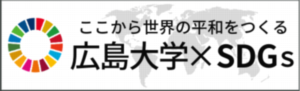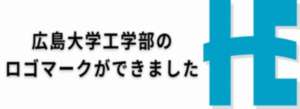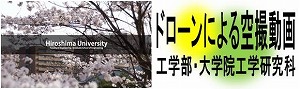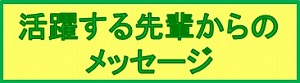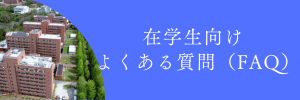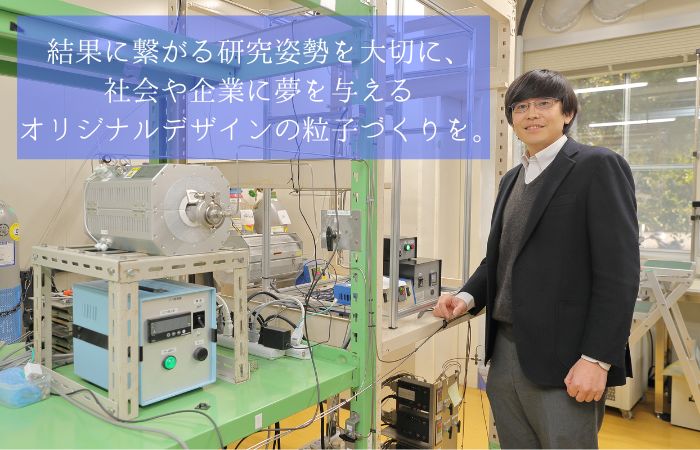
用途に応じた微粒子材料の作製と、微粒子作製プロセスの開発
微粒子をデザインする独自の製造プロセス
コーヒーの粉や砂に始まり、霧、薬、そして宇宙に至るまで、一説によると私たちの身の回りの約70%のものは微粒子でできていると言われています。私の研究室では、目的に応じて微粒子を作ったり、微粒子を作るプロセスそのものを研究・開発しています。まずは微粒子を作る方法を簡単にご紹介しましょう。作製方法は食塩水を煮詰めて食塩を取り出すのと似ていて、例えば作りたい微粒子の材料が混ざった液体を専用の装置に入れて噴霧し、高音の熱にかけて水分を蒸発させたり不要な分子を取り除いて、目的の粒子だけを取り出します。研究室には装置が複数台あり、使用
する素材が熱に強いかどうかや材料の状態(個体・液体・気体)によって使い分けています。
微粒子を作る技術はいくつかあるのですが、この研究室ならではの特徴は微粒子を「デザイン」できる点です。例えば実際に作製したものに、A材料がB材料に覆われた二重構造の微粒子(コアシェル微粒子)があります。これは磁石がシリカという素材に包まれた微粒子で、電子デバイスのインダクターなどに使用するために作製したものです。インダクターとは、スマートフォンやパソコンなどの通信機器、自動車、半導体、精密機器などあらゆる電子機器で活躍している必要不可欠な電子部品です。この材料には、不導体で覆われた小さな磁石の粒子(磁性粒子)が使われています。最近では、電子部品の小型化や高機能化に伴って、もっと小さく、球形で、大きさの揃った粒子が必要となってきています。私たちの研究室では、若手の先生や大学生が独自開発した実験装置を用いて、世界で初めてサブミクロン領域のサイズ(100nm~1000nm)で、不導体で覆われた小さな磁石の粒子を作製することに成功しました。
世の中のニーズに応えながら夢のある研究を
微粒子のデザインについて、もう少し詳しくお話ししましょう。例えば紙にコーヒーを垂らすと、乾く過程でコーヒーリングと呼ばれるしみができますが、あれはゆっくり乾燥する過程でコーヒーの成分が端に寄ることが原因です。このように液体の乾燥過程で粒子が配列することを「自己組織化」といって、材料が自分の力で形を作ってくれます。私たちはこうした性質を利用したり、粒子が組み上がる過程の条件を変えることで構造をデザインしているのです。例えば、液滴に600℃の熱で消える高分子を混ぜて約1000℃の加熱路を通すと、高分子があった箇所に穴が空いたような粒
子を作り出すことができます。穴が空くことでコストカットに繋がったり、反応しやすい粒子になったり、軽くなったりと様々なメリットがありますが、仮に車の排ガス処理用の触媒に使用する粒子であれば、少ない材料で有害ガスの無毒化にかかる時間を短縮でき、環境保全と資源の有効利用にも繋がるといったイメージです。
上記のもの以外にも様々な微粒子とその作製プロセスを研究していますが、その多くは企業の依頼によるものです。企業との共同研究は情報収集しながら世の中のニーズを知ると共に、自分たちの研究範囲を改め
て自覚し、視野を広げる上でも重要です。しかし、「すぐに実用化できない研究」や「ゼロからイチを生み出す研究」を大きなプレッシャーなくできるという大学ならではの環境下で、基礎研究を進めることもとても大切だと感じています。恩師の「企業に夢を与える研究を」という言葉を胸に利益だけに捉われない研究を心がけており、そのスタンスを守りつつ、将来的には唯一無二の微粒子設計拠点を広島に立ち上げることが私の最大の目標です。
日々一生懸命向き合ったことが成果に繋がる
私が研究者になれたのはもちろん恩師のおかげもありますが、予期せず成功した研究に救われてきたという側面も大いにあります。ドクターのころ、後輩と一緒にLEDに使われる粒子の研究をする傍ら、放熱材料に関する粒子の実験もしていたのですが、その実験結果を受けて後輩が「上手く光りましたよ」と報告してくれました。「今やっている実験は放熱材料だよ」と半信半疑だったのですが、確認すると本来光らないはずのものが光っていて、新発見だ!と興奮しました。恩師を驚かせたいと思いこっそりデータを揃えて報告するとすぐ論文を書くことになり、そのおかげで様々な賞をいただいたりドクターを2年で卒業することができたりと、その後の人生に影響するような出来事となりました。それと似たようなことがこれまでに数回ありましたが、そういった研究結果は狙って出せるものではなく、幅広い視点を大切にしつつ日々目の前のことに一生懸命取り組むことでしか得られないのではないかと感じています。
学生への指導もそうした経験による価値観が大きく作用しており、学生が達成感を感じる教え方、もしくは10年後に「良かったな」と思えるような教育を目指しています。例えば、解決策を簡単に教えない、テーマを変えたいと言ってもできるだけ粘らせる、といった具合です。研究の出口は一つではなく取り組んだことが何かしら成果として残るため、学生に能動的にチャレンジしてほしいと思っています。また、夢に向かって頑張ることはもちろん立派で素晴らしいことですが、私は成り行きに身を任せるのも一つの方法だと思っています。今は目標に向かってコストパフォーマ
ンス・タイムパフォーマンスよくやるのが主流かもしれませんが、高校生の皆さんはもっと肩の力を抜いて、失敗を恐れずやりたいことに飛び込んだり、自分にしかない視点や価値観を大事にしてみてください。大学は自分探し、研究は宝探し、無限の可能性を秘めた場所です。自分らしく世界を広げながらじっくり成長できる環境で、一瞬一瞬を大切に過ごしていってください。

荻 崇 教授
TAKASHI OGI
熱流体材料工学研究室
2008年3月 広島大学 大学院工学研究科 物質化学システム専攻 博士課程後期修了 博士(工学)
2008年4月 大阪府立大学 助教
2010年9月 広島大学 大学院工学研究院 助教
2015年1月 広島大学 大学院工学研究院 准教授
2015年4月 スイス連邦工科大学 Institute for Chemical and Bioengineering 客員教授
2020年4月 広島大学 大学院先進理工系科学研究科 准教授
2021年4月 広島大学 大学院先進理工系科学研究科 教授


 Home
Home