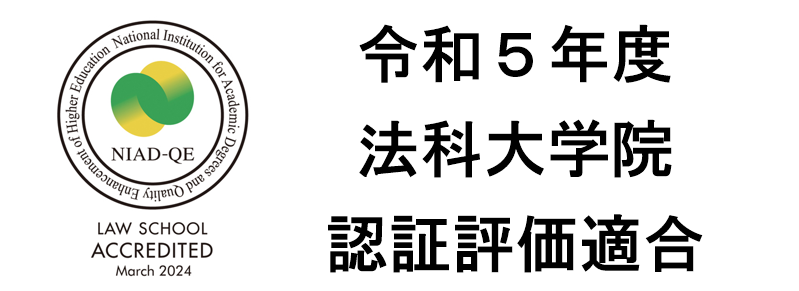ソクラテスは市井にあって市民をつかまえ、対話による問答法をもって、内面的自覚を伴った知識の助産術を施しました。特にソフィストに対しては、自らは無知を装って(というかまさに誠実に自らをそう考えて)、相手の見解を述べさせながら、その矛盾点を露呈させて、その知識の空虚さを指摘するのです。ただ、これは嘲笑を目的とするのではなく、相手の精神に真理が育つための雑草抜きであったと思います。
これは、混迷の度を深める現代社会において、従来の、情報等をストックして課題解決を生み出そうとする手法から、集めた情報等を速やかにフローさせて、ヘッジにおけるイノベーションを起こすディメンションへと変化する中では重要な手法であると思われます。未知の、あるいは予測不能な課題を事前に解決することが求められる法曹・法律家にとっても是非とも修得しておくべき技量でしょう。
その意味では、法曹という専門職を養成する法科大学院はもとより、有為な人材の育成を目的とする教育機関において教鞭を執る者に求められる能力、技量や経験はますます高まっています。それに応える学びは学生以上に必要となっています。少子化もあって教える場が小規模化すると、教える者の姿勢が学生に与える影響は学生の目指す方向が明確化し先鋭化するほど大きくなってくるように思われます。
昔、耳にタコができるくらい聞かされた言葉です。
「教えることが学ぶ者の潜在的能力を引き出すことにあるとすれば、学ぶ者の前では教える者は自身の 配慮をすべて捨てよ。自分がああだこうだとか言うことは意識的にも無意識的にも出してはならない。さもなくば、教壇は教える者の興行の舞台にすぎず、いくら双方向的な手法が取られても、一方的な押し付けにしかならない。自分が自分がという者には他人は見えていない。ただただ学ぶ者を見てその者が自立的に学ぶことができるようその能力を育てることを意識せよ。そのための方法論を学べ、自らはそれを実 践してその成果を確認せよ。それを伝えるのだ。そこから教える者の自己改革が始まり、教育の場が活力と創造に満ちる。」、と。
その当時は、敬虔さと跪拝なのかと思いました。その言葉の主が教壇にあがるとき、登壇の前に立ち止まって目を閉じるのですが、それは気を集中させているのかなと見ていたのですが、そうではなく、彼は自分の計らいを捨て、学ぶ者の潜在的能力に跪き敬っていたのだと知った時には、とても恥ずかしい思いをしました。
後に仏法を少しかじって「捨」の行と「積徳」の行とを学んだ時に、彼のその姿勢とこの言葉を一番に思い出しました。教壇に立つというのは我を捨てる行なのだと得心したものです。人を導く者は先達として前を歩んでいることが必要だからです。ただ、この知がソクラテスのいう知識になっているかは心許ないところですが・・・。
次回は「戯言」です。



 Home
Home