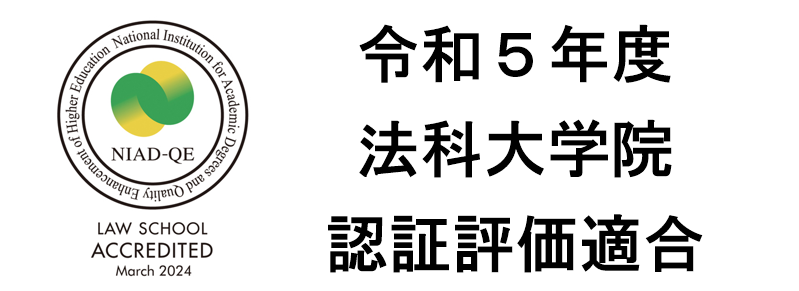川中・野口法律事務所 弁護士
川中 力 さん
東北大学法学部を卒業した後、民間企業での勤務を経験し、地元鳥取の高等学校の教師へ。親友の言葉を受けて司法の道を志し、広島大学法科大学院へ進学。見事司法試験に合格し、司法修習期間を経て、川中・野口法律事務所に入所。事件件数の少ない地方都市で、幅広い分野を取り扱うジェネラリストとしての活動をしている。依頼者が本当に求めていることは何なのか。またはクライアントのためにどういうことができるのかということを一旦クライアントの言葉で喋ってもらい、それを法律家としてかみ砕いて、また手続きに合わせて組み立てて理論づけしていくことを心がけている川中さん。その彼に第一線で活躍する弁護士の仕事について尋ねてみた。
親友の言葉が自分を弁護士の道にいざなった
Q. 法曹という仕事を選んだきっかけ
川中:私の司法試験受験に背中を押してくれたのは、高校時代の同期の男性友人でした。その同期は、現在公認会計士をしており、当時残業代の出ないブラック企業で消耗する姿を見て「川中は、同期の中で一番勉強ができたのだから、今からでももっと勉強して弁護士になるべきだよ。」と言ってくれました。今から考えるとそれまでの職歴を捨てて、勉強一本に専念することは、リスキーな選択であるとも思えますが、同期(高校時代3本の指に入るほどの私の親友)からの言葉や、弁護士50周年のベテランである父から、「弁護士になるためであれば、全面的に協力するよ」という言葉もあり、その言葉に背中を押されて司法試験受験の道を選びました。
Q. 主に扱われている案件の分野や取組内容について教えてください。
川中:都会の弁護士と違い、田舎の弁護士は例えば交通事故専門の弁護士ですとか、刑事事件専門の弁護士というふうに専門分野を絞ることができません。事件件数の少ない地方都市では、交通事故や刑事事件などの特定分野におけるスペシャリストでは食べていけないので、幅広い分野を取り扱うジェネラリストとしての活動をしているのがほとんどです。私の最近の取扱事件の中で、一番多いものが交通事故、二番目に離婚、次に遺産分割相談です。その他労働紛争、顧問企業に対する契約書のホームチェック・リーガルチェックや経営相談及び自己破産申立など幅広く取り扱っています。
自分一人の責任において仕事ができるというのが一番の魅力
Q. 法曹になって良かったことは何でしょうか?
川中:弁護士開業1年が経過しますが、ありがたいことに個人的な知人・友人からの相談や依頼が多くあり、法的紛争や問題に悩む人を助けられる実感がありました。一人の専門家として扱ってもらいますので、会社組織に属していた頃のような上司への根回しだとか、部下の不満を和らげるとか口をきくとか、そういうことはなくて、自分一人の責任において仕事ができるというのが一番の魅力です。良くも悪くも最終責任者ですので、組織上の上長との意見のすりあわせで神経をすり減らすことがなくなりました。
Q. 法曹になるまで、もしくはなってから、困ったことはありますか。
川中:弁護士の仕事は、毎日が研究・研究で、依頼される仕事もカテゴライズできるものもあれば、そうでない仕事もあります。ゆえに、相談を受けて、受任してから走りながら物事を調べて新しい事件だったら通達を見たりだとか、判例を見たりということをしながらやっております。弁護士になってから、裁判所に書類1枚提出するだけでも、訴訟法・訴訟規則や慣例に則って行う業界ですので、最初は、手探りの作業が多かったですが、ありがたいことに、うちの事務所では私を含めて5名の弁護士がおりますので、先輩弁護士(いわゆる「兄弁」)に教えてもらいながら、また聞きながら仕事を進めるということができております。ただ、先輩弁護士でも扱ったことがないような特殊な法律分野であるとか、法務業務の場合もありますので、そこら辺については随時本を買いながらやっております。また、勤続年数が長い熟練の事務員さんに教えてもらったりもしながら仕事をしています。民事訴訟規則上の手続ですとか、刑事訴訟規則上の手続ですとか、検察官刑事裁判記録の謄写をしてもらうことですとか、後は戸籍を取ってもらう住民票を取ってもらう。そういった事務仕事では大変助かっております。実務に出ると裁判所書記官の方や法務局の職員の方に見解や慣例についてお伺いすることもよくあります。
依頼者との信頼関係維持のためにコミュニケーションを充実させることを心がけています
Q. 法曹の仕事を行うのに、心がけていること、または必要と思うことは何でしょうか?
川中:どの仕事でも「ホウレンソウ(報告・連絡・相談)」は大切ですが、弁護士の取扱事件は、人の不幸であったり、不安感であったり、センシティブな問題ですので、依頼者との信頼関係維持のためにコミュニケーションを充実させることを心がけています。まずは自分なりに咀嚼するということが大切かと思います。本に書いてあることと同じことを言ってくる依頼者はいません。依頼者が本当に求めていることは何なのか。またはクライアントのためにどういうことができるのかということを一旦クライアントの言葉で喋ってもらうのですが、それを法律家としてかみ砕いて、また手続きに合わせて組み立てて理論づけしていくことを心がけています。
極真カラテを週1回は行けるようにしたい
Q. 仕事とプライベートのバランスはいかがでしょうか?
川中:ワーク9.5:ライフ0.5くらいの仕事量です。新人のころは、どうしてもひとつひとつの仕事に時間がかかります。仕事の量に比べて調べる量が大変多くなるというところです。常に新しいものに取り組んでいくわけですので、とにかく準備が大変ですね。そうなりますとどうしても夜は遅く帰ることになりますので、なかなかプライベートが過ごせないということはあります。プライベートでは、広大ロースクールに入る前からもともと、極真カラテを週に2、3回程度していたのですが、仕事が忙しく週1回行けるかどうかです。今後は、心身の健康のために少なくとも週1回は、行きたいと考えています。
臨機応変に瞬発力を持って対応できるような弁護士になりたい
Q. これからご自身が目指す将来について教えてください。
川中:日々研鑽の毎日ですが、このままのモチベーションで「基本的人権を擁護し、社会正義を実現する」(弁護士法1条1項)という弁護士の使命を果たし続けたいと思います。そいて、幅広い分野で活躍していかなければいけないと思っています。というのは、弁護士の数が20年前に比べると3倍ぐらいになっていまして、そうすると弁護士が増えたからといって事件が増えるわけではない。突然に来る事件、お客様というのもニーズが幅広いものになっていくと細分化されてきています。また、新しい制度や新しい法律、新しい手続きも増えてきていますので、常日頃から勉強はしなくてはいけません。一つ一つの事件に向かい合って、時には未知の、どこの本にもどこの先生も体験したことがないようなことに立ち向かっていくことにはなると思いますが、臨機応変に瞬発力を持って対応できるような弁護士になれればと思っております。
先生との距離が生徒の数が少ない分、非常に近い、人的な環境を最大限生かせる
Q. 広島大学の法科大学院で、学んで良かったと思うことはありますか。
川中:広島大学法科大学院は、教授の方は非常に専門知識に優れていらっしゃる。それから生徒の数が少ないので、自分の力でわからないところを聞きに行く。それからオフィスアワーですね。オフィスアワーを利用する、またはメールを利用するなどして質問しても返ってくるというのが特徴だと思います。修習中に大規模なロースクール出身の修習生もいましたけども、なかなか先生とのコミュニケーションというのは取りづらいと聞いております。その点、広島大学ロースクールですと先生との距離が生徒の数が少ない分、非常に近いのではないかなというふうに思っておりまして、人的な環境は最大限生かせるのではないかなと思います。
「今受かる。」という気持ちで日々勉強して下さい。休憩はもう少しあとで取れます。
Q. これから法曹を目指す方へメッセージをいただけますか。
川中:現代において企業が求める人材というのは、恐らくは専門的な知識、いわゆる手に職をつけた人材を求めているというふうに感じます。文系ですと大学学部段階で、そのような専門知識を得るに至る制度というのはなかなかないのでしょうけども、法科大学院ですと実務に通用する法的知識、またそのような法的考え方、思考方法、思考プロセスのいずれかを踏めるところがありますので、専門知識に限らず思考能力の展開ですとか、そういったことをアピールできると思います。その意味では、法曹課程に進む意味というメリットがあると思います。今、司法試験は合格者が多くなり、「受かりやすい」試験になっています。「今受かる。」という気持ちで日々勉強して下さい。休憩はもう少しあとで取れますので。ちなみに、勉強には「量か質か。」という問題がつきものですが、毎日最低限8時間は勉強して下さい。私は、大学で学習する中で、「やるならやる。やらないなら辞める。」という心構えで毎日勉強していました。

周田専攻長(法科大学院長:撮影当時)と
2024年2月17日取材
取材場所/広島大学法科大学院


 Home
Home