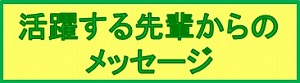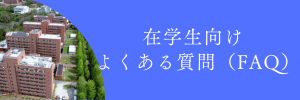以下の講義が2024年度後期の学部の「名講義」の上位10科目に挙げられました。(ただし、実習等及び受講者10人未満の講義は除いています。説明文は、講義概要や到達目標等から抜粋しています。)
伝熱論 荻 崇
基礎化学工学及び応用数学をベースとして、物質間の温度差に基づいて移動する熱エネルギーの移動の評価について基礎的事項を学び、物質の種類、熱源の有無、非定常性、流体の流動状態などによる熱の移動量の変化および熱の移動が関係する操作の設計の基礎を学ぶことを目的とする。
なお、「知識・理解」、「能力・技能」の評価項目は、下記のとおりである。
- 伝導伝熱、対流伝熱、放射伝熱の特徴および相違点を確認する。
- 熱伝導方程式を直交座標系、円筒座標系、球座標系で導出し、意義を確認する。
- 平板、円筒、球体での定常熱伝導を理解する。
- 発熱を伴う定常熱伝導を理解する。
- フィンからの放熱現象を理解し、放熱の重要性を把握する。
- 非定常熱伝導を理解し、変数分離法を取得する。
- 非等温流れにおけるエネルギー保存式の解法を理解する。
- 自然対流伝熱および沸騰伝熱における熱の移動を理解する。
- 伝熱係数の意義と求め方、関連する無次元数を理解する。
- 黒体および非黒体間の熱放射による熱の移動を理解する。
通信工学 亀田 卓
ブロードバンドインターネットやスマートフォンの普及に伴い、ネットワークの利用が日常生活に不可欠なものとなっている。本講義では無線通信システムを中心として、その基礎となる以下の内容について学ぶことを目的とする。
- はじめに(電気通信の歴史、有線による電気通信、無線による電気通信)
- 通信ネットワーク(インターネット、プロトコル、OSI参照モデル、信頼性)
- フーリエ変換とスペクトル
- 不規則信号と雑音
- アナログ変復調
- ディジタル変復調
- 多重伝送とアクセス方式
- 電波伝搬とダイバシチ技術
応用数学I 川下 和日子
基本的な常微分方程式の解法を習得し、微分方程式の応用に必要な数学的基礎を身につけること。
具体的には:
- 微分方程式に関する基本的な術語や概念を理解すること。
- 1階線形微分方程式の解法を身につけること。
- 変数分離形の微分方程式の解法を習得すること。
- 線形微分方程式の解法の一般的な原理を理解すること。
- 2階定数係数線形微分方程が解けること。
- 高階定数係数線形微分方程式と1階連立微分方程式の関係について知ること。
- 微分方程式のべき級数解を数学的に正しく扱うこと。
- 微分方程式の応用例について知ること。
海洋大気圏システム 作野 裕司
海洋、大気に代表される自然界の環境システムに関する基礎的知識を取得する。
計測工学 新宅 英司
物理量等を計測することは工学の基礎的手法として重要である。本講義では計測を行うために必要な装置と計測原理、使用方法、および、計測して得られる情報・データの統計的な処理について解説する。また、船舶、自動車、航空機などの輸送機器、環境機器における計測の利用例、役割について解説する。
- 単位、標準の意義を理解し、適切な単位、次元を選択することができる。
- 計測装置、計測原理・方法について理解し、対象とする現象に適した計測方法を選択することができる。
- 不確かさと精度について理解し、説明することができる。さらに、最小二乗法等を用いて計測データを統計的に処理することができる。
- 信号処理について理解し、説明することができる。また、計測データを適切な信号変換を選択して信号処理することができる。
量子力学 高根 美武
電子物性を微視的に理解するために必要な、量子力学の考え方とその簡単な応用について講義する。
この授業で学習する主な内容は次の通り。
- 調和振動子
- 水素原子
- 交換子と不確定性原理
- トンネル効果
- 非定常状態に対する摂動論
専門有機化学IV 田中 亮
高度な有機化学の反応性や性質を学習し、多彩で多様な有機化学を組織的に理解できる能力を身につける。
授業の目標:
- カルボン酸誘導体の性質、合成法、反応性を理解する
- カルボニル基α位の酸性度とそれに伴う反応性を理解する
- 遷移金属錯体上での基本的な素反応と、それらを組み合わせた代表的な反応について理解する
反応工学 長澤 寛規
反応速度を基礎にして体系化された反応工学を学ぶとともに、反応速度式の解析法およびこれに基づく反応装置の設計と操作法を修得する。
材料科学 松木 一弘
近年、技術の進歩に伴って、機械や機械システムの高度化のために新しい材料の開発が迫られる場面も多くなり、「材料のわかる機械技術者」や「機械のわかる材料技術者」の要請が強くなった。この場合の「材料」には微視的な性質や挙動にまで立ち入らなければならない内容が多く含まれるようになってきている。本講義では、後続の材料関連の講義の基礎として、機械材料の構造と変化をもたらす諸現象を理解する。
- 結晶構造の種類、結晶内の方向と面の表示、結晶欠陥および材料の構造を理解・説明できる能力。(B-1)
- 平衡の概念、平衡状態図および原子の拡散、相変態を理解説明できる能力。(B-1)
- 弾性変形、擬弾性および熱膨張等の原子の結合に起因する性質を理解・説明できる能力。(B-1)
- 結晶のすべり変形と塑性変形、転位の運動および材料の強化機構を理解・説明できる能力。(B-1)
なお、「知識・理解」、「能力・技能」の評価項目は、下記のとおりである。 「教科書の各章末問題を十分な知識・理解のもとに回答できる能力。」
システム制御II 脇谷 伸、木下 拓矢
「システム制御I」に続き、制御工学の基礎となる現代制御の理論、ならびに制御系設計法について講義する。また、近年産業界で注目されているモデルベース開発(MBD)において、制御系がどのような役割を果たすかについても概説する。 この講義で学習する主な内容は次の通りである。
- システムモデリング(微分方程式・状態方程式)
- システムの特性(可制御性・可観測性)
- 制御系の安定性(内部安定・入出力安定)
- 状態フィードバック制御系設計(極配置・オブザーバ)
- 最適制御系設計(レギュレータ問題・サーボ問題)
- モデルベース開発(MBD)と制御系設計


 Home
Home