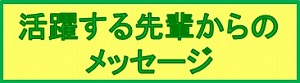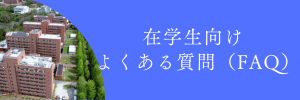以下の講義が2024年度後期の学部の「名講義」の上位5科目に挙げられました。(ただし、実習等及び受講者10人未満の講義は除いています。説明文は、講義概要や到達目標等から抜粋しています。)
専門有機化学III 池田 篤志
有機化学の基幹となす一群の化合物であるベンゼン誘導体、カルボニル化合物、および、これらから誘導される重要な化合物の性質、合成法および反応について講義し、以下に示す有機化学の学問に必要な基礎知識を習得することを目標とする。
(1) 不飽和共役分子の電子構造を理解し、その反応性、物性との相関を理解する。
(2) ベンゼン系化合物の芳香族性に関する基礎的な知識を習得し、その特異な安定性と特徴的な反応性について理解する。
(3) 各種芳香族求電子置換反応を学び、その類似点と相違点を理解すると共に、置換基の共鳴・誘起効果が置換反応の反応性と配向性に及ぼす影響を理解する。
(4) カルボニル化合物の構造的特徴に由来する求電子付加反応を習得し、その合成化学への有用性を理解する。
(5) カルボン酸の多用な化学的性質を学び、その付加-脱離機構についてふれる。
機械材料概論 岡本 康寛
機械工学における材料工学の重要性を認識する。また、機械技術者として必要な、金属材料を中心とした機械材料の基本特性を理解し、目的に応じた材料評価と材料選択の基礎を習得する。
応用数学II 川下 和日子
ベクトル解析の基礎的な事項を講義する。その際、各種の演算の物理的意味を明らかにし、電磁場・流体現象・力学などの工学分野への応用に配慮する。
(1) ベクトルや多変数関数の基本的な性質について知り、自由に演算ができる。
(2) 曲線・曲面の定義と径数の意味を理解し、曲線の長さや曲面の面積などを具体的な対象について計算できる。
(3) スカラー場やベクトル場の概念を理解する。
(4) 勾配・発散・回転などを自由に操ることができる。
(5) 線積分や面積分を自由に計算でき、種々の積分定理について理解し、さまざまに応用することができる。
(6) 電磁場や流れ場などの物理現象についての数学的記述を理解する。
粉体工学 福井 国博
工学分野では微粒子を対象にした操作が非常に多い。微粒子の物理的性質と粉体に関する基礎知識を修得し、公害防止管理者試験(大気,粉塵関係)の技術的設問が60%以上解けることを目標とする。 なお、「能力・技能」の目標は,下記のとおりである。
(1) 粒度分布の測定法と測定原理を理解する。
(2) 微粒子の運動方程式とその解法を理解する。
(3) 粒子の捕集及び分級の理論と各種の装置の測定原理を理解する。
(4) 粒子充填層の性質とその利用法を理解する。
(5) 遠心場を利用した粒子分離装置の捕集理論を理解する。
(6) ろ過理論,粉砕法則を理解する。
粘性流体と乱流の力学 陸田 秀実
到達目標に基づく本授業の目標か以下の通りである。
(1) 輸送機器周りの粘性流体に関して、知識・理解を深め、関連の問題解決ができる。
(2) 輸送機器周りの境界層に関して、知識・理解を深め、関連の問題解決ができる。
(3) 輸送機器周りの乱流現象に関して、知識・理解を深め、関連の問題解決ができる。


 Home
Home