2025年7月8日,広島大学ミライクリエにて,「第三回生物多様性まちづくり勉強会」を開催しました。本勉強会は,広島大学先進理工系科学研究科/SmaSo研究院の保坂哲朗教授が主宰する,生物多様性に関心を持つ研究者,学生,行政関係者,市民らが分野を越えて交流・議論することを目的としています。
第三回目となる今回は,東広島市に多数存在する「ため池」をテーマに,地域の多様な価値や課題について,多角的な視点から意見交換が行われました。
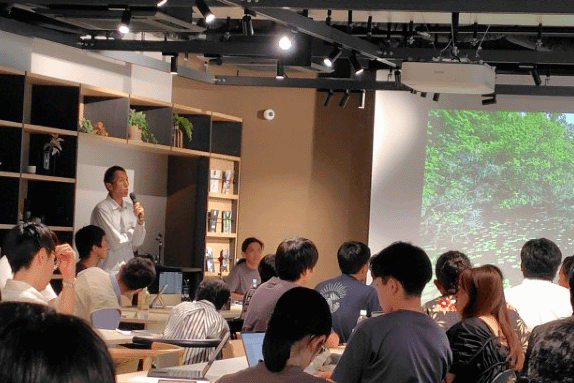

冒頭では,保坂教授より,生物多様性の包括的理解の必要性と,多様な立場からの対話の場を設ける意義について説明があり,生物多様性が持つ多面的な価値への理解を深める契機となりました。
続いて,人間社会科学研究科の熊原康博教授より,東広島地域に見られる「皿池」について,地形と歴史資料をもとに,人間の営みと地形の関係性を読み解く発表が行われました。
また,IDEC国際連携機構/SmaSo研究院の渡邉園子准教授からは,西条盆地に分布するため池群が,絶滅危惧種を含む多様な植物の生育地として重要な役割を果たしていること,そして近年の土地改変や管理の困難化,防災の観点により,それらが危機に直面している現状について報告がありました。
さらに,生物生産学部4年の有村拓真さんからは,東広島市内のため池を対象とした環境DNA調査の成果が紹介され,フィールドワークと分子生物学的手法を融合させた地域理解の新たなアプローチが提示されました。
地域資源について、地誌や地形、生態、社会の関係性を多面的に捉えることは、自然との共生や地域の持続可能な未来を考えるうえで欠かせません。
次回のまちづくり勉強会でも、生物多様性をめぐる多様な視点からの対話の場を引き続き提供していく予定です。今後の展開にもぜひご注目ください。


 Home
Home



