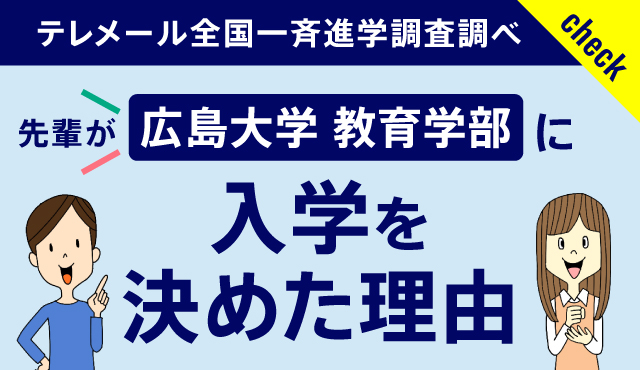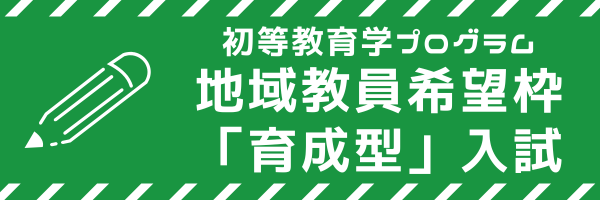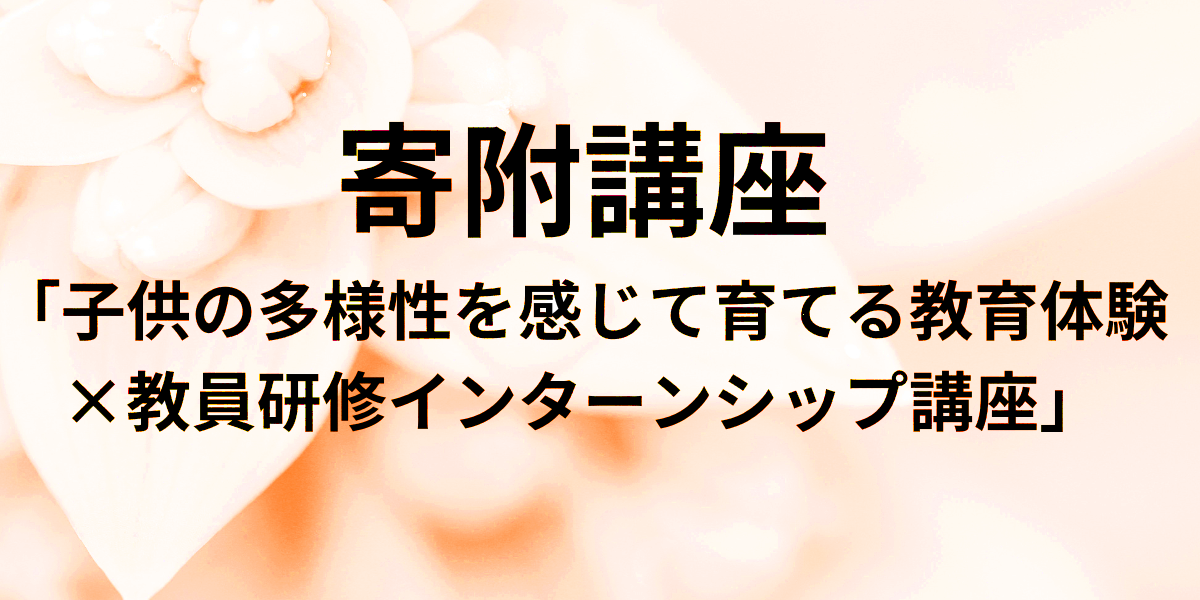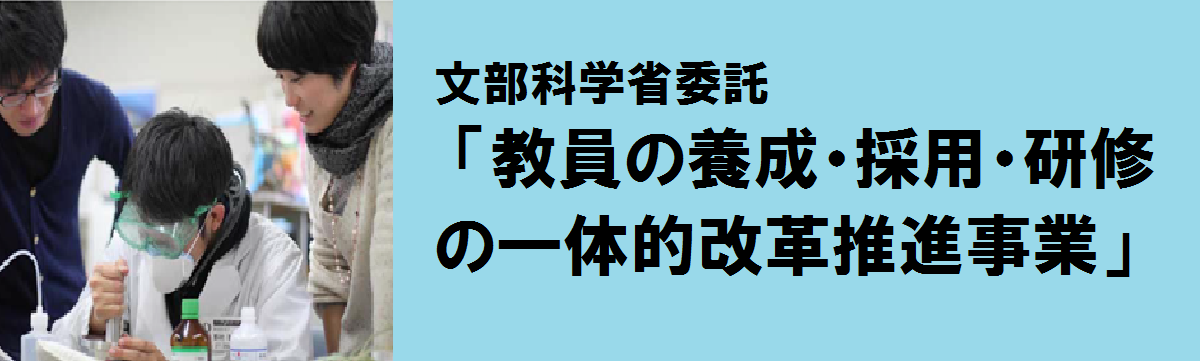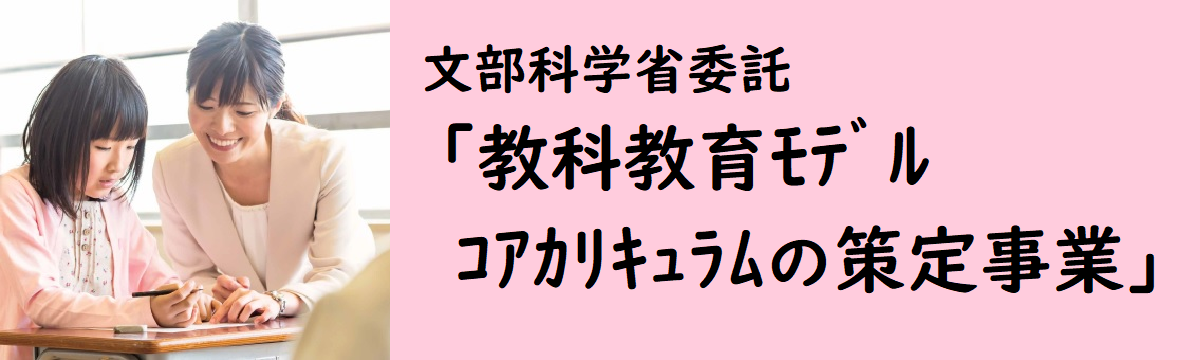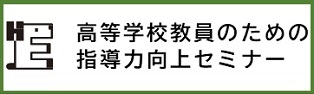E-Mail:evri-info(AT)hiroshima-u.ac.jp
※(AT)は@に置き換えてください

広島大学大学院人間社会科学研究科「教育ヴィジョン研究センター(EVRI)」は、2025年9月12日(金)に、定例オンラインセミナー講演会No.183「Research Exchange Meeting: Early Childhood Education & Care」を開催しました。幼児教育の研究者や大学院生を中心とした18名の皆様にご参加いただきました。
冒頭には、丸山恭司学部長より挨拶がなされました。挨拶では、ポーランドからの研究者らへの歓迎のことばが述べられました。また、日本の幼児教育やポーランドの幼児教育について相互に理解を深める場として、本セミナーへの方向づけがなされました。

挨拶をする丸山教育学部長
次に、司会の武島千明特命助教(広島大学)より、本セミナーの趣旨が説明されました。本セミナーでは、日本、ポーランド、ナイジェリア、中国、といった、多様な背景をもつ研究者らがそれぞれの視点から「日本の幼児教育」をテーマとした深い議論を行うことが目指されているということが確認されました。また、登壇者らは、セミナーに向けて広島大学附属幼稚園の2園舎をすでに訪問している、という情報が共有されました。
その後、4つの話題提供がなされました。
はじめに、中坪史典教授(広島大学) より、“Early Childhood Education and Care in Japan: Play as a children’s volintary activity”と題した話題提供がなされました。まず、日本の幼児教育システムの概要に関する説明がなされました。大きく3種類の幼児教育施設があるということや、『幼稚園教育要領』などで示されている幼児教育の理念などが整理されました。次に、日本の幼児教育の特徴として、「見守るアプローチ」が紹介されました。日本の保育者が、子どもの状況を理解しつつも、教育的な意図を持って介入を控えていることが、事例とともに説明されました。
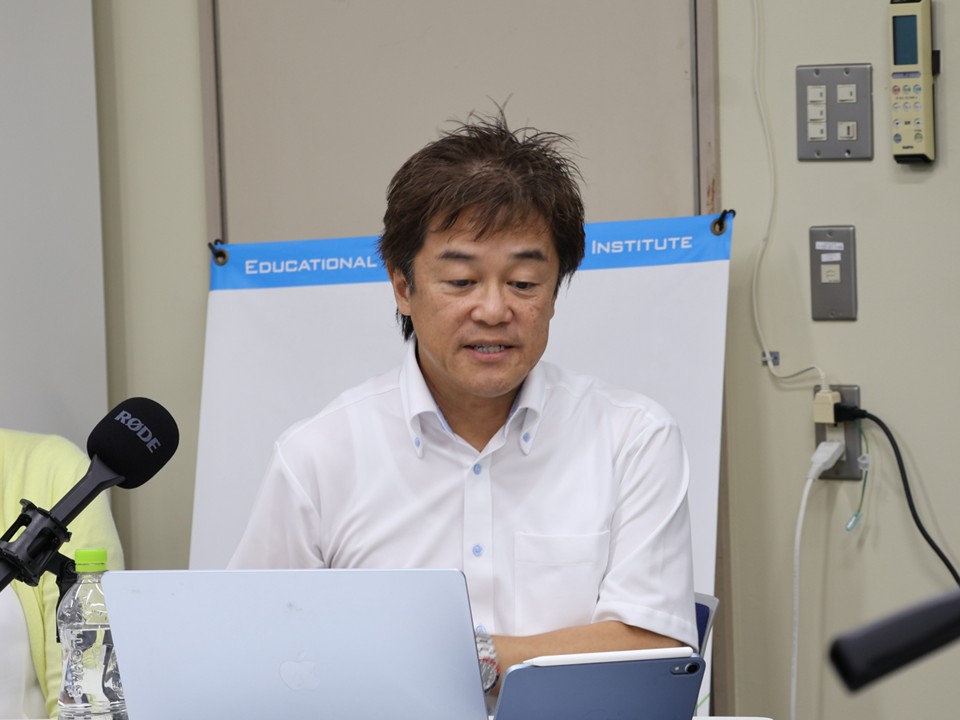
話題提供を行う中坪教授
その後、質疑応答がなされました。Zuzanna氏は、保育者による介入の有無において、日本とポーランドの状況が異なる、という気づきを共有しました。また、Agnieszka氏は、日本の保育者は、子どもとの関わり方について養成段階で学ぶのか、それとも実践のなかで学ぶのか、という質問を投げかけました。
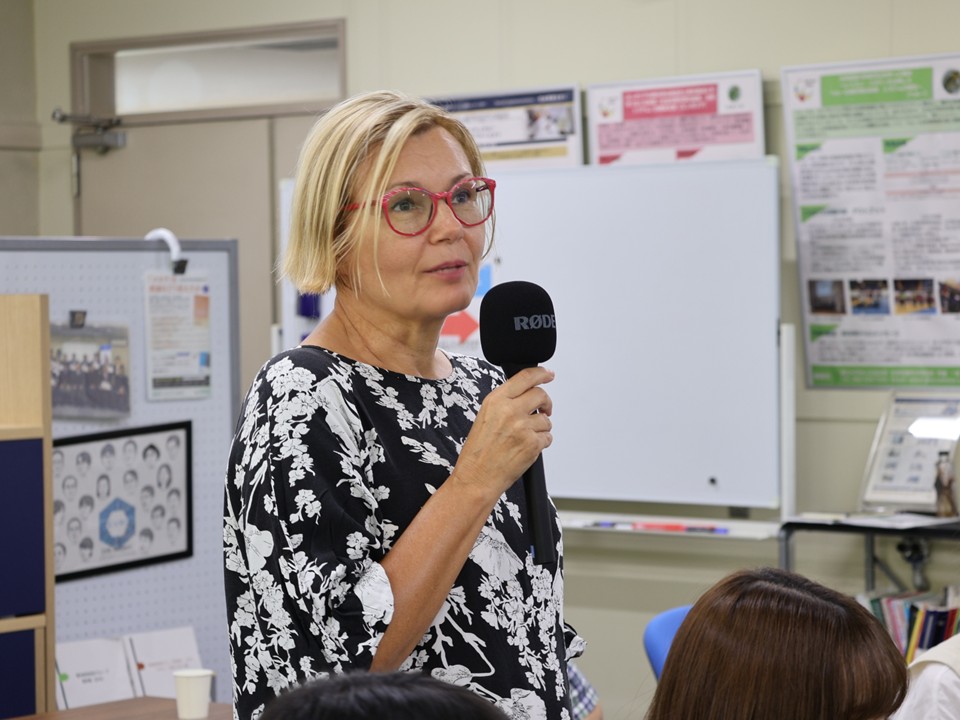
質問をするZuzanna氏
次に、Agnieszka Szplit氏(The Jan Kochanowski University of Kielce)、Zuzanna Zbróg氏(Jan Kochanowski University) 、Marcin Szplit氏(National Centre of Research and Development) より、“Preschool Education in Europe and Poland: Contemporary Perspectives and Challenges”と題した話題提供がなされました。ポーランドでは、3歳から6歳が幼児教育の時期とされています。そのなかでもとりわけ、6歳の時期が就学準備教育の時期として明確に位置づけられている点が特徴的な点として説明されました。また、ポーランドに限らず、ヨーロッパ全体の傾向として、子どもたちの能力を育むことを目指し、ワークシートのような教材が幼児教育において活用されていること、モンテッソーリ・メソッドやレッジョ・エミリア・アプローチなどを参考にした保育を行う園が存在したりしていることについて、事例を挙げながら説明がなされました。

Zuzanna氏(左)、Agnieszka氏(中)、Marcin氏(右)
また、質疑応答をとおして、①現在、ポーランドの幼児教育システムは子ども中心に移行しようと試みているところであり、そのために様々なメソッドが参照されていること、②ポーランドの幼児教育の現場では、保護者による教育に関する高いニーズに応えることが求められていること、が補足されました。
次に, Abraham Oluwatosin Gloryさん(広島大学・研究生)より、“What do Japanese Kindergartens Look Like From My Perspective as a Nigerian Kindergarten Teacher?”と題した話題提供がなされました。Abrahamさんは、ナイジェリアで保育者をしていた経験をふまえ、日本の幼稚園2園でのフィールドワークをとおして得た気づきを整理しました。まず、フィールドワークを行った2園は、①子どもたちの遊びが学びと同義である点、②保育のなかで、子どもたちの協調性と創造性が重視されている点、③屋外での遊びが保育に取り入れられている点、という3点の共通の特徴をもつということが整理されました。また、これらの特徴をもつ日本の幼児教育が、子どもたちの発達を促進していることをふまえ、ナイジェリアの幼児教育において、(1)早期の学問的学習に重点が置かれている点、(2)子どもを危険に晒すとして屋外遊びが制限されている点、が課題として指摘されました。最後に、理論的整理をふまえ、日本の幼児教育に見られる、バランスのとれたアプローチや自由さが、子どもの成長に重要な事柄であるとまとめました。

話題提供をするAbrahamさん
質疑応答では、フロアから「日本の幼児教育の課題点はどのような点にあると考えるか?」という質問がなされたほか、Agnieszka氏より、話題提供の内容に関連して、ポーランドの幼児教育の現状が情報共有されました。
次に、周偉傑さん(広島大学・大学院生)より、“A Pedagogical Art of Waiting”と題した話題提供がなされました。中国からの留学生である周さんは、日本の幼児教育の特徴である「見守るアプローチ」に着目し、日本・中国・フィンランドの三か国で調査を実施しました。三か国での調査結果の比較から、日本の「見守るアプローチ」においては、「待つこと」が最も究極的な目的とされていることが説明されました。日本の「見守るアプローチ」において、子どもたちの様子を「観察すること」はあくまで副次的な行為であり、「待つこと」によって子どもの様子の観察が促進されているのだ、として、「見守るアプローチ」の特徴がより詳細に示されました。
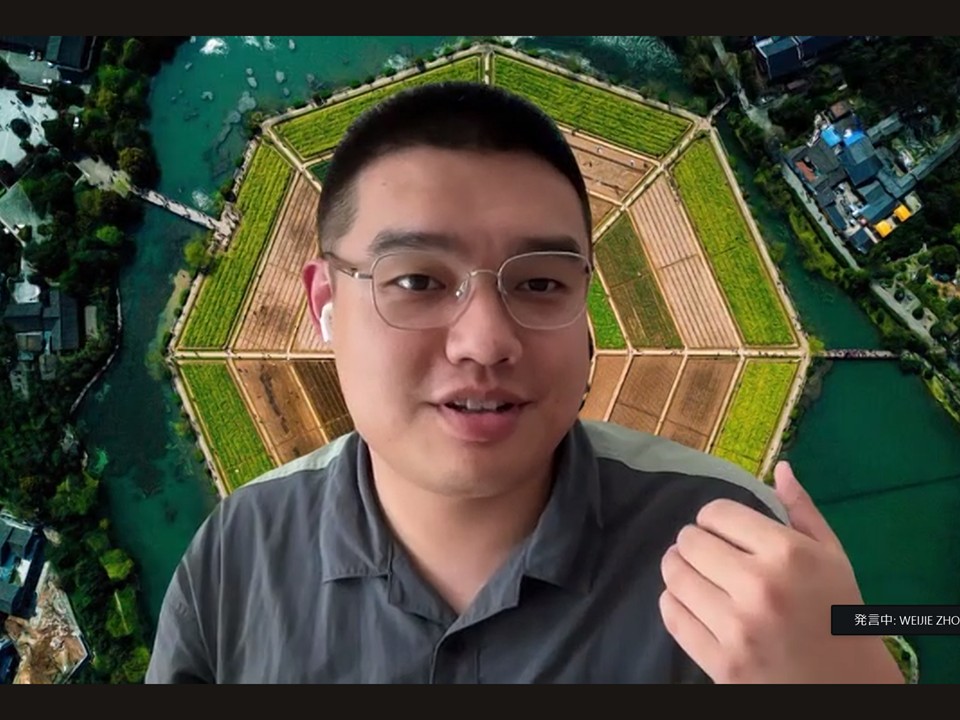
話題提供をする周さん
最後に、ここまでの話題提供を踏まえて総合討議が行われました。
登壇者の間では、「見守るアプローチ」を実現させている、日本の保育者の能力に関する議論が中心に交わされました。その後、フロアからの参加者も交えて、それぞれが前提としている社会文化的背景に意識を向けつつ、日本の幼児教育を受け止めることの重要性が共有されました。この点については、本セミナーでの交流の成果をふまえ、今後も議論を継続してまいります。

会場の様子
当日の様子はこちらをご覧ください。
広島大学教育ヴィジョン研究センター(EVRI) 事務室


 Home
Home