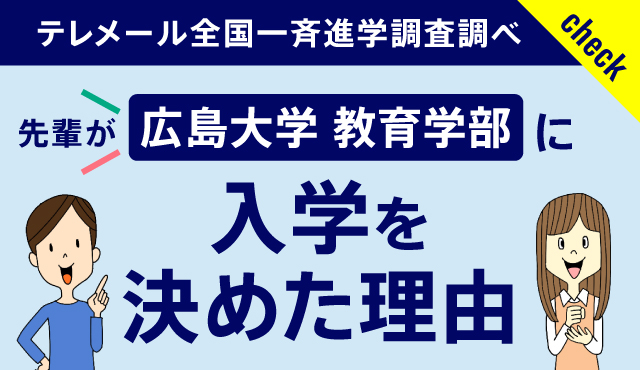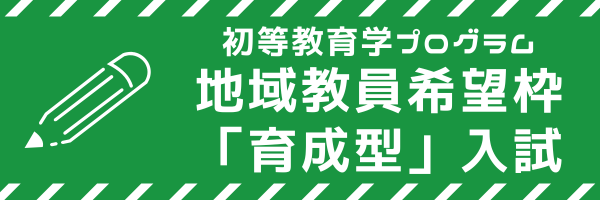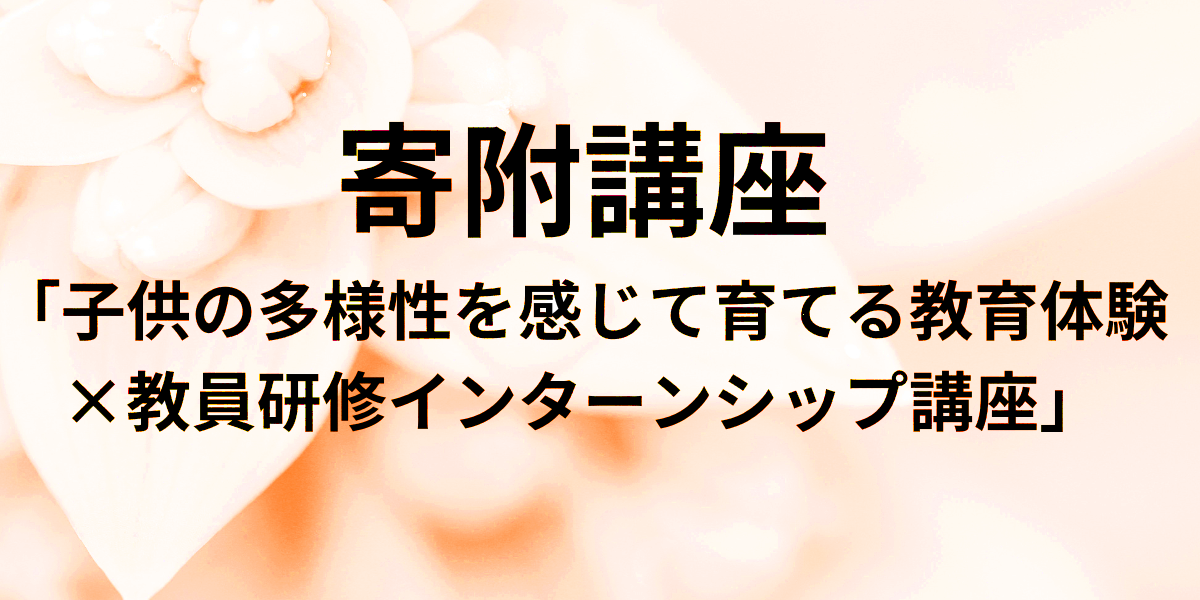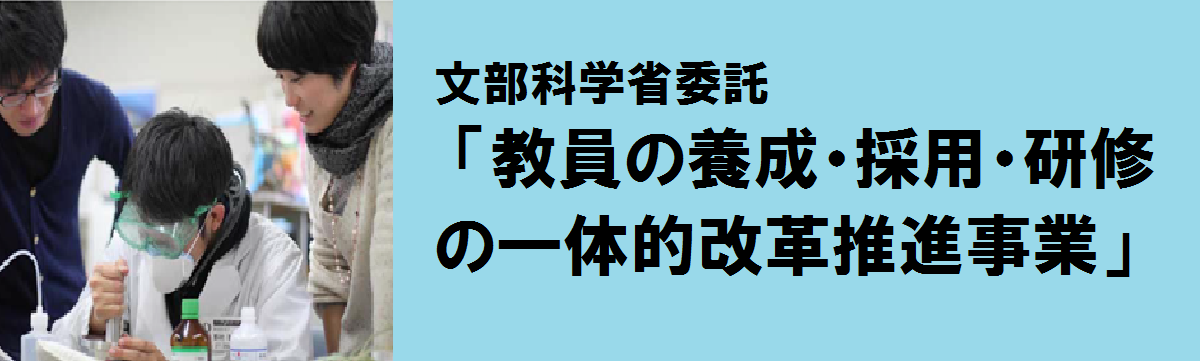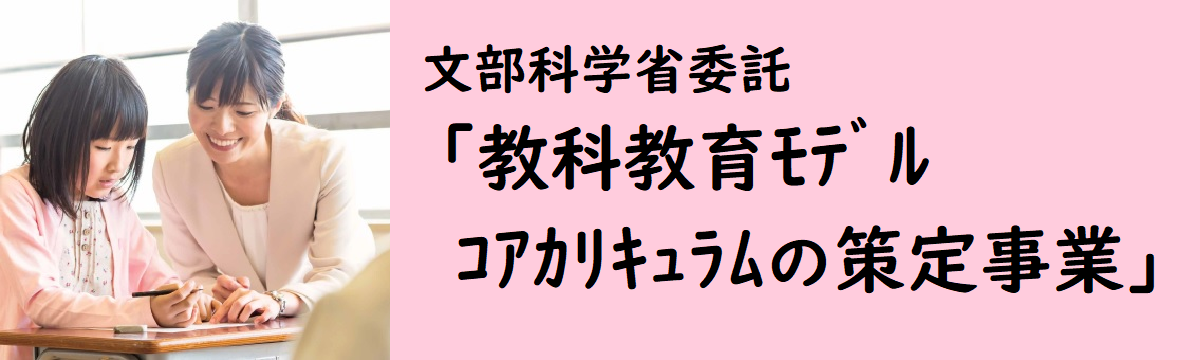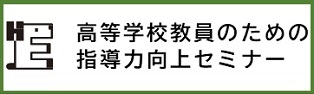E-Mail:evri-info(AT)hiroshima-u.ac.jp
※(AT)は@に置き換えてください

広島大学大学院人間社会科学研究科「教育ヴィジョン研究センター(EVRI)」は、2025年3月4日(火)に、定例オンラインセミナー講演会No.176「連続セミナー・授業研究を軸に教師教育を改革する・Learning Studyから考える授業研究―Yew Chung College of Early Childhood EducationのEric C. K. Cheng先生に学ぶ―」を開催しました。大学院生や学校教員を中心に、19名の皆様にご参加いただきました。
はじめに、司会の金鍾成准教授(広島大学)より、本セミナーの趣旨が説明されました。まず、EVRIの「連続セミナー・授業研究を軸に教師教育を改革する」という取り組みを通じて、日本の授業研究と海外のLesson Studyを比較し、互いに学び合う視点を深めてきたことが紹介されました。今回のセミナーでは、Learning Studyの専門家であるEric C. K. Cheng先生との交流を通して、Lesson StudyとLearning Study、そしてLearning Studyと授業研究を比較・検討し、実践者が授業や学習を研究する意義について理解を深めることが目的として共有されました。

趣旨を説明する金鍾成
次に、Eric C. K. Cheng先生による講演「Lesson Study vs Learning Study: A Comparative Analysis of Two Teacher Professional Development Approaches」が行われました。講演では、Learning Studyの基本的な考え方や, 香港における実践事例、さらに日本のLesson Studyとの関連が示され、特に「ヴァリエーション・セオリー(Variation Theory)」を中心に話が進められました。Learning Studyは香港で発展した授業研究のアプローチであり、日本のLesson Studyの影響を受けつつ、独自の理論的基盤としてヴァリエーション・セオリーを重視していることが説明されました。日本のLesson Studyでは、教員同士が授業を計画・実施・観察・評価・改善するPDCAサイクルを通じて授業の質を向上させています。一方、香港のLearning Studyは、このサイクルを継承しつつ、ヴァリエーション・セオリーを授業設計の中心的な指針として活用しています。Cheng先生は、ヴァリエーション・セオリーは学習者が重要な側面(クリティカル・アスペクト)を識別し、弁別することを支援する理論であり、授業では「何を変化させ, 何を変化させないか」を明確にすることが大切だと語りました。
授業デザインにおいては、まず学習対象(Object of Learning)を明確に設定する必要があると説明されました。例えば、四季の学習では、地球の軸の傾きや太陽光の当たり方がクリティカル・アスペクトとなります。また、授業ではコントラスト、分離、一般化、融合といった「パターン・オブ・ヴァリエーション」を活用し、学習者の深い理解を促します。例えば、分数の学習では、分母や分子を変化させて比較させることで、概念理解を深める方法が示されました。
Learning Studyでは、このようにヴァリエーション・セオリーを用いて授業設計・観察・評価・改善を進め、授業改善を繰り返し行うことが強調されました。これに対し、日本のLesson Studyでは授業改善や省察は重視されていますが、理論的枠組みとしてヴァリエーション・セオリーを位置づける例はまだ多くないとの説明もありました。

講演をするCheng先生
次に、川口広美准教授(広島大学)、吉田成章准教授(広島大学)による指定討論が行われました。
川口准教授は、Lesson Studyを行う中で論点が拡散し、子どもが知識をどのように獲得しているかを見逃す場合もあるが、Learning Studyではヴァリエーション・セオリーによって子どもが獲得する知識が明確になっていると語りました。そのうえで、二つの質問をされました。一つ目の質問は、「Learning Studyが好む知識の種類に偏りはあるか」というものでした。数学など教える内容が明確な場合には問題ないと思うが、社会科のように多様な考えを引き出す授業でもLearning Studyが有効なのか、という問いでした。これに対してCheng先生は、Learning Studyの限界をうまく指摘してくれたと言及し、Learning Studyは構造的な知識を教えることに特化していると答えました。しかし、社会科の場合でも、子どもが社会を理解するための枠組みのような構造的知識を学ぶ際には有効だと考えていると述べました。二つ目の質問は、「ヴァリエーション・セオリーで子どものすべての学びを読み取ることができるか」というものでした。これは、子どもの学びを読み取る視点には共感するものの、子どもの学びには構造的知識以外にも多様なものがあるのではないか、という前提での質問でした。これに対してCheng先生は、子どもの学びが構造的知識に限定されないという点には共感しつつ、近年は子どもの学びを拡張し、コンピテンシーや創造性などをヴァリエーション・セオリーで読み取る挑戦をしていると答えました。その際、セルフ・クエスチョニングや知識経営論なども補足的なアプローチとして活用していると補足しました。
吉田准教授からも二つの質問が出されました。一つ目の質問は、Learning Studyの世界的なネットワークに関するものでした。当日は香港を事例として講演が行われましたが、このアプローチがどのように広がっているのか、また実際に行われている共同研究プロジェクトはあるか、という質問でした。これに対してCheng先生は、Learning Studyの研究を、子どもの学びの研究、教師の学びの研究、ヴァリエーション・パターンの研究、教授学の研究という段階に分けて行っているが、現在は主に香港で進められていると答えました。そして、もちろん国際共同研究も歓迎すると述べました。二つ目の質問は、学校現場との関係づくりに関するものでした。日本では、草の根的に作られるコミュニティもあれば、学校を単位としたコミュニティもありますが、Cheng先生はどのようにして現場の先生方とつながっているのかと尋ねられました。これに対してCheng先生は、香港では政府から資金提供を受けた大学の研究チームが、現場の先生方にLearning Studyへの参加を促すため、トップダウン型になりやすいと説明しました。しかしながら、現場の先生方が自律的にLearning Studyに参加できるようにするために, 学校の管理職の理解を得ることや, プロジェクトに共感してくれる教師とともに成功事例を作り、それを広めることで多くの先生方に声をかけているとも答えました。主に、先生方の共同体を作るリーダーとして、時には省察を促すクリティカル・フレンドとして関わっていると語りました。

討論をする川口准教授

討論をする吉田准教授
次に、金准教授をファシリテーターとして、質疑応答が行われました。参加者の皆様からいただいたご意見・ご質問を大別すると、次の2点に集約することができます。
①ヴァリエーション・セオリーの理論的ルーツについて(心理学、認知科学、特定の人物など)
②ヴァリエーション・セオリーの適用(初等以外にも適用できるか)
これらの論点に関する議論を通して、教育心理学者であるフェントン先生が授業を観察するなかで見つけたバリエーションとその授業による子どもの学びのバリエーションをみとるなかでヴァリエーション・セオリーが登場したことが明らかになりました。また、ヴァリエーション・セオリーは構造的な知識を扱う授業であればどの発達段階でもどの教科でも適用可能であることが明らかになりました。
最後に、発表者および指定討論者がこれまでの講演と質疑応答をまとめるかたちで、セミナーが幕を閉じました。
今回のセミナーを通して、香港発のLearning Studyとヴァリエーション・セオリーについての理解を深めることができ、今後の国際共同研究の可能性も見え始めました。今後も日本の授業研究と海外の多様な実践・理論を比較・検討しながら、授業研究の意義を追求してまいります。
当日の様子はこちらをご覧ください。
広島大学教育ヴィジョン研究センター(EVRI) 事務室


 Home
Home