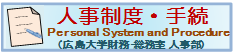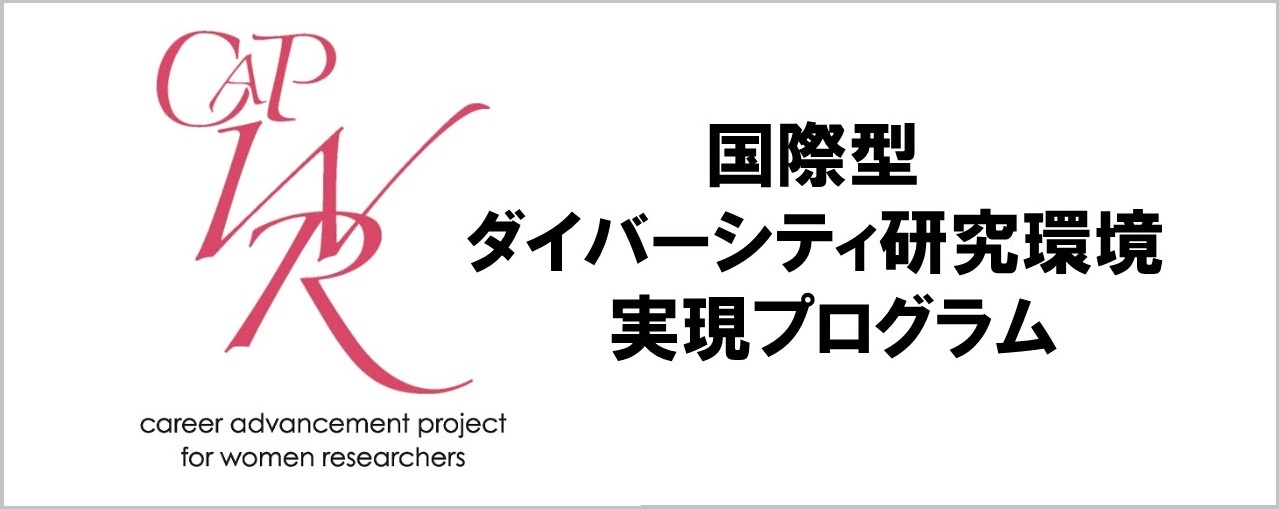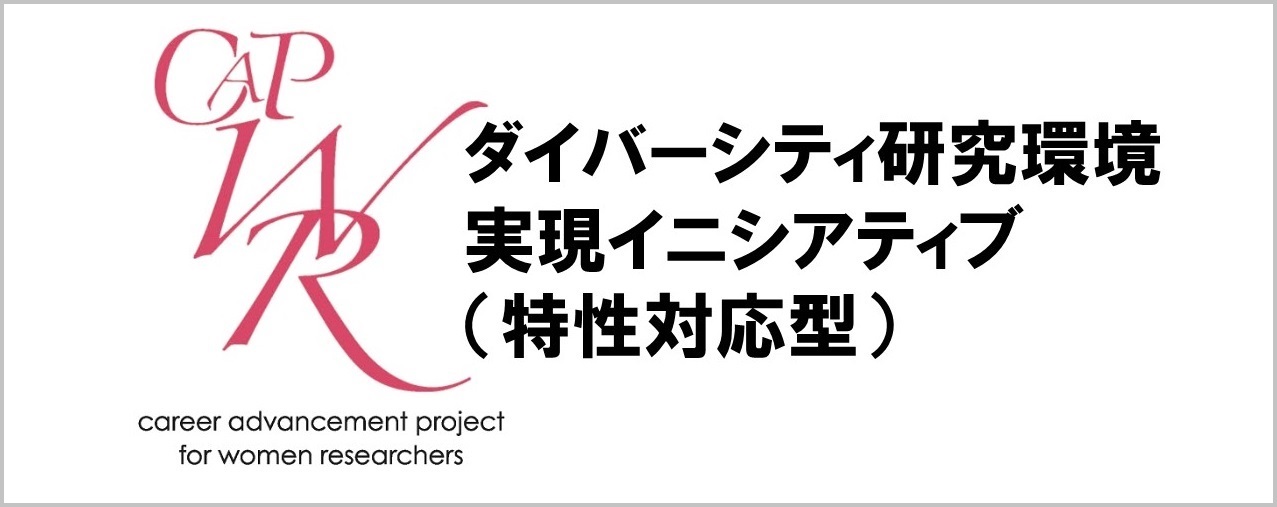大池 真知子 教授

基本情報
- 所属又は配属:ダイバーシティ&インクルージョン推進機構
- 職名:教授、ダイバーシティ&インクルージョン推進機構ダイバーシティ研究センター長
- 研究者ガイドブックのページはこちら
研究者になるまでの軌跡
小さいころから本を読むのが好きで、文学をもっと知りたいと思い大学院に進学しました。先輩から「研究者以外でもやっていける可能性が少しでもあるなら企業へ」と助言されましたが、スーツとストッキングで毎朝通勤する自分が想像できず、研究の道を選びました。
当時は返還不要の奨学金もあり、世はバブルで、役に立たない研究もやっていい雰囲気がありました。成果主義も今ほど強くなく、自由に探究できた時代でした。今なら違う選択をしたかもしれません。
研究の魅力
アフリカでHIV(エイズウイルス)とともに生きる人たちが自分の人生を物語る活動を研究してきました。最近は、被爆者や外国人実習生にもこの活動を広げています。
ダイバーシティ研究センターでは、少しでも生きやすい社会になるよう、各種プロジェクトに取り組んでいます。大きなプロジェクトで他者と協働するため、調整の難しさもありますが、深い理解が得られることも多いです。
若いときは、研究職に求道者の魅力を感じていましたが、最近は、専門知識やスキルを他者とあわせることで、より真に迫る結果を生み出すのに面白みを感じています。
ワークライフバランス
2002年、広島大学で講師をしていた頃に双子が生まれました。
子育ては予測不能なブラックボックスであり、どんな子が生まれ、どう育つか分かりません。そのため、仕事での挑戦がしづらくなります。私生活と仕事の両方でリスクを負うのが難しいからです。私も多くをあきらめました。
理想的には、仕事では同僚と、家庭ではパートナーとリスクを分担できればよいのですが、母親という立場から、子どもにまつわる責任をみずから一手に引き受けがちです。これは落とし穴です。子どもに「よそのお母さんみたいにして」と言われ、「ママはよそのお母さんの半分しかできてないけど、よそのお父さんの2倍以上はできてる」と返したこともあります。子どもにも多くをあきらめてもらいました。
今、2人の子どもが育ちあがり、ミッションを達成した満足感はありますが、機会も損失しました。仕事上、子育てしてよかったことは、人が生まれて育つまでの過程に深く関わって、凡人の私にも人間と社会への洞察が得られたことです。大変だけど面白い。やってみたいなら、ぜひ挑戦してみてください。
学生へのメッセージ
私は仕事も家庭もすべてをこなすスーパーウーマンではなく、「半人前×2分野=一人前」程度しかできていません。
現代社会では、いろいろな場に所属し、あちこちでさまざま要求されるでしょう。周りの人に助けてもらいながら、一部は「お付き合い程度」で乗り切りましょう。一人で全部はできないのだから。
(2025年7月掲載)
*所属・職名等は掲載時点のものです。

 Home
Home