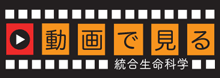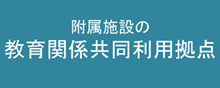染色体機能学研究グループ (広島大学自然科学研究支援開発センター 遺伝子実験部門)
(2018年8月1日)
数学の分野では、100年以上前から証明を待つ難問がいくつか知られているそうです。例えば、「ポアンカレ予想」など素人にはその予想の意味すら全く理解できないものですが、先年、ロシアの数学者グリゴリー・ペレルマンによって証明されたそうです。ポアンカレのような天才といわれる数学者はまず数式を思いつき、こんなに美しい数式が真理でないはずはないと考えるのだそうです。そして、後年、その数式は証明されて定理になるというわけです。生物学の場合、多くは新たに開発された解析装置によって革新的な発見がなされ、新たな生物観が誕生するとともに医療、産業に大いに貢献してきたといえるでしょう。例えば、 1950年代から多くの分野で活用された電子顕微鏡による細胞内小器官(ミトコンドリア、葉緑体、ゴルジ体など)の詳細な観察が、その後、それらの小器官にタンパクが選択的に輸送される経路や細胞外に分泌される経路の発見につながり、選択輸送されるタンパクに付くタグ(シグナル)配列の発見、そしてオートファジー経路につながっていったわけです。Randy Schekmanによる分泌関連遺伝子(sec)と大隅良典によるオートファジー関連遺伝子(apg)の解明は酵母を用いて行われたのですが、言うまでもなく、 Leland H. HartwellやPaul Nurseによる細胞分裂周期の研究とともに近年の細胞生物学における酵母遺伝学の輝かしい業績と言われています。
これらの革新的研究はひとえに研究者の独創的な才能がなせる業であるわけですが、一方では、ポアンカレ予想の証明は最新の数学理論などではなく古典的な熱力学の素養があったペレルマンだからこそ到達できたと言われています。同様に、細胞生物学においても先人達が作り上げた古典的解析法を駆使しながらも、独自の研究分野を展開してきたことが画期的業績に結び付いたことは上述のごとくです。
生物学にも世代を超えて受け継がれてきた研究課題がいくつかあります。例えば、動物は生長点が体の内側にあるため外側に向かって大きくなりますが、植物は反対に生長点が体の外側にあり細胞を内側に供給しながら成長します。真核単細胞生物が誕生したのち、植物は光合成細菌と共生することで動物系列と分岐して進化したと言われていますが、多細胞生物が生まれたとき、なぜ生長点が動物と異なる道を選んだのでしょうか?動物は生長点を体の内側に持つことで常に“癌”のリスクに曝されていますが、植物は癌化した部位を体から切り離すことで樹齢数千年の大木になることも可能なのかもしれません。もう一つ挙げれば、大きさ(Scaling)の問題です。もちろん、クジラはヒトに比べて千倍以上の細胞数で出来ていますから、受精卵から成体になるまでの間に細胞分裂回数が人に比べて10回程度(210=1024)多いわけですが、体の大きさは脳の大きさや寿命に比例することが知られていますし、単細胞生物における細胞分裂の研究領域を超えた問題のようです。また、細胞の大きさも千差万別で種や組織によって100倍程度の差があります。特に、染色体のDNA量に比例して細胞が大きくなるのは、細菌から動物・植物に至るまで普遍的な現象であることが知られています。これらの課題は、多くの遺伝子群がお互いに調節し合う大きなシステムとして捉えることが必要なのかもしれません。
私もそうでしたが、若いうちはすぐそこにある成果を手に入れたくて、むやみに最新の研究分野に飛び込み、大変な努力をしながらも後塵を拝することが多いのかもしれません。黙想して開眼すれば面白い研究対象・課題がいくつも転がっているのかもしれませんが、それに気づかないのが凡人の所以なのでしょう。
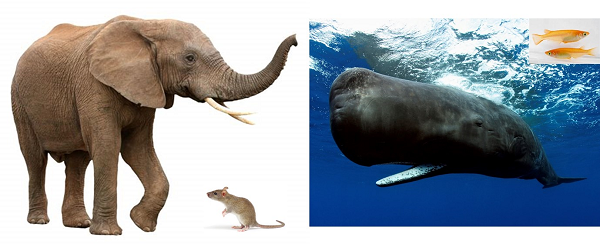

 Home
Home