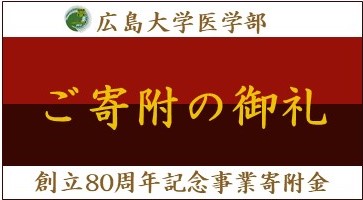【研究室主要論文】
・Low-Kilovoltage, High-Tube-Current MDCT of Liver in Thin Adults: Pilot Study Evaluating Radiation Dose, Image Quality, and Display Settings.Nakaura T, AwaiK, Oda S, Funama Y, Harada K, Uemura S, Yamashita Y,AJR,196(6)1332-1338,2011, American Journal of Roentgenology, 196巻, 6号, pp. 1332-1338, 20110601
・ A new technique for noise reduction at coronary CT angiography with multi-phase data-averaging and non-rigid image registration, EUROPEAN RADIOLOGY, 25巻, 1号, pp. 41-48, 201501
・T Categorization of Urothelial Carcinomas of the Ureter With CT: Preliminary Study of New Diagnostic Criteria Proposed for Differentiating T2 or Lower From T3 or Higher, AMERICAN JOURNAL OF ROENTGENOLOGY, 204巻, 4号, pp. 792-797, 201504
【教育内容】
画像診断学(放射線診断学)は、現代医療を支える重要な領域の一つです。当科では、医学部学生、大学院生、研修医等に、CT、MRI、PET等の核医学診断、デジタルラジオグラフィー等の基礎的および応用的な画像解析法、読影法を教育しているほか、画像誘導下で行う低侵襲治療(インターベンショナルラジオロジー:IVR)についても教育を行っています。
医学部学生の臨床実習では、当研究室で作成したデジタル教材を使用して学生自身がインターラクティブに画像解剖や基本疾患の読影を学べるようにしているほか、IVRの基礎的手技についても実技を通して学ぶことができます。
また研修医に対しては、指導医のもと画像診断報告書の作成をしながら、読影の基本、鑑別方法、高度な画像解析等が学べるようしています。
また、将来、放射線専門医を目指す人には、より高度な画像診断法、IVRの手技を教育しているほか、合理的で低侵襲な画像検査法あるいはIVR治療の立案法、画像検査に関する安全管理(造影剤のアレルギー・腎障害への対応など)についても教育をしています。
【研究内容】
画像診断学の領域では、320列CT・3テスラMRI・PET-CTなどを駆使した多彩な臨床研究を行っています。
また、画像工学的な見地からCT・MRIを中心とする新たな画像診断法の開発、画像診断における低線量X線被曝の生物学的影響の研究、等も行っています。
IVRでは、肝癌に対するIVRの新たな治療法の開発、門脈圧亢進症のIVR治療、IVR-CTシステムを用いた非血管系IVRの確立等の研究を中心に行っています。
本研究室は、広島大学原爆放射線医科学研究所、イリノイ大学、広島市立大学、熊本大学、東芝メディカルシステムズ、日立製作所等の国内外の大学や企業の研究所とも積極的に共同研究を展開しています。
具体的には以下の研究プロジェクトがあります。
・逐次近似画像再構成による超低線量胸部CTの肺がん検診への応用
・Massive training artificial neural network (MTANN)を用いた超低線量胸部CT画像の修復
・低線量肺がんCT検診に対するコンピュータ支援診断の応用
・心筋perfusion CTの解析手法の開発とその臨床応用
・心臓ダイナミックCT画像を用いた冠血流予備量比FFRの推定
・Dual Energy CTを用いた心筋遅延造影の描出能の検討
・CTによる冠動脈石灰化スコアリングにおける逐次近似画像再構成を使用した被ばく低減
・頸部ステント症例に対する逐次近似画像再構成の応用
・肝臓perfusion CTの解析ソフトウェアの開発.
・肝腫瘍の治療効果の判定に関する肝臓perfusion CTの応用
・Dual Energy CTによる多血性肝腫瘍検出に関する基礎的研究
・Dual-Energy CT による新たなCT Urography撮像法の開発
・CTによる尿管癌のステージングを目的としたヒストグラム解析
・Dual Energy CTによる脳腫瘍の診断に関する研究
・MRIにおけるTime-Slip法による唾液腺機能の定量評価
・新生児ガラクトース血症における門脈系の超音波等による形態解析
・逐次近似画像再構成による小児CT検査における被ばく低減
・CT・MRIによる骨髄腫、骨粗しょう症等の骨量・骨構造の定量解析
・肝癌に対するインターベンショナルラジオロジーに関する研究
・門脈圧亢進症に対する低侵襲治療の関する研究
・PNA-FISH法およびγH2AX定量によるCTの被ばくにおけるDNA損傷の解析
・CTにおける撮像管電圧のDNA損傷に対する影響
・低線量肺がんCT検診におけるX線被ばくのDNA損傷に対する影響の解析
【写真説明】画像解析室(読影室)で業務中のスタッフの様子

 Home
Home