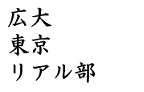<お問い合わせ先>
広島大学東京オフィス
TEL:03-6206-7390
E-Mail:tokyo(AT)office.hiroshima-u.ac.jp ※(AT)は半角@に変換して送信してください。
訪問日
2018年5月22日
センパイ
喜安浩平(キヤス コウヘイ)氏
1997年広島大学学校教育学部(現・教育学部)中学校教員養成課程(美術)卒業。1998年劇団『ナイロン100℃』の出演者オーディションに合格、1999年末に劇団員として所属。2000年に旗揚げした自身の劇団『ブルドッキングヘッドロック』では、脚本・演出として活動。声優としても、『はじめの一歩』(主人公・幕之内一歩役)、『テニスの王子様』(海堂薫役)など、多数作品の主要キャストを担当。近年では、テレビドラマ・映画の脚本での活躍も著しく、映画『桐島、部活辞めるってよ』では日本アカデミー賞優秀脚本賞を受賞するなど、受賞歴もある。
訪問記

喜安浩平氏(ナイロン100℃・ブルドッキングヘッドロック所属)
喜安「大学時代、演劇が職業になるとは思ってなくて、4年生になるまで自分は先生になるんだろうなとしか思ってなかったんです。」
喜安さんは広島大学時代、学校教育学部(現・教育学部)中学校教員養成課程(美術)に在籍し、同時に演劇サークル『劇団A.P.T.』に所属していました。演劇を仕事にするきっかけとなったのは、大学4年生の時。 中学校の教育実習で感じた、ある『違和感』にありました。
喜安「生徒の多くは美術の授業を、息抜きのつもりで来てるんですね。だから、受け持った授業もよく盛り上がって、教頭先生に呼び出されて絶賛されたこともあるくらい、順調だったんです。でも、同時に人気取りに走っている自分がいることもわかって。
やればやるほど『ウケようとしている』なって。それは教師が目的にすべきことじゃないと思えてきた。
そこからパーンと教師という目標と距離が空いてしまったんです。この領域に自分は踏み込んじゃいけないんだ、と思い始め、教師になることを辞めました。
でもその時点で、他の選択肢はなかったんです。
親には教師を目指すことを辞めたとは伝えられませんでした。答えが無いことを親に知らせても、より不安にさせるだけだと思ったというのもあります。
でも、どんどんリミットが近づいて、親にもバレるわけです。そうなった時、残ったものが演劇しかなかった。
演劇しか強がれるものがなかったんですね。
結局、卒業する間際に演劇をすることを親に伝えて、一時の実家暮らしを経て、一度上京することにしました。
親とは喧嘩もしなかったですね。半ば諦めていたんでしょう。どうせすぐ帰ってくるだろう、と思われてもいたのかもしれません。私自身もその確率は非常に高いと思ってました。
でも、ナイロン100℃の出演者オーディションを受けたら合格してしまったんです。それから4,5年は実家には帰るきっかけがありませんでした。」

広島大学を卒業後、ナイロン100℃に団員として加入。さらに2000年『はじめの一歩』のオーディションに見事合格し、主人公・幕之内一歩役を射止めました。喜安さんは、謙遜しながら当時を振り返りました。
喜安「主人公の年齢が15歳の設定で、私が受けさせていただく前にもオーディションをやられていたそうなんですが、その時は適当な方が見つからなかったようで、だから声優未経験というところまで的を広げて、俳優を探されていたようなんです。
オーディション合格後にうかがったのは、『私が、最終審査に残ったメンツの中で、一番下手だった。』ということです。
『はじめの一歩』は、いじめられっ子がやがては日本チャンピオンにまで成長する物語ですから、最初から上手では面白くない、というのが制作陣の意向だったらしいんです。
だから、自分で言うのもなんですが、下手でよかったなって。大抜擢ですから。誰だよって存在だったと思いますけど。
その時のプロデューサーさんが、アニメ界の生き字引のような方で、手塚治虫さんとお仕事なさっていたような、経験と、たくさんの実績をお持ちの方だったんです。
その方に面と向かって聞くほどの勇気はなかったですけど、きっと、どこの者とも知れない若者を、表現者にしていくだけのイメージや、メソッドをお持ちだったのではないかと思います。
ある種、博打ですけど、でも、夢だし、ロマンがあったんだと思うんです。そこに、たまたま声質の合う私がいた、ということですね。
これが作品が違ったなら、私なんて箸にも棒にも引っかからなかったと思います。
多分、私のパラメータの中で一番高いところがあるとすれば『運がいい』というところです。
東京で俳優をやらせていただいていると、オーディションを受ける機会も沢山いただけるのですが、私は打率で言うとかなり低い方だと思います。
ただ、たまぁに場外ホームランがある、という感じで。
東京に出てきて、勢いだけで受けたナイロン100℃という劇団の出演者オーディションに合格して、翌年、声優未経験のまま『はじめの一歩』のオーディションを受けて合格して、最近では、映画『桐島、部活辞めるってよ』で、初めて長編映画の脚本を書かせていただいたらたまたま日本アカデミー賞の優秀脚本賞をいただいて。
そういう場外ホームランを、なぜかときどき打ってしまうんです…、という感じです。」
自身のここまでの実績を『運の良さ』と謙遜する喜安さん。ただ、もちろん運ばかりでは継続して活躍することはできません。喜安さんの仕事論にも繋がるお話を伺いました。
喜安「声優さんは、直接オファーが来る場合もありますが、多くの場合は、どれだけキャリアのある方でもオーディションで選考されるんですね。
そういう意味で、声優業界って公正だなと思います。日々研鑚が維持できる人じゃないと役はもらえないわけですから。
さらに、声質によってメインの役に向いていたり、脇役に向いていたり、それは舞台俳優でも同じだと思いますが、役割があるんです。そんな、それぞれの個性や能力を理解して、キープする努力が大事ですね。
私は、いろんな表現の媒体に顔を出させていただいているのですが、オーディションを開催する側に立たせていただく場合もあって、何十人もの声優さんが同じ役のセリフを言うところを拝聴するわけなんですが、やはりそこには明確な力量の違いや、優劣が出てきます。残酷なくらい。ご自身を正確に理解して、相応の表現をする。当たり前のことがどれだけ大変かわかります。
私は残念ながら、『上手い』声優さんにはなれていないと思います。そのシーン、その画に、的確に、例えば汚い音ですら的確に汚い音を出して当てる技術を持たれている方はたくさんいらっしゃるんですが、私はそういう方々には到底及びません。
私の場合は、脚本家もやっておりますので、なるべくテキストを俯瞰して、自分なりの解釈・自分だからこその可能性を提示できるよう、努力をしています。全然見当違いっていう場合もありますけど(笑)」

ここで直球の質問。『モテましたか?』
喜安「モテなかったですね。私は、いつでも自分は傍観者だった、という記憶が強く残っています。例えば、好きな女の子がいて、その女の子が私の友人と付き合い始めたことがあったんです。
私の方はその女の子に告白したこともありませんでしたし、だから当然フラれたこともありませんし、友人から『あの子と付き合おうと思うんだ』という相談もなかった。
おかげで、『自分の好きな子が、友人と付き合うことになった』出来事に対して、私自身は観客席に座っているような気持ちになったんです。
そういう、観客席に座っているような、傍観者側だったような、そういう記憶が多く、強く残っていますね。
当時は『俺は観客席に…』なんて思ってもいませんでしたが、のちに脚本家になって、そういう経験を、もう一人のさらに俯瞰した私が『君、当事者じゃなかったよ』と言ってあげることで、どこかロジカルに、消化したりおかしむことができるようになったんです。
すっごい派手なフラれ方をしたとか沢山借金をしたとか、そういう大きな浮き沈みは無いですけど、そういう小さな、誰にでもありそうな傷を、執拗に覚えているタイプです。
『桐島~』は、登場人物に対してある意味冷徹な、平均的な目線で、誰にも肩入れせずに描くことを意図した話だと思っているんですが。
クライマックスは、監督が、神木隆之介君の役に寄り添うためにゾンビのシーンを挿入することにされたんですけど、そこに至るまでの、冷徹な、起きている出来事をただ見せるような描き方は、私自身の『学校』というものへの見方が影響しているんだと思います。
『桐島~』の登場人物で言ったら私は、休み時間に机に突っ伏して、名前も呼ばれなかったような奴だと思います(笑)
ただ、冷たいやつなのかな?とひどく不安になる時があります。
目の前で女性が泣いているのに、別の視点でその女性を見ているような。ああ、このタイミングでこう泣くのか。という。そういう意味では冷血漢なのかもしれないです(笑)」

芸能の仕事に身を置く喜安さん。芸能にもさまざまな『芸』が存在します。そんな喜安さんにとって『学びの多かったジャンル』について伺いました。
喜安「学びが多かったジャンルですか…。まず広島大学で絵画を学び、その途中で演劇に出会ったんですが、
私は、なんでしょう、こう…、冷血漢だけど寂しがり屋なんですね(笑)
一人で何かを制作して、大勢の人に見てもらうのが絵画ですが、僕は作る段階からいろんな味方がいて欲しいタイプだったんです。だから、集団を要する演劇は、性に合ったのかもしれません。
でも、演劇って、映像より自分の発想がまかり通りやすいというか、作家の方は稽古の中で納得いくまで俳優に意図を伝え、イメージが実現できるよう追い込んで行けますし、ヨーイハイって言えばなぜか俳優さんは動き出す。逆に俳優さんの方も、自分のやりたいことを試す機会が稽古本番と、ずうっとある。最悪、本番中に全てのセリフを違うようにしゃべったとしても、演出家には止められない。『何やってんだよ!』って思うしかないんです。そういう、発想がまかり通ってしまう時間があるということを、お互いが理解しあい、信用しあって、演劇は成り立つんです。そこが居心地の良さだと思います。
ところが映像の現場では、お互いの信用が一つ一つ形になっていかないと次に進まないんですね。演劇は脚本が無くてもとりあえず俳優を集めて稽古をすることができますけど、映像では、脚本ができなければその先には絶対に行けない。だから私にとっては、演劇の居心地の良さに甘えていた部分を、戒められるような出会いだったんです。
演劇だと、最終的に『俺が何とかするよ』って言えたけど、映画では、『あなたはあなたの仕事を確実にやって、次の人に渡してください』って言われるわけです。
でも、そこから、集団で創作することに対してよりポジティブになれたというか。例えば、脚本を書いている時に、どうにも分からない部分がある状態で打ち合わせに出なければならない時があるんですが、昔なら分からない部分も『答えです』みたいな顔をして、あとで自分で何とかしようと不遜な考えを持っていたんですけど、今は、分からない部分を分からないものとしてちゃんと人と共有できるようになりました。
すると今度は演劇に戻ってきた時に、まわりの人の能力や個性への頼りがいが実感できるようになったんですね。こんなにわかってくれるんだ、とか。
良い順番で色んなジャンルに出会えたな、と思います。」

多岐にわたる仕事の中で、2000年の旗揚げから現在まで、精力的に活動している劇団『ブルドッキングヘッドロック』の脚本・演出、そして主宰としての活動は喜安さんのライフワークになっています。2008年、喜安さんが32歳の時、ブルドッキングヘッドロックの主宰を一度、他の団員に譲ったことがありました。(2015年からは再び喜安さんが主宰に戻る。)
喜安「かつて、私は、主宰として劇団をプロデュースする仕事と、劇作家の仕事を兼務していた時期があったんですが、おそらく、もともとその二つを使い分けるのが得意ではなかったというか、無理だったんですね。
そこから主宰を引き受けてくれる仲間が現れて、劇作家としてのみ劇団に残ることになったんですが、任務を一つ手放すことで言い訳を一つ無くしたわけですね。
『無理なことをやってるから無理なんだ』と言えたところを、『無理なことはこっちで引き受けるから、やれることをしっかりやってくれ』と周りに言ってもらえて、作家としての活動を後押ししてもらえるようになったんです。そりゃあ言い訳はできません。
それから舞い込んできた作家の仕事はたくさんあると思います。
主宰交代後の初めての劇団公演が、『役に立たないオマエ』という高校生の美術部員を主題にした作品だったのですが、それを『桐島~』を一緒に作った監督の吉田大八さんが観てくださっていて、それで、監督のところに『桐島~』の映画化のお話が来た時に、『高校生を描くなら、喜安くんが面白いものを描きますよ』と推薦してくださって、私に脚本のお話が来た、という経緯があるんです。
32歳で、主宰を辞めると宣言をすることで、一つ荷物を下ろし、自分の立場を明確にした。そのことで、逆に可能性を感じてくださった方もいらっしゃったんだなと思います。」

喜安さんが大学卒業後、ナイロン100℃の出演者オーディションに合格(のちに団員として加入)したのが24歳の時でした。今年で43歳となる喜安さんは、仕事で年の離れたワカモノと接する機会が増えてきたそうです。
喜安「40代になって、ブルドッキングヘッドロックにも20代の団員が加入し、他の仕事でも10代20代の方に出会う機会が増えましたが、若者に対する明確な攻略法は、きっとありません。
昔だったら無条件に、『起立、気を付け、礼!』から始めていたものも、今では『起立、気を付け、礼、だけが選択肢じゃないよねえ』っていう教育になったからかも分かりませんが、多様性というか、それぞれに個別のナニかがあるから、一人一人とコツコツ対話するしかないな、と思っています。
凄く時間がかかるし、面倒だなと思うんですけど(笑)。一律に『こうしようよ』と言った時の受け取られ方が、こんなにも違うんだ、ということに薄い絶望を感じています(笑)
でも、おまえら全員アンテナを俺に合わせろ!と言ったってキリが無いし、合わないとイライラするので、私の可能な範囲で、その人それぞれに適した伝え方で、趣旨を伝えるようにしています。
あと、こっちのリクエストや問いかけに対して、相手からなんらかのコメントがあったとして、でもその後にアクションがなかった場合は、そこで見限ります。『動かないあなたを引っ張って行く暇があったら、私は他の人とあなたが手の届かない彼方まで行きます。』と思います。
アクションを起こして、その結果失敗するのは全然いいんです。でも、『がんばります』って言われても、言われただけでは嘘か本当か分かりません。漠然と熱意だけ伝えられた時は、『具体的には?』って言います。嫌がられますけど(笑)
悩んでいるよりは、やった方がいいと思います。やって、拾う人が拾ってくれたら成立するんです。アクションを起こせない人は、ご自分の中で乱反射しているんでしょうね。あーでもないこーでもないと。で、だんだん反射するエネルギーもなくなって、対象に対するモチベーションが落ちてくる。今だ!という時にバーンと出したら、それだけで気持ちいいはずなのに。何かが叶わないとしたら、それは自身の能力の有無ではなく、一歩でもそっちに近づいてみたか?ということを疑った方がいいでしょう。
あと、上手くいっていないことに対してどういう決断をするのかっていうのが大事ですが、そういう時の判断には経験も必要だし、センスもいると思うんです。
私の場合は、ナイロン100℃に入団した当初ボッコボコに怒られまくって、夜道を、自転車漕ぎながら、24,5歳にもなって泣いて帰ったりして、翌日、稽古前に神社に行って『今日は上手くいきますように』ってお参りなんてしちゃってました。
でも、そうじゃないだろって。自分が何に悲しがって涙を流しているのか。そんなことすら、その当時の私は分かってなかったんです。怒られたことがただ悔しくて泣いていただけだった。自分の表現を吟味する余裕などなかったんです。『怒られた』という現象にショックを受けて、なら怒られないようにしようと無駄な方向に努めていた。それで芝居が良くなるわけがない。先輩からしたら、泣かすつもりなんてない、『もっと来い』と言ってただけなんです。
私は、その辺りも運が良かったのか、周りの方が救ってくださったので、なんとか気付きながら年を重ねることができました。
若い人には、本人が具体的に気付けるようなフォローをしてあげたいですし、それもなるべく個別にやってあげたい。それくらいしかないです。」
演劇・芝居の世界で『働く』中で、喜安さんが響いた人からの教え、についてお伺いしました。
喜安「あの時のあれ、というよりは、その人の居方や振る舞いの方が響くことが多いように思います。
その中でも、未だに自分で実行できないな、と思うこともあります。
『はじめの一歩』の鴨川会長(一歩のコーチ)役の内海賢二さん(Dr,スランプアラレちゃん・せんべい役、ドラゴンボール・神龍役、北斗の拳・ラオウ役など)という、日本のアニメーションをずっと支えてこられた方がいらっしゃって、ものすごく親分肌な方だったんです。
その内海さんが、現場で唯一人キャリアの皆無な私に、毎週、収録の朝、『喜安、腹減ってるだろ』とおっしゃって、ハンバーガーを差し入れてくださるんです。
実は収録の時は、特にボクシングの試合のシーンなんて、本当に身体が持たないくらい疲弊するから、朝食は食べてから収録に来ていたんですけど、『金もないし、若いから腹減ってるだろ』と、ハンバーガーを買ってきて、僕の分だけ置いていてくださるんです。量でも金額でもない、その思いをいただいたら、誰だって頑張れますよ。そんな、気持ちを動かす差し入れだったんです。
後々、内海さんが私の居ないところで『あいつ、いいよな』って言ってくださっていたらしい、ということを伺ったんです。
でも直接言われたことはなくて。ハンバーガーを渡してくださることで、『お前のことを気にしてるぞ』という思いを、『おまえがやらないと成り立たないんだ』ということを、もちろん企画の趣旨もご理解された上で、伝えてくださっていた。若い俳優も戦える、そういうムードを作って下さっていたんです。
それが僕にはまだできません。その行動って、現場に来る時に、自分のことだけじゃなくて、『喜安がいる』ということまで考えてくださっているからできることじゃないですか。
その余裕というか、理解の深さというか、人への気配りなど、すべてひっくるめて、居方の素晴らしい方だったと思います。誰もができる事ではない、というのは、その後、いろいろんな現場を経験して、さらに感じるようになりました。みんながみんな、内海さんみたいにできるわけではないんだな、と。
あと、私が俳優で所属している劇団・ナイロン100℃主宰のケラリーノ・サンドロヴィッチが、我々劇団員と座談会をする企画をやった時に、話の流れでサラッと『俺はやりたいことしかやってないからね』とこぼしたんです。サラッと。
その一言は、自分にとって、モノづくりの指針になっています。モノづくりの現場の質は、才能だけじゃない、その人の居方考え方が決めるものなんだな、って。」
喜安さんは我々の質問に対して、真摯に一つ一つ丁寧に語ってくださいました。そして、喜安さんの人としての『芯』を垣間見たようでした。この記事をご覧になっている皆さん、特に広大生の方々、若手のOB・OGの方々にとって、厳しい現実に目を向けつつも、皆さんに勇気を与えるエールとして、喜安さんの言葉を噛みしめて頂けると幸いです。

(左から)北池(東京オフィス)、千野信浩氏(関東ネットワーク代表、総合科学部1986年卒)、川村(東京オフィス研修生)、三村友理氏(文学部2012年卒)、喜安浩平氏、池邊友大氏(総合科学部2018年卒)、長谷川(東京オフィス所長)
インタビュー感想
○池邊友大氏
喜安さんが運がよかったと何度もおっしゃっていたことがとても印象的でした。
でも、それは、目の前のことを全力で行った結果が引き寄せたものではないかと考えています。その場その場で全力をつくしていれば、大きな何かも大きな次につながる感じました。
僕も、人との関わりの中でこれから多くの仕事をこなしていくと思いますが、目の前の人とお仕事に全力を尽くすという気概は絶対に忘れません。
○三村友理氏
これまで私の中で、「クリエイティブの一線に立てるのは、誰よりも自分のオリジナリティを出し切れた者だ」という勝手なイメージがありました。
もちろんそういった面もあると思いますが、喜安さんのお話を聞き、完全に我を通すのではなく「自分」はこの作品にとって、またこのチーム(仕事仲間)にとって、どのような存在であるべきかを俯瞰して考えられることが大切で、だからこそ喜安さんは作品と上手くシンクロし、何倍も魅力的にできたのだろうと感じました。
お話しぶりから、その俯瞰する視点にはとてつもない敬意が込められているのだと思います。
作品やチームメイトへの敬意があるからこそ、ご自分は努力を惜しまず責任をもって現場に臨む。
素直にかっこいいなぁと思いました。
それは演劇や映画などに限らず、どんな仕事、あらゆる立場でもいえることで、自分にも、社会の中でやるべきことはたくさんあるし、果たすべき責任もたくさんあるということに改めて気づけました。
以前、私が劇団A.P.T. (※1)の最終公演を観に行った際、受付に、喜安さんをはじめ劇団A.P.T.の先輩方から贈られた立派な花かごが飾られていました。
その最終公演の作・演出をしたのが私の友達だったこともあり、大変感激し感謝していたということをお伝えすると、喜安さんは「自分は、いろいろな先輩に見出してもらい育ててもらったからこそ、後輩にもそのバトンをパスしたい」と話してくださいました。
全く知らない、何代も後の後輩に思いを馳せて、アクションを起こし、エールを送る。
表現者として尊敬するのはもちろんですが、こんなに後輩思いで責任感のある先輩がおられるということ、本当に有難いことなのだと思いました。
改めて、私たちは一人で生きているではなく、責任ある先輩方の脈々とつながるバトンパスの間に生きているのだということを感じました。
【(※1)喜安浩平さんが大学時代に所属していた広島大学の演劇サークル、2014年に最終公演ののち活動休止】
○研修生(川村)
私が広大生の時代に、演劇サークル『広島大学演劇団』に所属してました。喜安浩平さんのお名前は『広大にいた演劇の大先輩』として、その当時から存じ上げておりました。
6年越しにお会いした先輩の姿は、真摯に、冷静に、演劇・芝居の世界の仕事に取り組む、1人の社会人でした。
お話を聞きながら僕は特に、喜安さんの仕事におけるシビアさを感じました。
劇団主宰として時に団員を見放すのは、一見冷たくみられるかもしれません。
でもそれは、喜安さん自身が若手の時に、果てしない試行錯誤を繰り返し、先輩の背中を見て、沢山の教えを真摯に吸収し、行きついたもの。
常に自分とその周りを傍観して、冷静に考えて対応していくからこそ行きつく境地なのでしょう。
芝居の、一つ一つのプロジェクトを完遂させるために、喜安さんは内海さんとはまた違う、自分のやり方で、自分の背中を後輩に見せている、と感じました。
ざっくばらんな、色んな方向からの質問にも、真摯に受け答えして頂きました。
素敵な先輩の、その背中を見られたことを、嬉しく思います。

 Home
Home