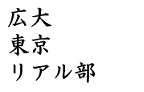<お問い合わせ先>
広島大学東京オフィス
TEL:03-6206-7390
E-Mail:tokyo(AT)office.hiroshima-u.ac.jp ※(AT)は半角@に変換して送信してください。
訪問日
2018年10月16日
センパイ
八子 知礼(ヤコ トモノリ)氏
1997年工学研究科(第二類)修了。
卒業後は松下電工、アーサー・アンダーセン(のちに吸収合併を経てベリングポイント)、デロイトトーマツ・コンサルティングの執行役員パートナー、シスコシステムズのビジネスコンサルティング部門のシニアパートナーとして同部門の立ち上げに貢献。2016年4月より現職。
株式会社ウフル
https://uhuru.co.jp/
訪問記

株式会社ウフル CIO(チーフ・イノベーション・オフィサー)兼IoTイノベーションセンター所長兼エグゼクティブコンサルタント 八子知礼様(1997年工学研究科(第二類)修了)
八子氏が電気分野に興味を示し始めたルーツは、少年時代のある経験にありました。
八子「もともとコンピューターに興味がありましたね。小学生のころ、電気屋さんの店頭に置いてあるパソコンに、雑誌に書いてあるプログラムを打ちこんで、走らせていましたね。」
―え、小学生で、ですか!?
八子「そうですね。その頃からコンピューターも好きでしたし、ゲームも好きだったんです。父親からも『お前は理系だ』と刷り込まれましたね(笑)」
―店頭のコンピューターは何でしたか?
八子「NECのPC-9801かPC-9821ですね。言語はベーシックです。」
―どんなプログラムを作っていたんですか?
八子「まず、ベーマガ(ベーシックマガジン)に載っていたプログラムをやっていて、そこから少しずつパラメータをいじって、そこに載っていないオリジナルのものをカスタマイズしていましたね。
でも日が暮れて午後8時になると店員さんが『坊や、そろそろ…』って言って、店内に蛍の光が流れ始めて『ああ、分かりました』って(笑)
その時にプログラムの保存の仕方が分からないので、店員さんにフロッピーディスクに書いてもらって、『また明日おいで』って言われて帰ってましたね。」
―よく店員さんもいじらせてくれましたね(笑)
八子「愛媛の新居浜なんで、ほとんど人もいないようなもんです。」
―いわゆる個人経営のお店だったんですか?
八子「いえいえ、大きな家電量販店でしたよ。」
―いい店員さんだったんでしょうね。
八子「好きだったんでしょうね、その店員さんも。僕がパソコンいじっている時に後ろから店員さんが『それはさ、ずっとそのカーソルキーで右側に行くんじゃなくて、リターンキーを押すんだよ』みたいなことを、教えてくれましたね。
まあさすがにずっと電気屋の店頭にいるわけにもいかないんで、『パソコン欲しい』って親に言って、その当時の安いパソコン、MSXっていう規格があったので、それを買ってもらって、家でプログラムを書いてましたね。
ただ、その割に勉強の方では、国語の方が得意で、数学も物理も苦手だったんです。
高校2年生になっていい先生に出会って、ようやく物理ができるようになって、理系でいこうと思ったんです。」

八子さんは平成2年に広島大学工学部に入学。学部では制御工学について学んでいたそうです。
八子「当時、画像処理をやっていたんですね。今で言う人工知能のはしりですね。
大学院では、ニューラルネットワークや、遺伝的アルゴリズムを活用して、人工知能、というより人工生命を研究していたんです。
研究室の中では不良な研究生で、教授からは『八子はもう早く、さっさと出て行ってもらった方がいい』と言われてました。
『お前は真面目に研究をやるつもりがないだろ』と。『社会に出た方が役に立つはずだ』という風に。」
―『真面目に研究をやるつもりがないだろう』と思われていたポイントっていうのは、今考えるとどこだと思いますか。
八子「当時は、仮説を検証する、というアプローチが弱かったように思いますね。自分でシナリオを描いて、そのシナリオ通りにこういう結論になりました、と教授に見せても、『こういう仮説もあるじゃん』と指摘された時に、ああ、言われればそうだな、という感じで。」
―ということは、勝手な解釈かもしれませんが、学問というよりもモノ作りの人だったんですかね。
八子「そうです。プログラムが思い通りに動いたことに、僕としては満足していましたね。
確かによく出来ていたんですよ。自分で言うのもあれですけど。
3D空間上に細胞らしきものが泳いでいく、泳動軌跡を表示するシミュレーションを作ったんです。
それなりの見栄で、先生も『そこだけは褒めてやる』と言って下さるんですが、一方で、『結果はシミュレーションの中で行われる中身で、見てくれじゃない』とおっしゃるわけです。いや、でもさっき先生見てくれを褒めてくれたのに(笑)とは思ったんですけど。
その後、第三類(化学系)の先生が同じものを見て『こういうものは分子生物学のモデリングに適している』と言われて。
そこから分子生物学を学ぶようになって、その過程で生物学も学ばなくてはいけなくなったんです。細胞の仕組みとか、大腸菌の泳動の理論とか。
面白かったですけどね。ただそのロボティクス研究室の中ではまったく異端の研究をしてましたね。」
―大学時代は、BEAUX(ボーズ)という企画系サークルにも所属されていたとのことですが――
八子「なんで知ってるんですか?」
―実は、今回八子様と我々をお繋ぎいただいたのが、学生時代に八子さんと同じBEAUXに所属していた我が校の職員なんです。
八子「あ、そうなんですか。ネタバレしてますね(笑)」
―BEAUXの中では、具体的には何をされていたんですか?
八子「その時は表舞台には出ていなくて、裏方だったんです。イベント会場の音響をやったり、イベントのプロデュースをやったり、キャンプの企画の時は総リーダーをやったり、色んなことしましたね。
その頃から、段取りをすることが好きでしたね。
上手くパチパチ、と組みあがって最後にスパッと通った時が好きだったんです。」
―結局、修士課程を2年やった。
八子「そうですね。大学院の後は早く社会に出たかったですね。
卒業後入社したのは松下電工なのですが、僕は最初、松下電工というのはパナソニックの子会社のちっちゃな電気工事屋さんだと思っていたんです。
そのまま願書も履歴書も出して、面接に向かう新幹線の中でパンフレットを読んでいたら『売上高1兆円』って書いてあって、あれ、僕が思ってる規模感と違うな…と思って、そこで思ったよりもドエライ会社に面接に行くぞ、と気付いたんです(笑)」

八子「面接で、大学ではさんざん研究をやったので、研究だけは嫌です、って言ったんです。でも蓋を開けてみたら『情報検知技術研究所』という所の配属になりましたね。」
―研究以外で何やりたかったんですか?
八子「企画とマーケティングです。」
―文系分野ですね。
八子「文系というか、ふわっとしたことよりも、数値で捉えて科学的に分析するようなことがやりたかったんです。
でも最初は研究分野で、通信機器を開発していましたね。
ISDNの回路設計・基板設計・筐体設計、あとは当時NECさんと協業していたので、NEC機器をOEMで仕入れたり、その後自社開発したりして宅内の情報分電盤に組み込むDSUやターミナルアダプタの開発などをやっていましたね。」
―言ってしまえば、今の社会を作る骨組みになっている技術ですよね。
八子「松下電工は配線器具や照明のソケット、人感センサーなどを利用した宅内設備機器や住宅建材を作っているのですが、そこの上流工程の部隊に放り込まれたんですね。松下電器産業と混ざりそうになると思うのですが、分かりやすく言うとコンセントよりも壁側は松下電工で作っていて、コンセントよりもユーザー側は松下電器産業の分担だったんです。」
―松下での研究開発の中で難しい局面に出会ったことはありましたか?
八子「一応、大学の時に通信技術についても学んでいたので、ああ、あの時のあれか、なるほどなるほど…という感じで、おぼろげながら覚えていたので、大学で学んだことも活かされているな、と思いましたね。」
―その研究所では何年働いたんですか?
八子「3年働きました。その後に、新しいことをやりたかったので、社内公募で介護機器の新規事業部門・ナイスエイジフリーというものに手を挙げて、移籍しました。
主に車いすの開発・車いすの電動化、あと当時は介護系商材が皆無だったのでTOTOさんからOEMで買ってきたものを、我々の仕様にすること等を手がけていました。例えばトイレの後付け自動洗浄機において、リウマチの患者さんが押しやすいように、2つだったボタンを1つにするなど、TOTOさんと協力しながら松下電工のものとして開発していました。
あとフランチャイズショップ周りで店頭のクレーム処理や新商品のロールアウトなどもやっていましたね。」
―お話がお上手なので、クレーム対応も難なく出来そうですよね。
八子「今でこそナンパな感じでたくさん喋りますけど…あ、ここ笑っていただかないと(笑)
当時は技術者あがりだったので、あまり弁が立つわけではなかったつもりですね。
時には黙ったまま、何も言えないままで、悔しい思いをしたこともありました。」
入社後に会社の洗礼を受ける中で、ある学びがあったと、八子氏は語ります。
八子「色々先輩とも熱く言葉を交わして、こうすればいいじゃないですか、って言うと『じゃあお前それやってみろよ』って言われて、先ほどのTOTOさんの例の時に、自分で開発の企画をして、自分でTOTOさんから製品を仕入れて、自分で量産に流して、フランチャイズの店舗に出して、店頭クレーム受けて、みたいなことをしてましたね。
そこまでやったら製造業が上から下まで一通りわかるんです。
印象的だったのが、フランチャイズの店頭で、ホントに喜んでいただけるお客さんと、ホントに喜んでいただけないお客さんがいたので、お客さんのニーズを汲み取って、もう一度製品の仕様を微修正するわけですが、ちゃんとニーズに合うものを作れば、少々高くても、お客さんは買ってくれるんですね。
そこから学んだことがあります。
一つは、お客さんとの関係性をベースにしたマーケティングや会社のあり方を追求した方がいいんじゃないか、ということ。
もう一つは、このままハードウェアばっかり売っていても埒が明かないのではないか、という漠然とした懸念を抱いたことでした。
ハードウェアと、ハードウェアだけでは足りない部分としてソフトウェアないしサービスを併せて提供しないと、顧客が本当に求めていることを十分満たせず、事業としては先行き立ち行かなくなるのではないか、と。
この考え方は、この会社だけじゃなくて、他の会社でも知ってもらおうと思いましたね。
あと同じ時期に、『V字回復の経営』で有名な経営者・三枝匡さんの『戦略プロフェッショナル』という著書を読んだのですが、三枝さんが三井石油化学工業にいた時の手法で『機械を売るんじゃなくて、検査材料を売ることで機械をタダにしましょう』ということが書かれていて。
まあ、今でこそ当たり前なんですけどその当時は、これや!と。
こういうビジネスモデルを考えられるようになりたい、と思ったんです。
ただ、それまでコンサルタントという職種の存在を知らなくて、三枝さんは何をやっている人なんだろう?と思ってコンサルタントの仕事を調べたりして、自分はこういう仕事をやりたいんじゃないか?と思い立って、大阪でアーサー・アンダーセンというコンサルティング会社の門戸を叩いたんです。」
―その時はおいくつですか?
八子「30歳ですね。」
―その間に合コンとか、遊びとかはしなかったんですか?
八子「(笑)いや、1年留年してから大学院に進んだので、社会人になった年が25歳だったんです。
なおかつ結婚したのが27歳だったので、もう合コンもないですし、研究所時代は他の会社の価格やマーケティングを、土日も使って研究していたり、異業種交流会にも顔を出したりしていたので、28で子供も産まれたので、遊びらしい遊びはしてなかったですね。」
―20代の頃の充実っていうのは大切ですね。

八子「2000年ぐらいで、ちょうどアーサー・アンダーセンとアンダーセン・コンサルティング(現アクセンチュア)が分離したんです。
残ったアーサー・アンダーセンは、ビジネスコンサルを行う部隊だったんですけど、やっぱり規模を大きくしていこうとするとシステムをやらざるを得ないと。
アクセンチュアとガチンコで戦っていかないといけない、という状況で、同時にかなりの人員が抜けて行ったので、人員の強化という課題を抱えていたんです。
アーサー・アンダーセンという相当なブランドの会社が、ある意味チャンスで、ある意味危機に瀕していたので、これは上手くいけばこの会社に入れるな、と思ったんです。」
―最初は大阪だったんですね。
八子「そうです。2年半大阪にいました、最初の半年間は京都の大手電子機械メーカーの調達改革に携わって、次の1年半弱ぐらいは福岡で中国・九州地域にまたがる大手飲料メーカーの営業改革・バリューチェーン変革プロジェクトに携わりました。
その後も東京でプロジェクトに従事し始めたのですが、大阪を離れてプロジェクトに従事することが多かったので東京に移ったんです。それが2003年の暮れですね。」
―モノづくりの現場からコンサルタントの現場に移ったこと、そして日本ルーツの企業から外資系の企業に移ったことの心境はいかがだったんですか?
八子「やっぱりコンサルタントの会社は「Up or Out」で非常に厳しいと思っていましたから、いつクビになるのか非常にドキドキしていました。
今思うと、そんなに簡単にクビにはしないだろう、とは思えるんですけど、当時は例えば、先輩たちがタバコ吸いに行って色々な話をして、『じゃあ、あの件ああしておいてな』って言っているのを聞いて、僕をクビにしようとしているのか…と疑心暗鬼になっていたりしたこともありましたね(笑)
だから入社後最初の半年間は、圧倒的なパフォーマンスを残さないとクビにされると思って、マーケティング・調達と名のつく本やABC/ABM、バランススコアカードなどのフレームワークやコンセプトの本を片っ端から買って頭の中に叩き込んでいました。
家内からは『あんた買い過ぎ』って言われるくらいで、貰った給料のうちの数%は本につぎ込んでいましたね。そのくらい恐怖感がありましたね。
あとやっぱり、アーサー・アンダーセンに入った時、社員の皆さんがピッカピカで、理路整然としていて、なおかつ、こちらが準備していても、その先を見越したかのような質問をされるんです。「なんだこりゃ、とんでもないところに来てしまったな」と思って。
でも、その当時の大阪事務所では、ありがたいことに、すさまじいスピードで周囲に認められていったと思います。
そのくらいのスピードでやらないと付いていけない、と自分でも思っていたので。
入社してから翌年の夏ぐらいには、周囲から『あいつは出来るから色々やらせよう』と言われていたんですが、その頃から僕、天狗になっていたんですね。
東京のプロジェクトにアサインされた時、現場のヒアリングを基にして、上位職の方々に楯突いたんです。
その時は『真実を伝えているだけ』だと思っていたんです。ただ、今思い返すと、ロジックは正しいことは言ったんですけど、解決策が無かったんですね。
上位職の方々からは『経営陣のことを考えずに現場のことばかりおもねっている。それは経営陣のことをバカにしているようなもんや。ストーリーが経営陣に刺さる形になっていないし、アクションを取ることができないレポートになっている。』と言われたんです。
その日の晩、先輩方がぶんむくれでドキュメントを書き直している中で、僕はしばらく何もしなかったんです。
そしたら先輩に『気が済んだか?』と言われて、結局自分も粛々と先輩を手伝いました。
その後先輩から『どうする?自分が賢いと思っているのか知らんけど、自分でやりたいことを突き詰めるんだったら一人でやれ。』と言われて、自分1人で案件を取ってくる術もないので、1人で出来ません、ってなったんです。
敗北感がありましたよね、その時は。鼻をボキンと折られたんです。
その後に先ほども言った、福岡の大手飲料メーカーのプロジェクトに加入したんです。
その辺りから、いい気になってた自分が無くなって、仕事に馴染みはじめたんです。
いくらロジックが通っていても、クライアントがアクションを取れなかったら、成果に繋がらなかったら何の意味もない、ということを学びましたね。」
―要するに、コンサルティングというのは経営陣が動けなかったら、結論にならないっていうことですか?
八子「デッドロックになる、っていうことですよね。前に進まないっていうことです。」
―それは今から考えると、周りの人たちは、失敗させようと思って敢えてやらせたんですか?
八子「そうでしょうねぇ。」
―ある意味、優しい会社ですね。
八子「まだ伸びしろがあるから叩いとかなきゃいけない、って思ってもらえたんでしょうね。
じゃないと放っておかれますから。ダメなヤツを鍛えるのは外資コンサルでは無駄なので。」

アーサー・アンダーセンは、2002年にエンロン事件の影響でKPMGコンサルティングにと吸収合併する形で、ベリングポイントとして再スタートしました。八子さんはしばらく後にベリングポイントを退社。その後デロイト・トーマツ、シスコ、現在のウフルと、最初の松下電工から全て入社約5~7年で次の会社に転職しています。
八子「飽きっぽい、っていうこともあると思います。あと、松下電工に入社した時から5年をめどにキャリアを変えて行こうと初めから決めていました。」
―キャリアを変えていくことに、ポリシーはあるんですか?
八子「ある程度まで到達すると成長が止まってしまうので、次の山(目標)を登らなければいけない。ご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが『ピーターの法則』(※一つの組織の中では上位に上がるにつれてその人の能力限界、すなわち“無能”に近づくという考え方)になってしまうんです。そうならないために、ある程度時間が経ったら今までと違う毛色の仕事をしようとしていますね。」
―普通はラクしたい人や、安定したい人が多いと思うので、常に成長を止めない努力をすることはとてもすごいことだと思います。
八子「会社を変えてまで成長機会を得ようとするかどうかはその人の価値観それぞれだと思いますけどね。
自分の父親は同じ会社を定年まで勤め上げた人なので、『お前は我慢のきかない男だ』と当時は言われたんですけど(笑)
組織が変わることが必須ではないのですが、もっともっと仕事をやっている人たちを見ると、その人たちと一緒の水に飛び込みたくなるんです。
松下電工の時に東京出張で、同い年のベンチャー会社経営者を紹介してもらったのですが、その人が、小さいオフィスで机いくつか並べて、寝袋を持ち込んで『夜もガンガン時間関係なくやってるんですよー』って疲れた顔にも関わらず嬉々として言っていて、会社としての業績も伸びていたんです。
それを目の当たりにした時に『人間として負けた感』があったんです。
彼はキッツキツの中で仕事をやっているのに爽快で、一方僕は松下電工で、余力のある中で仕事をやっているのになんとなく爽快じゃなかったんです。
その時から仕事をするときは、限界近くまでやって、爽快でいたいと思うようになったんです。」
―その志向は、生来の性格もあるんですか?
八子「祖父母がクリスチャンで、祖父はガンになって死にかけたところから復活したので『お釣りの人生だから、周りのために自分の能力を最大限使っていくしかない』という風に良く言っていたんです。
祖母からも『生きていると思いなさんなや。生かされているんやで。』とずっと教えられて育ちましたね。
だから僕も、生かされていると思って生きているんです。明日雷に打たれて死んでもしゃあないな、と思っているんです。
それだったらできるだけ思い切ってやるしかないな、と思っています。」

―今の会社ではどういう仕事をされているんですか?
八子「今年の7月からCIO(チーフ・イノベーション・オフィサー)という肩書なんですけど、要は『ちょっとインチキなおっさん』のおしゃれな言い方なわけですね(笑)」
(一同爆笑)
八子「まあ、周りから見るとインチキ臭く見えるんですけど、実はちゃんと先々仕組み化することを見据えて考えて色々やってるんですよ、という、旗振り役みたいなものですね。
例えば全国各地でハッカソンイベントをやっているんです。
周りから見ると『なんでそんなの儲からないのにやってんの?』って言われるんですけど、僕らからすると実はしたたかで、地域の課題を解決しながら共通プラットフォーム化を粛々とすすめているわけです。
まずは、地域の人たちが自分たちの困っている課題を持ち寄るんです。
ところが地域の課題はその地域の方々だけでは解決策としてのアイデアが無かったり、気づかないことも多く、そこに他地域や首都圏の人間が出ていって、地元の人たちと一緒になってITソリューションなどの洗練されたやり方や地元に拘らない視線で実現出切る解決策を探すんです。
それがハッカソンという短期間のイベント内で具体的な形になったら、行政の人たちを呼んでお見せするんです。
さすがにこんな短期間でよくそんなものを作ったな、と驚かれることが多いわけです。
そうなると我々は、『行政だけでなかなかここまでカタチに出来ませんよね。今だったらこのアイデアを次年度の予算に入れて頂くことが出来ますよね。しかもこれらのアイデアは皆さんだけだと一挙に1日半や2日で出来ませんよね。さあどうします?採用されなければ、こういったありがたいイベントは、来年からは開催することが難しいと思います。さあ自治体の皆さん、やるかやらないか、どっち?ちなみにここで開発や実装ができれば、他の地域に展開するお手伝いをしますよ。』っていうアプローチなんです。
一応企業としてのウフルは、IoTを主力事業として、自社製品「enebular」の提供や、システムの導入および、コンサルティング等のサービス、提供等をやっていますが、こうした我々のような部門が最上流で新しいやり方を推進していたりします。」
―お客さんの困ったことを解決していく役回りなのでしょうか?
八子「まあそうですね。そうなんですが、先ほどのハッカソンについては、地域には中々財源が足りないので、初めの段階は我々の持ち出しでやっていたりするんです。
スポンサードしているんですが、その代わり実績が出たら我が社や参画して下さったパートナー企業でのマーケティングで活用させていただきます、という風にしています。
去年も長野県伊那市でやっている実績としていくつかの事例を、著書やブログ、メディアに拡散させていって、それが広島県や新潟県、熊本県人吉市に飛び火していったんです。
飛び火した結果、伊那市で投下した人件費やスポンサーフィーをはるかに超越したリターンが返ってきているんですよね。そこからまた広島県での取り組みを見て、和歌山県や長野県など、他のエリアから同じ仕組みでやりたい、という声がかかるんです。」
―いわば一種のショーケースになっているんですね。
八子「そうですね。一方で総務省や経産省がやっているアプローチだと、まったくその意図がなくても、それぞれの地域が競争してしまうんですね。
人口が縮退する日本においてそれぞれの地域がバラバラな仕組みを作って統一化・標準化せずに手間ばかりかかる仕組みが蔓延してしまうことは非常にナンセンスだと思うんです。
それよりも共通化、プラットフォーム化するのが必要だと思っているんです。
だから、例えば伊那市の取り組みについても、他の地域でも同様に行うんですね。
加えて別の地域で開発した別のサービスやソリューションを同じ枠組みの発想を持っている人たちに横展開していく。そうすると自ずとプラットフォーム化していくんですね。
だからこれはある意味将来を見据えた『インチキなおっさん』の仕業ですよね(笑)」
―そのカギは、中心にいる『インチキなおっさん』がハブになっているんですね。
八子「ただ、僕だけでもダメで、現地・現場で困っている人や、現場側でコーディネートしてくれる人たち、そして解決策やソリューションを提供してくれる人達がいなきゃいけないんです。
我々はどちらかというとそういうことに対して、首都圏とか、エンジニアとか、周りの人たちを連れていく原動力を作ること、エコシステムやコミュニティを作るのが得意ですね。
僕らが最近、我が社を評して言うのは『企画会社』ということですね。システムも作るんですが、話題になる企画をどんどん打ち出しているんです。」

(左から)川村(東京オフィス研修生)、石飛尚樹様(1991年経済学部卒)、千野信浩様(1985年総合科学部卒)、八子知礼様(1997年工学研究科(第二類)修了)、松永州央様(1990年法学部卒業)、北池(東京オフィス)
研修生の感想
数多くの逆境に対して、惜しみない努力を向けることで成長し乗り越えてこられたことが印象的でした。また実際に八子様の取材を体感した者としてもっと印象的だったのは、話す八子様の熱量の凄まじさ、話術と情報量の豊富さでした。
それは取材に同行した皆さんも圧倒されたところだと思います。
人の思いは、抱える量が多ければ多いほど、自然とあふれてくるものではないかと思うのですが、八子様はそれが言葉や行動としてあふれているのだと感じました。
そして八子様のキャリアの転機には必ず、羨望や好奇心、もしくは恐怖感が原動力になっているように思いました。
その感じた気持ちに逆らわない、八子様の勇敢さがその気持ちをぶれさせなかったのだとも思います。
御祖父母様の教えがベースとなっていることも頷けます。
ただ、ピーターの法則について聞いてしまったことで、大学職員としては気が気ではありませんが(笑)
とても柔軟で、アグレッシブな八子様の姿から、たくさんのことを学ばせていただきました。
「実は、広大です」過去の記事は以下のURLから↓
https://www.hiroshima-u.ac.jp/tokyo/dousoukai/jyuzutunagi

 Home
Home