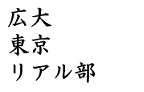<お問い合わせ先>
広島大学東京オフィス
TEL:03-6206-7390
E-Mail:tokyo(AT)office.hiroshima-u.ac.jp ※(AT)は半角@に変換して送信してください。
訪問日
2025年8月5日
センパイ
鉾岩 崇 (ホコイワ タカシ)氏
1988年 工学部卒業
建築家 株式会社佐藤総合計画 代表取締役社長

オフィスビル、商業施設から図書館、美術館、スポーツ施設や自治体庁舎などの公共建築、はては駅、港湾施設、公園まで、広い意味で都市をデザインするのが建築設計事務所。なかでもデザインから構造計算、設備設計、工事管理などトータルに建築に関わる大手のことは組織系設計事務所と呼ばれる。かの業界では大手10社と括られる、そのうちの一社が、東京ビッグサイトほか数多くの公共建築を手掛けていることで知られる佐藤総合計画。2023年6月、社長に就任したのが工学部第4類出身の鉾岩崇さんである。
-2023年に代表取締役に就任されています。どんなお気持ちでしたか。
鉾岩:正直、驚きました。取締役になって2年目、他の取締役は全員私より年上でしたので、多少戸惑いはありつつも、「前社長がとにかく若返りを図ろうとしていることや新しい風を吹かせたいのだな」という意図を感じました。驚きながらも、私がしっかりやっていこうという気持ちでした。
-交替時に前社長が「これからはデジタルを活用することで、情報にアクセスし、編集し、マネジメントする能力が問われる」(日経クロステッ2023.4.20)と話されています。どのような意味でしょうか。
鉾岩:設計者は建築単体の設計だけやっているのではなく、あらゆる分野の知識を取り入れながら、周辺環境との関係や街づくりも含めて計画していきます。ネット上に、様々な情報があふれている今の時代、その中から必要な情報をいかに取り入れて、組み合わせて、活かすかという能力が非常に重要だということです。
自分たちが必要とする情報を、AIも活用しながらいかに編集していくか、その能力が、これから重要だということですね。そのための若返りが求められていたのでしょう。
-一級建築士が200人以上もいます。個性の強い人たちをまとめたり引っ張っていくことの難しさはどんなところでしょうか。
鉾岩:私自信が引っ張っていくというより、会社の進むべき方向をしっかりと示した上で、社員の主体性を尊重し、それぞれの個性がもっと顔を出していくような会社にしたいと思っています。
佐藤総合計画という会社の名前はもちろん大事ですが、その中で「佐藤総合計画の誰々」という個人の名前をどんどん出していきたいと思っています。多様な個性が集まって混ざり合うことで、新しいものを生み出していくようなクロスブリード(混ざり合う)組織にしていきたいと。
-現実にはどんな難しさがあるのでしょうか。
鉾岩:キーとなっているのが、全社的に行っているデザインレビューです。全てのプロジェクトをデザインレビューにかけるのです。若い人も含めていろんな個性がありますので、意見を出し合って、提案の方向性を議論します。デザインレビューがあることで、佐藤総合計画の作品という品質を保ったものを世の中に出していくことができていると思っています。
このデザインレビューは、プロジェクトの関係者が全員集まって行います。私や設計本部長、地域の代表などのコアメンバーも参加し、プロジェクトチームと議論します。
そこで若い人が自由に意見を言えるような環境を作ろうとしています。具体的には否定しないことです。どんな意見でも否定せずに、まずは聞く場を作る、ということです。
-ベテランの方からすると、もどかしく感じることもあるのではないでしょうか。
鉾岩:もちろんそのような状況もありますが、今の若い人たちは、上から言われても聞かないですよ(笑)。「言われたから、しょうがないからやる」では新しいものは生まれません。
主体的に、本質的な思考を、自ら実行しないといけません。そういう環境をしっかり作っていきたいと思っています。
若い人たちは、感性が優れている面がありますが、建物を作るには経験が重要で、感性だけだとなかなか難しいわけです。いろんな経験を踏まえて出てくる「直観力」が必要なのですが、経験がない若い人には難しい。どうしてこのようなデザインにするのか、根拠を持ってきちんと説明をして、関係者を説得できることが求められます。20代から30代前半ぐらいの若い人にそれができるかというと、まだまだかなと。
-どんな経験を積めばいいのでしょうか。
鉾岩:実際のプロジェクトを通して学び経験することは当然ですが、さらに主体的にいろんな分野のこと、例えば歴史や文化、哲学、科学や芸術などあらゆることに関心を持って学ぶ、ということです。それから、工事現場を経験することもそうですし、街に出て社会の変化を感じ取るとか多くの人とコミュニケーションをとる、建築以外の分野の人とのネットワークをつくるとか、それは自分が主体的に努力するしかありません。いま、若手社員たちの間で自主的に企画して、外部の講師を呼んでセミナーを開いたり、コミュニケーションを高めるためのイベントを社内で自主企画する、という行動が生まれていますので、そのような活動は会社としてもサポートしています。
-ところで中国でのご経験が長いようです。
鉾岩:住んでいたわけではなくて、東京から出張する形で結構長く関わっています。1990年代の後半ぐらいにできた、清華大学との関係から始まっています。そのつながりが広がっていき、国際コンペに参加、2000年の初めに広州の国際展示場が初めて当選しました。私が最初に関わったのは、天津のオリンピックスタジアムでした。

天津オリンピックセンタースタジアム

深圳湾体育センター
-中国で物を作るということは、日本とはずいぶん違うのではないでしょうか。
鉾岩:全く違います。中国では施工図までを設計事務所が作成し、それを元にゼネコンが工事を行います。日本はいわゆる実施設計までを設計事務所が作成し、施工図はゼネコンが作成、工事も行います。クライアントの考え方も違いますし、技術力や制度も違います。
-中国では、国の方針に沿っていれば、かなり自由なことができるのではと想像します。
鉾岩:規制はむしろ厳しいですが、デザインについてはかなりの自由度がありました。当時はクライアントが、自分の威信や成果を示すために、巨大でインパクトのある、いわゆる「アイコン建築」が中国の国内で溢れました。我々は都市の文脈で、歴史や文化、周辺とのつながりなどを大事にするのですが、そういうことを一切考えず、市民との関係性も全て断ち切って、シンボル的な目立つデザインの建物を作る、という傾向がありました。
-中国とのビジネス上で、実績を残せた秘訣は何でしょう。
鉾岩:当社で手掛けるものは公共建築が多く、日本でも7~8割が公共建築です。中国でも公共的なものに関わっています。そこが民間の案件中心の他社とは違うと思います。公共建築は、その地域に必要な公共性の高いものなので、プロジェクトが止まったり、設計料が回収できないことが比較的少ない方です。また国際コンペで当選しているところが我々の強みでもあり、プロジェクトの実現性では信頼度が高いところが成功した秘訣といえるかもしれません。
-国際コンペで勝つのはとても大変なのではないでしょうか。
鉾岩:世界中から、ザハ・ハディドなどの著名建築家を含めて多くの応募がありますが、当社はデザイン力、提案力で他社に勝つことができています。社員の個々のレベルはもちろん高いのですが、個々の能力に会社としての総合的な知見を加えるデザインレビューが組み合わさった結果だと思います。
「知的構想力とデザイン力で唯一無二の存在になる」。それが設計事務所として生き残る道だと思っています。
-ところで広島大学に入学されたきっかけは。
鉾岩:私は愛媛の八幡浜出身です。中学校ではサッカー部でしたが、進学した八幡浜高校にはサッカー部がありませんでした。やることがないので、中学校のサッカー部の仲間とみんなで美術部に入ったんです。先生が面白かったことや、部活に入っていない人の受け皿になっていたこともあり、部員は80人ぐらいいました。
授業のクラスは理系コースでしたので、理系でありながらアートな部分を組み合わせることができる建築だったら面白そうだな、ということで、自然に建築を志望するようになっていきました。建築学科のある大学を探したところ、一番近いのが広島大学でした。
もう一つは、父親が熱烈な広島カープファンだったことです(笑)。毎日テレビやラジオから試合中継が流れてくるので、私も当然その影響を受けました。山本浩二、衣笠、ギャレット、ライトルが活躍した時代です。広島はすごく身近に感じていたので、ほとんど何の迷いもなく、「広島に行こうかな」という感じでした。
-大学生活はどうでしたか。
鉾岩:同じような境遇の人が多くて、居心地がよかったと思います。それから、高校時代にできなかったサッカーをやりたくて、サッカー部に入りました。いきなり本部のサッカー部に入っても絶対にレギュラーになれないのは分かっていたので、東雲のサッカー部に入って、レギュラーになりました(笑)。
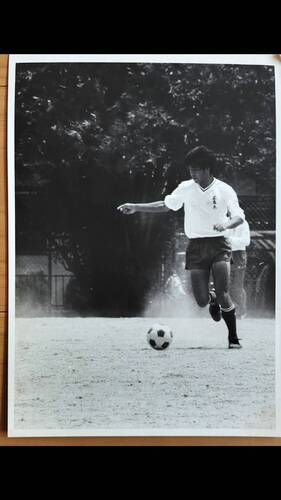
学生時代の鉾岩さん
写真提供:東雲サッカー部
-小さいところでてっぺんを狙うのは一つの戦略ですね。ところで師事された先生は。
鉾岩:杉本俊多先生です。先生がまだお若い時で、かなり尖っていましたね。「建築の現代思想」(鹿島出版会 1986年)を出版されたばかりで「広大にこんなすごい先生がいるんだ」と思い、杉本研究室を志望しました。(工学部第4類は他学科も一緒になっていますが、建築学科に行きたかったので)教養課程は一生懸命勉強しました。ところが研究室に入ると杉本先生の話す内容がまったく分からなくてついていけないので、最初は「失敗した」と後悔しました(笑)。
西洋建築史講座の試験の際には、答えが全くわからなかったので、答案用紙に、自分がデザインした椅子を回答欄に描いたこともありました。しゃれっ気のある先生なので、「もしかしたら温情で、かっこいいデザインにしておけば点数をくれるんじゃないか」と思っていましたが、もう、怒られた、怒られた(笑)。「ふざけるな、何考えてるんだ」と。
また当時の製図は、ケント紙にロットリング製の製図ペンで書いていました。通常は別に下書きを描いてからケント紙に清書しますが、私の場合はケント紙にいきなりスケッチを始めるんです。鉛筆でスケッチして、消しては書き直して、その上からインキング(※)をするので、紙がボロボロになります。それを提出した時に、「こんな学生、初めてだよ」と呆れられました。いろいろとありましたが、今でも先生と交流させてもらっているのは、私の宝だと思います。
(※)製図ペンや製図用シャーペンなどを用いて、図面に線や文字を描き込む作業
-杉本先生からはどんなことを学ばれましたか。
鉾岩:「ファサード(建物の正面、外観)を大事にする」ということです。「ファサードは単なるデザインじゃなくて、市民のコミュニケーションの舞台だ」とよく言われていました。
建築というのはいろいろな内部機能を備えていますが、その機能と、外部の人たちが接する中間領域的な空間がファサードには必要だと。「コミュニケーションの舞台」としてのファサードをしっかり意識して設計しなさい、というのが先生の教えで、それは今でもずっと大切にしているところです。
例えば中国の深圳のスタジアムもその一つです。ポーラス(多数の孔)で外皮が覆われていて、強烈な日射を緩和する半屋外の中間領域的な場所や広場がたくさんあり、市民が日常的に交流できるようになっています。
-先生の教えが今も生きているのですね。当時、憧れた建築家はいますか。
鉾岩:学生の頃衝撃を受けた建築のひとつは、原広司さんのヤマトインターナショナルです。
ヤマトインターナショナル 東京本社ビル
他にも槇文彦さんや、横浜港大さん橋を設計したイギリスの建築家ユニットForeign Office Architects (FOA)(アレハンドロ・ザエラ・ポロとファッシド・ムサヴィ)、も好きです。横浜港大さん橋はダイナミックな造形で、それでいてシャープなディテールが実現していて、一番好きな建築です。
横浜港大さん橋
-大学卒業後の進路は。
鉾岩:大阪の建築事務所に入社しましたが、自分がやろうとしていることと全く合わなくて、一年ちょっとで辞めました。
そして、公共建築をもっとやりたいと思っていたところ、当社の面接を大阪で受ける機会があり、入社することになりました。最初の赴任地は九州で13年間ぐらい、その後、中国のプロジェクトがきっかけで2002年に東京にきて今に至ります。
九州時代は本当に充実していて、ずっと九州にいたかったのですが、会社が許してくれませんでした(笑)。

鹿児島県上野原縄文の森・鹿児島県立埋蔵文化財センター
撮影:アイオイ・プロフォート

Gメッセ群馬
撮影:川澄・小林研二写真事務所
-公共建築に携わりたいという気持ちは、どこからきていますか。
鉾岩:世の中に形として残り、かつ社会に貢献できるようなものを設計したいという気持ちがずっとありました。公共建築はそれが使命とされていますので、そういうところに魅力を感じていました。
今でも当社に入社を希望する学生さんには「社会に最も貢献できる設計事務所です」とお伝えしています。組織設計事務所の中で公共の比率が一番高く、直接的に社会に貢献できるのは、我々のアピールポイントでもあります。
我々の若い頃よりも、「もっと社会に貢献したい」と本気で思っている学生さんが多いと感じます。利他性ということを言う学生さんも多いですね。多様性や包摂性をいわれている世の中の流れが影響している印象があります。一方で、SNSを中心にポピュリズムに走るような傾向もあり、両方の面があるような気もしています。
-地方大学の学生たちにとって何が大事で、どうしたら世界が広がっていくと思われますか。
鉾岩:今は、昔ほど東京と地方の学生の差がなくなってきていると感じています。広大生を見ていても、東京近辺の学生とレベル感は変わらないと思います。だからあまりそこは意識しなくてもいいのかなと思います。
ただ、地方は刺激がとにかく少ないので、いろんな建築を見て関心を持つことは大事だと思います。
また、これからは「アートとサイエンス」の考えが本当に重要だと思っています。感性と、研究力や論理力を結びつけるということ、ひらめいたものに対して仮説を作って、論理的思考やエビデンスで理論付けしていくことの繰り返しですよね。そういう感覚を、学生の頃から常に持ってもらいたいと思います。地方ではアートに触れる機会がどうしても少ないので、意識して触れてほしいです。
それから、学生時代しかできないようなことをやってもらいたい。特に様々な活動を通して仲間や先生方とのネットワークを築くことですね。社会に出てから必ず役立つことを伝えたいです。
-逆に地方で学ぶメリットは何でしょうか。
鉾岩:役員の間で、「地方から来た人間の方が伸びるね」という意見があがります。地方出身者の方が会社に定着して、伸びている人が多いと。素直さというところに強みがあるのかもしれませんね。


 Home
Home