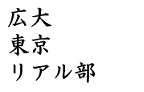<お問い合わせ先>
広島大学東京オフィス
TEL:03-6206-7390
E-Mail:tokyo(AT)office.hiroshima-u.ac.jp ※(AT)は半角@に変換して送信してください。
訪問日
2025年9月8日
センパイ
大賀 広之 (オオガ ヒロユキ)氏
1998年 法学部二部卒業
TBSスパークル ニュース本部 副部長

-学部やご出身についてお聞かせください。
大賀:法学部二部出身、1994年入学で1999年3月に卒業しました。当時の二部は5年制、現在の夜間主コースになってからは4年制になっていて、僕は二部の最後の学生です。 出身は栃木県小山市です。
親元を出たいということと、経済的な理由から、働きながら通える大学を探したところ、広島大学の法学部に二部があることが分かり、受験しました。
-関東地区には二部として学べるところはなかったのでしょうか。
大賀:当時はありませんでしたね。岡山大学、愛媛大学にも二部がありましたので、二部のサークル同士で交流がありました。
-昼間はどんなお仕事をされていましたか。
大賀:テレビ新広島でカメラアシスタントをやっていました。学内でアルバイト募集の掲示を見つけて応募したんです。当時は広島テレビ、テレビ新広島、広島ホームテレビ、NHK広島放送局の各局で広大生が報道カメラマンのアシスタントのアルバイトをしていました。
仕事の内容は、カメラマンが取材に行く時の荷物持ちです。ライト、バッテリー、三脚、それから音声機材などです。車で取材場所に行って、夕方のニュースで放送するので、必ず夕方までは帰ってくることができ、バイトを終えてから学校に行っていました。
-二部生にとっては理想的なアルバイトですね。
大賀:基本的には夕方のニュースまでにテレビ局に戻ってくるので、学校に行く時間はちゃんと確保できました。上の社員の人からも「必ず学校には行きなさい」と言われていました。
-就職活動はどのようにされましたか。
大賀:当時は超就職氷河期、内定が1個取れたら胴上げされるような時代で、本当に求人がありませんでした。
私はどうしても報道カメラマンになりたかったので、TBSの報道カメラマンをやっている会社はどこかを調べて、それが「日本ビデオ」という会社であることが分かりました。
ところが就職情報誌には「日本ビデオ」が全く掲載されていませんでした。
4年生の4月頃、TBS本社近くにある公園内の公衆電話で、タウンページをめくって電話番号を探し、電話をかけて、飛び込みで会社を訪問しました。
募集の予定はないということだったのですが、「他社の面接で東京に来たので寄らせてください」とお願いしたり、番組の感想を伝えたり、人事や総務の人たちとかかわりを持っていました。そうした熱意が伝わったのか、「今年は採用をやろうと思う」という話になって9月に内定をもらいました。

-そもそも、なぜ報道カメラマンになろうと思ったのですか。
大賀:アルバイト先のテレビ新広島では、カメラマンの人たちのバイタリティがすごく強くて、いい映像を撮れたらすぐ放送につなげ、いい放送ができたら「やったな!」と喜び合う、そういうノリがすごくかっこよく見えました。
高校生の頃からジャーナリズムに漠然とした憧れはありましたが、実際に報道カメラマンの姿を見て、「やっぱり報道カメラマンっていいな」という気持ちが強くなりました。
-実際に就職されて、お仕事はどうでしたか。
大賀:東京と広島では会社の規模が違うので、組織のスタイルが全然違いました。完全に分業制で、記者は原稿を書くだけ、カメラマンは映像を撮るだけ、照明はライトを当てるだけ、音声さんは音声だけ担当と、仕事が細分化しています。縦割りで、ステップアップがすごく難しい業界でしたので、カメラマンになるのはとても大変でした。
当時所属した会社の場合、アシスタント、照明、音声を何年か経験して、ようやくカメラマンに昇進します。その次のステップアップは基本的にないので、「カメラマン一筋30年」みたいな人がたくさんいました。
70人程度の部署で、カメラマンになれるのは年に1人か2人ぐらい、「将来絶対にカメラマンになりたい」と待ってる人が30人ぐらいいました。
-どういう人が認められるのでしょうか。
大賀:音声や照明担当の段階で「こいつには仕事を任せられる」という安心感は必要ですね。それでカメラマンをやらせてみてセンスがいいと、認められます。たとえばペットボトル一つを撮影するにしても、どの角度から撮るのか、絵の切り取り方によってセンスが問われます。
また、たとえば自民党の総裁選挙が前倒しになることがニュースになったとき(2025年9月上旬)、カメラマンは永田町の自民党本部の選挙管理委員会の現場に撮影に行きます。会議の冒頭を3分間撮影する「頭撮り」の時に誰を撮るか、誰と誰のツーショットを撮るのか、ツーショットからズームインしてどちらを最後に撮るか。後々、ニュースでの使われ方も変わってきますので、センスも下調べも必要です。
日頃からテレビや新聞で政治や経済をはじめ様々なジャンルのニュースを勉強することはとても重要です。
-音声・照明からカメラマンになるまで何年かかりましたか。
大賀:28歳の時でしたので6年かかりましたね。
センスが問われるので、「俺、下手だな」などと毎日悶々としながら過ごしていました。同年代のカメラマンがあの番組に呼ばれたとか、あいつの映像は良かったけど俺はうまくいかなかったなとか、自分の撮った映像について悩むことがたくさんありました。
結局、カメラマンは38歳で社会部にいくまでの10年間やることになります。
-なぜカメラマンから社会部へ。
大賀:カメラマンとしての才能に限界を感じて、一念発起、転身しました。ちょうどその頃から、TBSの報道カメラマンのセクションと、社会部や経済部で原稿を書くセクションとの人材交流が始まり、初期の頃に僕が選ばれました。やりたくないと断る人もいましたが、僕は「やります」と言いました。
-カメラマンから記者への転身は少ないのですか。
大賀:カメラマンは、「撮ってください」と言われたものを撮るのが基本なのですが、記者はネタを取ってくる、原稿を書く、足が棒になるまで現場を歩き回ってネタを探し回ったり、人に気を遣って頭を下げて、嫌な取材先にも頭を下げて「すいません、すいません」と言いながらなんとか食らいついて、という仕事、とても大変です。元々のタイプが違うのでカメラから記者というのは少ないですね。
特に記者に成り立ての頃、事件現場に行って、いわゆる地取り取材をするのですが、他局では22~23歳の社会人一年生たちが走り回っている中、38歳のおじさんが一緒になってやっていました (笑)。
目撃者探しや、事件の犯人の家の近くでインタビューをする機会がありましたが、「何軒かピンポンしたら話を聞かせてもらえるだろう」という軽い気持ちではなくて、ちゃんと真面目に、隈なく回らないと取れないんだな、ということをすごく感じました。
-社会部の仕事はいつまでされましたか。
大賀:オリンピックが終わる2021年の夏までです。国土交通省担当、東京都庁担当を経て、東京オリンピック担当も兼務することになり、その間にコロナが始まり、オリンピックが延期になりました。東京オリンピックが終わり、コロナも収束に向かいつつある時期に、記者としての活動は終わり、朝の情報番組のプロデューサーになりました。初めて記者ではなく管理者側として、事実誤認がなかったか、現場でトラブルがなかったか、予算管理やコンプライアンス的な問題がなかったかの確認などの業務を経験しました。

-今はどんなお仕事をされていますか。
大賀:編集長として、ニュースの順番を決める仕事をしています。主に平日お昼のニュースを担当していて、トップニュースをどれにするか、放送時間、担当者などを決めます。
-いろんな要素で順番が決まるのでしょうが、どうやって判断するのですか。
大賀:ニュース感覚を問われますね。「トップ項目にこれはダメだろう」と意見される時もありますし、逆に社会の反響を呼ぶような大きなネタが取れれば、各社が別のニュースをやっている中、うちだけ分厚く取り上げることもあります。
どのニュースを頭で取り上げるかの感覚は、経験で磨かれるところですね。自分が迷っていたら全員が迷ってしまうので、自分の判断でやるしかありません。意見がぶつかることもありますし、恨まれるようなこともあります。
-その時にどうやって相手を説得するのですか。
大賀:そのニュースが社会生活、市民生活にどれぐらい影響を与えるのかを社内で議論して、どれだけの視聴者にとって有益な情報なのか、の観点で判断するようにしています。
なんとか放送ができる形にしつつ、落としどころを探っていくこともありますし、他のニュースとの兼ね合いで放送時間の調整を求めたり、他の番組に持って行った方がやりたいことができるのでは、と提案したり、いろいろなケースがあります。
-うまくいくための経験則はありますか。
大賀:みんなが同じ方向を向いていることです。
TBSのニュースで放送することによって、どういう効果を生むかという大義の部分で方向性が同じだとうまくいきます。その方向感を同じく持てるか持てないかだと思います。
相手を説得する時には、TBSニュースで力を入れているところや、視聴者の関心がどこに向いているか、をベースに話し合います。
そのためには、日頃から、プライベートも含めて仲良く楽しく付き合っていくことも、すごく大事です。
-普段からコミュニケーションを必要とする相手は何人ぐらいいるのですか。
大賀:一つのお昼のニュースを作るために編集部にニュースを持ち寄ってくる社会部、外信部、経済部、政治部の4部があって、その4部に3人ずつぐらい「デスク」と呼ばれる責任者がいるので、社内だと15人ぐらいですね。
他にもJNNのネットワークには27の地方局があり、それぞれにデスクがいます。日頃は電話やメールのやり取りだけですが、年に1回全国会議があり、東京で3時間ぐらいの会議を行います。
会議が終わった後に、飲み会があるのですが、その飲み会が重要で(笑)。電話よりも相手の雰囲気がわかりますし、「この間はこういう風に放送できたのでよかったです」とか「もうちょっとこうやって欲しかったです」ということを、お酒の力も借りながら、ストレートに伝えることができるのは大事ですね。
現在担当しているお昼のニュースは、午前11時半から放送されますが、世の中が始まるのは概ね午前9時からなので、放送までに2時間ちょっとしかありません。その間に、事件や事故なら警察署などに電話をして聞き取り取材をして、カメラマンは現場で撮影をします。その後撮ってきた映像を編集して、字幕を付ける、という作業も含めて1時間~2時間、下手したら30分でやらないといけないという世界です。
だいたいのアウトラインは自分の頭の中だけでは前の晩ぐらいから考えていますが、そのとおりにはいきませんね。
どこで優先順位をつけるか、僕がずっと悩んでいたら仕事が進まないまま放送時間だけが近づいていくので、迷ったり止まったらダメなんです。時間との戦いですね。
-ストレスにはならないんですか。
大賀:僕には向いているみたいです。うまくいった時の方が「よっしゃ!」という感じで。
現場以外にも、記者クラブにいる記者さん、情報を取って発信する記者さん、本社で編成順を編集する僕みたいな人間、番組を編集する編集マン、放送に出すスタジオ、原稿を読むアナウンサー、みんながそれぞれの役割をやって初めて1個の番組ができます。みんなで作り上げていくのが、テレビ番組の好きなところです。
学生の時に大学祭実行員会をやっていましたが、それと同じ感覚です。
当時は二十歳前でしたが、それぞれの人間がやっていることは地味かもしれないけど、それが組み合わさって1個のものができるのがすごくいいなと思って、学生時代はずっと大学祭実行委員会をやっていました。二部は、社会人の人もいたし面白かったですね。
-現役の学生にはどんな生活を送ってもらいたいですか。
大賀:自分が住んでいる広島の枠にとらわれずに、広島以外だったらどうだろう、世界はどうなんだろうと、広く見ていくこと、決めつけないことじゃないかなと思います。
テレビ新広島のアルバイトで、人が行けないような場所にたくさん行くことができたのは、とてもいい経験でした。原爆ドームの中に入って撮影したり、当時まだ未公開だったレストハウスの地下に初めてカメラマンと一緒に入ったりしたこともありました。初めて見るものや、その場で感じた空気に刺激を受け、そういう経験がニュースの現場でいろんなことに揉まれるという今の仕事につながっているのかもしれないですね。
また、他の大学の人たちと平和に関する国際会議を作るサークルに入った時もありましたが、同い年で真面目に平和のことや世界のことを考えている仲間がいて、「俺が考えていることはちっぽけだな」と思う時もありました。広島にいるだけでも見ることができること、感じられることがたくさんあると思います。
今から振り返ると、お金がなくても、もっと旅に出ればよかったと思います。旅に出ると価値観が変わります。日本にいれば赤信号を渡っちゃいけないのが常識ですが、海外に行けば渡る人もいるだろうし、危なくなきゃいいじゃんという考え方もある。こういうやり方があるのか、とか、こんなんで済ましちゃう時もあるんだなとか、そういう気づきがあります。
人との出会いも大きいと思いますので、同じ大学の人とずっと一緒にいるだけではすごくもったいないので、たくさん交流して、「こんな人もいるんだ」と知るだけでとても価値があると思います。


 Home
Home