取材日:2025年2月20日

人間社会科学研究科の堀田実杜さんにお話を伺いました。
堀田さんは、令和4年8月に広島大学女性科学技術フェローシップ制度の理工系女性M2奨学生に採用され、令和5年度からは理工系女性リサーチフェローとして支援を受けています。また、令和7年度からは、日本学術振興会の特別研究員に内定されています。
今回は、堀田さんに、博士課程後期で実施している研究や生活の様子など、様々なお話を伺ってきました。(記載の情報は取材時点のものです。)
博士課程後期の研究内容について
堀田さんの研究内容について教えてください!
熱分析分野の基礎的研究と、主に高等学校化学で用いる教材開発を目指す化学教育分野の研究を行っています。基礎的研究により得られた知見を基にして、教材開発を行うことを目指していて、現在は、環境問題の解決策として注目されている科学技術の中で「Ca-loopingシステム」に着目し、実用化に向けた基礎的研究と、教材化に向けた教育研究を行っています。
「Ca-loopingシステム」とは、炭酸カルシウムの熱分解と酸化カルシウムの炭酸化の可逆反応を、エネルギー貯蓄技術と二酸化炭素吸着・分離技術に活用することによって、エネルギーの効率的利用と温室効果ガス削減の両面に役立てることが期待される技術です。炭酸カルシウムは貝殻や鉱物などとして地球上にありふれた素材であること、理論的には有害ガスを発生することなく繰り返しエネルギー貯蓄に利用できる点で優れた科学技術であると言えますが、一方で、実際には繰り返し利用すると効率が低下する現象が確認されており、実用化に向けては関係する化学反応の特徴をより詳細に明らかにする必要があります。
私の研究室では、熱重量測定という加熱による試料の質量変化を測定する手法によって反応速度データを取得し、速度式に基づき解析することで固体の反応挙動の詳細を明らかにする研究を行っています。私はこれまで、炭酸カルシウムの熱分解と酸化カルシウムの炭酸化をはじめとした気体-固体系の可逆反応について、反応温度や気体雰囲気条件による反応経路や反応速度の変化の特徴を調べてきました。また、反応速度の変化の様子と、反応による試料の形態変化の観察結果から、試料の表面での反応と内部での反応を区別して扱い、それぞれの熱力学的及び速度論的特徴を調査しました。さらに、反応進行に伴う反応速度の変化を、反応の進行度、反応温度、及び反応雰囲気中に含まれる気体分圧の関数として表すことにより、多様な条件下での反応挙動を予測することを可能にしてきています。
これらの成果により明らかになった反応の熱力学的及び速度論的特徴は、実験教材を開発する上での実験条件の決定にも役立つものです。「Ca-loopingシステム」を理解し探究するためには、反応速度、熱化学、及び化学平衡の内容を結びつけて理解する必要があります。そこで、このうち熱化学と化学平衡を結びつけて理解することを目指した高校化学の教材として、硫酸の酸解離を素材とした学習プログラムの開発と教育実践を行いました。また現在は、基礎研究の成果を基に、固体と気体の関与する可逆反応の特徴を探究するための実験教材の開発に向けて、試行錯誤しているところです。
このテーマを選ばれた背景を教えてください。
高校3年まで苦手だった物理が、ある先生との出会いをきっかけに好きになったという経験があり、それで一時は教員の道を志していました。そうした理由から教育研究もやってみたいと思っていたこと、高校で選択していた物理や化学分野での研究を希望していたことなどの理由で、物理化学分野の基礎的研究と化学教育研究を両立している今の研究室を選択しました。そして先輩が行っていた鉱物や貝殻などの自然由来の炭酸カルシウムの熱分解反応について基礎的研究の手伝いをする過程で、指導教員から「Ca-loopingシステム」についての話を聞き、その実用化に向けた基礎的研究と、教材の素材として活用する教育研究の着想を得て、研究テーマとしました。この分野では基礎的研究と教育研究をリンクさせて進めるということがまだあまり盛んではないので、そこを担っていけたら良いと思っています。
研究の面白さについて教えてください。
実験で得られたデータを解析してみたら、きちんと予想通り直線に乗ったり、文献値と合ったときなどは、達成感があります。また、学会発表などの場で他の研究者や学生と議論したり、コメントをもらったりするときも楽しいなと感じます。
それから出張授業です。今年も高校に出張授業に行ったのですが、実験の経験があまりない高校生たちにも、実験が楽しかったと言ってもらえたのは、とても嬉しかったです。


堀田さんが研究を行う様子
博士課程後期の生活について
毎日のスケジュールについて教えてください。
朝は10時頃に研究室に来て、帰るのは18時頃です。夜、解析や資料作成などの作業を自宅で行います。週に1回、研究室全体で進捗報告を行っていて、それ以外に週に1〜2回、個別に指導教員と面談し、研究の相談などをしています。
熱重量測定は条件にもよりますが、1時間から長くて20時間程度必要で、測定を待っている間に他の作業や解析を進めるという流れです。必要に応じて電子顕微鏡での試料の観察や、X線解析、赤外分光法などの装置を使った実験を並行して行っています。
教材系の研究では、どういう条件で実験を行ったら期待どおりのデータが得られるのかを考察したり、理科室にあるような器具で期待どおりの実験結果が得られる条件は何かを模索しながら実験を行います。その上で授業の流れを考えてワークシートやPowerPointの資料を作成し、今のところは大学生を相手に授業を行ってみて、どれだけ理解できたか、実験がうまく行ったかを評価しています。
気分転換はどうされていますか?
実験や研究が行き詰まったときは、たまに一人でカラオケに行ったりしますが、モチベーションが上がらない場合は、あまり頭を使わなくてもできる解析をしたりしています。それに、博士課程前期まで一緒だった他の研究室のメンバーと会うと、モチベーションが上がります。
趣味はピアノや登山、ゲームですが、最近あまり時間がとれていません。休日は家族や友人とショッピングに行ったり、家でのんびり過ごしています。また、ここ最近は手芸に興味があって、まとまった時間があれば縫物や編み物をしています。
研究室の雰囲気はどんな感じですか?
構成としては学部3年が3人、4年が4人、博士課程前期1年が1人、2年が2人で、博士課程後期は私だけです。私の研究室は、基本的には先輩が後輩を指導するスタイルで、今は私が一番上なので、後輩に教えたりすることもあります。
博士課程後期への進学について
博士課程後期への進学を決めたきっかけを教えてください。
親も研究者で、周りに研究者がいるという環境だったこともあり、元々漠然と研究職に対して興味や憧れはあったのですが、博士課程前期2年の春までは博士課程前期を修了したら就職するつもりでいました。しかし、当時進めていた研究が修了までに満足な形で終わりそうになかったことや、指導教員の勧めもあり、6月には進学を決意しました。経済的不安が大きかったので、女性科学技術フェローシップ制度の存在も進学を決めた理由の1つです。
進学について、不安はありましたか?
親は、研究者として実情を知っているがゆえに、あまり賛成してはいませんでした。それに先ほど言ったとおり、経済的な面でも不安がありました。それでも、自分が高校の先生だったとして、教え子から「博士課程後期に進学する」と言われたら羨ましく感じるだろうなと思い、進学しようという気持ちになりました。挑戦しなかったことを後悔したくはなかったということです。
将来のキャリアパスについて
将来はどのようなキャリアパスを考えていますか?
できればアカデミアで今までやってきた理科教育と基礎的研究を継続してやっていけたらいいなと思っています。企業への就職も考えましたが、私の場合は教育にも携わりたいので、そうなると大学が候補になるのかなと思います。
女性科学技術フェローシップ制度について
女性科学技術フェローシップ制度に採択されるまでの準備について教えてください。
博士課程後期に進学すると決めたのが遅かったため、学振のDC1の募集期限はもう過ぎていました。そうなると女性科学技術フェローシップ制度が最有力なので、申請書の作成はかなり頑張った記憶があります。幸い論文は幾つか執筆していたので、申請書に力を入れました。
(注:堀田さんが女性科学技術フェローシップ制度に応募された時の応募締切は、博士課程前期2年の6月でした。)
女性科学技術フェローシップ制度についてコメントがあれば、お聞かせください。
博士課程後期に進む場合、経済的自立が必要だったため、この制度がなければ進学はもっと迷ったと思います。生活費や授業料に充てられる研究専念支援金はもちろんですが、研究費が支給されるのはとてもありがたく感じました。特に昨年度、研究費を利用して海外での国際学会に参加できたことはとても刺激になり、貴重な経験でした。
後は、制度について目に触れる機会がもっとあれば良いなと思うことはあります。これまで何度か研究内容を発表する機会がありましたが、フェローシップ採用者以外の参加が少なく、発表している内容が外部へ発信できているかは分からないなと感じました。
理工系に進学する女性を増やすために思うことはありますか?
私は高校時代から周りに理系の女子が多かったので、あまり感じなかったのですが、実際学会に行ってみると女性の数は少ないです。やはり女性の数が少ないところに乗り込んでいくのはハードルが高いと思うので、今いる女性がもっと活躍をアピールすれば、少しはそのハードルを下げることができるのかも知れません。
博士課程後期を目指す学生へのメッセージ
もし学部生の自分にアドバイスができるとしたら、どんなことを伝えますか?
私は学部3年ぐらいまでは物理を専門にしようと思っていて、物理の研究室にも行ったのですが、基礎研究がしたくて今の研究室に移ってきました。今振り返ると、物理というひとつに縛られることなく、もっと視野を広げて色々勉強しておけば良かったと思っています。
それから英語を使う機会が想像以上に多いので、英語はもっと勉強しておくべきでした。例えば国際学会に参加する際、発表する内容は事前に英語で準備ができますが、それ以外の会話になると上手くコミュニケーションが取れず悔しい思いをすることも多いです。
最後に、博士課程後期を目指す学生たちにメッセージをお願いします!
進学にあたって能力という点を気にすることもあるかと思いますが、成長したいという気持ちがあれば、いずれ力は付いてくるので、今の能力はあまり気にしなくてもよいと思います。
それに博士課程で研究を続けていると世界が広がります。私の場合は、それまであまり海外に行ったことはなかったのですが、学会という場所に足を運ぶ機会ができ、海外で色々な人に出会えたことが、研究を頑張ろうと思うきっかけのひとつになりました。誰も未来を見通すことはできないので、進学したいという強い気持ちがあるのなら、あまり悲観的に考えず挑戦しても良いのではないかと思います。
取材者感想
「博士課程に進学する際に抱いておられた正直なお気持ちから、普段の研究での楽しさまで様々なお話をしてくださいました。特に、基礎研究と教育研究を並行して行われている堀田さんの研究者としてのタフネスや、並大抵ではない研究に対する熱意を感じました。日本社会の未来を担う両翼である「科学」、「教育」に貢献されている堀田さんの、ますますのご活躍をお祈り申し上げます。」(先進理工系科学研究科 量子物質科学プログラム 博士課程前期2年・横山貴之さん)
「堀田さんは基礎研究に取り組みながら、そこで得た知見を活かして教材開発にも携わるという、“二足の草鞋”で活躍されている姿が非常に印象的で、興味深く感じました。進学に対して不安を抱えながらも、自身の研究に強い関心を持ち、熱心に取り組まれている姿がとても素敵だと思います。この先、決して楽な道ではないかもしれませんが、堀田さんがさらに活躍される日を楽しみにしています。」(先進理工系科学研究科 応用化学プログラム 博士課程前期1年・山口龍一さん)
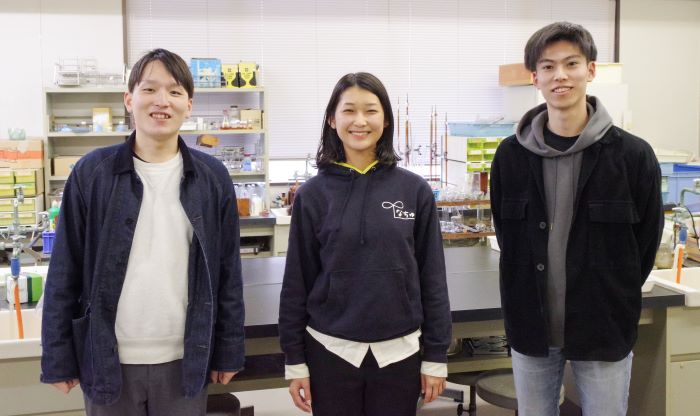
左から横山さん、堀田さん、山口さん

 Home
Home