取材日:2025年2月3日

先進理工系科学研究科の木戸理歩さんにお話を伺いました。
木戸さんは、令和5年8月に広島大学女性科学技術フェローシップ制度の理工系女性M2奨学生に採用され、令和6年度からは理工系女性リサーチフェローとして支援を受けています。また、令和7年度からは、日本学術振興会の特別研究員に内定されています。
今回は、木戸さんに、博士課程後期で実施している研究や生活の様子など、様々なお話を伺ってきました。(記載の情報は取材時点のものです。)
博士課程後期の研究内容について
木戸さんの研究内容について教えてください!
昨今の気候変動で雨が増えている現状において、豪雨が起きた際、山地からどれくらいのサイズの土砂が、どの程度の量で流れ出るかをシミュレーションしています。具体的には土砂の流れをパソコン上で解析するのが主ですが、実際に山地に行き、含水率の計測などで風化の状況を調査することもあります。
現在は豪雨対策としては水についてのみスポットが当てられますが、実際には土砂の動きや量も大きな影響を及ぼします。それについて明らかにすることで、河川の氾濫防止や安全な避難経路の提案に役立つことが期待できます。
このテーマを選ばれた背景を教えてください。
高校では物理を選択しており、3年生で将来の進路を考えたときに理学部と工学部を比較して、より社会の身近なところで役に立ちそうな工学部に進学することにしました。物理を選択していましたが、自然系も好きだったので、工学部で自然系のことが学べそうな社会基盤の分野を選びました。さらに私は、光や波、温度など、自分で見たり感じたりすることのできる自然現象に対しても興味を持っていたため、コンクリートや地盤、交通系など様々な研究対象がある中でも、自然現象を数式で表す水工学に魅力を感じて今の研究室に入ることにしました。
当初は災害時の避難に関するシミュレーションにも惹かれましたが、同時に世界的な気候変動も話題になっていたテーマだったので、興味を持ち、こちらを研究することにしました。
研究の面白さ、苦労について教えてください。
研究していて新しい発見があると、やはり嬉しいです。もちろん気候変動に関することというのは将来的な予測になるので、間違いのない正解があるわけではありませんが、説得力のある根拠に基づいた予測というものはあります。そういった結果が導き出せたときは楽しいです。あとは学会などで発表する内容について、しっかりしたストーリーで組み立てることができたときは達成感があります。
逆にこのテーマで研究をしている人が周囲におらず、悩んだときにも自力で調べるなどして解決しなければならないことには少し苦労を感じています。
D1の9月に短期の海外留学に行かれたとお聞きしました。
指導教員がアメリカに半年間留学されることになり、私も1か月だけ行くことができました。留学先はテキサス大学で、私が進めていた研究と同様の研究に先方の先生も携わっておられ、詰めの段階をディスカッションしながら協力して行いました。帰国後も共同で論文に仕上げたのですが、ネイティブのアメリカ英語は話すスピードが速く、ヒアリングに苦労した思い出があります。
加えて、アメリカの学生は研究への向き合い方が日本よりもアグレッシブで、発言も積極的。ゼミの中も、教員が一方的に話すのではなく、学生同士がアドバイスし合えている雰囲気がありました。そんな研究への姿勢を感じることができたのはプラスになりましたし、今後に繋がる良い縁を作ることができました。
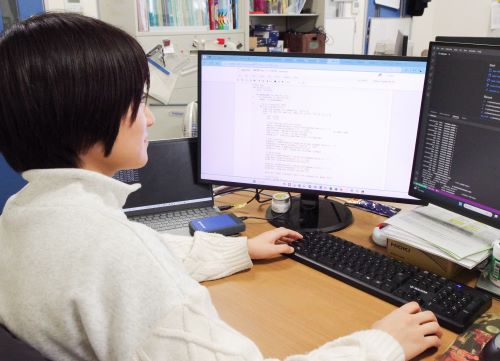

木戸さんが研究を行う様子
博士課程後期の生活について
毎日のスケジュールについて教えてください。
朝は9時に研究室に来て、午前中は自分の研究をして、午後からは後輩の指導も並行して行います。帰るのは19時台が多いです。また、週1回ほどのペースでゼミの発表会があります。
気分転換はどうされていますか?
切り替えが大事だと思っているので、深夜や休日に長く研究室に残ることはなるべくしないで、研究のことは一度忘れ、リセットするように心がけています。以前はヨット部に所属していたので、その繋がりで社会人クラブに入っていて、休日にヨットのレースに参加したりすることもあります。ヨットは冬でも乗りますが、ものすごくリフレッシュできます。他にも友人と遊びに行ったり、旅行に出かけるなど、家の中より外で活動することが多いです。
研究室の雰囲気はどんな感じですか?
構成としては教員が2人で、日本人学生は、博士課程後期が2人、博士課程前期2年が4人、1年が7人、学部4年が7人、留学生が9人です。人数が多いので、各々が課題を抱えたりしたときは、まず先輩が相談に乗り、それでも解決しない場合は教員の指導を仰ぐという流れです。最近になって後輩の学生が増えたので、卒論シーズンは指導も忙しくなります。また、留学生とのコミュニケーションは基本、英語で行うため、頑張って英語を話していたら、だんだん慣れてきました。
博士課程後期への進学について
博士課程後期への進学を決めたきっかけを教えてください。
博士課程前期1年の終わりくらいまでは就職を考えていて活動もしていましたが、その頃に指導教員に博士課程後期進学という選択肢を提案されました。指導教員は、社会人を経てから博士を取られたので、ご自身の経験から、今の段階で博士を取っておいた方が後々の選択肢が広がるというようなアドバイスをしていただきました。研究も楽しくやっていましたし、経済的な面でも女性科学技術フェローシップなどの支援の制度があったため、それなら今のうち挑戦しようと思い、博士課程後期への進学を決めました。
家族からも、経済的な面が自分で何とかなるのであれば、好きにしていいよと言われていました。
進学について、不安はありましたか?
この職に就きたいというような目標があって進学を決めたわけではなかったので、博士課程後期の3年間を自分にとって意味あるものにできるのか、就職した方がよかったと思ってしまわないか、という不安はありました。経済的な部分は女性科学技術フェローシップ制度のおかげで不安なく過ごせています。
将来のキャリアパスについて
将来はどのようなキャリアパスを考えていますか?
社会基盤分野の卒業生は、学部・修士だと公務員、建設コンサルタント、ゼネコン、公共インフラ系への就職が多く、博士だと大学教員、研究所、建設コンサルタントの開発系が主な就職先となります。私は研究を続けたいと思っているので、大学や高等専門学校を中心に模索しています。また地元志向でもあるので、可能であれば大分に戻り、博士課程で得たスキルを防災の分野で活かすことができれば、と思っています。
女性科学技術フェローシップ制度について
女性科学技術フェローシップ制度に採択されるまでの準備について教えてください。
指導教員から博士課程後期への進学を勧められたのと同じ時期に、この制度についても教えてもらいました。学振の申請書とほぼ同じ内容でしたので、両方の準備をして申請しました。
学振の場合も同様ですが、審査員と自分が専門とする研究分野が同じとは限らないので、専門でない人に対して自分の研究内容をいかに分かりやすく伝えるか、という視点を重視して書類を作成しました。
女性科学技術フェローシップ制度についてコメントがあれば、お聞かせください。
この制度がなかったら経済的に苦しかったと思うので、博士課程後期への進学はしなかったかもしれません。また、博士課程前期2年から採用され、博士課程後期進学後の支援も決まっているのは、とても安心感がありました。
理工系に進学する女性を増やすために思うことはありますか?
アメリカの大学に行ったときには、工学部系の研究室でも、女性が半分くらいの比率だという印象でした。それを考えると日本の理工系分野において女性はやはり少ないと思います。高校の段階から既に理系に進む女子が少ないので、博士課程にまで進むとなるとなおさらです。その意味では、女性科学技術フェローシップのような制度は、博士課程進学を迷っている女性を後押しできているのではと感じます。
博士課程後期を目指す学生へのメッセージ
学部生にアドバイスするとしたら、どんなことを伝えますか?
勉強にしろ、サークル活動にしろ、アルバイトにしろ、時間を無駄にせず行動することが良い大学生活に繋がると思います。大学生活は勉強だけではないと思うので、色々なことに挑戦してください。
最後に、博士課程後期を目指す学生たちにメッセージをお願いします!
博士課程後期進学は、自身の専門色を強めていく進路であり、周囲に同じような人生を歩んでいる人は少ないと思います。そこで自分の軸があれば、迷うことも少なくなる。こだわりをひとつ決めたら、楽になるんじゃないか、と母親に言われたことがあり、確かになあと。自分が納得できる選択ができればそれが一番だと思います。
取材者感想
「ご自身の研究内容である土砂について丁寧にご説明頂き、災害から安全な暮らしを守る重要な基礎研究をされていることに敬服致しました。また、研究内容のみならず日々の研究生活や趣味のヨットについてもお話頂き、特に、将来のキャリアや研究に対する堂々とした向き合い方には心を打たれました。研究者としての木戸さんの今後のさらなるご活躍をお祈りします。」(先進理工系科学研究科 量子物質科学プログラム 博士課程前期2年・横山貴之さん)
「シミュレーションによって豪雨時に山地から流れ出る土砂の量を調べる研究は、災害大国である日本の防災に貢献するかもしれない素晴らしい内容だと思いました。また、私生活でもアクティブに過ごされている印象を受け、その活気ある姿がとても魅力的でした。博士課程後期で研究に励まれている姿勢に感銘を受け、今後のさらなるご活躍を陰ながら応援したいと思います。」(先進理工系科学研究科 応用化学プログラム 博士課程前期1年・山口龍一さん)
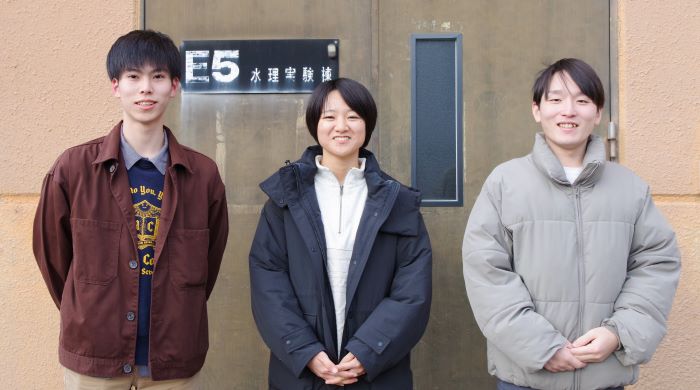
左から山口さん、木戸さん、横山さん

 Home
Home