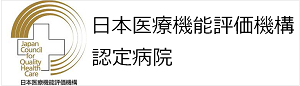広島大学病院に、高精度の撮影ができるキヤノンメディカルシステムズの次世代コンピュータ断層撮影装置(PCD CT)が導入されました。被ばく線量を低く抑えられるうえ、従来のCTでは困難だった腫瘍の境界や、動脈にできたこぶと腫瘍の鑑別などがしやすく、診断精度が向上しました。臨床での使用が可能なプロトタイプで、2年先をめどに製品化が進められており、導入は世界で3台目です。
CTはX線を使って人体の断面を画像化(輪切り)して体内の様子を立体的に把握でき、病気の広がりや治療効果の判定などに使う医療技術です。従来のCTはX線をいったん光に、さらに電気信号に変換して画像を取得するのに対し、PCD CTは検出器に半導体を用いることで、X線を直接電気信号に変換でき、より小さな部位や病変と非病変部の違いを際立たせることができます。また、放射線被ばく線量は、臓器により従来のCTの3~9割の低減が見込まれます。
広島大学病院では2024年4月に導入し、これまでに成人約100人の患者さんを診断しました。膝関節を撮影した画像では、骨内の微細な構造が明瞭に描出されたほか、小さな血管との連続性が確認でき、腫瘍性の病変と判別しづらかった症例を動脈瘤と診断できたケースがありました。
今後は、患者さんの負担をより軽減しながら、高い診断精度を実現していく考えです。広島大学大学院医系科学研究科放射線診断学の粟井和夫教授は「診断が難しい肝臓や膵臓の腫瘍、神経への浸潤、小さいリンパ節への転移などが検出できるよう期待している」と話しています。


 Home
Home