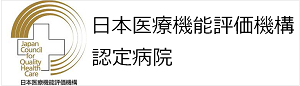気管支喘息
疾患について
気管支喘息とは、ダニやカビなどの環境アレルゲンやその他様々な危険因子が原因となって、気道(呼吸をするときの空気の通り道)に慢性のアレルギー性の炎症を生じ、気道の平滑筋が増大・収縮して気道が狭くなり、咳や喘鳴(ゼーゼーヒューヒュー)、息苦しさを繰り返し生じる呼吸器系の病気です。狭くなった気道は、自然にあるいは治療によってある程度は元の状態に回復しますが(これを可逆性と言います)、治療をせずに放置したり自己判断で治療を中断すると気道の炎症が持続して気道の構造が変化し、元の状態に回復しなくなってしまいます。そうなると治療への反応が悪くなるため、喘息症状はより生じやすくなり重症化してしまいます。早期に適切な診断を受けて吸入ステロイド等の長期管理薬を開始して気道の炎症を抑えこみ、症状がおさまっても治療を継続することが重要です。
診断について
症状や各種検査の結果によって総合的に診断します。
- 症状・・・咳、喘鳴、息切れなど
- 検査・・・呼気NO(一酸化窒素)検査、肺機能検査、気道抵抗検査、気道可逆性検査、気道過敏性検査、ピークフロー値測定、血液検査(末梢血好酸球数、非特異的IgE、特異的IgE)、誘発喀痰検査など
治療について
常日頃の症状をコントロールする長期管理薬、喘息発作をしずめる発作治療薬があります。
発作治療薬としては、吸入短時間作用型β2刺激薬、内服・点滴のステロイド薬などを用います。
長期管理薬としては、気道の炎症を抑える作用が強い吸入ステロイド薬が基本であり、それに加えて重症度に応じて、狭くなった気道を拡げる気管支拡張薬(長時間作用型β2刺激薬、徐放性テオフィリン薬)やロイコトリエン受容体拮抗薬などを併せて服用していきます。
重症例では、喘息の病態に大きく関わる分子(IgE、IL-5、IL-4、IL-13、TSLP)を標的とした生物学的製剤(抗体治療薬:ゾレア®、ヌーカラ®、ファセンラ®、デュピクセント®、テゼスパイア®)が近年使用可能となり、これらの生物学的製剤は2週間~2ヶ月毎に皮下注射を行うことで効果を発揮します。
最後に
気管支喘息で重要なことは、早期に適切な診断を受けて吸入ステロイド等の長期管理薬を継続することです。そのような治療でも症状が治まらない場合は専門施設での精密検査や治療をお勧め致します。

 Home
Home