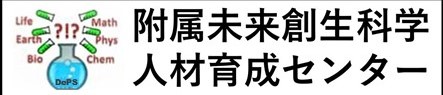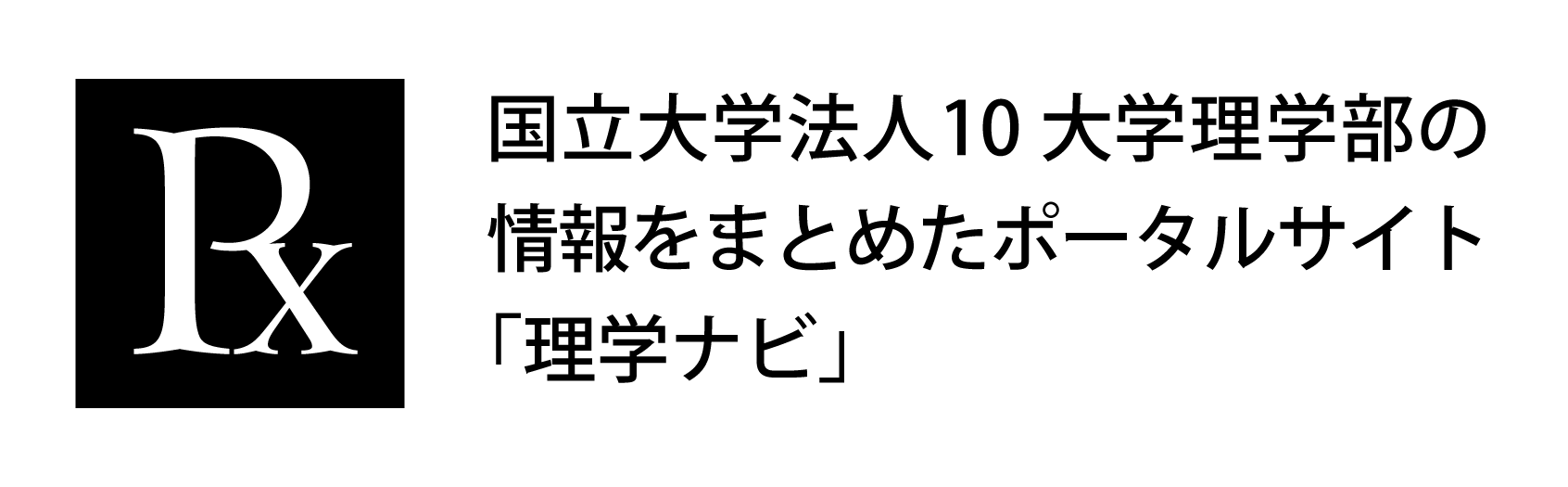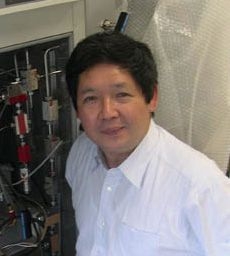
広島から世界へ
氏名:嶋本 利彦
専攻:地球惑星システム学専攻
職名:教授
専門分野:構造地質学、岩石レオロジー
略歴:生まれは現在の広島市安佐北区でカープファン。1969年広島大学理学部卒(地学科)、同大学院博士課程3年時にテキサスA&M大学に留学、1977年に同大学でPh. D.取得。1977~1989年広島大学理学部(助手、助教授)、1989~1998年東京大学地震研究所(助教授、教授)、1998~2007年京都大学大学院理学研究科(教授)、2007年より母校に戻って現職。この間、テキサスA&M大学(PD, 客員助教授)、オーストラリアCSIRO(訪問研究員)で研究生活。日本地質学会賞受賞。
「君に青春があったか」と聞かれると、私はためらわず「あった」と答える。テキサスA&M大学大学院博士課程に留学した4年間である。27~31歳のおくれた青春であった。私は広島大学出身で、大学院博士課程で学位論文を書けばよいところまできていたが、学位を終わっても就職のあてが全くなかった。最後の賭だと思って留学したのは27才の時、片道切符と2ヶ月の生活費をもって覚悟の渡米であった。結局私はこの大学でPh. D.を得て、日・米の大学院にほぼ同期間在籍することになった。その後私は、広島で11年余り、東京で9年余り、京都で9年間勤めて2年前に母校に戻り、来年(2010年)3月に停年を迎える。テキサスでの大学院時代は、私のこれまでの人生の中で全く悔いのない唯一の時期である。限界に近いほど勉学と研究に打ち込み、週末に1日ほど思い切り楽しんだ。振り返ってみて、自分の研究の基盤を作ったのはテキサスでの4年間だったなと思う。
幅広い米国の大学院教育
留学先は構造物理学研究所(Center for Tectonophysics)で、フィールド・実験・理論を融合して地球のテクトニクスの研究を推進していた。所長のJ. W. HandinはD. T. Griggsとともの戦後実験岩石力学の研究を主導してきた方である。研究所が創設されて10年たらず、私が滞在した時期は研究所がもっとも活気に満ちた時期だった。
米国の大学院で印象に残るのは、非常に充実した大学院カリキュラムである。必修科目はせいぜい4~5科目と少なく、他の課目はアドバイザーと相談して院生の個性と研究目標に合わせて決められている。院生の受ける授業課目は様々であり、このことは多様な人材を生み出すのに非常に役立っている。私はコアコース4科目を含めて地球科学の講義を6科目、理工系数学の講義を4科目、弾性論・塑性論・粘弾性論など材料科学の講義を6科目受けた。講義で単位を取るのは楽ではなかった。渡米直後に受けた理工系学生のための数学の講義では、1学期に200頁前後の問題集を3冊勉強させられ、毎週1回試験をやられた。地球科学の講義では毎週30~50頁の論文とか教科書を読まされ、期末試験もきちんとやられた。これらの講義を通じて得た理工系にまたがる幅広い知識が、その後私が研究を進める基盤となった。それにしても、アドバイザーの故・M. Friedman教授は、私が希望したとはいえ、他分野の講義をよくあれほど勧めて下さったものである。
私は広島大学での院生時代から地質構造の形成機構をモデリングで解く研究をおこなっていた。渡米2年目には航空工学のStricklin教授の非線形有限要素法に関するプロジェクトに参加する機会を得た。カリフォルニア大学バークレー校が開発したNONSAPという大型ソフトを、岩石と土に使えるように拡張したいとのことであった。私はソースプログラムが手にはいるので狂喜したが、組み込むように言われた岩石の非弾性変形を記述する応力と歪の関係がなぜ成立するかがわからなかった。私は教授にお願いして塑性論が岩石に対して成立するかどうか検証する仕事をさせていただき、結局プログラムは1行も書かないで終わった(結果は要・修正)。1年後に”I am satisfied with your work.”と言っていただいたが、これを契機に岩石の性質を仮定したモデリングに意味があるとは思えなくなった。そうして、J. M. Logan教授のもとで地震の発生機構の解明を目的として「断層の力学」の実験的研究を始めた。29才の時であったが、これが私の一生の研究テーマになった。周囲は驚いたが、私には納得の決断であった。また、テキサスの4年間で研究分野の垣根が私の意識から消えた。
研究の戦略:広島から東京へ
学位を終えて私は運良く広島大学に助手として採用していただいた。テキサスでは様々な分野の勉強をしてすごい研究をする人がいることを痛感していたので、3年くらい、その連中とどう競争するか考え続けた。彼らになくて私にあるものは何か?それは、広島大学で鍛えてもらったフィールドの経験だと気づいた。そうして、「フィールドで着想を得て、実験でそれを調べる研究をしよう」と決めた。フィールドと実験の融合は簡単に見えて、変形の分野でそれを実行している人は現在でも非常に少ない。
1983年にテキサスA&M大学に3度目の滞在をする機会があった。到着するとLogan教授が、「客員助教授にしてやるから、大学院の特別講義をしろ」と言う。ためらいながらも逃げるのは嫌だから私は引き受けた。そして、研究戦略を3年間考えていたおかげで、講義の指針で迷うことはなかった。断層・変形実験・地震の論文を読みあさり、今後何を研究するべきかを講義した。シュードタキライトという摩擦溶融でできる岩石があること、地震時の断層運動が実験では全く再現できていないことを知ったのはこの時である。地震性断層運動を再現する高速摩擦実験は私のライフワークとなった。停年間際になって振り返ると、私はこの講義でリストアップした未解決問題の半部も終わることができなかったな、というのが正直な印象である。
広島大学に世界をリードできるラボを作りたいというのが当時の夢であったが、研究費がとれなかった。しかし夢は地震研究所に移って実現した。兵庫県南部地震など、悲惨な3つの地震被害調査などに追われながらも、研究費には恵まれて6台の試験機を製作できた。テキサス・広島でリストアップした未解決問題を解くには、それだけ必要だった。地震を再現する高速摩擦試験機は外国にもないものだった。地震研は私の夢をかなえてくれたが、学生が少なかった。
教育上の戦略:実りあった京都時代
私は次世代を担う学生を求めて京都大学に移った。その頃、欧米と一人でどう競争するかを本気で考えた。そして考えついたのが、試験機の開発と国際化である。変形試験機は需要がすくないために地球科学で役立つ市販の試験機はほとんどない。従って研究者が試験機メーカーと共同で開発するしかないのだが、欧米では試験機が開発できる若手を育ててはいない(現在でも)。私は、実験岩石力学の講義で試験機の設計方法を教え、外部用には「試験機設計セミナー」を始めた。もうひとつの「国際化」は、地理的に孤立した日本人が世界と競争する上では不可欠に思えた。
効果は絶大であった。私の研究室にきた院生のほとんどは試験機の設計ができるようになった。研究室には外国人特別研究員か留学生が切れ目なく滞在していたし、年間に10名近い訪問研究者がいて、セミナーは常に英語でおこなった。1~2年で院生全員が英語での発表と議論に困らなくなった。2008年の米国地物連合の会議で、私のところにいた人たち約20名が集まって食事をしてくれたそうである。日本人と外国人がほぼ半々で、彼らが今後連携して研究を進めてくれることを期待したい。
再び広島に戻って
停年まで3年になって、私は母校に戻る機会を与えていただいた。これによって、試験機を3機関に配分することもできた。広島に4台もってきて、「広島にラボをつくる」という願いは30年近くたって実現した。母校でどうしても実現したかったのは、(1)大学院教育の大幅な拡充と(2)国際化であった。私は推進者ではなかったが、どちらも大学院教育プログラム「世界レベルのジオエキスパート」として実現していただいた。それが定着することを心から願っている。
実は京都大学の大学院教育委員会で、国際化を推進するために英語の授業を導入するべきであると提案したことがある。副学長クラスの方から「英語の講義は京大生には無理だ」とたちどころに反論された。自分の研究室での経験から環境さえ整えれば誰でも英語での講義などについていけることはわかっていたから、私は反論したかった。しかし広島に戻ることが決まっていたから、それなら広島でやってやろうと思って黙った。
広島での学生の反応はどうであったか。最初の授業評価は散々だった。ゴアの「不都合の真実」の映画をみて英語の講義を聴く訓練をした講義に対しては、「これを講義と呼ぶなら他の多くの素晴らしい講義はなんと呼べばよいのか」と書いた学生もいた。英語の大学院講義に対しては、「英語を教えたいのか、専門を教えたいのかわからない」と書かれた。その一方で、私の研究室の院生は多数の外国人訪問者とつきあって、英語での発表と議論にはほとんど抵抗がなくなった。2年目、3年目の学部生の反応も全く違ってきた。とくに進級論文の調査指導では、4名の学生と自然の中で話ができて本当に楽しかった。私は今では、すべての広大生が英語で講義を聴き、世界の人たちと国際舞台でいっしょに仕事をするポテンシャルをもっていると確信している。
この長い「軌跡」をここまで読んで下さった学生の人たち、ぜひ英語を習得して国際的視野を養っていただきたいと思う。それは、国際化社会でビジネスをおこなう上でも、地球環境のような困難な問題に世界と強調して取り組むためにも必要なことなのだ。

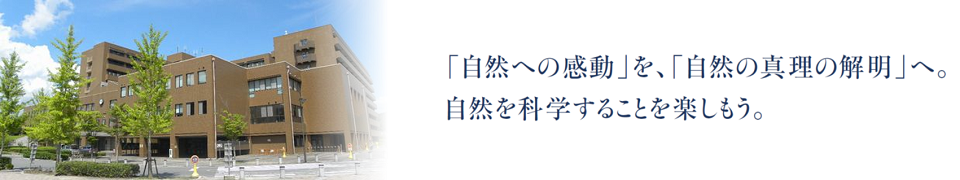
 Home
Home