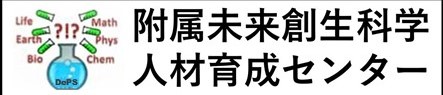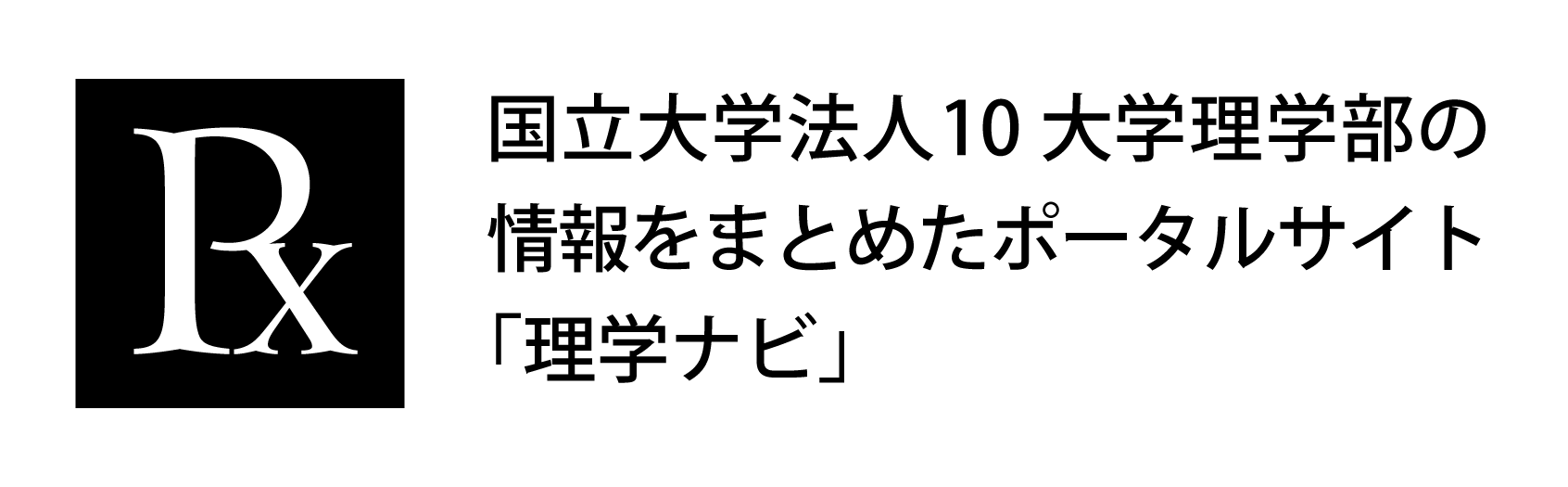私の研究者人生:渡邉 洵(地球惑星システム学専攻)
氏名:渡邉 洵
専攻:地球惑星システム学専攻
職階:教授
広報委員会から、このような題で、しかも若い人達にいい意味での刺激を与えるような文章を書くように、という依頼を受けた時には、正直のところ困ったことになったなあと思いつつ、ともあれ、ご要望に沿うたものになるかどうかは別として、これまでの私の「研究者人生」というものを振り返ってみたいと思います。
先ず、私の専門分野について簡単にご紹介いたします。
それは鉱床学(最近では資源地質学とか地球資源学などとも呼ばれています)といい、地球科学の一分野を占めています。さて、鉱床学は、金属資源ならびに非金属資源(資源のことを鉱床ともいいます)を研究対象とし、それら鉱床の生成プロセス、即ち、元素・物質の移動・濃集・固定のプロセスを明らかにしようとするものです。最近では、鉱床の生成プロセスについて熱力学データを駆使してシミユレーションしたり、さらには鉱山の開発が終了した後の環境汚染と関連させて、鉱床を構成していた元素・物質の分散という環境化学的な観点からも研究されています。
ついでにいえば、日本の鉱床学の現状は、国の文教政策を反映してか、残念ながら鉱床学研究室が大幅に縮小されています。具体的に分かりやすい数字で示しますと、30年前と現在の鉱床学の教授の数で見るとほぼ1/5に減少しています。この間、この状況を変えようと私共鉱床学研究者は「資源地質学会」等を通してそれなりに努力してきたつもりですが、悲しいかな、私共の力不足も否めません。ところが、海外の有力大学に目を転じると、そこでは決してそのような状況には無く、基礎分野として他の分野と同じように、重要な位置を占めています。その違いが生じたのは、資源立国であるか否かに係わらず、伝統に裏付けられた各学問分野の調和的発展を重視しているか否かによるものと思われます。
前置きが長くなりましたが、この辺で本論に戻りたいと思います。卒業論文では、杉浦精治先生のご指導のもとで、十和田湖のすぐ北東にある八甲田山の南麓に位置する「上北鉱山」の鉱床を研究対象としました。ここの鉱床は、所謂「黒鉱鉱床」と呼ばれる範疇に入るものでした。ここに春・夏・秋併せて3ヶ月近く滞在し、月の輪熊を気にしながら、山深い鉱山の周辺を踏査したり、朝から夕方まで坑内に入って調査したり、サンプリングする毎日は大変でしたが、それなりにとても充実したものでした。キスリング・タイプのザックに沢山の試料を詰め込み、それを背負って坑外に出た時の開放感は、言葉には尽くし難いものがあります。何しろ鉱石試料は、その比重が普通の岩石の倍以上ありますので、ザック一つでも30〜40kgにもなります。長期にわたってこのような体験をしたせいか、後年、一寸腰をいため、病院で検査を受け、X線写真をみた医師が、「あなたは、何か重い荷物の運搬に係わる仕事に就いていますか?」と聞かれた時には思わず苦笑してしまいました。
鉱山会社(当時の日本鉱業株式会社)のご好意で、「食事付きの独身寮」の一室を格安の値段でご提供いただき、さらには資料整理のために夜は「探査課資料室」の使用を許可され、そこで図面整理や大学院入試の準備などに当たりました。その当時の大手の鉱山会社所有の鉱山現場は、実習に来山した学生を大事にされ、どこもほぼこのような状況にあったと記憶しています。その意味でも、当時は、良き時代であったと思います。
さて、「黒鉱鉱床」とは、第三紀中新世に生じた、グリンタフ地域と呼ばれる日本列島の内帯に限って産するもので、今から1500万年程前に、活発な海底火山活動に伴って形成された銅ー鉛ー亜鉛ー金ー銀を主とする多金属硫化物ー硫酸塩鉱床です。しかも鉱床母岩は、どんな火山岩でもよいわけでは無く、必ず石英安山岩〜流紋岩(つまり、SiO2含有量が約60%以上)に限られるわけです。十和田湖の南側には「北鹿地域(Hokuroku district)」といって、「黒鉱鉱床」が密集していることで、世界的にもよく知られた地域があります。ここで見られる鉱床には、どの鉱床においても、下位から上位へ向かって、「珪鉱帯」、「黄鉱帯」、「黒鉱帯(狭義の黒鉱)」、「重晶石帯」、「鉄石英帯」という累帯配列が認められます。
ところが、「上北鉱山」の場合には、このような鉱石の配列が全くみられません。その代わりに、これら各帯を構成していたと考えられる鉱石ならびに母岩の一部が、礫ないしは礫状物質として集まって層をなしています。つまり、鉱石礫と母岩礫からなる一種の「礫岩層」を形成しており、しかもその中では礫の大きさおよび比重の違いによる級化構造が顕著でした。この事実は、「上北鉱山」の場合には、初生的には上記の累帯配列が存在したものの、海底地震などによって誘発された地辷りのため、破壊され、二次的に移動し、「礫岩層」として再堆積したものであることを意味します。いろいろ興味深い事実が観察されましたので、何らかの形で公表を考えていたのですが、私よりも1年早くここの鉱床を東大の「修士論文」として研究されていた韓国からの留学生(李明成さん、Lee Mingson)がおられ、彼が先に論文を発表したこともあって、そのチャンスが失われてしまいました。李明成さんとは、坑外および坑内調査を幾度かご一緒しました。その後も現在(在ソウル)に至るまで親しくおつき合いをさせていただいています。
次いで、修士論文では、立見辰雄先生のご指導の下で、「北鹿地域」にある「相内鉱山」の「黒鉱鉱床」を研究しました。ここには、初生的な累帯配列を示す鉱床と、「上北鉱山」類似の「礫岩層」型の、2種類の鉱床がみられます。初生的な累帯配列を示す鉱床を中心に、今では考えられないような多数の研磨片と薄片を作り、その顕微鏡観察と鉱物中に含まれる流体包有物の加熱実験に明け暮れました。当時(1969年から 1970年)は、実験装置といっても限られ、未だEPMA分析もコンピューターもそれほど普及していない時代でした。
一般に、累帯配列を示す「黒鉱鉱床」では、下位から上位に向かって、鉱物組合わせが変化することはそれまでにわかっていたことですが、勿論ここでもこのことが確認されました。
それと同時に、それまでは「黒鉱鉱床」について断片的には言われていたことですが、「相内鉱山大黒鉱床」において、下位から上位に向かって鉱石組織を連続的に詳細に観察していくと、その分布には空間的な規則性があることに気付きました。「珪鉱帯」に産する鉱石は、火山砕屑岩中の割目(脈)などの間隙を充填する単純な組織が普遍的であり、その上位の「黄鉱帯」の鉱石はその上部程、「黒鉱帯」を含めて、鉱石組織が細粒で複雑となることが明らかになりました。細粒で複雑な組織とは、具体的には、各種のコロフォーム組織、樹枝状組織および墨流し状組織などで、これらは急冷或いは過飽和度の高い条件下で生じるものです。
このことの地質学的な意義は、このような組織が認められる場所(層準)とは、環境の変化を意味するということです。
つまり、下位の「珪鉱帯」や「黄鉱帯」の下半部は、鉱化流体が海底に達する前に海底よりも下位で生じたものであり、「黄鉱帯」の上半部およびその上位の「黒鉱帯(狭義の黒鉱)」、「重晶石帯」、「鉄石英帯」は、鉱化流体が直接海底に出て急冷されて鉱石鉱物が沈澱したものと考えました。
このことは、次のように言い換えることができるかもしれません。前者(つまり、下位の「珪鉱帯」や「黄鉱帯」の下半部)は、現世の海嶺や背弧盆に伴う熱水鉱床に例えていえば、マウンドの下部の海底には出ていない部分に相当し、後者(つまり「黄鉱帯」の上半部およびその上位の「黒鉱帯(狭義の黒鉱)」、「重晶石帯」、「鉄石英帯」)は、マウンドおよびその上に生じたチム二ー(“煙突”)ならびにそれらの壊れた残骸の集合体に相当すると考えられます。
指導教授の立見先生のお薦めもあって、修論の一部を論文(Watanabe, M. (1974):On the textures of ores from the Daikoku ore deposit, Ainai mine, Akita Prefecture, Northeast Japan, and their implications in the ore genesis)として「鉱山地質特別号6号」に投稿しました。
1974年に出版された本特別号(「GEOLOGY OF KUROKO DEPOSITS、435p」)は、当時の「日本鉱山地質学会(現資源地質学会)」が総力を挙げて世界に問うたもので、それまでの日本における「黒鉱鉱床」についての各方面からの研究の集大成ともいうべきものでした。蛇足ですが、この本は世界中に飛ぶように(?)売れ、その結果、版を重ねて、「日本鉱山地質学会」は大きな黒字を手にし、それがある基金となったと、うかがっております。
それまでは、「黒鉱鉱床」は日本に固有のものと考えられていましたが、この論文集が世界中に行き渡るようになると、「黒鉱鉱床」類似の鉱床(これを「黒鉱鉱床」と区別して「黒鉱型鉱床」と呼ぶ)が、世界中の先カンブリア時代から鮮新世~更新世に至るいろいろな地質時代の岩層の中に見い出されるようになりました。
さて、博士課程に進学してからは、研究対象を単一の鉱床とはせずに、「グリンタフ地域における金属鉱化作用」という広域的な観点から研究に着手しました。既述のように、「グリンタフ地域」というのは大規模な海底火山活動が活発であった地域であり、それ自体、新第三紀内帯における「構造区」かつ「鉱床区」を形成しています。「グリンタフ地域」には、「黒鉱鉱床」に加えて、「黒鉱鉱床」類似の鉱物組合わせを有する「鉱脈(型)鉱床」が多数胚胎しています。
この両者(「黒鉱鉱床」と「鉱脈(型鉱)床」)には、鉱化作用に海水が関与したであろうという「作業仮説」の基に、それまでの研究手段に加えて、この両者に共通に産する硫酸塩鉱物(重晶石、硬石膏、石膏)の酸素および硫黄の安定同位体比測定を取り入れました。
当時、既にこの分野の指導的立場におられた岡山大学温泉研究所(現固体地球研究センター)の酒井均先生のご指導を仰ぐことになり、三朝(三朝温泉の入り口)に移り住みました。当時酒井研究室には新進気鋭の助手として松葉谷治および木島宣明のお二人の先生がおられ、やはりいろいろご指導をいただきました。殊に、松葉谷先生にはその後秋田大学に移られてからも、酸素および水素同位体分析では大変お世話になりました。
研究所では、先ず「ガラス細工」、「鉱物の化学分離」、「真空装置」、「冷媒」の扱いなどご指導いただきました。これらすべての事が初めての経験であり、これらのことが「同位体質量分析」のための基礎となったわけです。「真空装置」の一部を構成するガラス器具を壊して、水銀が実験室の床に飛散するなど、ここで経験したいろいろな失敗は、いまでも懐かしく思い出されます。また、実験していると、立っている時間が長く、これが意外と疲労をもたらしましたが、これも間もなく慣れていきました。
この研究所に滞在してみて驚いたことは、酒井先生はじめスタッフの皆さんは夕方には一旦実験・仕事を止めて夕食のため帰宅し、程なくするとまた戻ってきて仕事を開始し、21時頃になると皆さんがある部屋に集まってきます。アルコールなどを片手に当時の先端的な分野での議論が沸騰し、また時には世間話ありで、この研究所での実験と共に、この素晴らしい一時は私の脳裏に鮮明に焼き付いています。私はその後も少し実験を続けて、後始末をすると宿にかえるのがいつも24時近くとなりますが、その後の温泉(研究所が泉源を所有している!)がその日の疲れを癒してくれました。温泉研究所滞在中は、月曜日から土曜日まではほぼ毎日このような生活を送り、日曜日や休日だけは、全くフリーな1日としました。
そのような生活を何ヶ月か送っていたところ、立見先生から大事な話があるので帰京するようにとの連絡がありました。早速先生のところに出向くと、「広島大学の土井正民先生から助手を求めてきていますが、いってみませんか」というお話にとても驚いたのをよく覚えています。今の時代なら「公募」という厳しい競争に曝され、助手に採用されることはかなり大変です。その意味では、私にとって、当時はとても善き時代であったと思われます。また、この時代は未だ多くの鉱山が稼行中で、多くの鉱床を見学することが出来た、という意味でも「鉱床屋」にとっては善き時代でした。
また、当時は全国の鉱床関係者が組織化され、文部省の「総合研究(“鉱床総研”)」に組み込まれて、全国の院生(博士課程後期)から教授までが一所に集まり、ほぼ毎年、鉱床見学やらシンポジウムがもたれました。これは、特に若い人達とベテランの先生方との交流を含めて、他大学の研究者と知り合うよい機会となり、且つまたベテランによる若者の“教育”の場でもあったように思います。
1971年11月に、広島大学に着任してからは、「学位論文」の取りまとめをしながら、鉱床学講座の先生(土井正民教授、添田晶助教授)および学生諸君と共に中国地方の主に花崗岩に伴う鉱床(“雑鉱鉱床”)についての研究を始めました。この中で、最初に論文にしたのは、島根県の都茂鉱山のスカルン鉱床に関するものでした(Watanabe, M., Soeda., and Ohtani, T. (1978): Skarnization and ore deposition at the Maruyama deposit, Tsumo mine, Southwest Japan, with particular emphasis upon their intimate associations. Jour. Japan. Assoc. Min. Pet. Econ. Geol., 73, 283-299)。
その当時、“雑鉱鉱床”のいくつかは既に休山となっており、止む負えず鉱山跡の廃石(ズリ)について調査・研究をする機会もかなり増え、そのことから「広島大学のグループは、ズリ鉱床学を始めた」等と冗談半分に言われたこともありました。
1976年には、遅ればせながら「学位論文」(Geological and geochemical studies on the Neogene mineralization in the Green Tuff region in Japan, with special reference to the nature and origin of the ore-forming fluids.)をまとめることができました。この中から、以下の3論文を公表しました:
(1) Watanabe, M. (1979): Fluid inclusions in some Neogene ore deposits in the Green Tuff region, Japan. Mining Geol., 29, 307-321.
(2) Watanabe, M. (1983) : Geochemical environments of the Neogene ore formation in the Green Tuff region, Japan. Jour. Sci., Hiroshima Univ., Ser. C, 8, 67-94.
1978年に海底火山活動に伴って生じた火山性塊状硫化物鉱床(VMS) の成因についてのアメリカー日本ーカナダ共同研究プロジェクトが始まりました。その成果が1983 年に、(3) ECONOMIC GEOLOGY MONOGRAPH 5 『The Kuroko and Related Volcanogenic Massive Sulfide Deposits, 604p』として出版され、幸いにも、Watanabe、M. and Sakai, H. : Stable Isotope Geochemistry of Sulfates from the Neogene Ore Deposits in the Green Tuff Region, Japanも掲載されました。
そうこうするうちに、 湯川正敏さんという、よき共同研究者に恵まれて、以前から考えていた四国三波川変成帯に分布する「別子型鉱床」の研究に着手しました。
この種の鉱床は、「黒鉱鉱床」とは異なり海底玄武岩活動に伴って生じたものですが、「黒鉱鉱床」同様、VMS(火山性塊状硫化物鉱床)の範疇に入ります。しかしながら、層状のCu(±Zn)鉱床であり、Coの濃集という点でも、「黒鉱鉱床」とは異なります。「別子型鉱床」は、白亜紀初期に海洋底で形成された後で、高圧・低温型変成作用の場に置かれて、三波川変成作用を被り、その後、隆起・上昇したものです。高変成度の鉱床では形成時の情報が全く残存していませんので、それらの保存されている可能性のある変成度のより低い鉱床を中心に研究を進めてきました。
広域的に調べてわかったことは、鉱床に見られる鉱物組合わせも周囲の母岩に見られる鉱物組合わせも、変成度を反映して、系統的に変化していることでした。
この関連分野では、Yukawa, M. and Watanabe, M. (1983): Opaque minerals and composition of fluids attending the Sambagawa metamorphism in the Sazare mining district, SW Japan Neues Jb Miner. Abh., 150, 11-23 が最初の論文で、その後、例えば、Watanabe, M. et al. (1993,1997,1998) 他の論文を公表してきました。
「別子型鉱床」についての研究を始めた頃、幸いなことに、星野健一さんという有能な共同研究者が与えられ、そのことで私共の「鉱床学グループ」の研究の厚みと深さが増したように思います。彼との最初の論文は、星野健一・渡辺洵・添田晶(1982):山口県藤ケ谷鉱山明見谷第5鉱体における脈状スカルンの帯状配列について, 鉱山地質, 32, 443-456です。
その後、星野さんは、私共との共同研究(例えば、
(1) Hamasaki, S., Murao, S., Hoshino, K., Watanabe, M., and Soeda, A. (1986);
(2) 添田晶・渡辺洵・星野健一(1988);
(3) Watanabe, M. and Hoshino, K. (1991) など)の傍ら、先程の星野健一・渡辺洵・添田晶(1982)を基にして、交代作用の理論的解析を発展させ、その後は熱力学データを駆使したシミュレーションを推進してきました。(例えば、
(1)Hoshino, K. and Watanabe, M. (1997) : Exsolution mechanism of bornite from chalcopyrite solid solution. Neues Jb. Miner. Mh., Jg. 1997(4), 145-154;
(2) Hoshino, K., Yamamoto, Y., Gu, X.P., Lee, S.Y., and Watanabe, M. (2000): Preliminary examinations of the ore-forming process by fluid mixing - a test of MIX99. Resource Geol., 50, 185-190).
その他、“雑鉱鉱床”に関する研究としては、例えば、以下のものが挙げられます:
(1) Watanabe, M. and Soeda, A. (1981) : Distribution of polytype contents of molybdenite from Japan and possible controlling factor in polytypism. Neues Jb. Miner. Abh., 141, 258-279;
(2) 渡辺洵・島田允尭・吉田哲雄(1981):都茂鉱山地域における花崗岩類および関連鉱床の流体包有物の研究, 鉱山地質特別号, 9 号, 145-162;
(3) Nakashima, K., Watanabe, M., and Soeda, A. (1981) : Mineralogy of the Cu-Bi-W-Co-As-S mineralization associated with the Hobenzan granitic complex. Jour. Japan. Assoc. Min. Pet. Econ. Geol., 76, 1-16;
(4)添田晶・渡辺洵(1982):都茂鉱山丸山鉱床における錫元素の挙動, 鉱山地質, 32, 117-127;
(5)Soeda, A., Watanabe, M., Hoshino, K., and Nakashima, K. (1984): Minmeralogy of tellurium-bearing canfieldite from the Tsumo mine, SW Japan and its implications for ore genesis. Neues Jb. Miner. Abh., 150, 11-23;
(6)Nakashima, K., Watanabe, M., and Soeda, A. (1986) : Regional and local variations in the composition of the wolframite series from SW Japan and possible factors controlling compositional variations. Mineral. Deposita, 21, 200-206).
1986年から1年間、JICA Expert(Project Leader)として、ボリビアのSanandreas大学の鉱床学研究所に派遣され、富士山の頂上よりはるかに高い、標高4000m位のところで、ボリビア人相手にいろいろ得難い経験・体験を積むことができました。その数年前に初めて国外に出たのは韓国でしたが、その時には差程違和感を感じませんでしたが、ボリビアに長期滞在して初めてculuture shockというものを経験しました。一つだけ例を挙げれば、「約束」というものの「重みの軽さ」です。特に彼等が悪意をもって我々に対するというのではなく、言わば、そういうものに対する考え方の違いによると考えることで、より良いcommunicationが取れるようになったような気がします。いろいろありましたが、ボリビア滞在中に切実に感じたことは、今まで以上に海外に目を向けるべきではないか、ということでした。
帰国後、機会を見つけては、学生を海外に連れていき調査を始めるようになりました。そのために先ず、学生実習の受け入れに関して、海外の鉱山や地質調査所を何ケ所か当たりました。いろいろな反応があり、securityなど一番反応のよかったのがAustralia のQueensland州の内陸部にあるMount Leyshon 鉱山でした。学生の中にたまたま修士論文で是非外国の鉱床について研究したいという人がおり、結局、ここの花崗斑岩に伴う金鉱床を調べることになりました。この学生(上本武さん)は、後にUWA (University of Western Australia) のPh.D Courseに入学し、学位を取得し、現在日本の会社で活躍しています。
さて、この鉱山およびその周辺地域は、砂漠同然の環境で、高温と乾燥のために、ドリル・コアを外に放置しておくと、すぐにボロボロになるという凄まじい自然環境にありました。修士論文を基に、Uemoto, T., Watanabe, M., Hoshino, K., Kagami, H., Hodkinson, I. P., and Orr, T. O. H. (1992):Geochemistry of gold mineralization and related magmatic events at the Mount Leyshon mine, Queensland, Australia. Resource Geology, 42, 361-378という論文を公表しました。
その後、星野さんや学生諸君と供に、韓国、中国などに足を延ばし、いくつかの鉱床の調査を手掛けました。国情の違い、文化の違いなどで、いろいろ戸惑うことが多々ありました。特に、何度か訪れた韓国での話ですが、今の韓国の政治状況からは考えられないことですが、休戦ライン近くのある鉱山の鉱床調査の際には、韓国が正に「臨戦体制」にある、ということを肌に感じたことを思い出します。これらの調査を通して得られた成果については、主に私の怠慢により、未だほんの一部しか公表しておりません。
さて、中国地方に身を置く者としてのある意味での責任として、これまでに私共がまとめたものならびに鉱床学研究室において蓄積された公表・未公表データなど(例えば、(1) Watanabe, M., Shibata, K., and Soeda, A. (1984) : K-Ar ages of base and precious metal mineralization in the Tungsten Province, Southwest Japan. Geochem. Jour., 18, 189-193; (2) Watanabe, M., Nishido, H., Moriwaki, H. Higashimoto, and Kubota, Y. (1986) : K-Ar ages of skarn deposits in the Inner zone of southwestern Japan. Geochem. Jour., 22, 231-236; 卒論・修論など)に基づいて、地質発達史との関連において、西南日本内帯における鉱床生成期についての総括を行いました:Watanabe, M., Nishido, H., Hoshino, K., Hayasaka, Y., and Imoto, N. (1998): Metallogenic epochs in the Inner Zone of Southwest Japan. Ore Geology Reviews, 12, 267-288。この論文では、西南日本内帯というくくりにはなっていますが、実はほぼ日本列島全体をカバーしているという、ほのかな自負を抱いております。つまり、西南日本内帯というのは、日本のほとんどのタイプの鉱床が見い出される、ということで特徴付けられる、ということでもあるわけです。
ところで、私の研究者人生にとって一大転機となったのは、なかなか一歩を踏み出せずにいた先カンブリア時代のVMS(火山性塊状硫化物鉱床)を研究するためのオーストラリア行きでした。
というのも、VMSが、海底火山活動の場において海水と地殻との相互作用の産物である限り、地球表層環境の変化が何らかの形でVMSに記録されているはずであるという作業仮説にたって、先ずはなるべく古い時代に生じた鉱床を研究することがその第一歩となると考えたからです。このことは、実は、学位論文をまとめる頃から考えてはいましたが、そのきっかけを見出せずにおりました。
幸い、1993年、西オーストラリア大学(UWA)のGledden Fellowshipを得て、同大学のKey Centre(鉱床学研究所)に滞在し、いくつかの鉱床を調査する機会に恵まれました。その中でも最も驚いたのは、30億年近く前に生成された「黒鉱型鉱床」であり、母岩といい、産出鉱物といい、鉱石組織といい、日本の「黒鉱鉱床」にとてもよく似ており、しかもそれよりはるかに古い時代に生成したにも拘らず、細粒で複雑な鉱石組織等で代表される初生の性質をよく保存しており、「黒鉱鉱床」以上にprimitiveであったことです。構成鉱物は極めて細粒で、そのせいか閃亜鉛鉱(ZnS)にしても重晶石(BaSO4)にしても、通常の「黒鉱鉱床」ではよく見られる筈の流体包有物(それらホスト鉱物の沈澱・成長の過程で鉱化流体(一般にNaCl-CO2-H2O系で近似)の一部をトラップしたものであり、一般に常温では気ー液2相からなり、鉱化流体の“化石 ”とみなしうる)が、仮にあったとしても小さ過ぎて、流体包有物を観察することが出来ません。
この鉱床は、規模が小さいことなどの理由で、未だ開発されておりません。本鉱床については、野外調査とドリル・コアに基づいて、UWAの大学院生(パートタイマー大学院生)によって「学位論文」としてまとめられました。UWA滞在中、たまたま私が「黒鉱鉱床」に関係しているということから、彼女の「学位論文」についてしばしば相談にのり、しかも、私自身その後、彼女の「学位論文審査委員」として、いろいろ協力する機会が与えられました。私も別の観点からこの鉱床について調べてみようと考え、共同研究を視野に入れて、帰国後、彼女にサンプルなどについての協力をお願いしたところ、先方に連絡が届いていなかったのか、余程多忙だったのか、結局、彼女からは梨の礫であって、それに対してこちらから更にアクションを起こさなかったことは、大いに悔やまれるところです。
さて、地質時代に生じた「黒鉱(型)鉱床」および「別子型鉱床」(即ち、これらは現在陸上に存在している!)の研究をすすめる上で、生成後それほど時間の経っていない、つまり変成作用など生成後の二次的な影響を受けていない、中央海嶺や背弧盆に伴う熱水鉱床は必然的に重要となります。以前からこのプロジェクト研究(例えば、JAMSTECによる海洋についての国際的な共同調査など)に参加したいと思いながらも、その一歩を踏み出せずにいましたが、幸いなことに、1998年に偶然その機会が与えられました。
琉球大学の大森保教授のもとで、南部EPR(南部東大平洋海膨)および沖縄トラフの熱水鉱床を研究(修士論文)した韓国からの留学生(李受映さん、学位取得後、日本の企業で活躍中)を博士課程に迎える、という願ってもないチャンスが到来しました。彼女と共に MAR(大西洋中央海嶺)のRainbow Hydrothermal Fieldの研究に着手しました。
ここの鉱床は他の海嶺系のものとは異なり、玄武岩中ではなく、その下位、つまり上部マントルの超苦鉄質岩(蛇紋岩)の中を暖められた海水の循環した結果、生じたものであることが判明し、先ずこのことを報告しました:Lee, S.Y., Watanabe, M., Hoshino, K., Oomori, T., Fujioka, K. and Peter Rona (2002): First report of linnaeite (Co3S4) and millerite (NiS) from active submarine hydrothermal deposits: Rainbow hydrothermal field, Mid-Atlantic Ridge at 36゜14´N. Neues Jb. Miner. Mh, Jg.2002, 1-21。
この数年来、沖縄トラフの熱水鉱床についても、卒論、修論を通して研究を重ねてきました。その契機となったのは、日本とドイツの共同研究により、沖縄トラフのJADE siteから「黒鉱鉱床」類似のものが初めて見い出された(Halbach, P., Nakamura, K., Wahsner, M., Lange, J., Sakai, H., Käselitz, L., Hansen, R -D., Yamano, M., Post, J., Prause, B., Seifert, R.,, Michaelis, W., Teichmann, F., Kinoshita, M., Märten, A., Ishibashi, J -I., Czerwinski, S. and Blum, N. (1989): Probable modern analogue of kuroko-type massive sulphide deposits in the Okinawa trough back-arc basin. Nature, 338, 496-499)ことにあります。このことは私自身、予想もしていなかったことですが、その時に私は新鮮な驚きと共に、VMS研究の鍵は沖縄トラフにあるのではないか、という直感みたいなものを感じ取りました。
実はその発見よりずっと以前(1970年代半ば頃)に地球物理学の上田誠也先生にお会いした際に、先生は既にそのことを予想されており、「沖縄トラフに黒鉱型鉱床が見つかる可能性については、鉱床学の専門家としてどう考えますか?」と問われ、私は即座にそういうことは考えられません、とお答えしたことを、今赤面の思いで思い出しています。
ところで、ここで対象としている中央海嶺や背弧盆に伴う熱水鉱床についての研究は、ある意味では10年程前に研究のピークが終わったかに見えます。重要な問題点がすべて解決しているわけでは、決してありません。今やそれらは、鉱床や岩石そのものではなく、それらに伴う微生物を含む特異な生物群集に基づいて、生命の起源・進化という新しい観点からの研究に軸足が移されています。惜しむらくは、折角潜行調査を実施しても、生物関連の試料のみを採集し、そこにある岩石や鉱床試料を回収することはないという現状です。
そうした状況の中で、私達は先ず、南部沖縄トラフの玄武岩に伴う鉱床について記載しました(Watanabe et al., Hoshino, K., Shiokawa, R., Takaoka, Y., Fukumoto, H., Shibata, Y., Shinjo, R. and Oomori, T. (2006): Metallic mineralization associated with pillow basalts in the Yaeyama Central Graben, Southewrn Okinawa Trough, Japan. JAMSTEC Rept. Res. & Dev., 3, (in press)。さらに、沖縄トラフに伴ういくつかの鉱床についての研究を通して、極めて単純なことですが、重要な事実を明らかにすることができました。それは、沖縄トラフには、石英安山岩〜流紋岩に伴う熱水鉱床と玄武岩に伴うものとがあり、両者とも鉱物学的特徴や地球化学的特徴が殆ど共通しており、後者に「別子型鉱床」を伴うことは決してない、ということでした。この事実については私達は次のように考えています。
沖縄トラフのように、地殻が大陸的でしかも厚い未固結堆積物の存在するような場において、換言すれば、海洋地殻が存在しないような場において、暖められた海水がその中を循環すれば、関連する火山岩が珪長質であるか苦鉄質であるかには係わらず、その結果生じる鉱床は、全て「黒鉱型鉱床」となると結論付けました。単純といえばこれ以上単純な結論はないような気もします。
つまり、海底火山活動に伴ってどのようなVMSが形成されるかは、そのような鉱化作用が起こった場の地殻の性質ー大陸的であるか海洋的であるかーに義的に規制される、と考えました。現在、在任中の締めくくりとしてその論文化を急いでいます。
さて、「黒鉱鉱床」というVMS(火山性塊状硫化物鉱床)に始まった私の旅は、いろいろ寄り道をしながら沖縄トラフのVMSの話になり、いよいよ「私の研究者人生-鉱床学の旅」も幕を閉じることになりますが、最後に私の夢の実現ということをご紹介することで、締めくくりとしたいと思います。

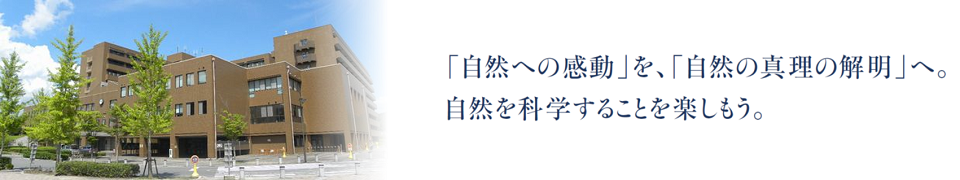
 Home
Home